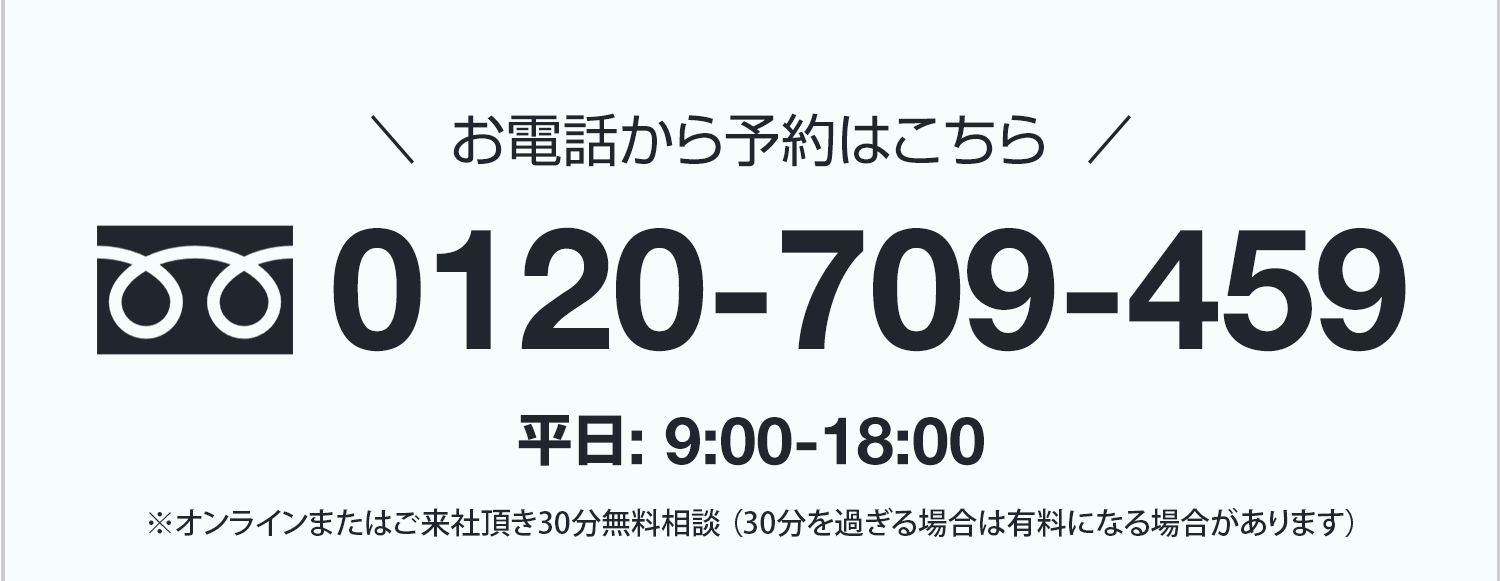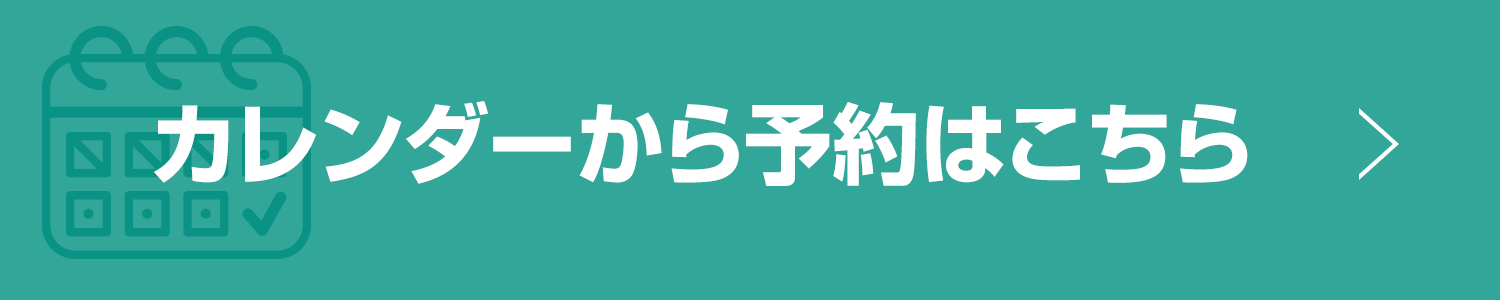永住権とは
永住権とは、在留資格「永住者」を所持している外国人の事で、取得後は期間の制限なく日本に在留出来る事になります。申請先は申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。
永住許可申請代行サービスとは
永住権の申請にあたっての最初のヒアリングから、必要書類の収集、理由書含む申請書類の作成のサポート、入国管理局への申請、申請後の入国管理局からの追加提出書類等への対応、許可後の在留カード受取までを行政書士が責任を持って対応を行います。
永住許可申請代行サービスの特徴とは
ビザ申請の専門家である行政書士が親身になってワンストップで対応を行うので、本人が時間をかけて準備を行い申請をするよりもスムーズに申請まで進み、許可率も高くなります。最初のヒアリングを基に集めて頂く書類の案内も行います。
永住許可申請代行サービスの業務内容


①永住権(永住ビザ)申請手続き全般に関する相談対応(無制限:電話、メール、チャットワーク等のSNSで対応させて頂きます。)
➁永住申請書類作成
➂申請理由書の作成サポート
④必要に応じてその他書類の作成、提出必要書類のチェックなど
⑤入国管理局への申請代行
⑥入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑦結果通知の受取
⑧在留カードの受取
永住許可申請代行サービスを利用しているお客様の例
| 当初の問題点(こんなお悩みありませんか?) | |
|---|---|
| Before | After |
| ①永住権の取得を考えているが、何から手を付けたら良いか分からない… ②永住権の取得に興味があるが、入国管理局のページを見ても難しくてよく分からないし、取得出来る条件を満たしているのかもよく分からない… |
①永住権含むビザ申請に詳しい行政書士がヒアリングや説明を丁寧に行った上で準備を進めるので、申請までの道筋が明確になり、申請までスムーズに進める事が出来た! ②しっかりヒアリングを行って、取得可能性を判断し説明を行った上で、申請へと進んでいくので、無駄無く進める事が出来た! |
永住権や永住許可申請代行サービスについてのQ&A
永住権の許可件数と許可率は?
永住権を取得するための永住許可申請の統計データは下記のようになっています。
| 年度 | 申請件数 | 許可件数 | 許可率 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 57,570件 | 29,747件 | 51.7% |
| 2021年 | 64,149件 | 36,691件 | 57.2% |
| 2022年 | 58,927件 | 37,992件 | 64.5% |
| (出入国管理統計に基づき作成) | |||
許可を取得するための期間は?
出入国在留管理庁が公表している「標準処理期間」は4か月となっていますが、 申請件数の増加もあって近年は1年程度からそれ以上の期間がかかるのが一般的と なっています。なお、審査期間中に現在所持している在留資格の期限を迎えてしま う場合には、その在留資格の更新等が必要となります。
永住権を取得するための要件は?
取得するための主な要件は下記となります。
①素行が善良であること(素行要件)
この点について、法務省が公表している永住許可に関するガイドラインでは、
「法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること」とされています。
下記の国益要件の項目にある罰金刑や懲役刑を受けた事があると、素行不良と判断され大きくマイナスになりますし、軽微な交通違反を繰り返しているような場合も素行不良と判断されます。
②独立した生計を営むこと(生計要件)
・安定した収入・資産があり、日本で自立して生活できること
一般的に年収300万円以上が目安(扶養家族がいる場合はさらに高い収入が必要)
・定職についている(パート・アルバイトのみでは厳しい)
③10年以上日本に継続して在留していること(居住要件、特例あり)
・そのうちの直近5年以上は就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)または居住資格で在留していること
・留学ビザの期間は含まれない(ただし、留学後に就労資格を取得し、その後5年以上継続して在留していればOKです)
※配偶者ビザや高度専門職ビザでは期間の短縮あり
④日本の国益に合致していること(国益要件)
➀罰金刑や懲役刑を受けていないこと。
➁納税義務等の公的義務を履行していること
・税金(住民税・所得税)や社会保険(年金・健康保険)を適切に納付していること
・公的負担(生活保護など)を受けていないこと
➂現在の所持している在留資格が「最長の在留期間(通常3年または5年)」であること
取得できない場合がありますか?
①収入が不足しているもしくは不安定
年収が概ね300万円以上であることが求められ、扶養家族がいる場合はさらに高い収入が必要とされます。
②海外出国歴が多い
永住申請では、上記に記載しているように「居住要件」があり、海外出国歴が多い(下記に該当する)と継続して在留している事にならなくなり、永住権申請に必要な在留期間を満たす事が出来なくなり許可を取る事が難しくなります。
・1回の出国で3カ月以上連続した出国
・1年で合計150日以上の出国
③税金の未納がある
直近5年間に税金の未納があると100%永住申請は許可されません。
期限内に納付できず、支払いが遅れてしまった事があるような場合でも大きなマイナス要素となります。
申請には適正に支払い初めてから5年間の支払い歴とその事を証明する資料の提出が必要となります。
④年金や健康保険料の未納がある
直近2年間に年金や健康保険料の未納があると100%永住申請は許可されません。
期限内に納付できず、支払いが遅れてしまった事があるような場合でも大きなマイナス要素となります。
申請には適正に支払い初めてから2年間の支払い歴とその事を証明する資料の提出が必要となります。
⑤身元保証人に問題がある
永住申請する場合には、「日本人もしくは永住者」の身元保証人が必要となります。さらに定職についており、目安として300万円以上の安定した年収があり、納税義務を果たしている人物である事が必要です。
上記に該当しない人を身元保証人にした場合は不許可の原因となります。
⑥犯罪歴があるもしくは交通違反等の軽微な違反回数が多い
罰金刑や懲役刑がある方や交通違反等の軽微な違反回数が多い場合は、大きなマイナスとなり、不許可の原因となります。
永住権の申請書類は何が必要になるか?
①永住許可申請書1通
②写真(縦4cm×横3cm)1葉
③理由書 1通
④申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
⑤申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する在職証明書等の資料
⑥直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
・直近5年分の住民税の納付状況を証明する資料
・源泉所得税等の国税の納付状況を証明する資料
⑦申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・直近2年間の年金の支払い状況が分かる資料
・健康保険の加入状況が分かる資料
⑧身元保証人に関する資料
了解書 1通
⑨パスポート及び在留カード(申請時に提示)
※上記は必ず必要になるものの例示であり、申請人の在留資格や状況によってその他の資料も必要となります
永住権の獲得にはどのくらいの日本滞在が必要ですか?
上記の永住権を取得するための要件は?の項目にも記載した通り、原則は10年以上日本に継続して在留していることが必要となります。
日本人の配偶者として永住権を申請する際の特別な要件とは何ですか?
永住権の申請をしようとしている方が、日本人の配偶者または永住者の配偶者の場合で、実態のある結婚生活を3年以上行い、かつ、日本に1年以上在留している場合は、永住申請の特例要件に該当するため、10年間の在留期間が無くても申請を行えます。
永住権を取得するとどのような事ができるのか?
永住者になると、在留活動の制限が無くなります。つまり仕事の制限が無くなり、どんな職種や業種であっても制限無く働ける事となります。会社を経営するといった事も可能です。そして在留期間の制限も無く更新の必要も無くなります。
在留資格「永住者」「特別永住者」「帰化」との違いは何か?
「永住者」「特別永住者」「帰化」は以下のように異なる。
・「帰化」と「永住者」の違い
「帰化」は外国人が日本国籍を取得して日本人となることを指します。
一方、「永住者」は外国人が現在の国籍のままで、期間の制限が無く、日本に滞在出来る在留資格を有している人を指しています。
・「特別永住者」について
「特別永住者」とは、歴史的背景により特別に設けられた永住資格であり、1991年11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められている在留資格を有している外国人の事です。
第二次世界大戦中に日本が占領していた朝鮮半島や台湾の方は日本国籍を与えられていましたが、日本が第二次世界大戦を敗戦した事により日本国籍から離脱する事となりました。この事により日本国籍を失った人々とその子孫の方に対して、特別に永住を許可したものとなり、永住者とは別のものとなります。
永住権(永住許可)の取り消し理由について
永住権(永住許可)は期間の制限無く日本に住んでよいという許可ですが、無条件のものではありません。問題があれば、入国管理局は許可を取り消す事が出来ます。
これまでは、無期または1年を超える懲役・禁錮の実刑に処せられたとき、薬物に関する犯罪で有罪判決を受けたとき等は、永住者であっても退去強制の対象となり、永住者の在留資格を失います。また、永住許可申請に虚偽があったような場合も取り消しの可能性がありました。
それが令和6年に入管法が改正され、今後は永住者が入管法上の義務を遵守せずまたは故意に公租公課(法人税、所得税、住民税などの租税や健康保険料や社会保険料などの租税以外の金銭的負担)の支払いをしない場合も取り消しの対象となります。
永住許可申請の方法
申請者本人か法定代理人か行政書士等の取次者が必要事項等を記入した申請書やその他必要資料を申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に持参して申請を行います。
永住権が不許可となった場合の対応は?
①不許可理由の確認
不許可理由の確認は申請した地方出入国在留管理局で行えます。入国管理局の担当官は許可理由の全てを伝える必要が無く、また不許可理由のヒアリングは1回のみとなるので、うまく質問して漏れなく不許可理由と改善点を確認する必要があります。
②不許可理由の検討
不許可理由を検討して、解消できるかどうかを確認します。
そもそも永住要件を満たしていなかった等、すぐに解消出来ないものであれば、要件を満たしている状態が来るまで待つしかありません。
解消できる場合は、再申請を行う事も出来ます。
※永住申請は1度不許可となると、再申請した際のハードルが上がる面があります。
永住権の更新期間はありますか?
在留資格「永住者」は在留期限が無制限のため、更新手続きはありません。
ただし、「在留カード」の有効期間は「7年」となっているため、永住権を持っている外国人でも、必ず7年に1度、在留カードの更新手続きをする必要があります。
永住許可申請までにかかる準備期間は?
永住許可申請までにかかる準備期間は、申請人の在留資格や個人の事情によっても異なってきますが、平均で2カ月程かかります。必要書類の収集に1カ月程度、申請書や理由書等の作成及び申請するまでが1カ月程度となります。
永住権の許可申請は誰に依頼するべきか?
永住申請は他の在留資格の申請に比べても許可率が低いものとなります。
また、申請人自身で申請を行おうとすると、時間や労力の面でかなりの負担がかかります。申請自体も平日日中の時間帯に仕事等を休んで、管轄の入国管理局を訪問して行う必要があります。行政書士であれば、申請人の代わりに入国管理局を訪問して申請を行えます。
そのため、依頼する費用はかかりますが、申請人の負担を減らして許可率を高めるためには専門家である行政書士に依頼するのがおすすめです。
専門家はどのような事を実施してくれるのか?
①永住申請に向けたヒアリング及び総合的なコンサルティング
②個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ビザ申請書類一式の作成
④申請理由書の作成
ヒアリングを元に個人に合わせた永住理由書を作成致します。
⑤申請に必要な各種書類のチェック・追加書類の作成
⑥入国管理局への申請の代行
⑦入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料等への対応
⑧結果通知の受取り、許可後の在留カードの受取り
専門家に依頼するメリットは?
- 事前にある程度許可の可能性が分かる
- 許可の可能性を高められる
- 仕事等を休んで入管に行く必要が無い
- 行政書士が代わりに確実に申請まで行います
- 入国管理局から追加資料請求や追加説明要求が来た場合、その対応を適切に行える
- 許可後に代わりに在留カードも受け取ってもらえる
専門家に依頼した場合の流れは?
一般的に専門家である行政書士に依頼した場合は下記のような流れとなります。
- 事前相談
- 依頼・着手金の支払い
- 各種必要書類の収集と申請書等の作成
- 入国管理局に申請・受理
- 入国管理局での審査
- 結果通知
- 在留カード受取
専門家に依頼する場合の費用の目安は?
申請者(会社員)・・・12万円~15万円(税抜)
申請者(役員) ・・・14万円~17万円(税抜)
同居家族1名追加につき+3~5万円(税抜)
※その他として本国書類の翻訳費用が発生する場合があります。また、必要書類の収集を専門家側にどこまで任せるか等によっても料金が異なる場合があります。
※別途、入国管理局への申請手数料として1万円がかかります。
こちらは申請が認められた時に収入印紙を購入して納めます。
永住権申請で頼れる行政書士とは?
・永住権申請の実績がある行政書士
・役割を明確にして説明してくれる行政書士
特に必要書類の収集について、どちらがどこまで行うかしっかり確認しておくようにしましょう。
・不安点や疑問点を解消してくれる行政書士
親身になって対応してくれ、追加料金が発生する場合や不許可の場合の対応についても明確でしっかり説明してくれる行政書士を選ぶことをおすすめします。
永住許可申請代行サービスの無料相談の流れ
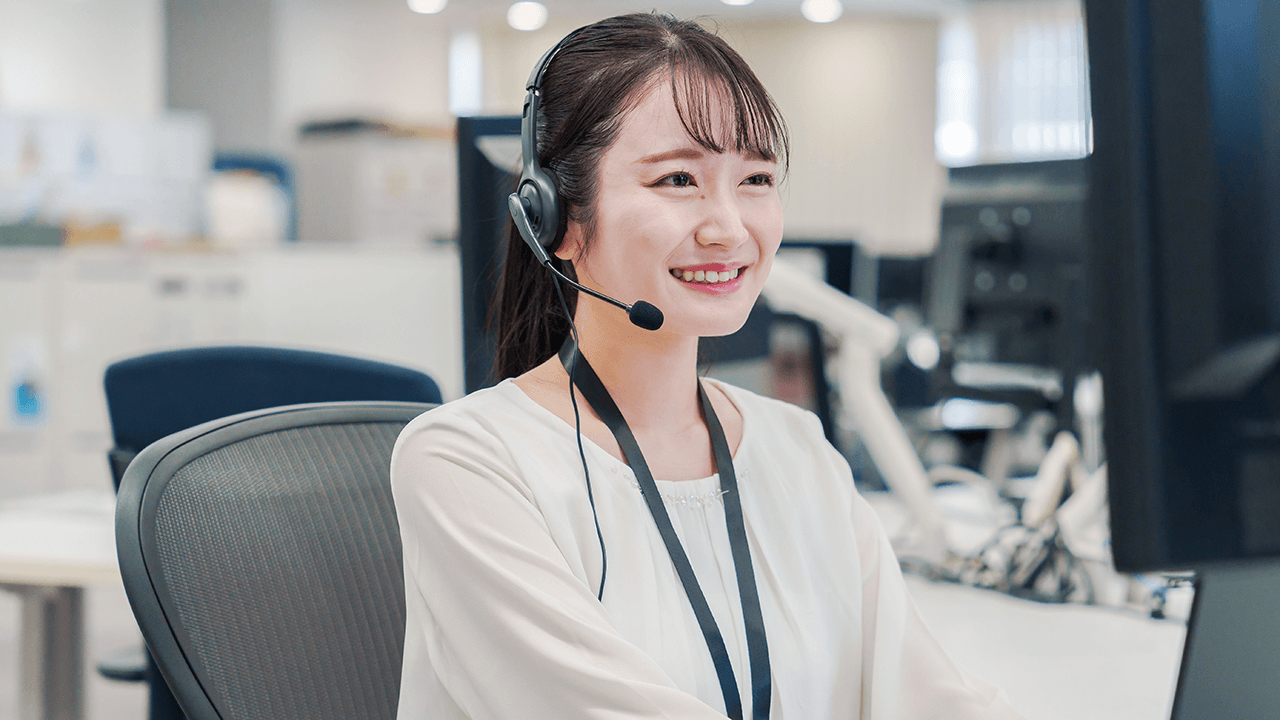
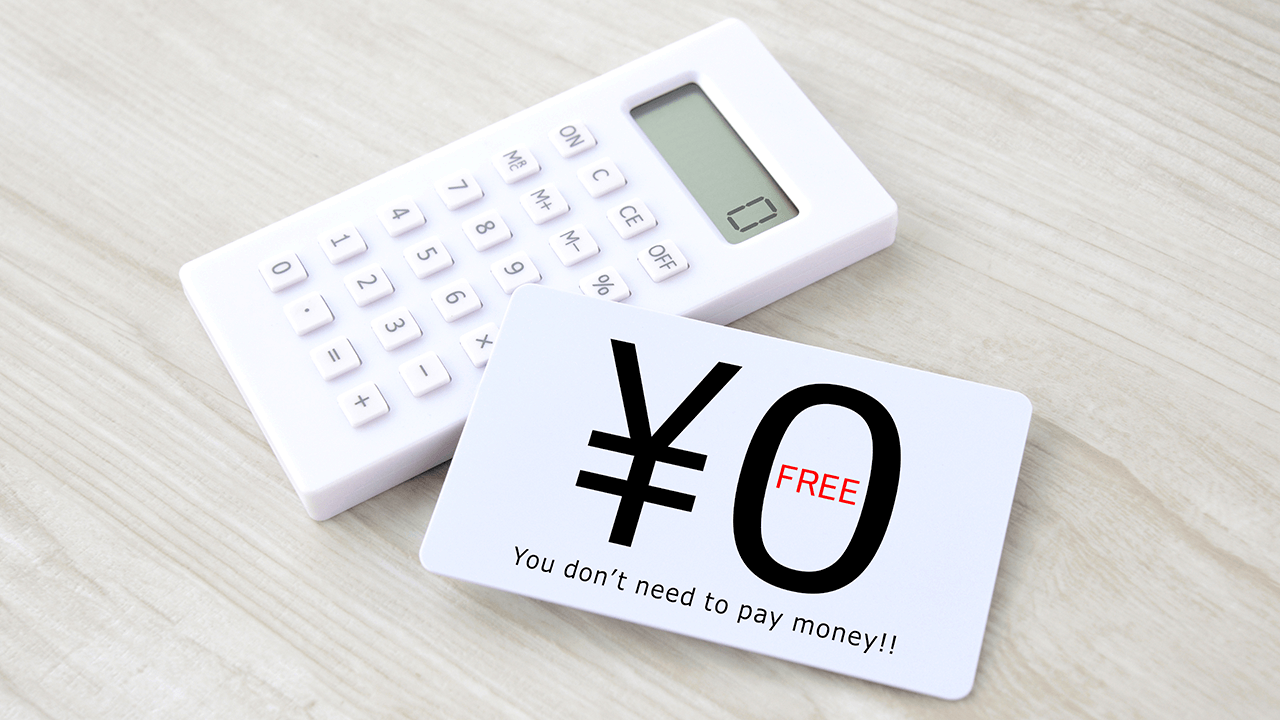
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑤申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。
⑥お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑦申請結果
申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。
こんなお悩みはありませんか?
- 遺言書の作成をしたいが、書き方がわからない。
遺言書の起案及び作成指導サービス内容
遺言書の文案・内容についてのアドバイスをいたします。
| 遺言書の起案及び作成指導費用 | |
|---|---|
| 行政書士報酬(税抜) | |
| 遺言書の起案及び作成指導 | 50,000円〜 |
※上記は報酬額の目安です。詳細については、各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので、個別見積をご請求の上ご確認ください。
※上記の報酬額には、通信費・交通費等の実費は含まれておりません。
初回相談に必要なもの
初回相談時に必要な物はございません。ヒアリング、ご契約後に必要資料をお伝えいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
遺言書の起案及び作成について
遺言書とは?
遺言書には、「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の2種類がありますが、通常事前に行政書士に依頼するのは「普通方式遺言」です。※普通方式遺言には下記3つの方法があります。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書の全文を自分で手書きして作成するタイプの遺言書です。3種類の普通方式遺言の中で最も簡単に作成できます。公正証書遺言や秘密証書遺言のように公証役場に行く手間はございません。
作成した自筆証書遺言は自宅で保管したり、信頼できる知人や弁護士などの専門家に預けたりして保管します。また、2020年7月からは自筆証書遺言を法務局で保管する制度が導入されたため、保管手数料を払って申請すれば法務局で保管することも可能です。
② 公正証書遺言
公正証書とは公証役場で作成する公文書で、公証役場に行って公正証書の形で作成する遺言書が公正証書遺言です。証人2人以上の立会いのもと、遺言者から公証人が遺言の内容を聞き取って遺言書を作成します。
公証人と事前に打ち合わせを行うなど手間はかかりますが、公証人という専門の人が遺言書を作成するので、形式面でミスが生じて遺言書が無効になる心配は基本的にありません。出張作成制度を利用すれば病院や家で寝たきりの人でも遺言書を作成できます。作成した公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがなくて安心です。
③ 秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたい場合に使う遺言書です。自分で遺言書を作成して封印した状態で公証役場に持ち込み、公証人が日付などを記載して遺言者および証人が署名・押印します。
遺言書を自分で作成する点は自筆証書遺言と同じですが、自筆証書遺言と違って秘密証書遺言の場合は本文をパソコンなどで作成しても良く、自筆証書遺言のように自署(自分で手書き)する必要はありません(ただし、署名は自署する必要があります)。
なお、秘密証書遺言は公正証書遺言と同じく公証役場で手続きをしますが、秘密証書遺言の場合は公証役場で保管してもらえるわけではなく、自宅などで保管します。
・相続トラブルを回避できる
・相続人の相続手続き負担を軽減できる
・財産を渡したい人に渡せる
永住許可申請代行サービスの無料相談の流れ
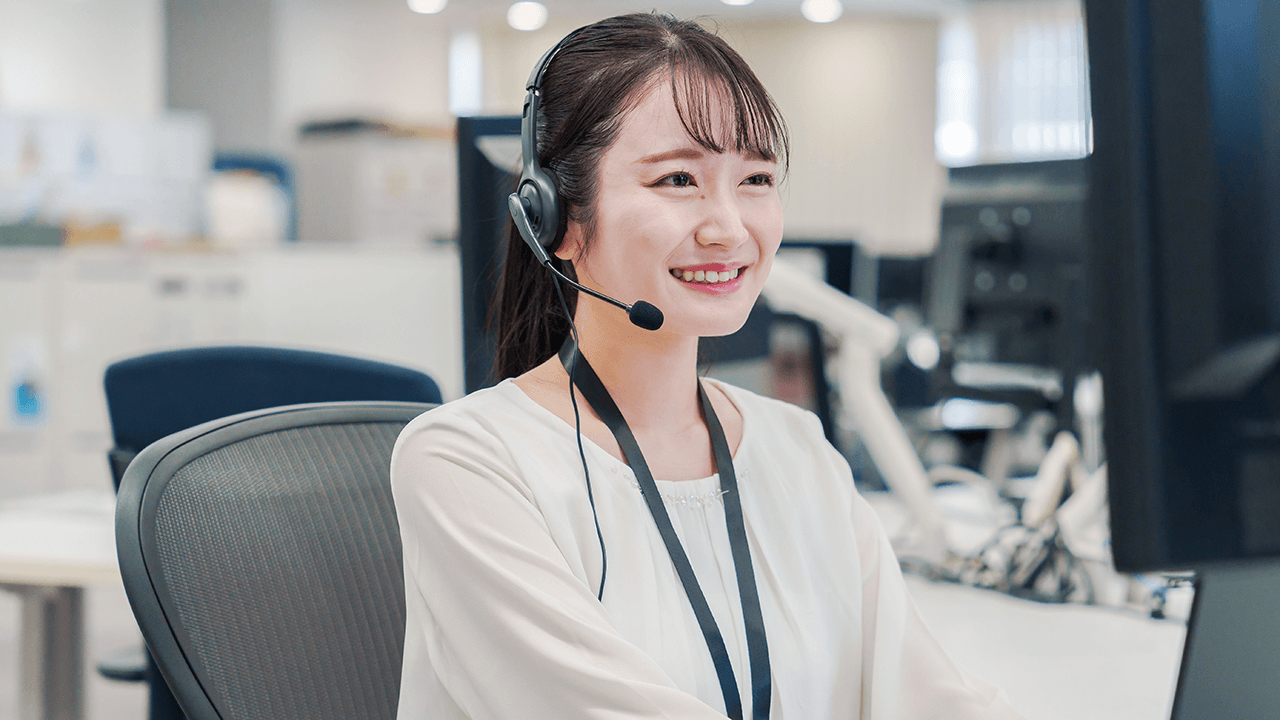
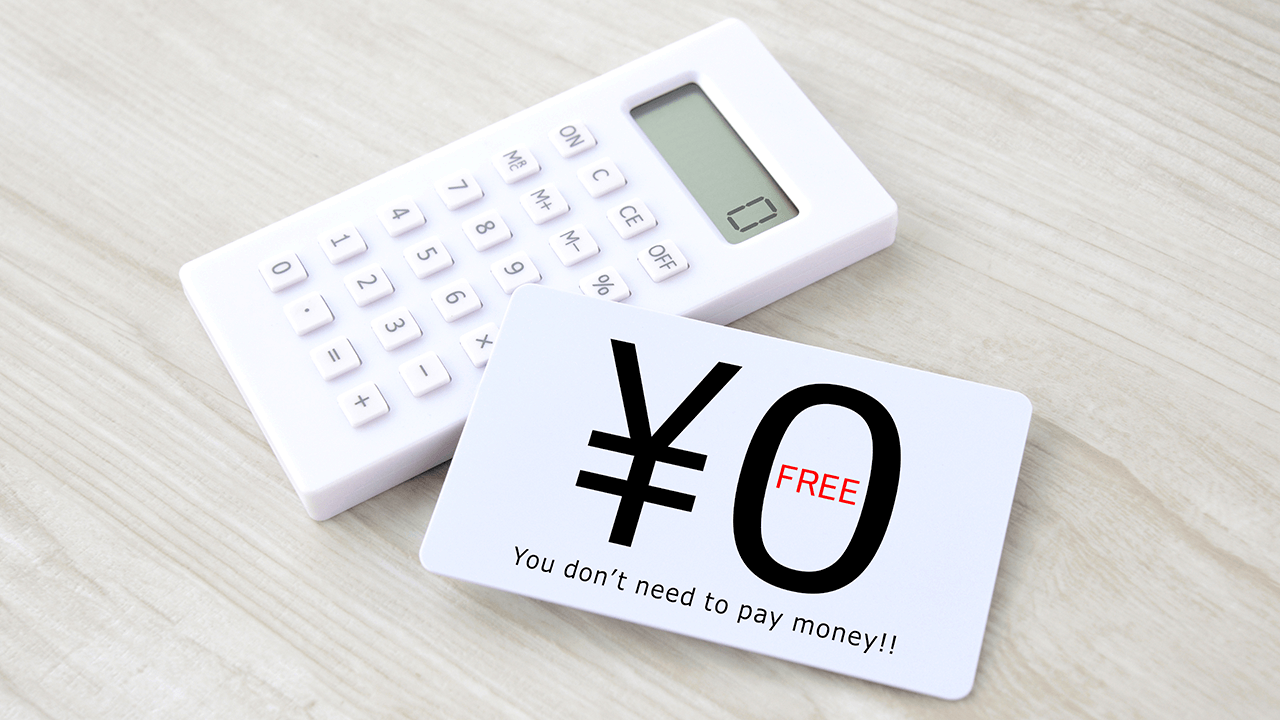
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、許可申請に必要な情報をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④ご契約
申請の進め方にご理解頂きましたら、ご契約を結ばせて頂き、着手金として当社報酬の50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑤申請準備、申請代行
当社で用意する資料、お客様のみがご用意できる資料を収集し、当社より各所申請機関に申請を行います。
⑥お振込み
申請が完了しましたら、当社報酬の残り50%を指定口座にお振込み頂きます。
⑦申請結果
申請先機関からお客様に許可通知が郵送されます。