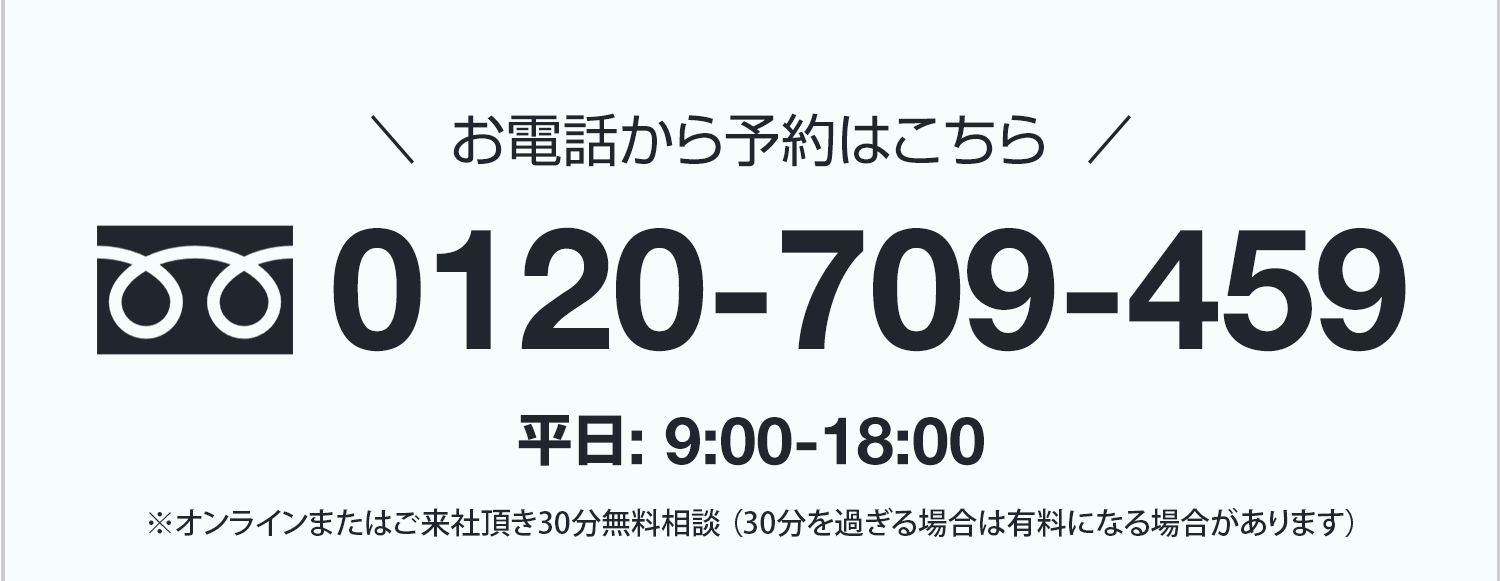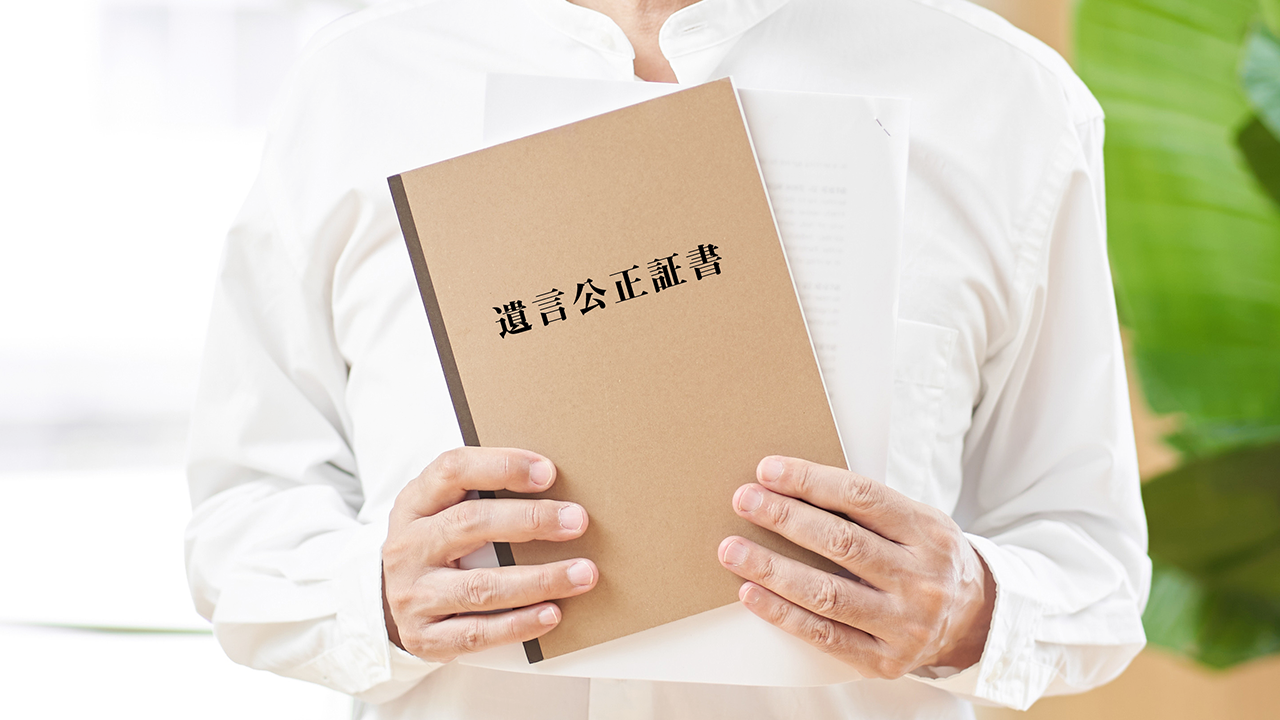
遺言書とは?
言書とは、本人が自分の死後の財産の分け方や身分関係に関する意思を法律的に表明した文書のことです。民法で方式や効力が定められており、遺言者の死亡によって効力が発生します。
遺言書の形式
1. 自筆証書遺言
特徴
費用がかからない: 自分で作成するため、費用はかかりません。
手軽に作成できる: 形式を守れば、いつでもどこでも作成できます。
作成方法
- 全文を自筆で書く: 財産目録を除き、全文を本人が自筆で書く必要があります。パソコンなどで作成したものは無効です。
- 日付を入れる: 〇年〇月〇日と、正確な日付を入れます。
- 名を自署する: 署名します。
- 捺印する: 認印でも構いませんが、実印が望ましいです。
メリット
- 手軽で費用がかからない。
デメリット
- 形式不備で無効になるリスク: 形式を守らないと、法的に無効になることがあります。
- 紛失・偽造のリスク: 保管場所が不明になったり、誰かに偽造・改ざんされたりする可能性があります。
- 検認手続きが必要: 相続開始後、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。
遺言書保管制度
2020年7月から、自筆証書遺言を法務局が保管する制度が始まりました。これにより、紛失や偽造・改ざんのリスクを避けられ、検認手続きも不要になります。
2. 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
特徴
公的な遺言書: 公証役場で公証人が作成するため、最も確実な遺言書です。
費用がかかる: 遺産額などに応じて、手数料がかかります。
作成方法
- 証人2人以上の立ち会い: 証人2人以上の立ち会いの下、公証人が本人から遺言内容を聞き取り、作成します。
- 署名・捺印: 公証人が作成した遺言書の原本に、本人と証人が署名・捺印します。
- 原本を公証役場で保管: 原本が公証役場で保管されるため、紛失の心配がありません。
メリット
- 形式不備のリスクがない: 公証人が作成するため、無効になるリスクがありません。
- 紛失・偽造のリスクがない: 公証役場で保管されるため安心です。
- 検認手続きが不要: 相続開始後の手続きがスムーズです。
デメリット
- 費用と手間がかかる。
- 証人を探す必要がある(公証役場で紹介してもらうことも可能です)。
3. 秘密証書遺言
特徴
内容を秘密にできるが、形式の不備や紛失リスクがあるため、あまり利用されません。
作成方法
本人が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人2人以上の前で提出し、封印します。
遺言書作成の注意点
- 遺留分(いりゅうぶん): 兄弟姉妹以外の相続人には、法律で保障された「遺留分」があります。遺言書でこの分を侵害すると、トラブルになることがあります。
- 日付: 「令和〇年〇月吉日」のような日付は無効です。特定できる日付を記載する必要があります。
- 署名・捺印: 忘れずに行いましょう。
ご自身の最後の意思を伝えるためのものですので、確実に遺言内容が実現出来るよう遺言書作成をサポートいたします。
遺言書作成サービス無料相談の流れ
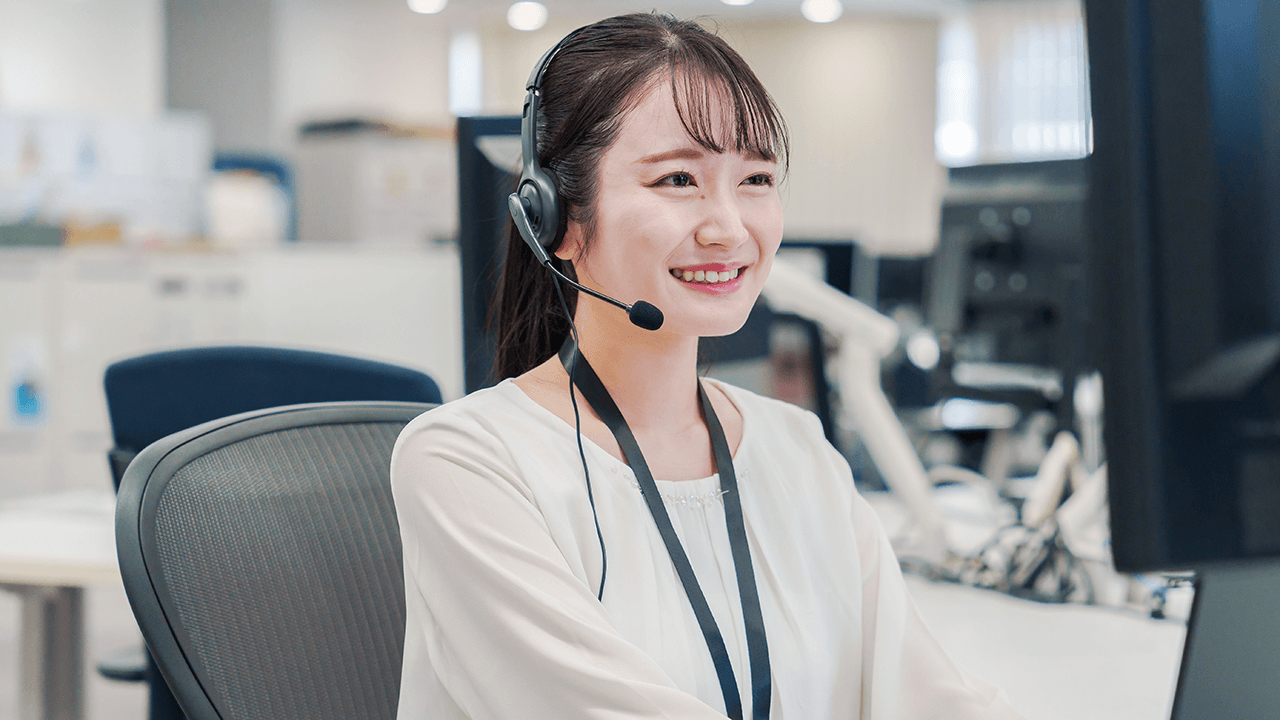
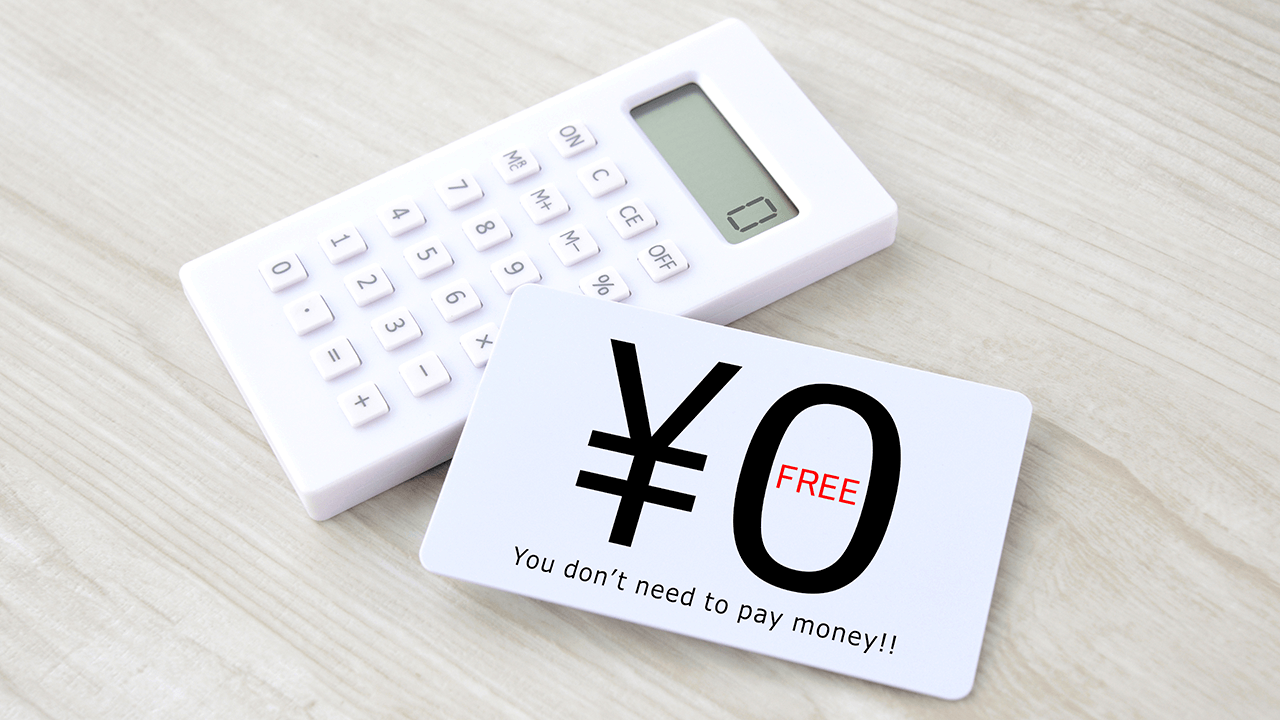
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、お客様にとって必要な手続きを確認させていただきます。
③お見積書の作成
お見積書のと共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④お振込み
手続き費用をお振込みいただきます。
⑤必要書類の準備、作成
各種手続きに必要な書類の準備、必要書類の作成