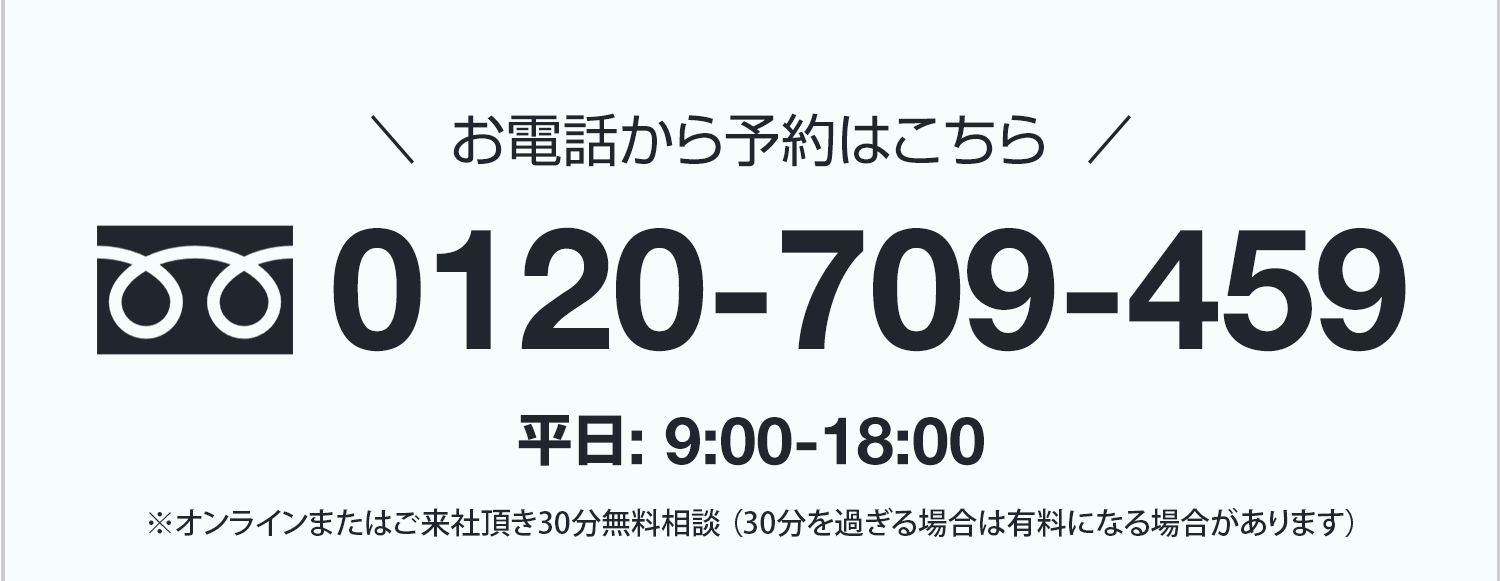会社設立(株式会社・合同会社・一般社団法人・一般財団法人など)
「会社設立」とは、法務局に登記申請を行い、法律上の人格を持つ法人を成立させることを指します。これにより、事業は経営者個人とは切り離された「会社」のものとなり、法律上の権利や義務の主体となることが出来ます。
株式会社
株式会社は、株式を発行して出資者(株主)から資金を募り、事業を行う法人形態です。
設立費用
公証役場での定款認証手数料(資本金100万円未満の場合「3万円」、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」、その他の場合「5万円」)、印紙代「4万円」(電子定款の場合は不要)。登録免許税(資本金の7/100または最低15万円)。設立にかかる費用は比較的高くなります。
運営方法
株主総会が最高意思決定機関となります。株主と経営者が分離しているのが一般的です。
社会的信用度
一般的な法人形態であり、社会的信用度は高いとされます。株式を公開することで、さらに信用を高めることも可能です。
合同会社
合同会社は、出資者全員が有限責任社員となり、会社の所有と経営が一致している法人形態です。
設立費用
定款認証が不要なため、設立にかかる費用は印紙代「4万円」(電子定款の場合は不要)、登録免許税(資本金の7/1000または最低6万円)で、株式会社よりも安価に設立できます。
運営方法
出資者全員が経営に参加することが原則です。柔軟な組織運営が可能で、利益配分も自由に定められます。
社会的信用度
株式会社よりは信用度が低いと見なされることもありますが、近年は設立件数が増加しており、認知度も上がってきています。
一般社団法人
一般社団法人は、人の集まりで非営利を目的とする法人です。
設立費用
登録免許税(6万円)と公証役場での定款認証手数料(約5万円)がかかります。
運営方法
非営利事業を行うことを目的としますが、収益事業を行うことも可能です。ただし、収益は社員に分配できません。
社会的信用度
法人格を持つことで、社会的信用を得やすく、特に学術団体や業界団体などで利用されます。
一般財団法人
一般社団法人は、財産の集まりで非営利を目的とする法人です。
設立費用
登録免許税(6万円)と公証役場での定款認証手数料(約5万円)がかかります。
運営方法
非営利事業を行うことを目的としますが、収益事業を行うことも可能です。ただし、収益は社員に分配できません。
社会的信用度
法人格を持つことで、社会的信用を得やすく、特に奨学金事業、学術・研究助成、社会福祉事業、文化事業などで利用されます。
一般社団法人との違い
一般財団法人と一般社団法人の最も大きな違いは、設立の基盤です。一般社団法人が2人以上の社員(設立者)を必要とする「人の集合」であるのに対し、一般財団法人は「財産の集合」を基盤としています。このため、一般財団法人は社員の概念がなく、運営は評議員や理事、監事が行います。
会社設立の流れ(株式会社)
① 打合せ(会社の基本事項の決定)
↓
② 定款の作成及び登記必要書類の作成
↓
③ 公証役場で定款の認証
↓
④ 法務局に登記の申請
登記が完了することによって法務局で会社の登記事項証明書や印鑑証明書が取得出来るようになります。
必要書類(株式会社:発起人1人で、発起人が取締役に就任)
- 定款
- 払い込みがあったことを証する書面
- 発起人の決定書
- 就任承諾書
- 印鑑証明書
- 印鑑(改印)届出書
- 印鑑カード交付申請書
役員変更
変更登記が必要なケース
以下のケースに該当する場合、役員変更登記を行う必要があります。
- 役員の就任: 新しい役員が選任された場合。
- 役員の辞任: 役員が任期途中で辞任した場合。
- 役員の再任: 任期満了後も同じ役員が継続して務める場合でも、登記が必要です。
- 役員の退任: 任期満了や死亡などにより役員が退任した場合。
- 役員の氏名・住所変更: 役員の結婚による氏名変更や、転居による住所変更があった場合。
登記申請の期限
役員変更登記は、変更が生じた日から2週間以内に申請しなければなりません。この期限を過ぎると、過料(罰金)が科される可能性があるため、注意が必要です。
必要書類(役員変更の内容によって、必要な書類は異なります。)
就任、再任の場合
- 株主総会議事録
- 就任承諾書
- 印鑑証明書又は住民票
- 株主の名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
辞任の場合
- 役員の辞任届
- 辞任する役員の個人の印鑑証明書(法務局に印鑑を登録している代表取締役が辞任する場合)
登録免許税は、資本金が1億円以下の会社で1万円、1億円を超える会社で3万円です。
本店移転
会社の本店は登記事項であるため、本店所在地を変更した際に必要な登記手続きです。
登記の期限と申請先
本店を移転した場合、新しい本店所在地を登記する必要があり、変更が生じた日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。この期限を過ぎると、過料が科される可能性があります。申請手続きは、新本店の所在地によって異なってきます。
同一法務局の管轄内での本店移転
現在の本店所在地を管轄する法務局に、登記申請をします。
この場合の登録免許税は3万円です。
管轄外の法務局への本店移転
移転前の本店所在地を管轄する法務局に、移転前と移転後の両方の法務局宛ての申請書をまとめて提出します。この場合、2つの法務局で手続きが行われるため、同一管轄内での本店移転より登記完了までの時間も費用も多くかかります。
登録免許税は各管轄法務局に対して3万円かかりますので、合計6万円かかります。
- 総会議事録
- 取締役議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面
- 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
目的変更
会社目的とは、会社がどのような事業を行うかを具体的に定めたもので、会社の定款に必ず記載しなければならない事項です。これは単なる事業の紹介ではなく、会社が法的に行える事業活動の範囲を定めたものであり、登記事項となります。
目的変更をした場合、変更が生じた日から2週間以内に登記申請を行わなければなりません。この期限を過ぎると、過料が科される可能性があります。
必要書類
- 株主総会議事録
- 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
登録免許税
3万円
増資・減資
増資の登記とは、会社が資本金を増やす手続き(増資)をした際に、その変更内容を登記することが必要になります。増資には主に以下の種類があります。
増資の種類と登記
募集株式の発行(第三者割当・株主割当)
方 法
新たに株式を発行し、その対価として出資を受け、資本金を増やす方法。
手続き
株主総会の特別決議や取締役会決議を経て、新株の発行内容を決定し、登記申請を行います。
資本準備金の資本組入れ
方 法
会社に積み立てられている資本準備金を資本金に振り替えることで、会社の資本金を増やす方法。新たな出資はありません。
手続き
取締役会(取締役会がない会社は取締役の過半数)の決議で決定します。
剰余金の資本組入れ
方 法
会社に積み立てられている剰余金(利益剰余金など)を資本金に振り替える方法。新たな出資はありません。
手続き
株主総会の普通決議で決定します。
登録免許税
増資した金額×7/1000。計算した金額が3万円に満たない場合には3万円。
資本金の額の減少(減資)
資本金の額の減少の登記は、会社が資本金の額を減少させる手続き(減資)を行った際に、その変更内容を登記することが必要になります。減資には、株主への払戻しを伴う「有償減資」と、資本欠損の補填を目的とする「無償減資」があります。
減資の目的
減資は主に以下の目的で行われます。
- 無償減資(資本欠損の補填): 業績悪化などで累積した赤字(資本欠損)を補填し、財務体質を改善するために行います。資本金を減らすことで、将来の配当が可能になります。
- 有償減資(株主への払戻し): 会社の余剰資金を株主に払い戻すために行います。ただし、これには株主総会の特別決議と債権者保護手続きが必要です。
登記手続きの概要
- 株主総会の特別決議:減資は会社の重要な事項であるため、原則として株主総会の特別決議が必要です。
- 債権者保護手続き:減資は会社の財産を減少させるため、債権者に不利益が生じる可能性があります。そのため、官報への公告や個別の催告を行い、債権者が異議を申し立てる機会を与えなければなりません。この債権者保護手続き期間は最低でも1か月必要となります。
- 効力発生日の到来:債権者保護手続きが完了し、減資の効力発生日に効力が生じます。
必要書類
- 株主総会議事録
- 官報及び催告をしたことを証する書面
- 株主の氏名又は名称、住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
登録免許税
減資による変更登記1件につき3万円です。
組織再編(合併・会社分割・株式移転)
合併
合併は、複数の会社が法的に一つになる組織再編の手法です。これにより、会社の事業や資産、負債、権利義務が包括的に承継されます。合併には、大きく分けて以下の2つの種類があります。
吸収合併
1つの会社(存続会社)が他の会社(消滅会社)を吸収し、存続会社のみが存続する合併方法です。消滅会社は解散し、そのすべての権利義務は存続会社に引き継がれます。
例: 企業Aが企業Bを吸収し、企業Bは消滅し、企業Aとして事業を継続する。
新設合併
複数の会社が共同で、新しい会社を設立する合併方法です。合併する全ての会社(消滅会社)は解散し、その権利義務は新設会社に引き継がれます。
例: 企業Aと企業Bが合併して、新たに企業Cを設立する。企業Aと企業Bは解散し、企業Cとして事業を継続する。
合併の一般的な手続き
- 1. 合併契約の締結: 合併する会社間で合併契約を締結し、合併の条件(合併比率、効力発生日など)を定めます。
- 2. 事前開示書類の備置: 株主や債権者が合併の内容を把握できるよう、合併契約書な どの書類を本店に備え置きます。
- 3. 株主総会での承認: 合併契約について、各社の株主総会で特別決議(原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成)による承認を得ます。
- 4. 債権者保護手続き: 合併に異議のある債権者は、会社に対して異議を申し立てることができます。会社は、官報公告や個別催告などにより、合併の事実を債権者に通知します。
- 5. 合併の効力発生: 合併契約で定めた日に合併の効力が発生します。
- 6. 登記: 合併の効力発生日から2週間以内に、法務局で変更登記(吸収合併)または設立・解散登記(新設合併)を行います。
債権者保護手続きの公告期間が最低でも1か月は必要になるため、手続き開始から合併の日(効力発生日)までに時間を要します。手続きに漏れがないように余裕をもって計画する必要があります。
会社分割
会社分割は、会社が特定の事業に関する権利義務を、他の会社に承継させる組織再編の手法です。これにより、会社は事業を切り離したり、独立させたりすることができます。
会社分割には、以下の2つの主な種類があります。
吸収分割
会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、既存の他の会社に承継させる手法です。
例: 企業Aが、自社のIT事業を既存の企業Bに承継させる。
新設分割
会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、新たに設立する会社に承継させる手法です。
例: 企業Aが、自社の新規事業部門を切り離し、新たに設立した企業Cに承継させる。
会社分割の対価
会社分割の対価として、事業を承継する会社から、事業を承継させた会社(分割会社)またはその株主に対して、株式や金銭などが交付されます。
分社型分割
分割の対価が分割会社に交付される場合です。分割会社の資産構成が変化するだけで、株主の構成は変わりません。
分割型分割
分割の対価が分割会社の株主に交付される場合です。株主は、元の会社(分割会社)の株式に加えて、新たに承継会社の株式などを取得することになります。
会社分割の一般的な手続き
- 1. 会社分割計画書または会社分割契約書の作成: 分割の詳細(承継する事業、対価など)を定めた計画書または契約書を作成します。
- 2. 事前開示書類の備置: 株主や債権者が分割の内容を把握できるよう、計画書などの書類を本店に備え置きます。
- 3. 株主総会での承認: 分割計画または契約について、各社の株主総会で特別決議による承認を得ます。
- 4. 債権者保護手続き: 分割に異議のある債権者は、会社に対して異議を申し立てることができます。会社は、官報公告や個別催告などにより、分割の事実を債権者に通知します。
- 5. 会社分割の効力発生: 計画書または契約書で定めた日に、会社分割の効力が発生します。
- 6. 登記: 効力発生日から2週間以内に、法務局で登記を行います。吸収分割の場合は変更登記、新設分割の場合は設立登記と変更登記が必要です。
債権者保護手続きの公告期間が最低でも1か月は必要になるため、手続き開始から会社分割の日(効力発生日)までに時間を要します。手続きに漏れがないように余裕をもって計画する必要があります。
株式移転
株式移転は、1つ以上の会社が発行済み株式のすべてを、新たに設立する会社に取得させ、完全な親子会社関係を構築する組織再編の手法です。これにより、既存の会社は新しく設立された会社の完全子会社となり、既存の会社の株主は新設会社の株式を受け取って完全親会社の株主となります。
会社分割の一般的な手続き
- 1. 株式移転計画の作成: 株式移転によって設立する親会社の商号や本店の所在地、発行する株式の総数などを定めた計画書を作成します。
- 2. 株主総会での承認: 株式移転の計画について、各社の株主総会で特別決議(原則として議決権の過半数を持つ株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成)による承認を得ます。
- 3. 債権者保護手続き: 株式移転によって資本金が減少するなど、債権者に影響がある場合は、債権者保護手続きが必要です。
- 4. 登記: 株式移転の効力発生日(新設会社の設立登記日)から2週間以内に、法務局で新設会社の設立登記を行います。
債権者保護手続きの公告期間が最低でも1か月は必要になるため、手続き開始から株式移転の日(効力発生日)までに時間を要します。手続きに漏れがないように余裕をもって計画する必要があります。
株式交付
株式交付は、会社が他の会社を子会社にする目的で、その会社の株式を取得し、その対価として自社の株式を交付する組織再編の手法です
株式交付と株式交換・株式移転との違い
株式交付では、必ずしも対象会社の議決権のすべてを取得する必要はなく、3分の2超(特別決議を単独で否決できる議決権)を保有し、子会社化することが目的です。一方、株式交換と株式移転は、完全子会社化(議決権の100%取得)を目的としています。
株式交付の一般的な手続き
- 1. 株式交付計画の作成: 株式交付を行う会社は、取得する株式の種類や数、交付する自社株式の数などを定めた計画書を作成します。
- 2. 株主総会での承認: 株式交付計画について、原則として、親会社となる会社の株主総会で特別決議による承認を得ます。
- 3. 効力発生: 計画書で定めた日に株式交付の効力が発生します。
- 4. 登記: 株式交付によって資本金が増加する場合、効力発生日から2週間以内に法務局で変更登記を行います。
解散・清算結了
解散
解散登記とは、会社が事業活動を停止し、清算手続きに入る手続きです。取締役は退任し、代わりに清算人が選任されて会社の清算事務を行います。
清算結了
解散登記後、清算人が清算事務を完了させ、最後に清算結了登記を行うことで、会社の法人格が消滅します。
1. 株主総会の決議による解散
株主総会の特別決議(議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。この決議により、会社の事業活動を停止することが決定されます。
2. その他の解散事由
株主総会の決議以外にも、以下のような法定事由によって会社は解散します。
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた解散事由の発生
- 合併による消滅
- 破産手続き開始の決定
- 裁判所の解散命令または解散判決
- 休眠会社のみなし解散 (最後の登記から12年以上経過した場合など)
解散後の手続き
解散した会社は直ちに消滅するわけではありません。解散後は、会社財産を整理・清算する手続きに移行します。
1. 清算人の選任
会社は解散と同時に清算人を選任します。通常は、定款で定めた者、または取締役が清算人となりますが、株主総会で選任することも可能です。清算人は、会社の財産を管理し、清算事務を行います。
2. 解散および清算人選任の登記
解散決議後、2週間以内に法務局で解散の登記と清算人選任の登記を同時に行います。
3. 官報公告と債権者への催告
清算人は、会社の債権者に対して、債権を申し出るよう官報に公告し、知れている債権者には個別に催告を行います。この期間は2ヶ月以上です。
4. 会社財産の換価と弁済
清算人は会社の資産を現金化し(換価)、債務を弁済します。全ての債務を支払った後、残った財産があれば、株主へ分配します。
5. 清算結了の登記
清算事務が全て完了したら、株主総会で決算報告書の承認を得て、清算結了の登記を行います。この登記によって、会社の法人格が正式に消滅します。
商業・法人登記サービス無料相談の流れ
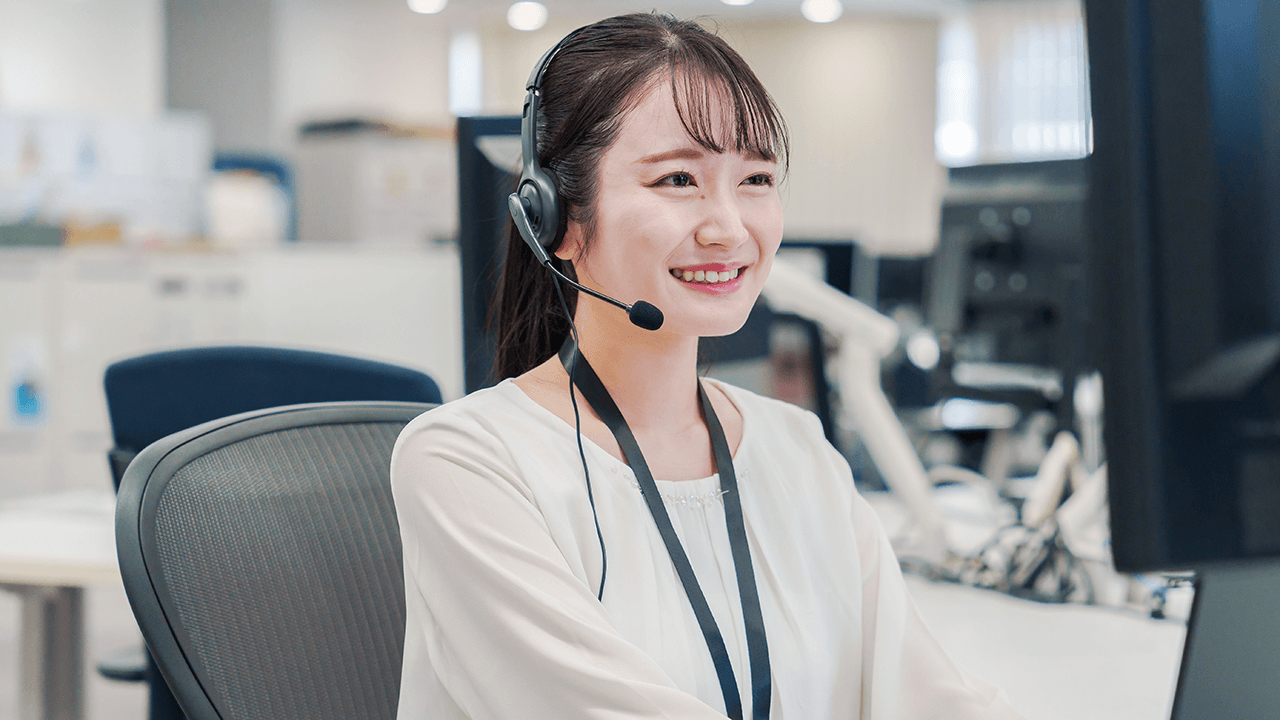
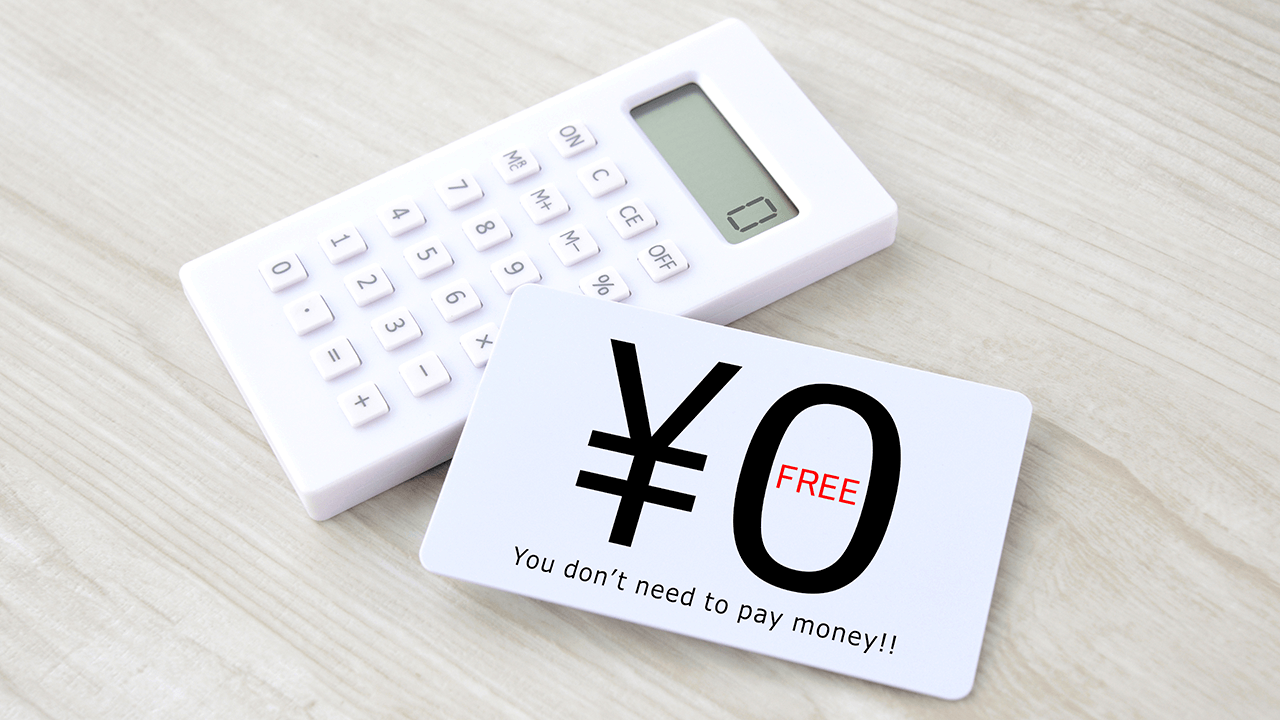
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、登記の要否、登記申請に必要な書類をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④必要書類の準備と登記申請書の準備
必要書類のお預かりと登記必要書類へのご署名・ご捺印、ご本人様確認と意思確認
⑤お振込み
登記費用をお振込み頂きます。
⑥登記申請
法務局へ登記の申請
※登記完了まで日数がかかります。詳細は管轄法務局の完了予定日をご参照下さい。
⑦書類のご返却
登記完了後、法務局から書類の返却があります。返却書類と登記完了後の登記事項証明書をお客様へご返却致します。