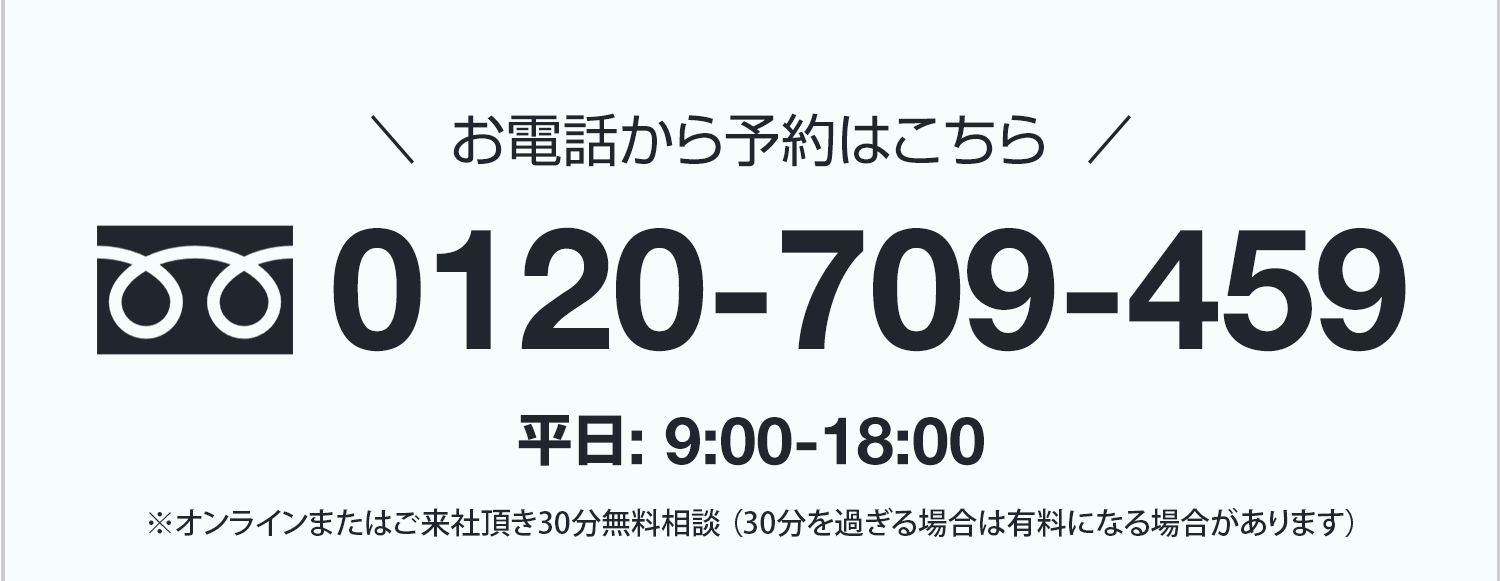後見人とは?
後見人とは、病気や障害などで判断能力が不十分な人のために、財産管理や契約などの法律行為を代わりに行います。後見人制度には、本人の判断能力の程度に応じて、いくつかの種類があります。
法定後見制度
本人の判断能力がすでに不十分な場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。本人の判断能力の程度によって、以下の3つの類型に分けられます。
後見
本人の判断能力がほとんどない場合に利用されます。後見人は、本人の財産管理や法律行為を包括的に代理します。また、本人が行った不利益な契約などは、後見人が取り消すことができます。
保佐
本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用されます。保佐人は、本人が特定の重要な法律行為(不動産の売買、遺産分割など)を行う際に、同意を与える役割を担います。
補助
本人の判断能力が不十分な場合に利用されます。補助人は、本人が単独で行うことが不安な特定の法律行為について、同意を与えたり、代理したりします。
後見人の役割と責任
後見人は、本人の財産管理(預貯金の管理、不動産の売買など)や身上保護(福祉サービスの契約、医療に関する手続きなど)を代行します。ただし、後見人は本人の意思を尊重し、本人の心身の状態や生活状況に配慮することが義務付けられています。
リーガルサポート
「リーガルサポート」とは、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートのことで、成年後見制度を専門的に担う司法書士によって設立された団体です。
リーガルサポートの主な目的と活動
- 成年後見制度の支援と普及: 高齢者や障がい者の権利擁護と福祉の増進を目的として、成年後見制度の利用を支援しています。
- 専門職後見人の養成と供給: 研修を通じて、財産管理や福祉に関する知識を身につけた司法書士を成年後見人として養成しています。そして、家庭裁判所に後見人候補者名簿を提出することで、身近に後見人となる人がいない場合に、専門家である司法書士が後見人に就任する機会を提供しています。
- 相談業務: 成年後見制度に関する相談に応じています。無料の電話相談や面談相談を行っている支部もあります。
- 司法書士会員の監督と支援: 会員である司法書士が適正に後見業務を行えるよう、指導や支援を行っています。これにより、万が一会員が不誠実な行為を行った場合でも、本人への損害を補てんする仕組みを設けています。
リーガルサポートの役割
リーガルサポートは、市民が安心して成年後見制度を利用できるように、高い専門性を持つ司法書士を後見人として供給し、その活動をバックアップする重要な役割を担っています。
成年後見制度の利用を検討している場合、リーガルサポートの各支部や、リーガルサポートに所属する司法書士に相談することで、手続きや後見人について具体的なアドバイスを受けることができます。
成年後見申立支援
後見申立てとは、家庭裁判所に対して、精神上の障害により判断能力が不十分となった人(本人)のために、成年後見人などの援助者を選任してもらうよう求める手続きです。後見申立ては集める資料も多くなりますので、当方で申し立てのサポートをさせていただきます。
申立ての流れ、必要書類
申立書類の準備
家庭裁判所から申立書や添付書類のひな形を入手し、記入します。主な書類は以下の通りです。
申立書
申立人、本人、後見人候補者などの情報を記載します。
本人の戸籍謄本、住民票、診断書
本人の身分や判断能力の状態を証明します。
財産に関する資料
扱いやすい預金通帳のコピーや、不動産の登記簿謄本など、本人の財産状況がわかる書類を揃えます。
家庭裁判所への提出
必要書類を揃えたら、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
調査・審理
裁判所の調査官が、申立人や本人、後見人候補者などから事情を聴取したり、本人の親族に後見人候補者に対する意見を照会したりします。
鑑定
裁判所の判断で、本人の判断能力について医学的な鑑定を行う場合があります。
審判
調査や鑑定の結果に基づき、裁判官が後見人を選任する旨の審判(決定)を下します。
登記
審判確定後、裁判所が東京法務局に後見登記を嘱託します。この登記により、後見人が正式に就任したことが公的に証明されます。
申立てができる人
後見申立ては、誰でもできるわけではなく、申立てができる人が法律で定められています。
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族(子、孫、ひ孫、親、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、甥、姪、叔父、叔母など)
- 市区町村長(身寄りのない高齢者などの場合)
- 検察官
任意後見契約
任意後見契約は、本人が将来的に判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、財産の管理や生活上の手続きを任せるための契約です。
任意後見契約の特徴
任意後見契約は、法定後見制度とは異なり、本人の意思に基づいて事前に準備できる点が大きな特徴です。
- 本人の意思を反映: 誰にどのようなことを任せるか、本人が自由に決めることができます。
- 家庭裁判所の関与: 契約は、公正証書で作成することが義務付けられています。また、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の仕事を監督します。
- 効力発生時期: 契約を結んだ時点では効力は発生しません。本人の判断能力が不十分になったと家庭裁判所が認めたときに、任意後見監督人が選任され、契約の効力が生じます。
任意後見契約で定められる主な内容
契約書(公正証書)には、以下の内容を記載するのが一般的です。
- 任意後見人の氏名と住所: 誰に代理を任せるかを明記します。
- 代理権の範囲: 任意後見人にどのような権限を与えるかを具体的に定めます。例えば、「預貯金の管理」「不動産の売買」「介護サービスの契約」などです。
- 任意後見人の報酬: 報酬の有無や金額を定めます。
任意後見契約のメリット・デメリット
メリット
- 本人の希望が叶う: 信頼できる人に、自分の望む形で財産管理などを任せられます。
- スムーズな移行: 判断能力が低下した際に、速やかに支援を開始できます。
デメリット
- 家庭裁判所の監督: 任意後見監督人が選任されるまでは、本人の判断能力が低下しても、代理権の行使ができません。
- 契約の有効性: 公正証書で作成する必要があるため、費用と手間がかかります。
財産管理契約
財産管理契約とは、本人の財産管理や、生活上の手続きを、信頼できる第三者に任せるための契約です。認知症などで判断能力が不十分になった場合に備える任意後見契約と似ていますが、効力が生じる時期が異なります。
財産管理契約と任意後見契約の違い
| 項目 | 財産管理契約 | 任意後見契約 |
|---|---|---|
| 効力発生時期 | 契約締結後、すぐに効力が発生 | 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時点 |
| 契約の目的 | 判断能力がある間の財産管理・身上保護 | 将来、判断能力が低下した後の財産管理・身上保護 |
| 監督者 | 原則として監督者なし | 任意後見監督人が家庭裁判所から選任され監督する |
財産管理契約は、本人が判断能力を失うと効力を失うため、任意後見契約とセットで締結されることが多いです。
財産管理契約でできること
- 財産管理: 銀行との取引、預金の出し入れ、不動産の管理、家賃や税金の支払いなど。
- 生活上の手続き: 病院や介護施設の利用契約、入院手続き、福祉サービスの利用手続きなど。
財産管理契約の注意点
- 本人の意思能力: 契約を結ぶには、本人が契約内容を理解し、判断できる能力が必要です。
- 委任事務の範囲: 契約でどこまでの権限を与えるか、明確に定めておく必要があります。
- 受任者の選び方: 信頼できる第三者(家族、親族、専門家など)に依頼することが重要です。
財産管理契約は、任意後見契約と組み合わせることで、本人の判断能力の有無にかかわらず、切れ目なく支援を受けることができます。そのため、両方の契約を同一人物と結び、公正証書として作成するケースが一般的です。
後見人サービス無料相談の流れ
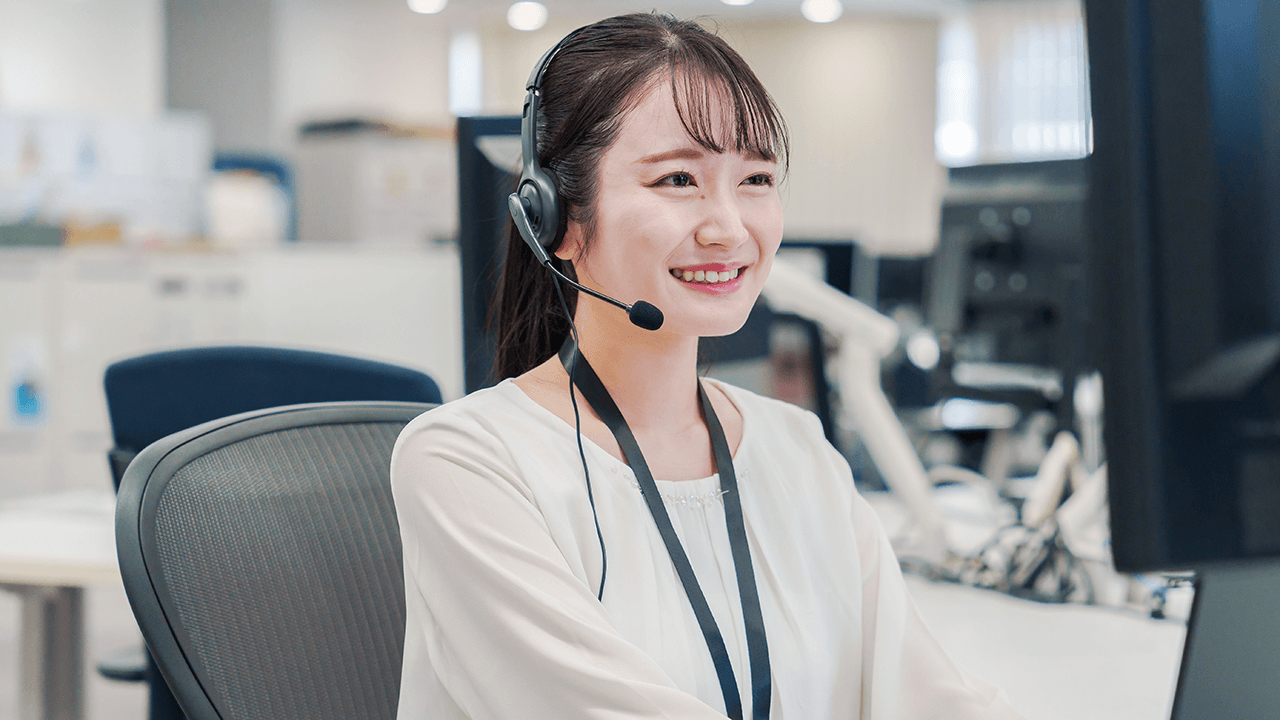
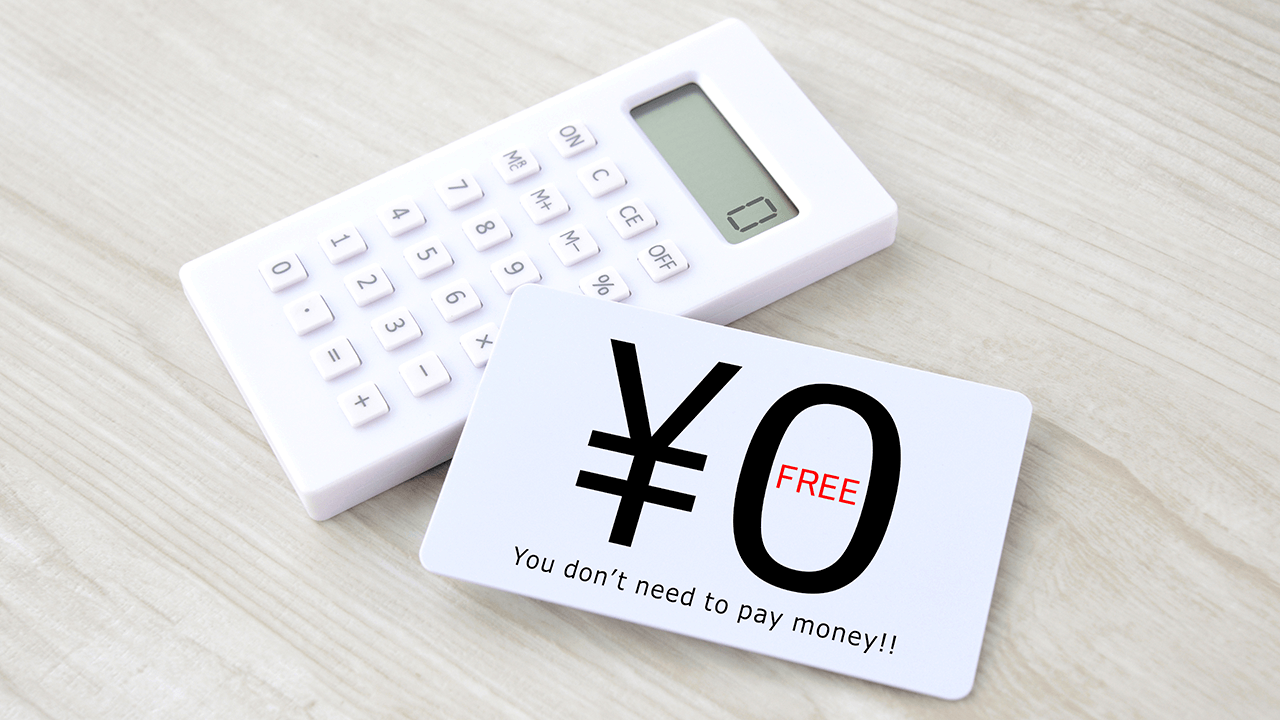
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、お客様にとって必要な手続きを確認させていただきます。
③お見積書の作成
お見積書のと共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④お振込み
手続き費用をお振込みいただきます。
⑤必要書類の準備、作成
各種手続きに必要な書類の準備、必要書類の作成