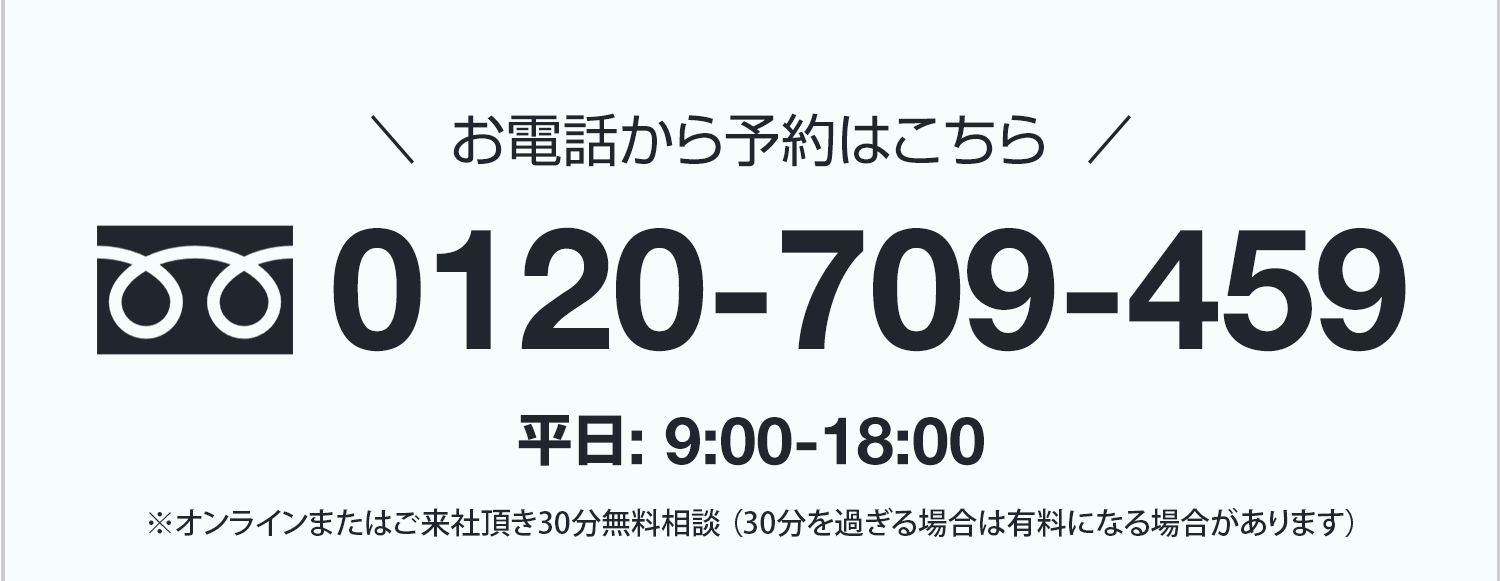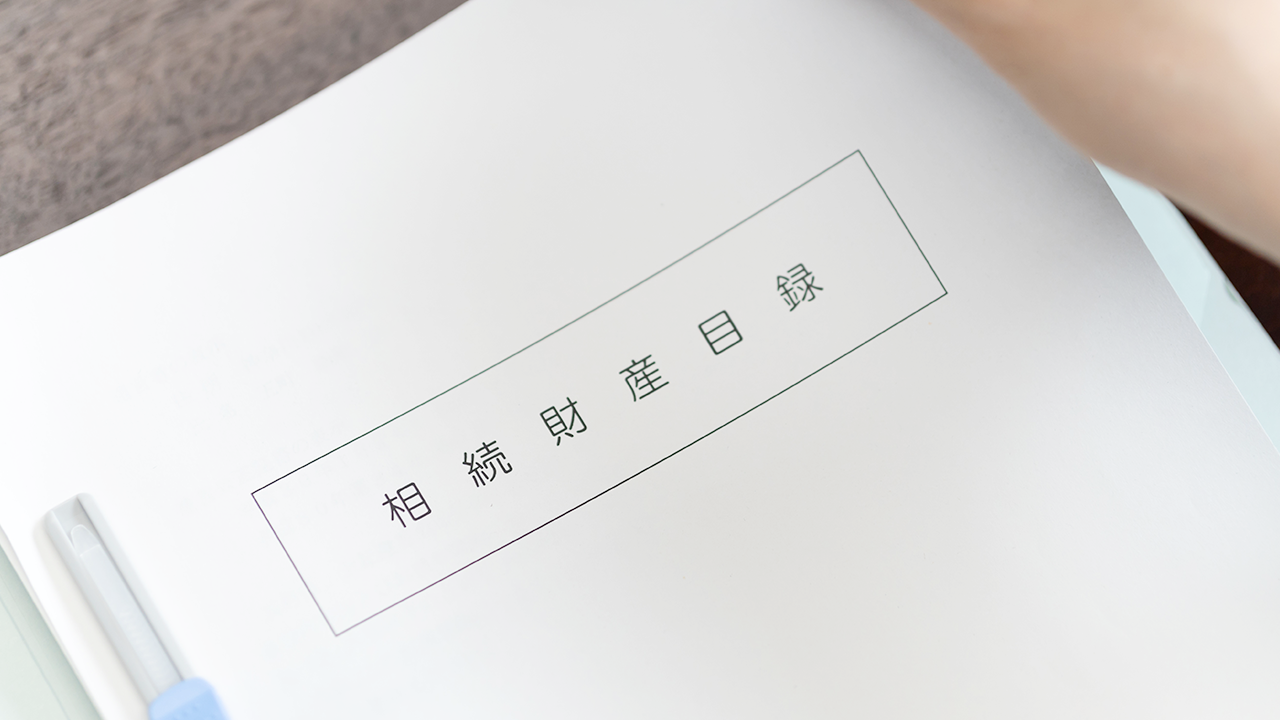
不動産の名義変更(相続登記)※相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(故人)名義の不動産を相続人名義に変更する手続きのことです。
義務化により、不動産取得を知った日から3年以内に相続登記を行わなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
義務化された理由は、所有者不明の土地の発生を防止するためです。所有者不明の土地は、所有者の探索に多大な時間と費用が必要であったり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されず放置され、隣接する土地への悪影響が発生したりするなど、様々な問題が生じています。
不動産の名義変更(相続登記)
相続が発生すると被相続人の権利は法律で定められた相続割合で相続人に承継されます。その為相続登記においては、被相続人の相続人を確定させることが必要になり、集める書類の量が他の登記と比べると多くなります。
また、相続手続きにおいて遺産分割協議書を作成して手続きをすることが一般的ですが、不動産については遺産分割協議が成立したからといって常に協議の結果を第三者に対抗できるわけではありません。第三者に遺産分割協議の内容を主張するには、やはり登記が必要になってきます。つまり、遺産分割協議が成立したのであれば、自分の権利を守るために速やかに登記をするべきです。
例:夫が死亡、相続人は妻と子供2人/遺産分割協議
一般的な必要書類
- 被相続人(夫)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人(夫)の死亡時の住所記載の徐住民票又は戸籍の附票
- 各相続人(妻と子供2人)の戸籍
- 遺産分割協議書
- 各相続人(妻と子供2人)の印鑑証明書
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 名寄帳、個体資産評価証明書など
登録免許税
不動産の価格×4/1000
例:夫が死亡、妻に全財産を相続させる旨記載ある遺言書がある場合)
一般的な必要書類
- 遺言公正証書 ※自筆証書遺言の場合には検認が必要
- 被相続人(夫)の死亡の記載のある戸籍
- 被相続人(夫)の死亡時の住所記載の徐住民票又は戸籍の附票
- 相続人(妻)の戸籍謄本及び住民票
- 名寄帳、固定資産評価証明書など
登録免許税
不動産の価格×4/1000
法定相続情報証明の作成
法定相続情報証明制度とは
相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸籍謄本等の必要書類一式を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを交付してもらう制度です。
法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に利用できるため、本制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
さらに、法定相続情報一覧図の写しを利用できる手続は、相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など、様々なものがあり、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。
例:夫が死亡、相続人は妻と子供2人
一般的な必要書類
- 被相続人(夫)の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人(夫)の死亡時の住所記載の徐住民票又は戸籍の附票
- 各相続人(妻と子供2人)の戸籍
- 各相続人(妻と子供2人)の住民票
- 申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類
遺産分割協議書作成
相続が発生した場合の相続分の割合は民法に規定されています。しかし、相続人全員で合意をすれば法定相続分と異なる割合で遺産を分けることができます。遺産分割協議書とは、この合意した内容をまとめた書類です。この書面を作成することで、後の相続手続きが円滑に進みトラブルを防ぐことができます。
預貯金・有価証券の払い戻しなどの遺産承継業務
遺産承継業務とは、相続人から依頼を受け、被相続人(故人)の不動産や預貯金、株式などを相続人へ承継させる手続きを相続人の代理人として行う業務のことです。司法書士は司法書士法施行規則第31条などで法令を根拠に業務として行えます。
遺産承継業務の主な内容
- 相続人確定のための調査(戸籍・住民票の収集など)
- 相続財産の調査
- 残高証明書などの取得、預貯金、株式、有価証券の名義変更、解約
- 不動産登記、商業登記
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税申告や年金手続きはストラーダグループの別法人で対応いたします。
相続手続きサービス無料相談の流れ
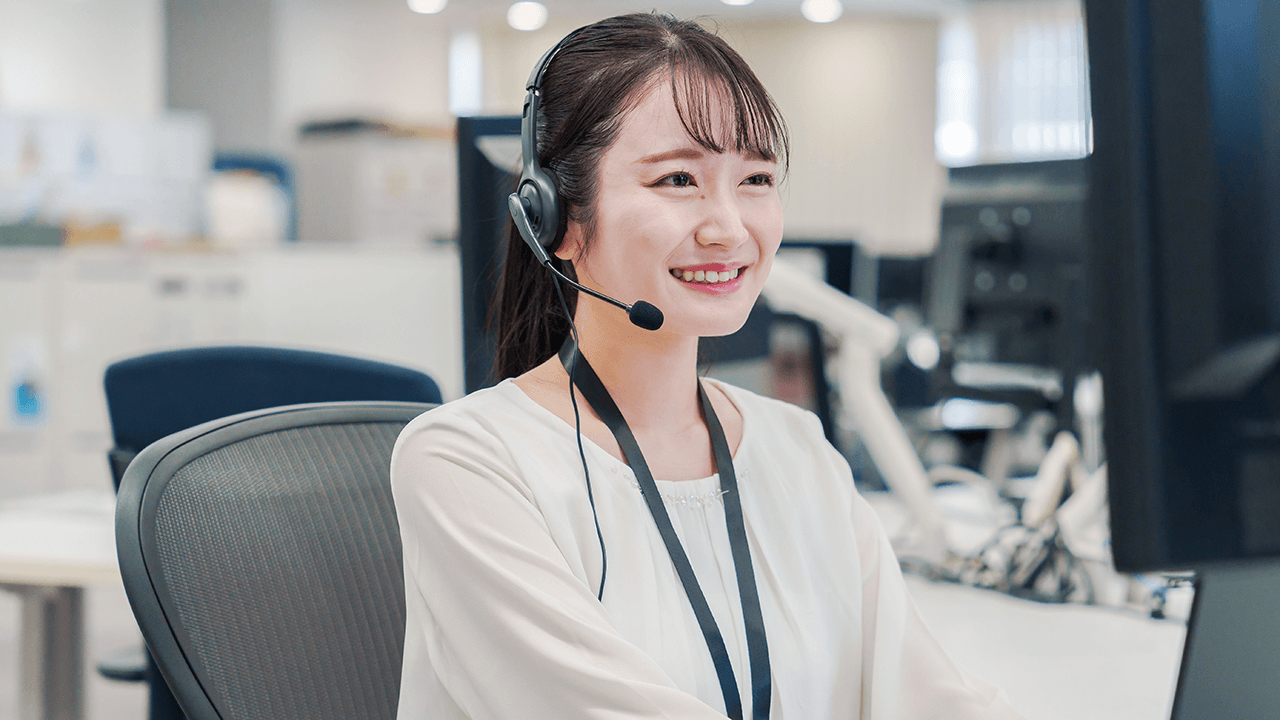
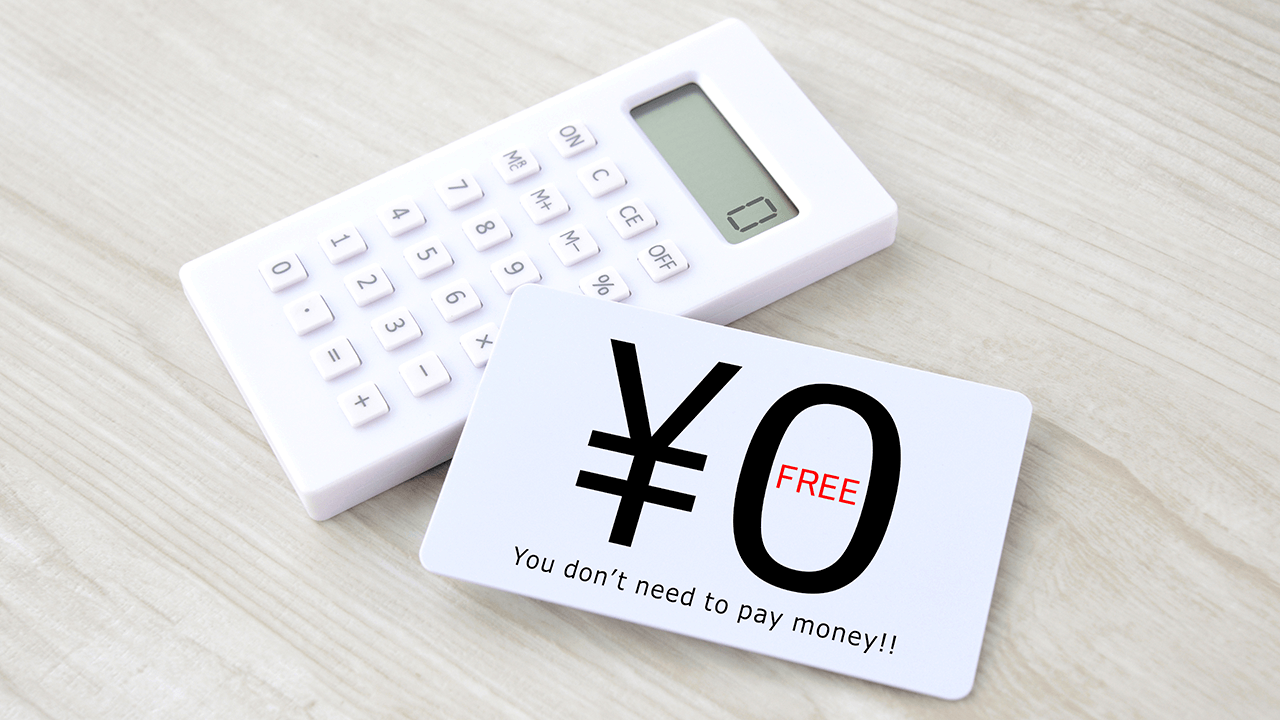
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、登記の要否、登記申請に必要な書類をご共有頂きます。
③お見積書のご共有
お見積書と共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④必要書類の準備と登記申請書の準備
必要書類のお預かりと登記必要書類へのご署名・ご捺印、ご本人様確認と意思確認
⑤お振込み
登記費用をお振込み頂きます。
⑥登記申請
法務局へ登記の申請
※登記完了まで日数がかかります。詳細は管轄法務局の完了予定日をご参照下さい。
⑦書類のご返却
登記完了後、法務局から書類の返却があります。返却書類と登記完了後の登記事項証明書をお客様へご返却致します。