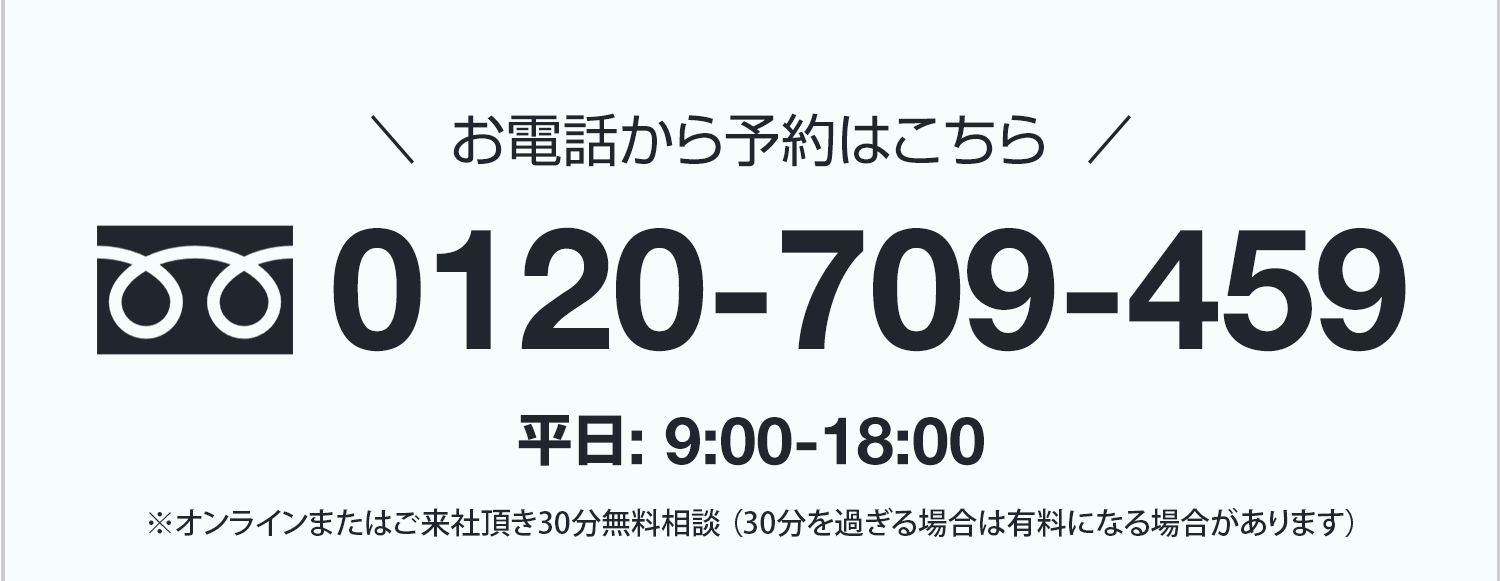遺言書の検認
遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の存在と状態を確認する手続きです。これは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、相続人全員に遺言書の存在を知らせることを目的としています。
検認が必要な理由
家庭裁判所の関与なしに遺言書が開封・発見された場合、相続人にとって不利な内容が記載されていたとしても、遺言書自体が偽造・変造された可能性があるため、その有効性について紛争に発展するリスクがあります。検認手続きは、遺言書が発見された時点の状態を裁判所に記録することで、将来的なトラブルを未然に防ぎます。
検認が必要な遺言書
以下の遺言書は、原則として相続開始後に検認が必要です。
- 自筆証書遺言(法務局に保管されていたものを除く)
- 秘密証書遺言
検認が不要な遺言書
以下の遺言書は、すでに公的な手続きを経ており、偽造・変造の恐れがないため、検認は不要です。
- 公正証書遺言
- 法務局に保管されていた自筆証書遺言
検認手続きの流れ
1. 申立て: 遺言書の保管者または発見者が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認を申し立てます。
2. 必要書類の提出: 申立書に加えて、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本などを提出します。
3. 検認期日: 家庭裁判所が指定した日時に、申立人や他の相続人が立ち会い、裁判官が遺言書を確認します。
4. 開封: 封印された遺言書は、この検認期日で裁判官が開封します。封印を勝手に破ると5万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
5. 検認済証明書: 検認が終わると、裁判所は遺言書に「検認済証明書」を添付します。この証明書がなければ、不動産の相続登記や預貯金の名義変更などの手続きができません。
注意事項
- 検認は、あくまで遺言書の形式的な確認であり、その内容の有効性(効力)を保証するものではありません。
- 検認手続きを怠り、勝手に開封してしまった場合でも、遺言書自体が無効になるわけではありませんが、過料の対象となります。
- 遺言書を偽造・変造した場合は、相続欠格事由に該当し、相続権を失う可能性があります。
相続放棄
相続放棄の申立ては、被相続人(亡くなった人)の財産(借金を含む)を一切引き継がないために、家庭裁判所に行う手続きです。
1. 相続放棄の期限
相続放棄は、相続人が自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。この3か月の期間を「熟慮期間」と呼びます。
2. 相続放棄の申立て方法
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書を提出して行います。
必要書類(一般的なもの)
- 相続放棄申述書: 家庭裁判所から入手します。
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票: 被相続人の死亡時の住所を証明します。
- 申述人の戸籍謄本: 申述人が相続人であることを証明します。
- 被相続人の戸籍謄本: 相続関係を証明するために、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。
3. 相続放棄の効果
- 相続放棄が家庭裁判所に受理されると、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
- 被相続人のすべての財産(プラスの財産、マイナスの財産)を相続しないことになります。
- 相続放棄は、放棄した相続人一人ひとりで個別に行う必要があります。他の相続人の同意は不要です。
4. 熟慮期間の延長
3か月の熟慮期間では判断が難しい場合、家庭裁判所に期間の延長を申立てることができます。延長期間は通常3か月程度です。
5. 相続放棄の注意点
- 一度受理された相続放棄は、原則として撤回できません。
- 相続財産を処分したり、一部でも使用したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。例えば、被相続人の預貯金を使って葬儀費用を支払う場合でも、その使途や金額によっては単純承認とみなされる可能性があるため、注意が必要です。
家庭裁判所の手続支援サービス無料相談の流れ
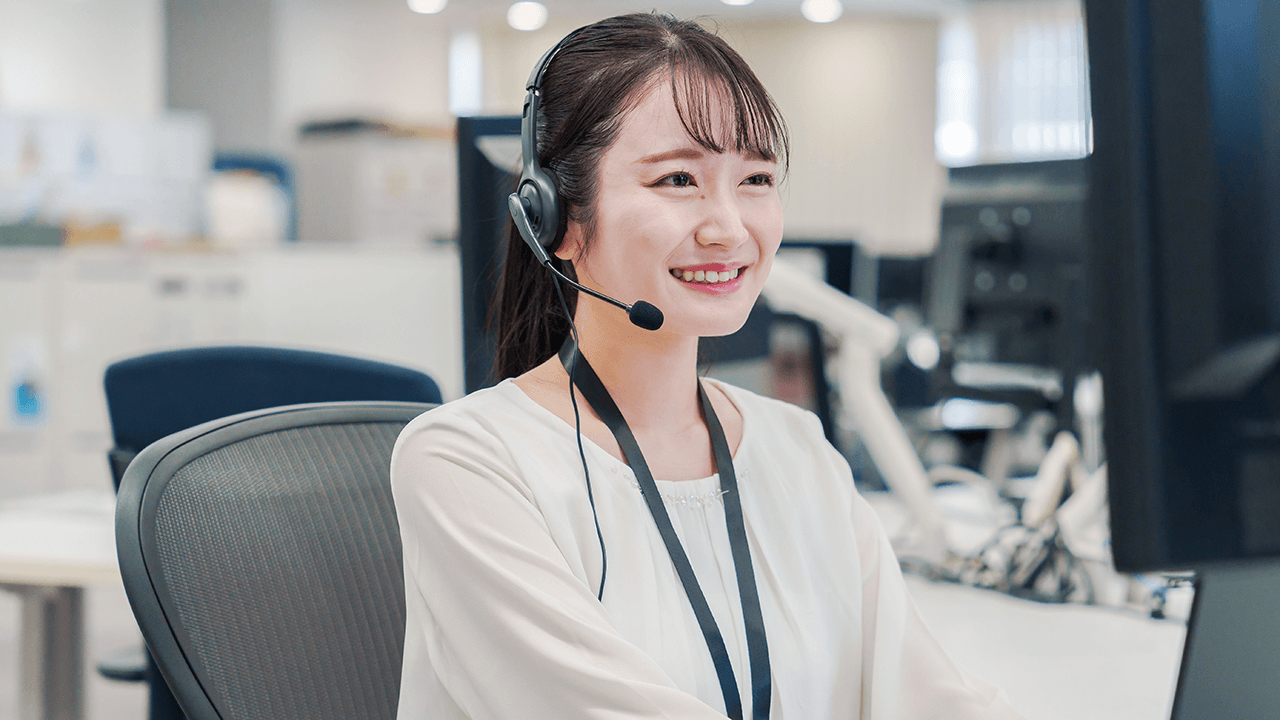
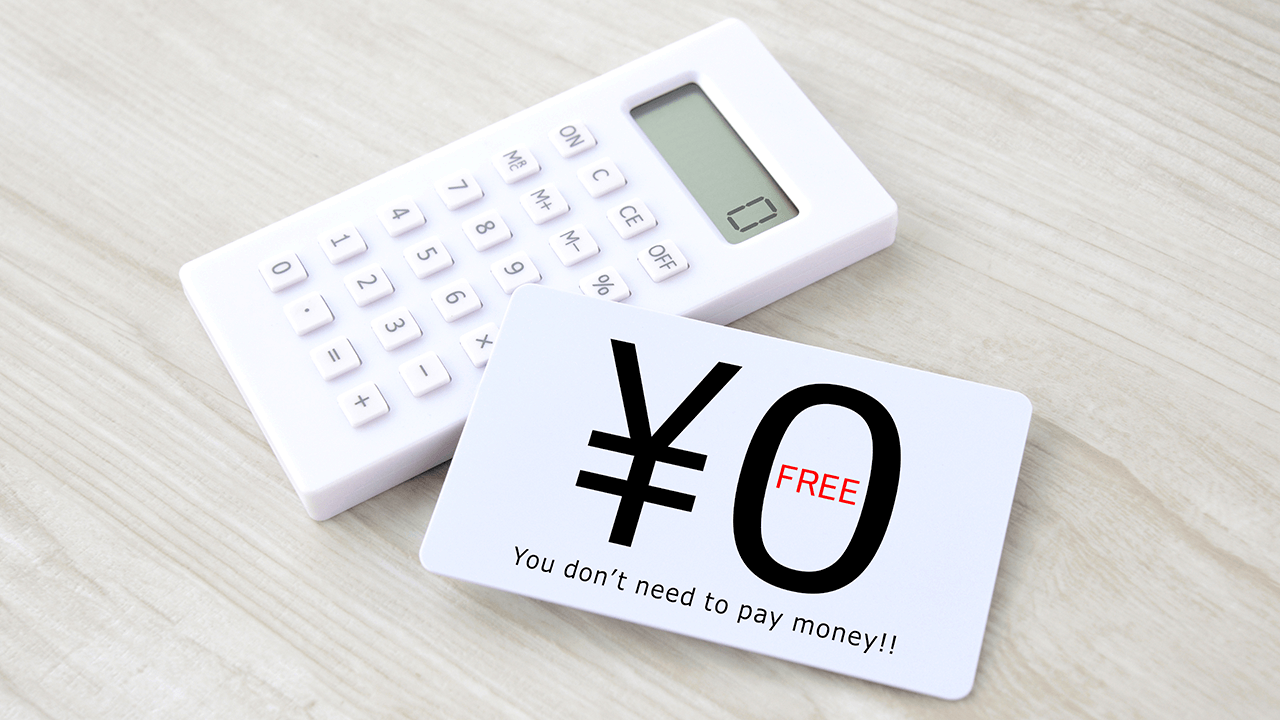
①お問い合わせ(電話、WEBにて30分無料でご相談可能です。)
お電話は平日9時~18時、WEBは翌営業日を目安にご連絡を差し上げます。
②ご相談(直接、オンライン、電話相談)
お客様の現在のご状況をヒアリングし、お客様にとって必要な手続きを確認させていただきます。
③お見積書の作成
お見積書のと共に今後のスケジュールについてご共有いたします。
④お振込み
手続き費用をお振込みいただきます。
⑤必要書類の準備、作成
各種手続きに必要な書類の準備、必要書類の作成