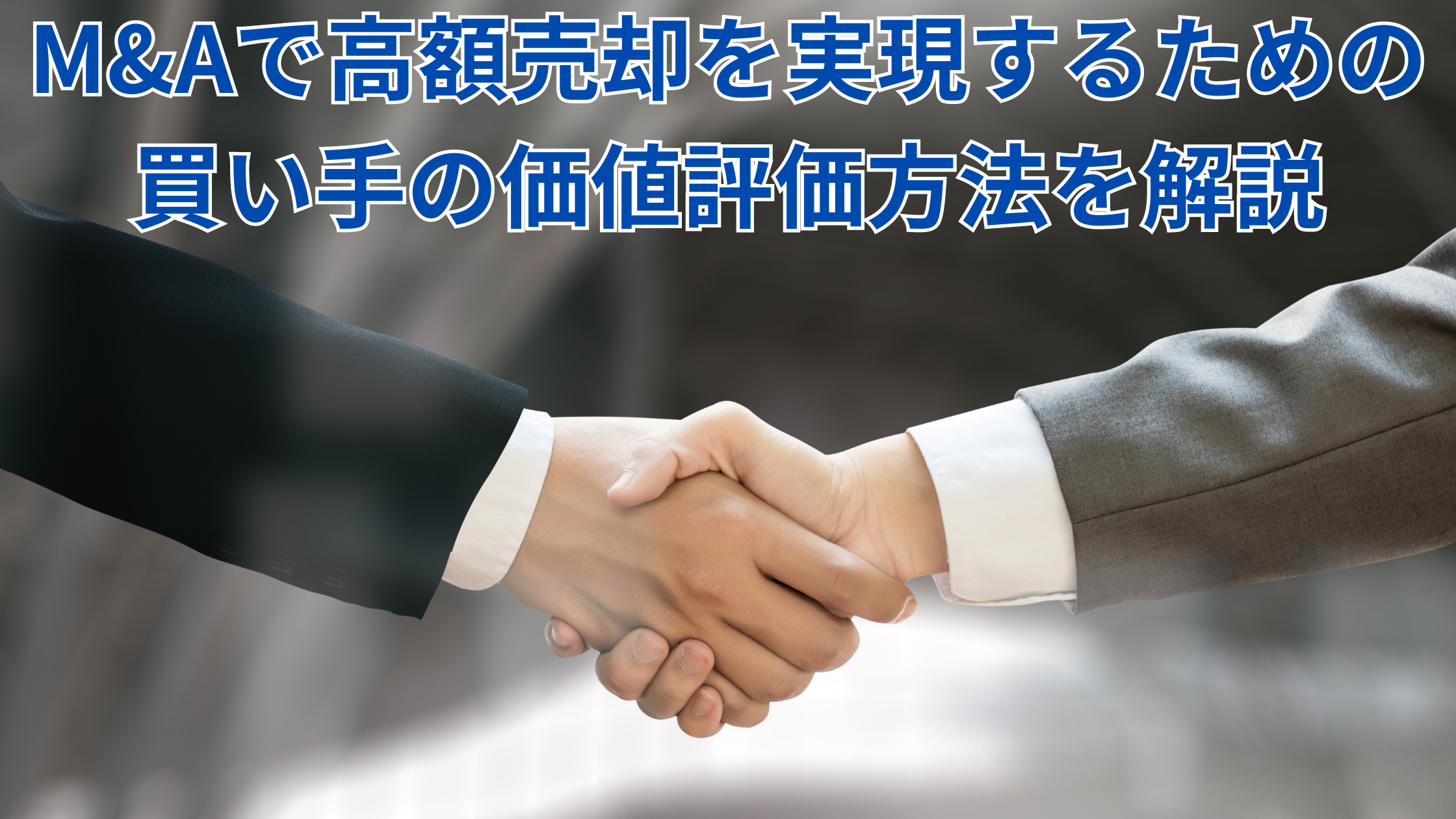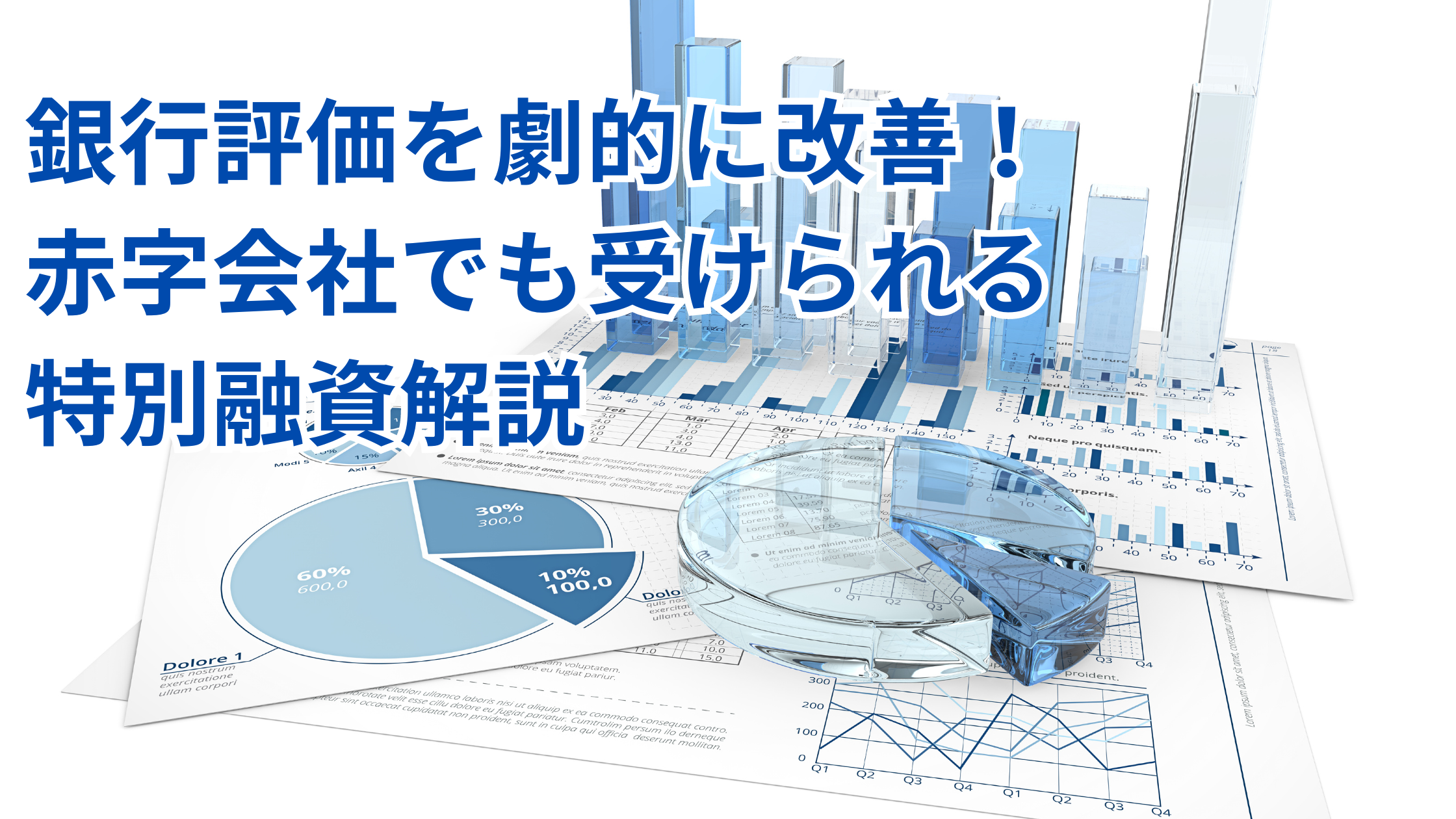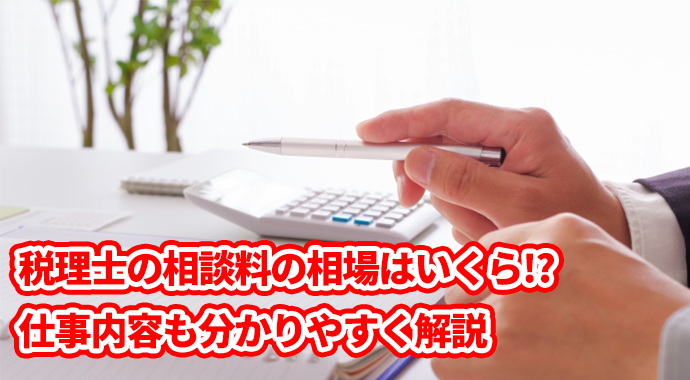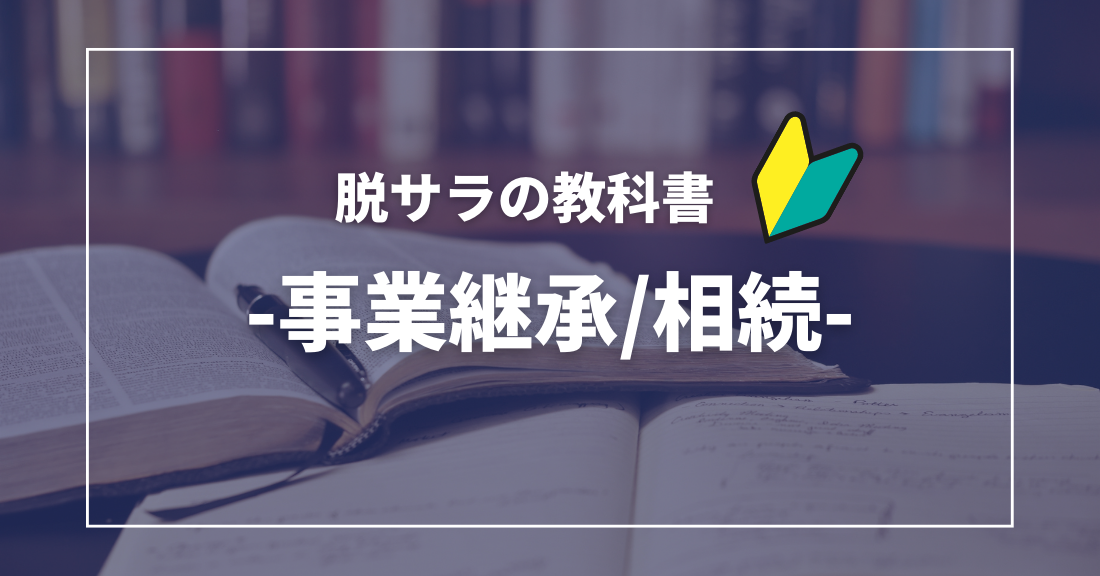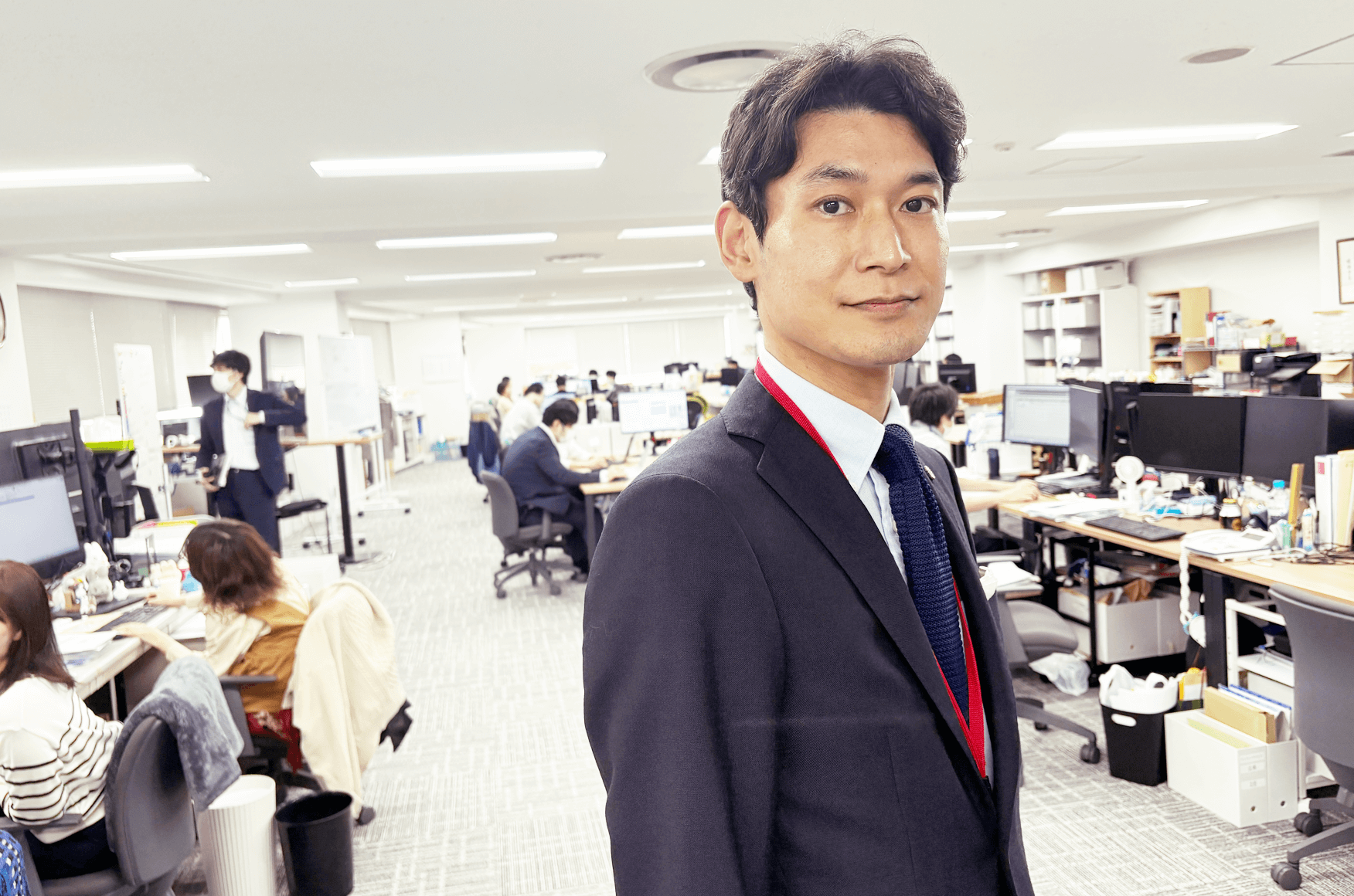相続した不動産の名義変更を行う「不動産登記相続」。この手続きを後回しにしてしまうと、相続人同士での意見の対立や、登記の不備による申請却下、さらには放置することで売却や活用ができなくなるなど、取り返しのつかない事態に陥るケースも少なくありません。
この記事では、不動産登記相続の基本的な流れや必要書類を整理しつつ、実際によくあるトラブル事例と、その防止策をわかりやすく解説します。これから相続登記を控えている方や、手続きを自分で進めようと考えている方にとって、スムーズに相続を進めるためのヒントとなるはずです。
Contents
不動産登記とは?

不動産登記とは、土地や建物の所有権や抵当権といった権利関係を、法務局が管理する公的な帳簿に記録する制度です。不動産登記法に基づいて運用されており、不動産取引を安全に行うために欠かせない仕組みとなっています。
この制度の大きな目的は、権利関係を第三者に公示してトラブルを防ぐことと、誰が所有者なのかを明らかにして取引の安全を守ることにあります。
不動産登記相続の流れと必要書類

相続によって不動産を受け継いだ場合は、名義変更を行う「相続登記」が必要になります。相続登記をしないと、不動産を売却したり担保にしたりすることができず、将来的に相続人が増えることで手続きが複雑化する恐れもあります。
ここでは、相続登記の基本的な流れと準備すべき必要書類について整理していきます。
不動産登記相続の基本的な流れ
相続登記は、以下のステップで進めるのが一般的です。
- 1.被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集し、相続人を確定する
- 2.不動産の内容を確認(登記事項証明書や固定資産評価証明書の取得)
- 3.遺産分割協議を行い、不動産を誰が相続するかを決定する
- 4.遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印する
- 5.相続登記申請書を作成し、必要書類とともに法務局へ提出するる
この一連の流れを経て、登記簿に新たな所有者として相続人が記録されます。
不動産登記相続に必要な書類
相続登記を行う際には、法務局に以下のような書類を提出する必要があります。状況によって追加書類が求められることもありますが、代表的なものを整理しました。
| 書類名 | 内容・取得先 |
|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までのすべての戸籍(市区町村役場) |
| 被相続人の徐住民票 | 死亡時の住所地を確認するため(市区町村役場) |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続関係を確認するため(市区町村役場) |
| 相続人全員の住民票 | 現住所を確認するため(市区町村役場) |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員が署名・押印したもの |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 遺産分割協議書に押印した印鑑が実印であることを確認するため |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場で取得、登録免許税の算出に使用 |
| 相続登記申請書 | 法務局に提出する申請書(自作または司法書士作成) |
これらの書類が揃って初めて相続登記が可能になります。
不動産登記相続でよくあるトラブル事例

相続登記は必要書類が多く、関係者も複数に及ぶためスムーズに進められないことも少なくありません。特に、登記を放置した場合や相続人間の意見の食い違い、申請書類の不備などはよくあるトラブルの原因となります。
ここでは代表的な事例を取り上げ、どのようなリスクがあるのかをまとめてご紹介します。
相続登記を放置した場合のリスク
相続登記を長期間行わないと、次のような問題が起こり得ます。
- ・不動産を売却したり担保にしたりできません。
- ・相続人が死亡すると新たな相続人が増え、権利関係が複雑化します。
- ・共有状態が長引き、管理や利用が難しくなります。
- ・令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
特に「相続人が増える」という点は大きなリスクです。例えば、相続登記を放置している間に相続人が亡くなった場合、その子どもなどが新たに相続人となり、関係者が一気に増えてしまいます。
相続人同士で起きやすいトラブル
不動産は分割しづらい財産のため、相続人の間で意見がまとまらないことも多いです。典型的なトラブルには次のようなものがあります。
- ・誰が不動産を相続するかで対立する
- ・遺産分割協議がまとまらず、登記ができない
- ・被相続人の戸籍を取得して相続人を調べたら知らない相続人がいた
こうした事態になると、家庭裁判所で調停を行う必要が生じ、時間と費用がさらにかかってしまいます。
書類不備や申請ミスによる却下
相続登記は、必要書類が揃っていなかったり、申請書の記載に不備があったりすると受理されません。よくあるミスとしては次のようなものがあります。
- ・被相続人の戸籍が出生から死亡まで揃っていない
- ・遺産分割協議書に相続人全員の署名押印がない
- ・登記申請書に誤字や記載漏れがある
- ・必要な登録免許税が不足している
これらの不備があると再度書類を集め直す必要があり、手続きが大幅に遅れてしまいます。特に戸籍の収集漏れは頻発するため注意が必要です。
相続登記をスムーズに進めるための防止策

相続登記は必要書類が多く、相続人全員の協力も不可欠なため少しの準備不足が大きな遅れにつながります。トラブルを避けてスムーズに進めるためには、事前に必要な手順を理解し適切に対処していくことが重要です。
ここでは代表的な防止策を整理してご紹介します。
必要書類を早めに揃える
相続登記では、戸籍や住民票、評価証明書など複数の書類を揃える必要があります。特に戸籍は「出生から死亡までの一連の記録」を収集しなければならず、複数の役所に請求しなければならないケースも多くあります。
※戸籍謄本は広域交付が開始(令和6年3月1日施行)され、最寄りの役所で各市区町村の戸籍謄本を取得することが出来るようになりました。
時間がかかることを前提にできるだけ早めに収集を始めておくことが重要です。途中で抜け漏れがあると再度取り寄せが必要になり、手続きが大幅に遅れる原因となります。事前に必要な書類をリストアップし、余裕を持って準備を進めるようにしましょう。
遺産分割協議をしっかりまとめる
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのかを話し合い、合意を文書化する必要があります。
- ・相続人全員が参加して合意することが必要
- ・協議の内容は「遺産分割協議書」にまとめる
- ・協議書には全員の署名と実印による押印が必要
一人でも同意しない相続人がいれば登記は進みません。早めに話し合いの場を設け、意見の食い違いを解消しておくことが重要です。
司法書士へ依頼するメリット
相続登記は自分で行うことも可能ですが、戸籍収集や申請書の作成は複雑で時間がかかります。司法書士に依頼することで次のようなメリットがあります。
- ・必要書類の収集や作成を代行してもらえる
- ・書類不備や申請ミスを防げる
- ・相続人間の調整や説明のサポートを受けられる
- ・手続きにかかる時間を大幅に短縮できる
費用はかかりますが、特に相続人が多い場合や遠方に住んでいる場合には専門家に依頼することで安心して手続きを進められます。
不動産登記相続なら「ストラーダ司法書士法人」にお任せください

相続登記は、戸籍の収集や書類の作成だけでなく、遺産分割や相続税の検討など幅広い知識が求められる複雑な手続きです。自分だけで進めようとすると時間がかかるだけでなく、書類の不備や手続きの遅れが大きなトラブルにつながることもあります。
ストラーダグループは、司法書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士・行政書士といった各分野の専門家が在籍する士業の専門家集団です。不動産登記相続に関しても、単に登記を代行するだけでなく、税務や相続人同士の調整など幅広い視点からサポートできる体制が整っています。