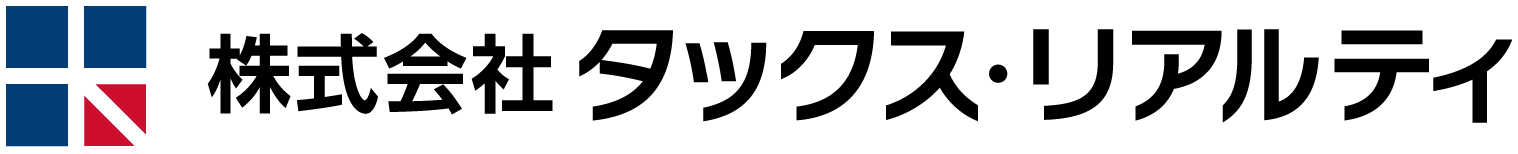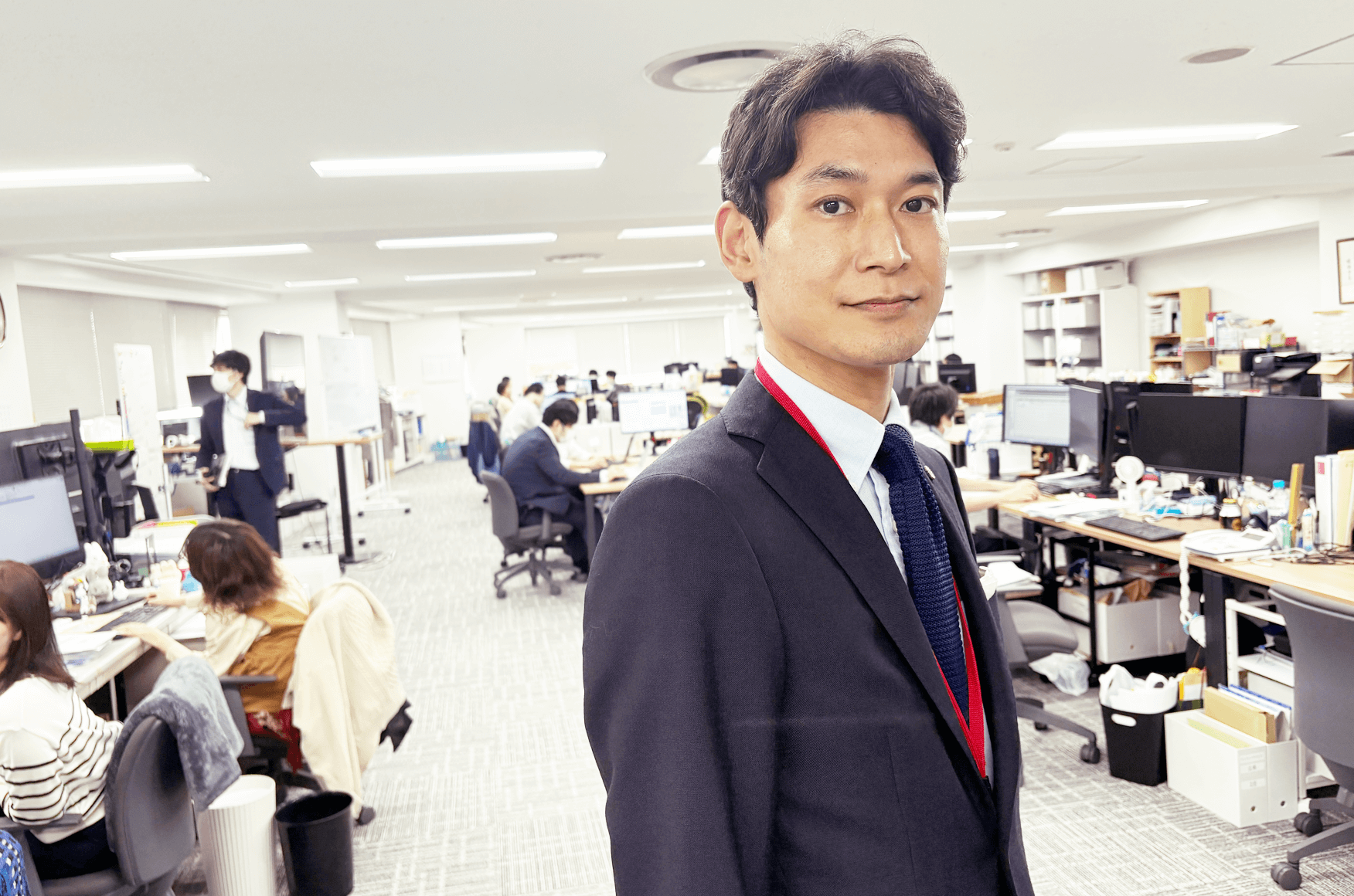不動産売買は、人生における大きなターニングポイントのひとつです。マイホームの購入や投資用物件の売却、相続した土地の処分など、様々な場面で「不動産の取引」が関わってきます。しかし、売買のプロセスや費用、契約書類、トラブル回避の方法まで、知っておくべき知識は多岐にわたります。
この記事では、不動産売買をこれから検討している方や、実際に取引を進めている方に向けて、知っておくべき基礎知識から成功のためのコツまでをわかりやすく解説します。不動産売買をスムーズに、そして安心して進めるために、是非参考にしてみてください。
Contents
不動産売買の基礎知識

不動産売買は、単に「買う」「売る」といった行為だけではなく、法律・税務・手続き・費用といった多岐にわたる知識が求められる重要な取引です。不動産は金額が大きく、人生に与える影響も大きいため、しっかりとした基礎知識を持つことで、安心して取引を進めることができます。
不動産とは?種類と特徴を理解しよう
「不動産」とは、土地および土地に定着している建物などの「動かせない資産」のことを指します。不動産はその性質上、利用方法や売買方法、法的な取り扱いが異なるさまざまな種類に分類されます。
| 不動産の種類 | 説明 | 代表的な用途 |
|---|---|---|
| 土地 | 建物の建設や農業、商業活動などに活用される地面 | 住宅用地、商業地、農地など |
| 一戸建て住宅 | 土地と建物を一体で所有する形態の住宅 | マイホーム、賃貸物件 |
| マンション(区分所有) | 建物の一部を所有し、共用部分は共有する | 自宅用、投資用 |
| 商業用不動産 | 事業を行うための建物や敷地 | 店舗、オフィスビル、倉庫 |
| 投資用不動産 | 資産運用や家賃収入を目的として購入する不動産 | アパート、マンション、テナントビル |
不動産売買とは?その重要性と基本的な考え方
「不動産売買」とは、土地や建物の所有権を売主から買主へと移転する契約行為です。一般的な商品売買と異なり、不動産売買は高額かつ複雑な取引であるため、法律や契約書、税務知識が欠かせません。
不動産売買の目的は多様で、大きく以下の3つの用途に分かれます。
- ・自己利用(マイホーム購入)
- ・投資
- ・事業用
自己利用であれば生活拠点を確保すること、投資用であれば賃貸収入や資産価値の向上を目指すなど、目的によって取引における意思決定も異なります
また、不動産売買にはそれぞれ以下のような重要な意味があります。
- ・生活の質や利便性を左右する(マイホームの場合)
- ・資産運用の手段としての効果(投資用不動産)
- ・事業の拠点としての役割(オフィス・店舗)
不動産売買は資産運用やライフプランに密接に関わるため、慎重な計画と判断が必要です。
不動産売買にかかる手数料と費用のすべて

不動産売買を行う際には、物件の代金以外にもさまざまな手数料や税金、諸費用が発生します。これらの費用は、取引の規模や内容によって大きく異なるため、事前にしっかりと把握しておくことが重要です。
不動産売買 仲介手数料の計算方法と相場
不動産売買において、仲介会社を利用する場合は「仲介手数料」が発生します。これは、物件の売主・買主双方が不動産仲介会社に支払う成功報酬のようなものです。
仲介手数料の計算方法は宅地建物取引業法で上限が定められており、以下の式で算出されます。
- 売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税
例えば、3,000万円の物件を売買した場合の手数料は以下のようになります。
| 項目 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 物件価格 | 3,000万円 | |
| 仲介手数料(税抜) | 3,000万円 × 3% + 6万円 | 96万円 |
| 消費税(10%) | 96万円 × 10% | 9.6万円 |
| 合計 | 96万円 + 9.6万円 | 105.6万円 |
なお、物件価格が400万円以下の場合は、別途「売買価格 × 5%(上限)」の計算式が適用されます。また、売主・買主ともに仲介業者を利用する場合、双方が手数料を支払うことになります。
仲介手数料の相場としては、売買価格の3%+6万円(+消費税)を上限とした取引が一般的ですが、物件や地域、交渉次第で割引されるケースもあります。
不動産売買契約書にかかる印紙代と税金
売買契約を締結する際には「不動産売買契約書」を作成し、印紙税を納付する必要があります。印紙税は国税であり、契約書に貼付する印紙の額は、取引金額によって変動します。
以下は、印紙税額の一覧です。
| 契約金額(売買価格) | 印紙税額(軽減税率適用後) |
|---|---|
| 100万円超〜500万円以下 | 1,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 5,000円 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 3万円 |
| 1億円超〜5億円以下 | 6万円 |
印紙は、売主・買主のいずれかが貼付するケースが一般的ですが、どちらが負担するかは事前の取り決め次第です。
また、契約書に貼付する印紙税以外にも、不動産売買には以下のような税金が発生します。
- ・登録免許税
- ・不動産取得税
- ・消費税
印紙税は一度契約書に貼り付けた後に消印を行うことが義務付けられており、納付漏れは税務調査時に指摘を受けるリスクもあるため、十分注意しましょう。
不動産売買で発生するその他の費用一覧
仲介手数料や印紙税以外にも、不動産売買においてはさまざまな費用が発生します。以下は主な費用の一覧です。
| 契約金額(売買価格) | 印紙税額(軽減税率適用後) | 印紙税額(軽減税率適用後) |
|---|---|---|
| 100万円超〜500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
| 100万円超〜500万円以下 | 1,000円 | 1,000円 |
これらの費用は、物件の種類や契約条件によって異なります。特に、住宅ローンを利用する場合には金融機関に支払う諸費用も発生しますので、総額の資金計画を立てる際は仲介手数料や税金だけでなく、これらの費用も考慮しておきましょう。
不動産売買契約の基本と進め方

不動産売買における最も重要なステップのひとつが「契約」の締結です。不動産は高額な資産であるため、取引を法的に成立させるための契約書作成や署名捺印、さらには契約内容の十分な確認が不可欠です。
不動産売買契約書の種類とその違い
不動産売買契約書には、いくつかの種類や形式があります。大きく分けると「個人間売買」と「仲介業者を介した売買」で契約書の形態に違いがあります。
個人間売買契約書
個人同士が直接売買を行う場合に作成する契約書です。法的効力はありますが、専門知識が必要なため、契約内容に不備が発生しやすいというリスクがあります。トラブル防止のためには、司法書士や弁護士などの専門家に契約書をチェックしてもらうことが推奨されます。
仲介業者による標準契約書
不動産仲介会社が間に入るケースでは、宅地建物取引業法に基づく「標準契約書」が使われることが一般的です。こちらは、不動産取引の専門知識を踏まえて作成されているため、トラブルリスクを最小限に抑える内容が網羅されています。
不動産売買契約書の作成時に必要な書類
契約書を正式に作成するためには、いくつかの添付書類が必要となります。これらの書類は、売主・買主ともに準備するものが異なります。
| 書類名 | 売主が準備するもの | 買主が準備するもの |
|---|---|---|
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | ○ | 不要 |
| 公図・地積測量図 | ○ | 任意 |
| 固定資産税納税通知書 | ○ | 任意 |
| 本人確認書類 | ○ | ○ |
| 印鑑証明書 | ○ | ○ |
| 住宅ローン事前審査承認書 | 不要 | ○(ローン利用時) |
| 重要事項説明書 | 仲介業者が作成 | 仲介業者が作成 |
売主は「物件の正確な情報」を、買主は「購入意思」と「資金面での裏付け」を示すための書類を準備します。
さらに、仲介業者が関わる場合は、取引前に「重要事項説明書」を必ず確認することが法律で義務付けられています。
契約締結時のチェックリスト
契約締結時には、以下のようなポイントを必ず確認しましょう。
- ・契約書の記載内容が正確か
- ・契約条件が合意通りか
- ・瑕疵担保責任の有無・内容
- ・印紙の貼付と消印
- ・重要事項説明の実施
- ・双方の署名・捺印
契約締結後は、いかなる修正も難しくなるため、少しでも不明点があれば契約直前に必ず仲介業者や専門家に相談するようにしましょう。
不動産売買の具体的な流れと成功のコツ

不動産売買は、事前準備から契約、引渡しまで多くのプロセスを経て進められます。売却する側と購入する側では進め方に違いがあり、さらに途中で発生しやすいトラブルにも注意が必要です。
ステップ別|売却と購入のプロセス
不動産売買には、大きく「売却」と「購入」の2つの視点があります。それぞれの立場で行うべきプロセスは異なるため、両者の流れを把握することが重要です。
| ステップ | 売却の流れ | 購入の流れ |
|---|---|---|
| 1. 情報収集・準備 | 査定依頼、売却価格の決定、必要書類の準備 | 購入資金の計画、ローン事前審査 |
| 2. 仲介会社選び | 信頼できる不動産会社を選定、媒介契約締結 | 仲介会社の選定、希望条件の相談 |
| 3. 販売・物件探し | 物件広告、内覧対応、価格交渉 | 物件情報の収集、内覧、条件交渉 |
| 4. 売買契約締結 | 契約書作成、署名捺印、手付金の受領 | 契約書確認、署名捺印、手付金支払い |
| 5. 決済・引渡し | 残代金受領、登記手続き、物件引渡し | 残代金支払い、登記申請、物件の引渡し |
| 6. 売却・購入後 | 確定申告 | 不動産取得税の納付、住宅ローン控除手続き |
売主は「売却準備から販売活動」、買主は「物件探しから資金計画」のフェーズに重点を置きます。どちらの場合も、仲介業者との密な連携や、契約書・登記などの法的な手続きをスムーズに進めることが、成功の鍵となります。
不動産売買時によくあるトラブルとその回避法
不動産売買は高額な取引であり、法的手続きも複雑なため、さまざまなトラブルが起こりやすいのが実情です。
| よくあるトラブル | 主な原因 | 回避策 |
|---|---|---|
| 契約内容の認識違い | 口頭での確認不足、契約書の不備 | 契約書の内容を詳細に確認 |
| 瑕疵の未申告 | 売主が物件の不具合を開示しない | 売主側は誠実な情報開示、買主側はインスペクション(住宅診断)の実施 |
| 手付金・残代金の支払い遅延 | 資金計画の甘さ、手続きの遅延 | 事前に資金繰りを綿密に確認、ローン審査を早めに完了 |
| 引渡し後の設備不良・未修繕 | 契約条件に未記載のまま引渡し | 引渡し前に設備確認、修繕項目は契約書に明記 |
| 登記手続きの遅延 | 司法書士手配の遅れや必要書類の不足 | 司法書士との早期連携、必要書類は事前に揃える |
特に注意が必要なのは、「認知症の親名義の不動産売却」や「親子間売買」などのケースです。これらは法的リスクや税務上の課題も多いため、事前に専門家への相談が不可欠です。
H3: 不動産売買契約の適切なタイミングとは?
不動産売買における「契約締結のタイミング」も、成功の可否を分ける重要な要素です。タイミングを誤ると、後々トラブルや損失に繋がる可能性が高まります。
適切な契約のタイミングは、以下の条件が揃ったときが目安となります。
- ・価格・条件交渉が完了している
- ・ローン審査の目処が立っている
- ・契約書および重要事項説明書が完成している
- ・インスペクション(住宅診断)の結果を確認済み
売主側にとっては、売却時期の市場状況や買主の資金計画などを踏まえて、慎重に契約日を設定することが重要です。一方、買主側も物件情報を十分に調査したうえで、焦って契約を急がないことが失敗を防ぐポイントとなります。
不動産売買に必要な準備と注意点

不動産売買を成功させるためには、事前準備が非常に重要です。準備段階で物件の査定、選定、資金計画、内覧対応をしっかり行うことで、契約後や引渡し時のトラブルを未然に防ぐことができます。
査定・物件選定時のポイント
物件の査定や選定は、不動産売買の第一歩です。売却側・購入側のそれぞれで押さえるべきポイントは異なります。
売却側の査定ポイント
- ・複数の不動産会社に査定依頼を出す
- ・市場の売却相場を確認する
- ・物件の築年数や立地、設備の状態を考慮した適正価格を設定する
購入側の物件選定ポイント
- ・エリアの利便性
- ・将来的な資産価値
- ・物件の条件(間取り、築年数、設備、管理状況など)
- ・管理費・修繕積立金(マンションの場合)の確認
購入側は「資産価値」を意識し過ぎて、実生活での使い勝手を軽視するケースもあります。生活スタイルや将来の家族構成なども踏まえたうえで、バランスの取れた物件選定が大切です。
内覧で確認すべきチェックポイント
購入を検討する物件が見つかったら、次は内覧です。内覧は実際の状態を自分の目で確認できる貴重な機会であり、後々の不安要素を減らすためにも細かくチェックしましょう。
以下は、内覧時に確認しておくべき代表的なチェックポイントです。
| チェック項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 建物の外観・構造 | 外壁や屋根にひび割れや雨漏り跡がないか |
| 内装の状態 | クロスの剥がれ、床のきしみ、カビや汚れなど |
| 配管・水回り | キッチン・浴室・トイレの水漏れや排水の異常 |
| 日当たり・通風 | 日照時間、窓の位置、風通しの良さ |
| 騒音・周辺環境 | 騒音や振動、隣接する建物や道路の状況 |
| 管理状況(マンションの場合) | ゴミ置き場や共用部の清掃状態、管理人の有無 |
| 設備の動作確認 | 給湯器、エアコン、インターホンなどの動作チェック |
購入資金の準備
購入側にとって、資金計画は不動産購入をスムーズに進めるための大前提となります。特にローンを利用する場合は、無理のない返済計画を立てることが重要です。
自己資金(頭金)は通常、物件価格の20%程度を用意するのが理想的です。さらに、売買価格の他に、以下のような諸費用が必要です。総額で物件価格の7〜10%程度が目安です。
| 費用項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 物件価格の3%+6万円+消費税 |
| 登記費用(登録免許税・司法書士報酬) | 数十万円 |
| 印紙税 | 1万円~3万円(物件価格により変動) |
| ローン手数料・保証料 | 数万円~数十万円 |
| 火災保険料 | 数万円~ |
住宅ローンの選び方
ローンは複数の金融機関のプランを比較することが大切です。以下のポイントを比較しながら検討しましょう。
- ・金利タイプ
- ・団体信用生命保険
- ・繰上返済手数料や金利優遇の有無
- ・融資実行までのスピード
信頼できる不動産会社・専門家の選び方
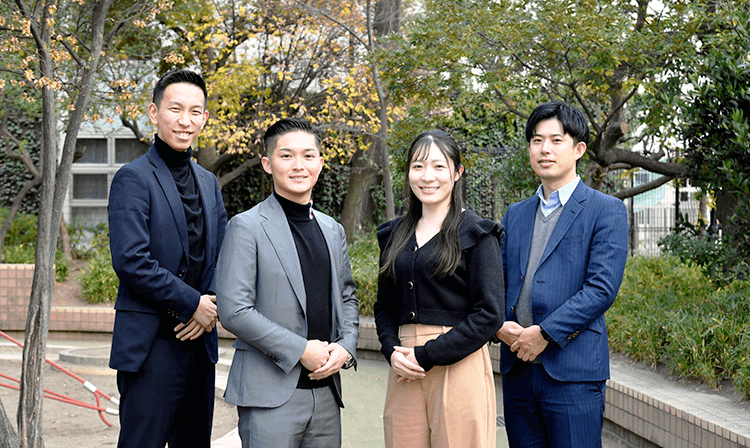
不動産売買は、契約書の作成や物件調査、法的手続き、税務対応など幅広い業務を伴うため、信頼できる専門家や不動産会社のサポートが欠かせません。適切なパートナーを選ぶことで、スムーズで安全な取引を実現できます。
不動産売買を依頼する会社の選び方
不動産会社は、売主・買主双方にとって取引の成功を左右する重要な存在です。信頼できる不動産会社を選ぶ際は、以下のポイントをしっかり確認しましょう。
- ・宅地建物取引業免許の有無
- ・取り扱い物件の種類と実績
- ・担当者の対応力・説明力
司法書士・税理士など専門家の役割とは
不動産売買には、法務・税務面での対応が求められる場面も多く、以下のような専門家が関与するのが一般的です。
司法書士
不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記などを代理で行います。登記手続きは法律上のルールが厳格に定められているため、司法書士のサポートが不可欠です。司法書士は決済当日に立ち会い、登記申請書の提出や登記費用の支払いなどを担当します。
税理士
売主側は譲渡所得税の計算や確定申告、買主側は不動産取得税や住宅ローン控除の適用判断などを行います。不動産売買には多額の税金が関わるため、税理士のアドバイスを受けることで適切な節税対策が可能になります。
弁護士
トラブルが懸念される場合や、個人間売買などで契約書のリーガルチェックが必要なケースでは、弁護士の助言が役立ちます。複雑な相続案件や、認知症の親名義の不動産売却にも対応してくれます。
サポートを受けることで得られるメリット
不動産売買において不動産会社や各専門家のサポートを受けることで、次のようなメリットがあります。
- ・トラブル回避
- ・スムーズな手続き
- ・価格交渉や売却戦略の提案
- ・節税できる
不動産売買には法律・税務・登記など複雑なルールが関わるため、専門家のチェックを受けることで契約書の不備や法的リスクを防ぐことができます。登記申請や税金の申告、住宅ローンの手続きなどを専門家に依頼することで、煩雑な作業を効率的に進められます。また、不動産会社の営業担当は、エリアの相場や顧客のニーズを把握しているため、適切な価格設定や売却戦略を提案してくれます。より有利な条件で売買を進めることが可能です。
さらに税理士のサポートにより、譲渡所得税の特別控除や住宅ローン控除の適用可否などを正確に判断してもらうことができます。結果的に節税にもつながります。
個人間での不動産売買を行う場合

不動産売買は通常、不動産仲介会社を通じて行われますが、族間や知人同士などで取引する「個人間売買」という方法もあります。仲介手数料がかからないなどのメリットがある一方で、法律や契約に関する専門知識が求められるため慎重な対応が必要です。
個人間売買のメリットとデメリット
個人間売買の代表的なメリット・デメリットは以下の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 仲介手数料が不要 | 契約や手続きの知識が不足するとトラブルに発展しやすい |
| 売主・買主間で柔軟な条件交渉が可能 | 契約書の不備による法的リスク |
| 親族間や知人同士での取引がしやすい | 価格の客観性が欠けやすく、適正価格を見失う恐れがある |
| 売買スピードが比較的早い | トラブル時に仲介業者によるサポートが受けられない |
特に親族間での取引では、贈与税や相場とかけ離れた価格設定による税務リスクも発生します。価格の妥当性や税務上の影響については、事前に税理士等に相談するのが安全です。
個人間で必要な契約書類と作成のポイント
個人間売買でも、不動産取引を適正に行うためには正式な契約書の作成が不可欠です。
個人間でも必要となる書類は以下の通りです。
- ・不動産売買契約書
- ・登記簿謄本
- ・公図・地積測量図
- ・売買物件の固定資産税評価証明書
- ・本人確認書類
- ・印鑑証明書
契約書を作成する際は、売主・買主双方の情報を正確に記載し、売買物件の所在地や面積などの内容が登記簿謄本と一致しているか確認します。また、売買価格や手付金、残代金、支払期日などの支払条件、引渡し日や所有権移転登記の時期についても明確に記載する必要があります。さらに、瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲を明示し、印紙税額に応じた印紙を貼付・消印することも重要なポイントです。
契約書は雛形を利用することも可能ですが、個人間取引はケースバイケースで条件が異なるため、専門家に内容をチェックしてもらうのが望ましいです。
個人間売買でトラブルを避けるための対策
個人間売買では、仲介業者が介在しないため、当事者間の合意形成や手続きの不備からトラブルに発展するケースが多く見られます。以下のような対策を講じ、リスクを最小限に抑えましょう。
- ・契約書の徹底作成と第三者チェック
- ・インスペクション(住宅診断)の実施
- ・税務リスクの事前確認
- ・支払い・登記スケジュールの明文化
- ・親族間でも必ず書面化する
親しい間柄でもこうした対策を講じることで、より安全に不動産取引を進めることが可能になります。
不動産市場の相場と最新動向
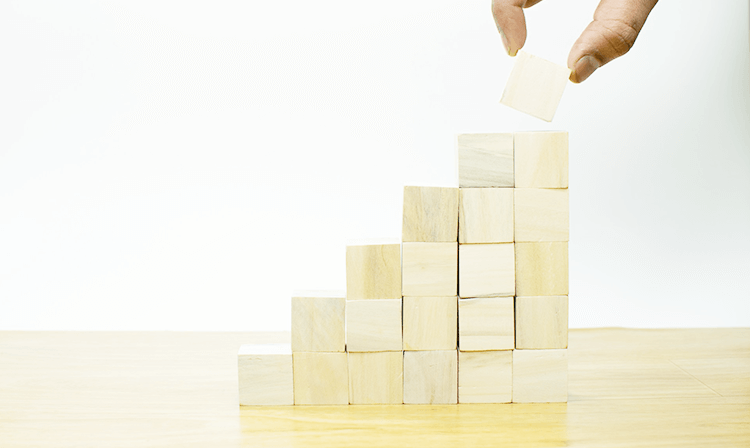
不動産売買を成功させるためには、物件の適正価格を把握することが欠かせません。そのためには、市場相場の理解や競合物件の調査、さらには将来の市場動向までを把握しておかなければなりません。
市場相場を知る|価格設定のコツ
不動産の価格は、立地や築年数、間取り、地域の需要と供給バランスなど、さまざまな要素によって決まります。適正な価格設定は、売却時には早期成約、購入時には無駄な支出の防止に直結します。
売却時の価格設定では、以下の要素を総合的に判断することが重要です。
| チェック項目 | ポイント |
|---|---|
| 立地 | 駅からの距離、周辺施設の充実度、地域の治安 |
| 物件の状態 | 築年数、リフォーム履歴、耐震性能など |
| 市場動向 | 直近の取引事例を参考にする |
| 供給・需要バランス | エリア内の売出し物件数と購入希望者数 |
| 将来的な資産価値 | 再開発計画や人口動態など |
価格設定の基本は、周辺相場を参考にしつつ、過度に高額・低額にならないようバランスを取ることです。査定依頼は複数の不動産会社から取り、客観的な視点で価格を決めるのが成功のコツです。
競合物件の情報収集と調査方法
物件を売り出す際や購入検討時には、同じエリア・条件の競合物件の情報を集めましょう。競合物件の調査は、価格交渉や販売戦略の立案に役立ちます。
競合物件調査は、不動産ポータルサイトを活用し、近隣エリアの類似物件の築年数や面積、間取りが似た物件の売出価格を調べます。また、プロ向けの物件データベース「レインズ」に登録されている過去の成約事例や現在の売出物件を不動産会社に依頼して調査という方法もあります。実際に現地に足を運び、販売中の物件や周辺環境を確認するのも良いでしょう。
今後の不動産市場の動向と見通し
不動産市場は、経済状況や政策、人口動態、世界経済の影響を受けながら常に変化しています。今後の市場動向を見極めることで、売却や購入の最適なタイミングを判断することができます。
特に、住宅ローン金利や政府の政策・税制改正は市場に直接的な影響を与える要因です。低金利が続けば購買意欲が高まり市場は活発化しますが、金利が上昇すると買主の負担が増え、取引は減少傾向にあります。また、住宅ローン控除や不動産取得税など、政策面での動きも注視すべきポイントです。加えて、日本では長期的な人口減少や高齢化が進行しており、地方では空き家問題が深刻化する一方、都市部では再開発やインフラ整備によって安定した需要が続いています。さらに、為替や世界経済の変動により、都心部やリゾート地などを中心に海外投資家による不動産購入が活発化するケースも増えています。
不動産売買後に必要な手続きと対応
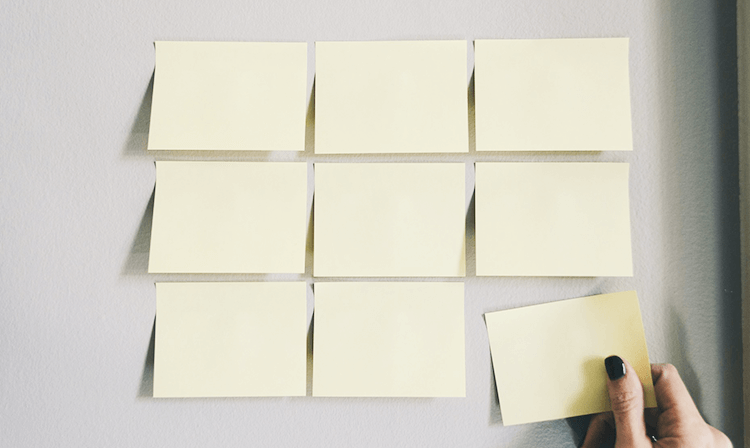
不動産売買は、契約や引渡しを終えた後も、さまざまな手続きや対応が必要になります。引渡し時の注意点から、税務申告、さらには売買後のトラブル対応まで、最後まで気を抜かずに対応しましょう。
引渡し時の注意点と手続きの流れ
不動産の引渡しは、買主が残代金を支払ったタイミングで行われます。スムーズな引渡しを行うためには、事前に必要な手続きや注意点を確認しておきましょう。
| 手続き項目 | 内容 |
|---|---|
| 残代金決済 | 買主が金融機関から融資を受け、売主に残代金を支払う。売主は領収書を発行し、印紙税の処理も行う。 |
| 所有権移転登記 | 司法書士が関与し、買主名義への所有権移転登記を行う。抵当権付き物件は、抵当権抹消登記も同時に手続き。 |
| 固定資産税・都市計画税の清算 | 引渡し日を基準に、売主と買主で固定資産税や都市計画税を日割りで精算する。 |
| 物件引渡し | 売主から買主へ鍵を引渡し、マンションの場合は管理組合や近隣への挨拶も実施。 |
引き渡しの際に注意しておきたい点は以下の通りです。
- ・設備や内装の最終確認
- ・付帯設備表との相違チェック
- ・電気・ガス・水道の名義変更
- ・管理費・修繕積立金の精算(マンション)
買主側は、引渡し後に不具合を発見するケースもあるため、引渡し時に設備や内装の最終確認を必ず行いましょう。
譲渡所得税・確定申告のポイント
不動産を売却した場合、売主は「譲渡所得税」の申告が必要となります。売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行い、譲渡所得税を納付します。
確定申告時に必要書類は以下の通りです。
- ・売買契約書の写し
- ・取得費関連の領収書(購入時の契約書、リフォーム費用など)
- ・売却時の仲介手数料の領収書
- ・登記事項証明書
- ・印鑑証明書
- ・本人確認書類
また、買主は「不動産取得税」の納付(取得後半年~1年以内に通知が届く)や、住宅ローン控除の適用がある場合は確定申告を行う必要があります。
アフターサポートやトラブル対応について
以下のようなトラブルに備えて、契約時に「契約不適合責任」の範囲や期間をしっかり明記しておくことが重要です。
- ・引渡し後に発覚する設備の不具合
- ・物件に瑕疵があった
- ・売主が退去後、契約条件と異なる物件状態で引渡された
また、仲介会社を通した取引であれば、担当者に相談し、売主との調整を依頼することも可能です。個人間取引の場合は、弁護士などの専門家に速やかに相談することで、解決への道筋が見えやすくなります。
不動産売買(購入・売却)の関連記事
不動産売却の税金や手数料完全マニュアル・手取りを最大化する方法
不動産投資を初心者が最速で成功する方法【プロ直伝】
賃貸物件選びのコツと契約時に注意すべきポイント【2026年】