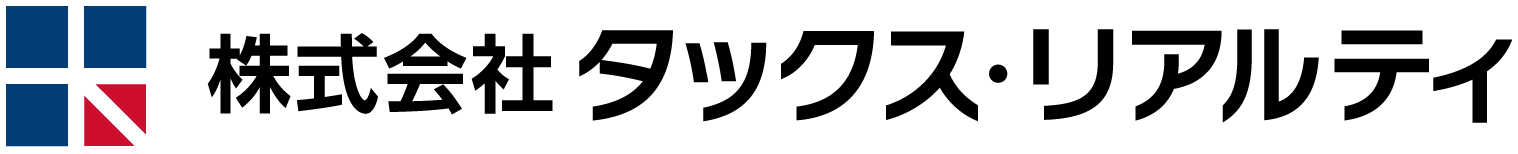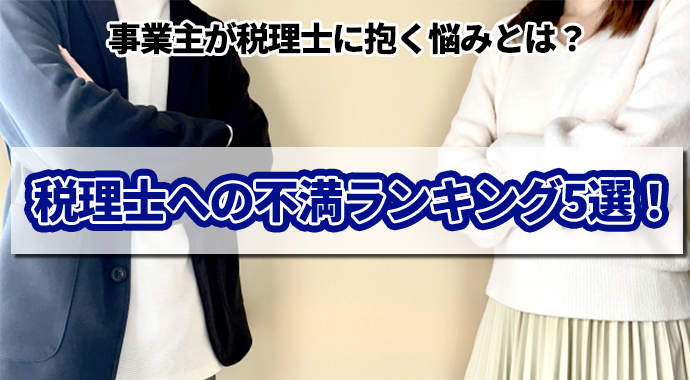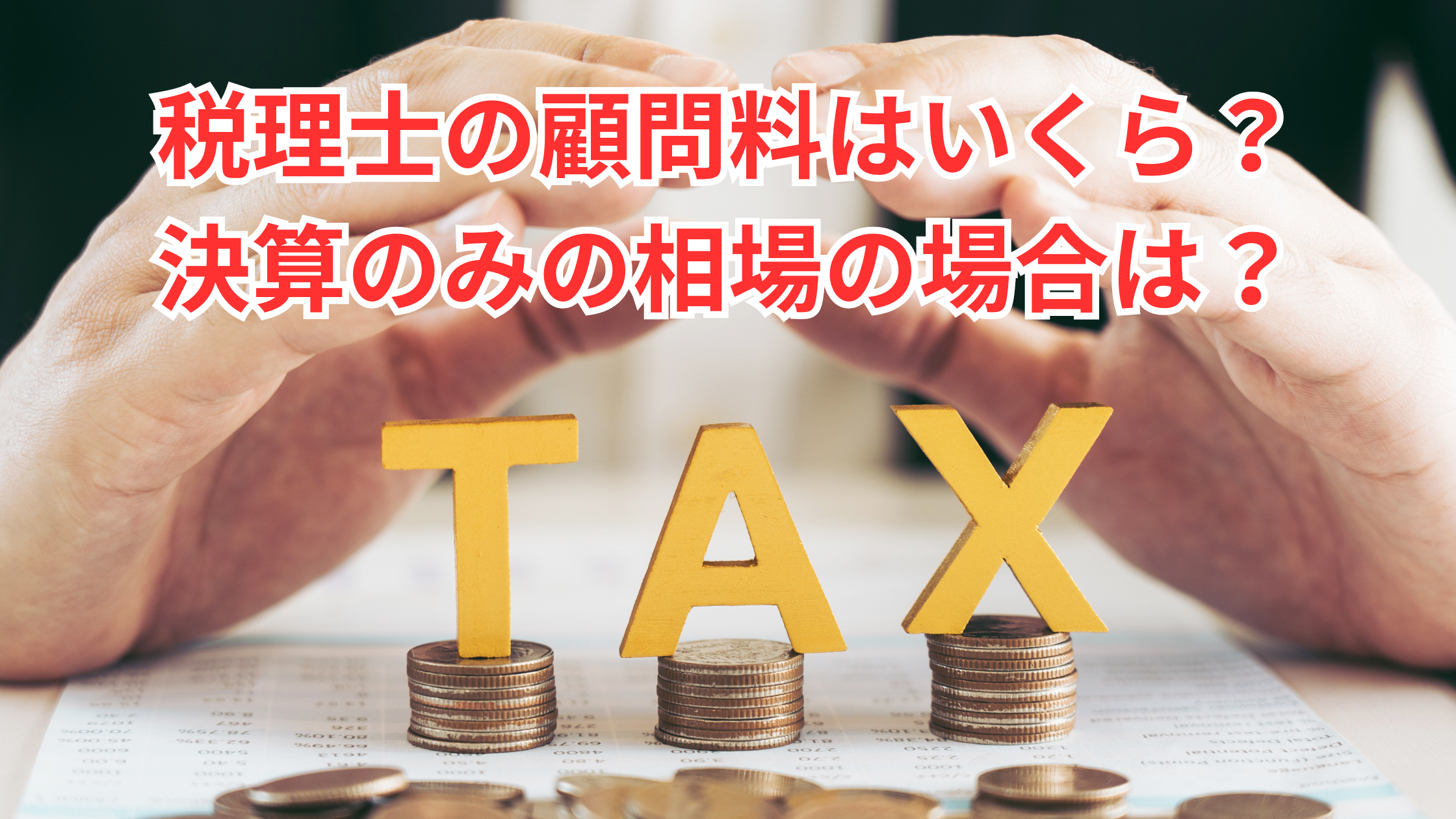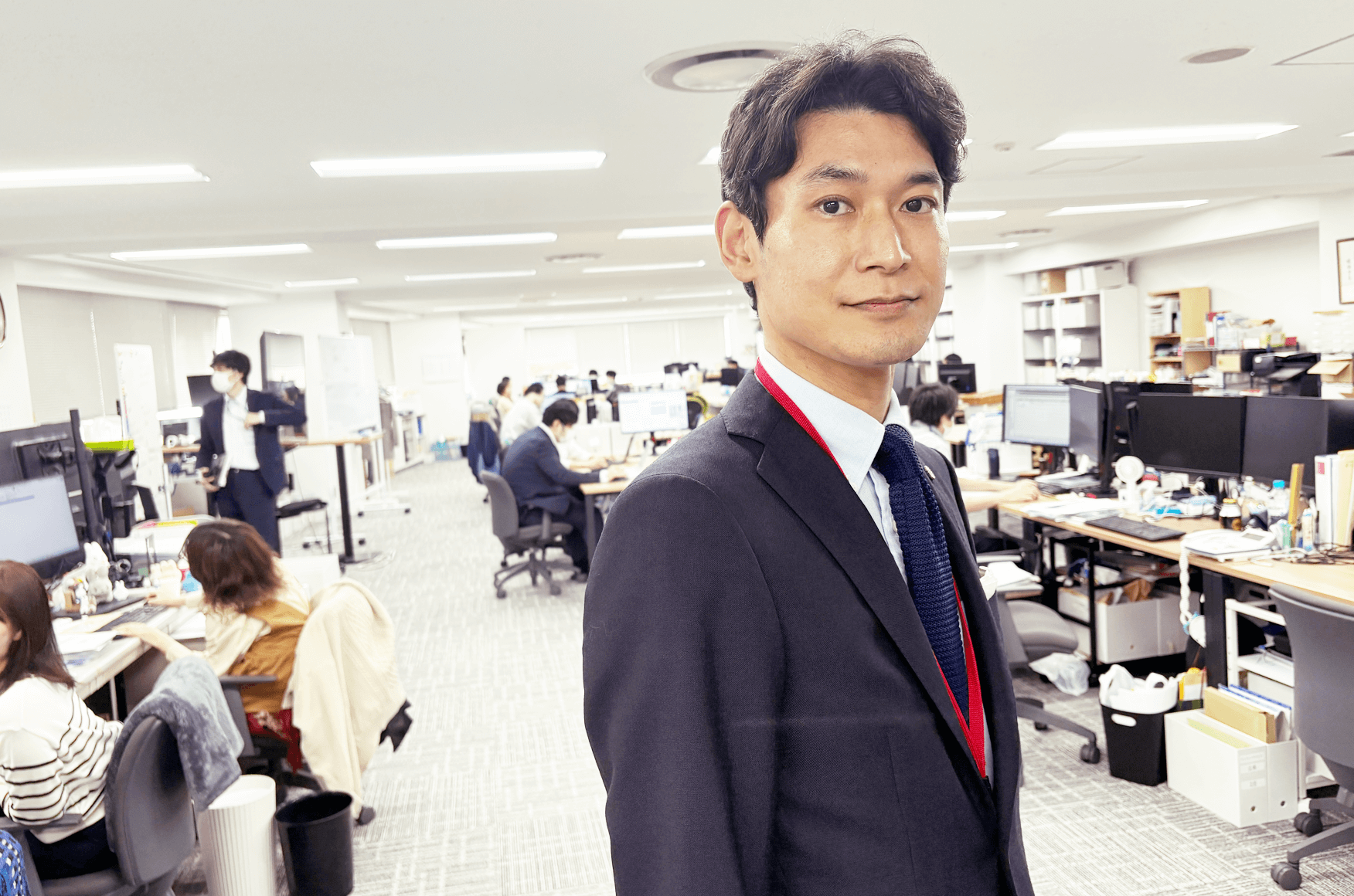物価上昇や年金だけに頼れない将来への不安から、資産形成を目的に不動産投資を始める人が増えています。一方で、インターネットには体験談や口コミが数多くあり、中には誤った情報や過度に不安を煽る内容、さらには“投資詐欺まがい”の手法を紹介するケースも見受けられます。
そのため、「何を信じて進めればいいのか分からない」という声が多いのも事実です。そこで本記事では、不動産投資初心者が最短ルートで成果を出すために必要な基礎知識・投資の種類・始め方の流れを、プロ視点でわかりやすく徹底解説します。
さらに、失敗しないためのポイントも合わせて紹介し、安心してスタートできる実践的なガイドをお届けします。
Contents
不動産投資とは?押さえておきたい基礎知識

不動産投資は、不動産を購入し、家賃収入や売却益で利益を得る投資手法です。他の金融商品と比較して値動きが安定しているため、長期の資産形成に向いています。
ここでは、不動産投資を始める前に理解しておきたい4つの基礎知識を紹介します。
インカムゲイン
不動産投資の大きな魅力は、毎月安定した家賃収入(インカムゲイン)が得られる点です。景気の変動に左右されにくく、長期的に継続して収入が見込めるため、資産形成の基盤として活用しやすい特徴があります。
キャピタルゲイン
キャピタルゲインは、物件価格が購入時より高いタイミングで売却することで得られる利益のことを指します。特に、再開発エリアや人気沿線の物件は上昇しやすく、戦略次第では高い収益性が期待できます。
利回り
利回りとは、投じたお金に対して”どれだけ効率よく収益が得られるか”を示す指標で、不動産投資の収益性を判断するうえで欠かせません。利回りには主に「表面利回り」と「実質利回り」の2種類があります。
表面利回り
物件価格に対する年間家賃収入の割合を示す、もっともシンプルな利回りです。
計算式:表面利回り=年間家賃収入 ÷ 物件価格 × 100
ただし、管理費・修繕費・固定資産税などの経費を考慮していないため、実際の手取り額と差が生じる可能性があります。
実質利回り
実質利回りは、諸経費を反映したうえで算出する、実際の収益性に近い指標です。
計算式:実質利回り=(年間家賃収入 − 諸経費) ÷(物件価格+購入時の諸経費)×100
管理費・修繕積立金・火災保険料・固定資産税・仲介手数料など、購入〜運用にかかる費用を含めて判断できることから、投資判断では実質利回りを重視するのが基本です。
レバレッジ効果
不動産投資におけるレバレッジ効果とは、銀行ローンを活用することで、自己資金以上の規模で投資を行える仕組みを指します。購入する物件を担保に融資を受けられるため、手元の資金が少なくてもより高額な資産の取得が可能となり、投資機会を広げやすくなります。
たとえば自己資金が500万円でも、融資を組むことで2,000万〜4,000万円規模の物件を確保し、家賃収入を得ながら効率的に運用を進めることができます。
不動産投資の種類

一棟投資
アパートやマンションをまるごと1棟購入する方法です。世帯数が多いため、入居者が一時的に減っても収入が途切れにくく、収益の安定性を確保しやすい運用形態といえます。家賃設定・設備投資・修繕計画など、オーナーの裁量で建物全体の価値を高められる点が特徴です。
区分投資
マンションの1室を購入し、単身者やカップル向けに貸し出す、もっとも一般的な方法です。購入価格のハードルが低く、管理会社を活用すれば入居者対応をほぼ任せられるため、忙しい会社員でも取り組みやすいという利点があります。
戸建て投資
一戸建てを購入し、ファミリー層向けに貸し出す方法です。入居者の居住期間が長くなる傾向があり、退去が少ないため、運用が安定しやすい点が魅力です。また、ペット可・駐車場付きなど、戸建てならではの条件を設定しやすく、周辺物件との差別化も図れます。
不動産投資のメリット・デメリット
メリット

副収入が得られる
不動産投資では、入居者がいる限り毎月の家賃収入が安定して得られます。株式や仮想通貨のように価格変動を気にする必要がなく、継続した収入源として活用できる点が多くの投資家から評価される理由のひとつです。
会社員であれば、給与に加えて“第二の収入の柱”ができるため、日々の生活に余裕が生まれると共に、教育費や老後資金の準備など、長期的な備えをサポートしてくれます。
節税効果が期待できる
不動産投資は、税金面でも優遇を受けやすい資産運用方法です。運用の中で発生する管理費・修繕費・ローン金利・火災保険料などに加え、建物部分の減価償却費も経費として計上できます。これらを適切に処理することで、最終的な課税所得を抑えられ、節税効果が期待できます。
年金代わりになる
ローンを完済すると、家賃収入のほとんどがそのまま手元に残るようになります。たとえば月8万円の家賃収入なら、年間96万円の収入源を安定して確保できます。老後の不安が高まる中、公的年金だけに頼らず、自ら継続的な収入源を持てる点は心強い安心材料になります。
生命保険・死亡保険として活用できる
不動産投資で融資を受ける場合、多くの金融機関では「団体信用生命保険(団信)」への加入が条件となっています。契約者に万が一のことがあった場合、団信によって残りのローンが全額完済されるため、遺族は負債を負うことなく、物件と家賃収入を受け継ぐことが可能です。
一般的な生命保険・死亡保険が“現金”のみを残すのに対し、不動産投資では「毎月の収入を生み出す資産」が受け継がれる点が異なります。家族の生活を長期的に支える仕組みとしても有効です。
インフレに強い
インフレが進むと現金の価値は下がりますが、不動産は物価上昇とともに資産価値が高まりやすい資産です。建築費が上昇すれば新築物件の価格が上がり、それに連動して中古物件の価格も底堅く推移しやすくなります。
また、家賃相場もインフレに合わせて上昇するケースが多く、長期的にみて収入が極端に減りにくい点も、資産運用上のメリットとなります。
デメリット

自己資金や初期費用がかかる
不動産購入には物件費以外にも、仲介手数料・登記費用・火災保険料・ローン事務手数料などの諸費用が必要になります。これらを合計すると、物件価格の7〜10%ほどに達することが一般的です。
流動性が低い
不動産は、株式のように「売りたいときにすぐ現金化できる資産」ではありません。内覧・条件交渉・金融機関の審査など、売却には一定の時間がかかります。
空室時は収入が入らない
入居者がいない期間は家賃収入がゼロになり、その間もローン返済や管理費などの支出だけが続きます。空室期間が長引くほど収支が圧迫され、資金繰りに余裕がなくなる可能性があります。
家賃滞納が発生する可能性がある
賃貸経営では、入居者が家賃を期日通りに支払わない「家賃滞納」が発生することがあります。近年は家賃保証会社の普及で対応しやすくなりましたが、こうした問題を完全に避けることはできません。入居審査の基準を適切に設定するなど、事前の対策が重要です。
建物の老朽化や修繕リスクがある
不動産は時間の経過とともに設備の故障や外壁の劣化が進むため、給湯器・エアコン・配管・外壁工事など、一定のタイミングでまとまった修繕費を負担する必要が出てきます。内容によっては高額になる場合もあり、収支に影響を与える要因となります。
そのため、購入前に物件ごとの長期修繕計画を確認し、将来的に必要な修繕の時期や概算費用を把握しておくことが望まれます。あらかじめ積立を行っておくことで、急な出費にも対応しやすくなり、運用の安定性も確保できます。
不動産投資の始め方

情報収集を行う
不動産投資の第一歩は、仕組みを正しく理解するための情報収集です。基礎知識が不足したまま始めてしまうと、重要な判断を誤り、思わぬ損失につながるケースもあります。書籍や専門サイトで基礎を学ぶことはもちろん、実際に運用に携わる専門家の話を聞くことで、数字だけでは判断できない“実務の視点”も得られます。
特に不動産投資の経験が浅い場合、ネット上の不確かな情報に影響されやすいため、信頼性の高い企業が提供するセミナーや個別相談を活用することが、効率的で安全な学び方と言えます。
投資の目的を明確化
不動産投資では、老後の収入源を確保したいのか、毎月の手取りを増やしたいのかなど、目的によって選ぶべき物件や立地、ローンの組み方が大きく変わります。目的が明確になっていると、自分に必要な条件が自然と整理され、数多くの物件の中から適切な選択肢を絞り込みやすくなります。
まずは「何年後に、どれだけの収入を得たいのか」という具体的なゴールを設定するところから始めることで、投資の方向性がブレずに進められます。
投資物件を探す
不動産投資の収益性は、物件そのものの状態だけでなく、立地条件にも左右されます。外観や内装が魅力的であっても、最寄り駅からのアクセスや周辺施設の利便性が不足していれば、入居者が集まりにくく、空室が長期化する可能性があります。
そのため、駅からの距離・周辺環境・治安・再開発の動きなどを総合的に確認し、賃貸需要が安定するエリアを選ぶことが、失敗を防ぐうえで重要なポイントです。また、内覧時には建物の管理状況や共用部の清潔度、過去の修繕履歴を細かく確認し、長期運用に適した物件であるかを判断しましょう。
ローンの審査を受ける
金融機関によるローン審査では、年収・勤務先・勤続年数・既存の借入状況・信用情報といった個人要素に加え、物件の収益性が評価対象になる場合もあります。
借入条件は運用後の手残りに直結するため、金利や返済期間、借入可能額、団体信用生命保険の内容などを比較し、自身の資金計画に最も適した金融機関を選ぶことが大切です。
物件の購入
次に、売買契約へと進みます。物件の購入時には登記費用や火災保険料、固定資産税の精算金といった、物件価格以外の費用も発生するため、総費用を正確に把握しておくことで、後のトラブルを避けやすくなります。
管理会社を検討する
賃貸管理には、入居者募集や家賃の入金確認、退去時の立会い、クレーム対応、修繕手配など、日常的に多様な業務が伴います。これらをすべて自分で行うのは負担が重く、管理会社に委託することで運用の効率性と安定性を高めることができます。
入居者を募集して運用開始
管理体制が整ったら、いよいよ入居者募集の段階に進みます。管理会社は仲介会社と連携し、広告掲載・写真撮影・内覧対応などを進めながら、地域の相場に即した家賃設定で入居者を確保していきます。
また、広告写真の質や掲載のタイミングは、問い合わせの数や内覧希望者の動きに大きく影響します。清潔感のある室内写真を用意し、繁忙期(1〜3月)に合わせて募集を強化することで、早期の入居が期待できます。
初心者が不動産投資を成功させる4つのポイント

余裕のある資金計画を立てる
不動産投資には、ローン返済に加えて、管理費・修繕積立金・固定資産税・突発的な修繕費など、想定しておくべき支出が複数あります。
収支シミュレーションを実施する際は、理想的な数字だけで判断するのではなく、空室期間や修繕費を織り込んだ“やや厳しめの計画”でも運用できるかを確認しておくことをおすすめします。
初心者の場合、「収支が黒字であれば問題ない」と捉えがちですが、返済比率が高すぎると生活資金や貯蓄に負担が生じるケースもあります。毎月の返済額が年収に対して適切な範囲に収まっているか、長期的に無理なく続けられるかを冷静に判断する必要性があります。
レバレッジ効果を活かす
不動産投資は、銀行融資を活用して自己資金以上の投資規模を確保できるという強みを持っています。ただし、レバレッジは高ければ良いというものではありません。
返済比率が高すぎる借入は、空室や修繕が発生した際に資金繰りを圧迫しやすくなります。逆に、適切な借入であれば、毎月の返済を無理なく続けながら資産形成を加速させることができます。
金利や返済期間の設定によっても収支は大きく変わるため、複数の金融機関を比較し、過度なリスクを取らずにレバレッジ効果を最大限活かすことが成功へとつながるポイントです。
人口が進んでいる都市部で物件を購入する
賃貸需要は立地に強く依存するため、人口増加・再開発・利便性の高い都市部は、空室になりにくく、初心者にとって比較的安全性が高い選択肢となります。
物件選びでは、駅からの距離、大学やオフィス街へのアクセス、商業施設の充実度といった生活利便性の高さも重要な判断材料です。快適な環境が整っている物件ほど入居期間が長くなる傾向があり、運用の見通しが立てやすくなります。
信頼できる不動産会社を選ぶ
不動産投資を成功させるためには、物件選びと同様に、信頼できるパートナー(不動産会社)を見つけることが重要です。
たとえば、客観的な収支シミュレーションを提示してくれるか、デメリットについても透明性のある説明を行うか、購入後の管理やサポート体制が整っているかなど、信頼性を確認するための評価基準は多岐にわたります。
また、投資は長期的に取り組むものだからこそ、販売して終わりではなく、購入後の運用まで見据えて支援してくれる企業を選ぶことでより安心して投資を継続できます。
不動産投資を味方につけて、将来の資産形成を加速させよう

不動産投資は、正しい知識と判断を積み重ねることで、初心者でも十分に成功を狙える投資手法です。家賃収入という安定したキャッシュフローを得ながら、節税や資産価値の維持、老後の収入確保など、多くのメリットを享受できます。
また、不動産投資を着実に進めるためには、適切な資金計画や賃貸需要の高い立地の選定、信頼できるパートナーの存在など、押さえておきたいポイントがいくつかあります。これらを一つひとつ丁寧に実践することで、将来的に大きな資産を築くための確かな基盤が整います。
ストラーダグループでは、目的のヒアリングから物件選び・ローン相談・購入後の運用サポートまで、一連の投資プロセスをトータルで支援しています。
不動産投資をご検討中で、「何から始めればよいかわからない」「自分に合う物件を知りたい」と感じている方は、ぜひ弊社までお気軽にお声掛けください。ご相談はLINE・お問い合わせフォームより無料で承っております。
将来の資産形成に向けて、確かな一歩をともに踏み出していきましょう。
不動産投資の関連記事
不動産売買(購入・売却)の基礎知識と成功のコツを徹底解説【2026年】
不動産売却の税金や手数料完全マニュアル・手取りを最大化する方法
賃貸物件選びのコツと契約時に注意すべきポイント【2026年】