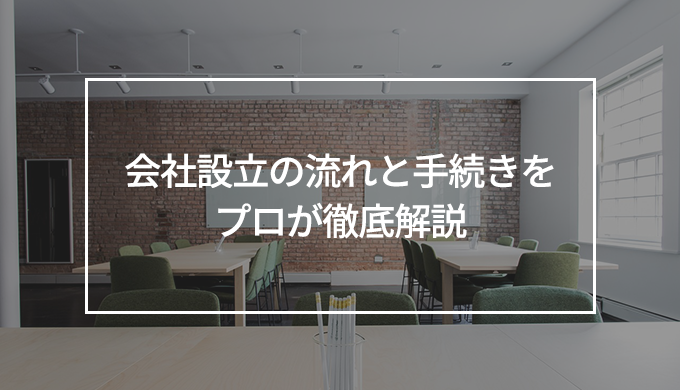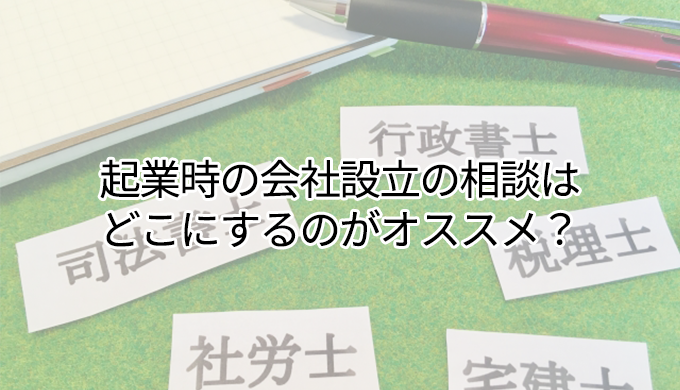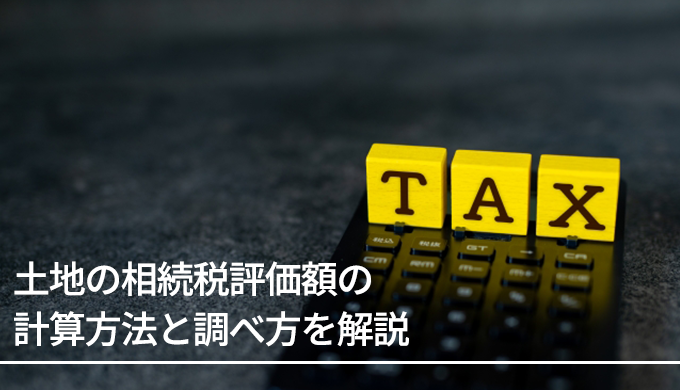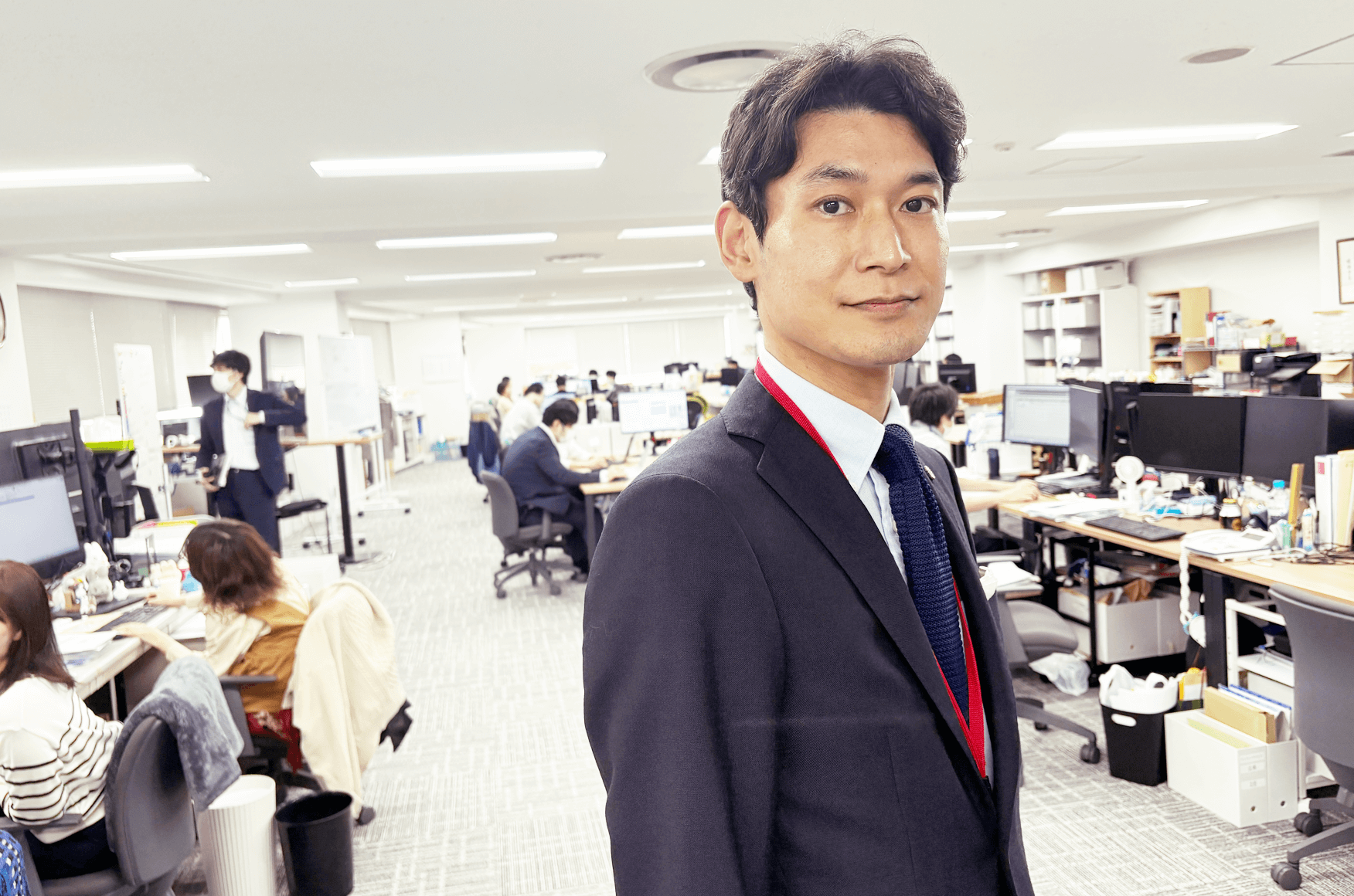相続は、家族が亡くなった後に避けて通れない重要な手続きです。相続税の計算や遺産の分割、登記など、専門的な知識が求められる場面が多く、何から手を付けてよいのか戸惑う方も少なくありません。また、相続の進め方を誤ると、思わぬ税負担や親族間のトラブルに発展するケースもあります。
本記事では、相続税と相続手続きの基本的な流れをはじめ、トラブルを防ぐための事前対策についてもわかりやすく解説します。相続に関する不安をお持ちの方は、ぜひ参考にしてください。
Contents
相続税とは?対象となる財産の種類

相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した際に課される税金です。すべての財産に課税されるわけではなく、基礎控除額を超える場合にのみ発生します。
相続税の課税対象となる主な財産は以下の通りです。
| 財産の種類 | 主な内容 |
|---|---|
| 金融資産 | 現金・預貯金・有価証券・公社債など |
| 不動産(土地) | 宅地・農地・山林・原野・牧場・借地権・地上権・賃借権など |
| 不動産(家屋) | 家屋・倉庫・駐車場・借家権・マンション・アパートなどの物件 |
| 動産 | 家具・貴金属・宝石・書画骨董品・自動車など |
| 各種権利 | 著作権・特許権・商標権・電話加入権・ゴルフ会員権など |
| 事業用資産 | 機械・備品・商品・原材料・農産物・牛馬・売掛金など |
また、借入金や未払い税金などマイナスの財産も相続の対象となります。課税対象額を算出する際には、これらの資産・負債を正確に把握し、正しい評価額で計算することが重要です。
相続税の計算方法
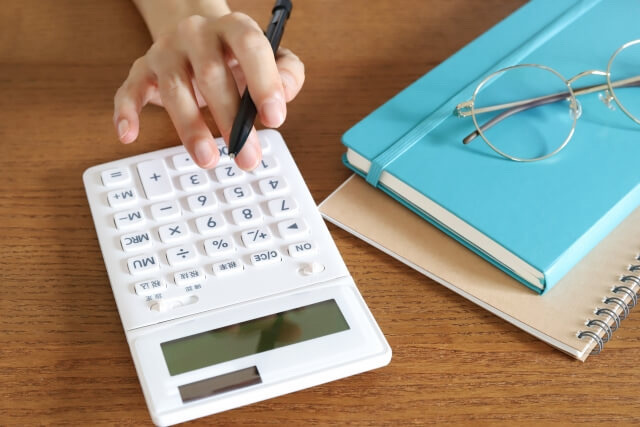
相続税の基本的な計算方法は、以下の通りです。
①課税価格(正味の遺産額)を求める
まず、被相続人が残したすべての財産(現金、預貯金、不動産、株式、保険金など)を合算し、そこから債務や葬儀費用などの法定の控除を差し引きます。これが「課税価格の合計(正味の遺産額)」です。
②基礎控除を差し引く
課税価格の合計から、基礎控除額(=3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引きます。差し引いた残りが「課税遺産総額」です。相続人の中で相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算に用いる法定相続人の人数は変わりません。
③法定相続分で按分して各相続人分の仮の取得額を計算
課税遺産総額を、法律で定められた法定相続分の割合に従って分けます。例えば、相続人が配偶者1人と子ども2人の場合、配偶者は全体の1/2、子どもは残りの1/2を2人で均等に分けます。こうして得られる金額が、相続税を計算するための仮の取得額です。
④按分した各金額に税率を当てはめて合算する(相続税の総額)
法定相続分に応じた仮の取得額をもとに、以下の速算表の税率を当てはめ、控除額を差し引いた上で各相続人の相続税額を計算します。(具体例:仮の取得額が5,000万円の場合は、「税率20%」を掛けて「控除額200万円」を引くという流れになります。)
その後、全員分の税額を合計すると「相続税の総額」が求められます。
| 法定相続分に応ずる仮の取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ー |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
⑤実際の取得割合に応じて最終的に按分する
最後に、算出した相続税の総額を、相続人が実際に取得した割合(遺産分割後の取得額)に応じて按分します。こうして各人の確定税額が決まります。
相続手続きの流れについて

遺言書の有無の確認
まず行うべきは、遺言書があるかどうかの確認です。遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などがあり、それぞれ手続き方法が異なります。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、家庭裁判所で「検認手続き」が必要です。検認手続きとは、遺言書の内容を開封して確認し、改ざんや偽造を防ぐための制度で、遺言の執行前に実施します。公正証書遺言であれば検認は不要で、すぐに内容の執行が可能です。
相続人の調査・確定
次に、戸籍謄本や除籍謄本を取得し、法定相続人を調査します。相続人には、配偶者は常に含まれ、子ども・直系尊属(両親や祖父母)・兄弟姉妹が順に優先順位を持ちます。相続人の調査を誤ると、後にトラブルとなる可能性があるため、慎重に手続きを進めることが大切です。
相続財産の調査
相続財産の調査は、相続税額の基礎となる重要な工程です。不動産、預貯金、株式、保険、負債などを漏れなく洗い出し、一覧化します。通帳の履歴や登記簿謄本、証券会社の残高報告書などを確認するほか、生命保険会社や勤務先への問い合わせも行います。
相続の種類の選択
相続では、財産や負債の状況に応じて、次の3つの方法から選ぶことができます。
単純承認
単純承認とは、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて無条件で相続することです。特別な手続きは不要で、相続開始を知ってから3か月以内に限定承認もしくは相続放棄の申述をしなかった場合は、自動的に単純承認したとみなされます。
限定承認
限定承認とは、相続した財産の中に借金などのマイナスの財産が多い場合に、相続したプラスの財産の範囲内でのみ負債を支払う方法です。これにより、相続人は自分の固有の財産を使って負債を返済する必要がなく、安心して相続を承認できます。
相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続せず、相続人としての地位も放棄する手続きです。相続人ではないと扱われるため、借金などの負債を負うことはありません。
遺産分割協議
相続人全員で、財産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。協議がまとまった場合は「遺産分割協議書」を作成し、全員が署名・押印します。協議が難航する場合や相続人間で意見が合わない場合は、調停・審判といった家庭裁判所の手続きに進むこともあります。
相続税の申告・納付手続き
相続税の申告・納付は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に実施 する必要があります。遺産分割が終わっていなくても、期限までに申告を済ませる義務が生じるため、その点に十分注意しましょう。税額の計算や特例の適用可否は複雑なため、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。
相続登記
不動産を相続した場合、所有権を相続人名義に変更する「相続登記」が欠かせません。2024年4月からは相続登記が義務化されており、3年以内に登記を行わない場合、過料が科される可能性があります。登記の際には、遺産分割協議書や相続人の印鑑証明書など、所定の書類を揃えて申請することが求められます。
相続トラブルを未然に防ぐ方法

現状の財産を確認する
まずは、現状の財産を正確に把握することが重要です。資産・負債の一覧を作成し、家族にも内容を共有しておくと、相続時の混乱を防ぐことができます。なかでも、不動産や株式など評価額が変動しやすい資産は、定期的に見直しておくとより安心です。
遺言書の作成
遺言書は、相続トラブルを防ぐ最も有効な手段です。「誰に」「どの財産を」「どのように分けるか」を明確にしておくことで、相続人同士の争いを未然に回避できます。特に相続人以外に財産を残したい場合や、事業承継を円滑に行いたい場合には、公正証書遺言の作成が適しています。
生前贈与を活用
生前贈与を活用することで、相続発生前に財産を計画的に移転でき、相続税の負担を軽減できます。年間110万円までは贈与税がかからない「暦年贈与」や、住宅取得資金・教育資金の贈与非課税制度など、制度を上手に利用しましょう。
生命保険を活用
生命保険金は「みなし相続財産」として扱われますが、非課税枠(500万円×法定相続人の数) が設けられています。また、受取人を指定することで、現金をすぐに受け取れる点もメリットです。葬儀費用や納税資金として活用できるため、相続時の資金準備としても有効です。
家族信託
家族信託とは、自分の財産管理を信頼できる家族に任せる仕組みです。認知症や判断能力の低下によって財産管理が難しくなった場合でも、スムーズな資産運用・承継が可能になります。近年では、高齢期の財産管理や二次相続対策として注目されています。
専門家へ相談する
相続や税金の問題は、一人で判断すると誤解や漏れが生じやすい分野です。税理士や司法書士、行政書士など専門家へ早めに相談することで、リスクを最小限に抑えられます。
相続手続きのお悩みはストラーダグループへ

相続に関する手続きは多岐にわたり、専門知識と正確な判断が求められます。ストラーダグループでは、「何から始めればいいのか分からない」「相続税がかかるか不安」といった初期相談から、相続登記や申告・生前対策まで、状況に応じた最適なサポートをご提案いたします。
相談予約は無料で承っております。お電話または公式サイトのお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。