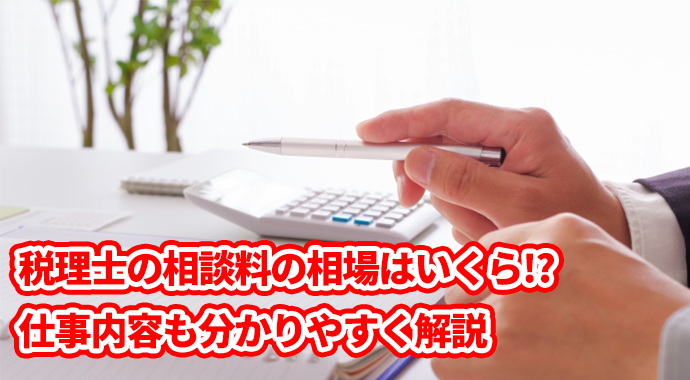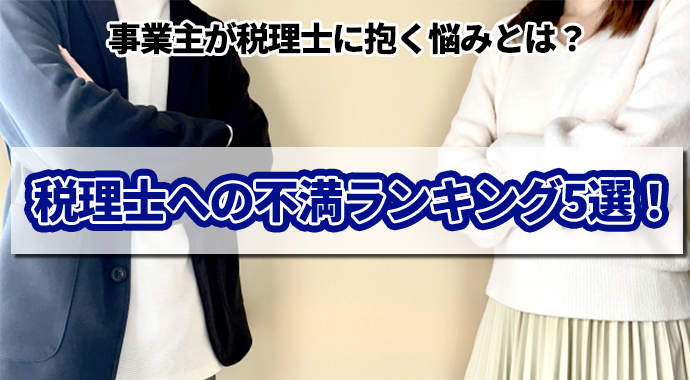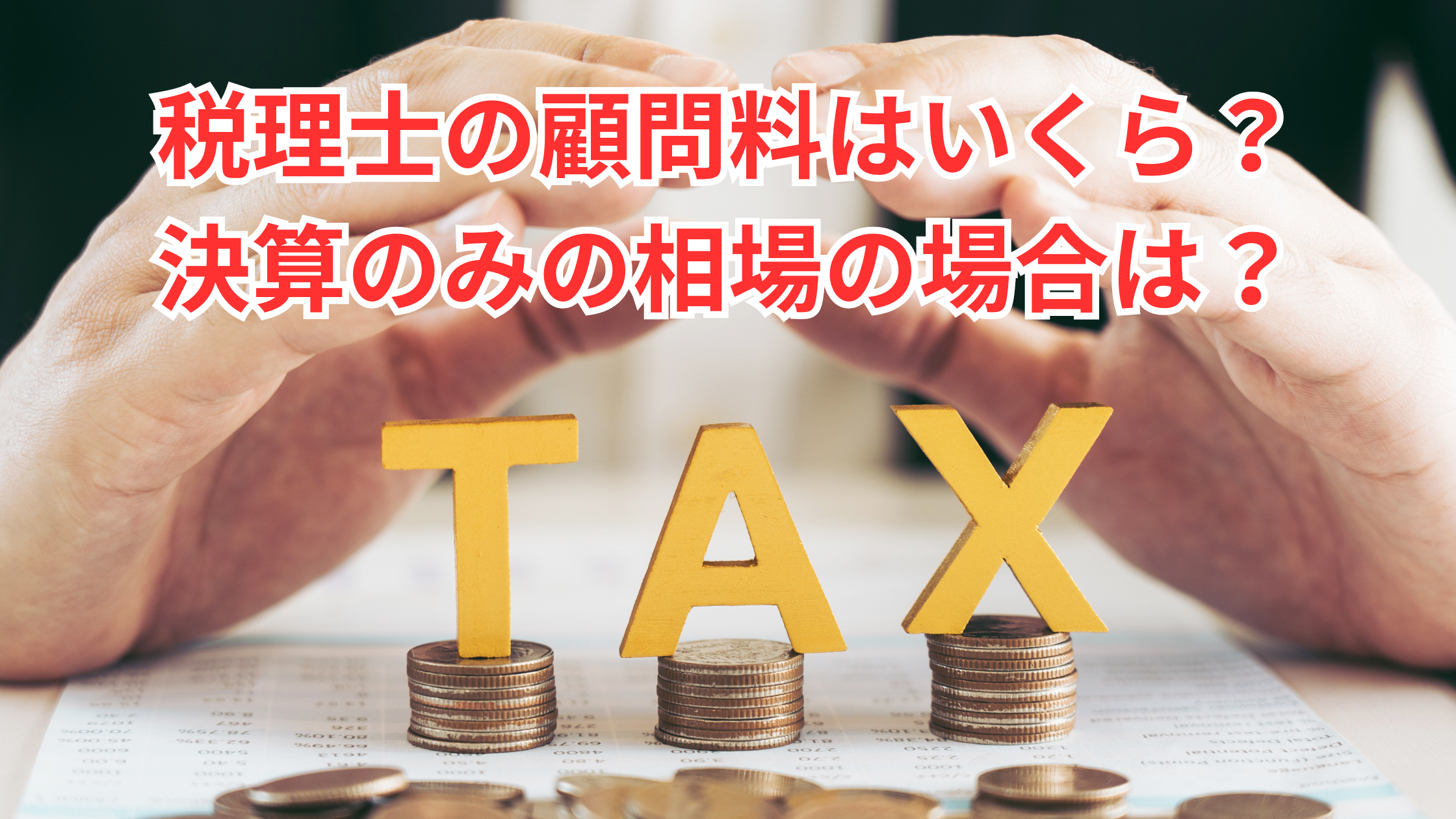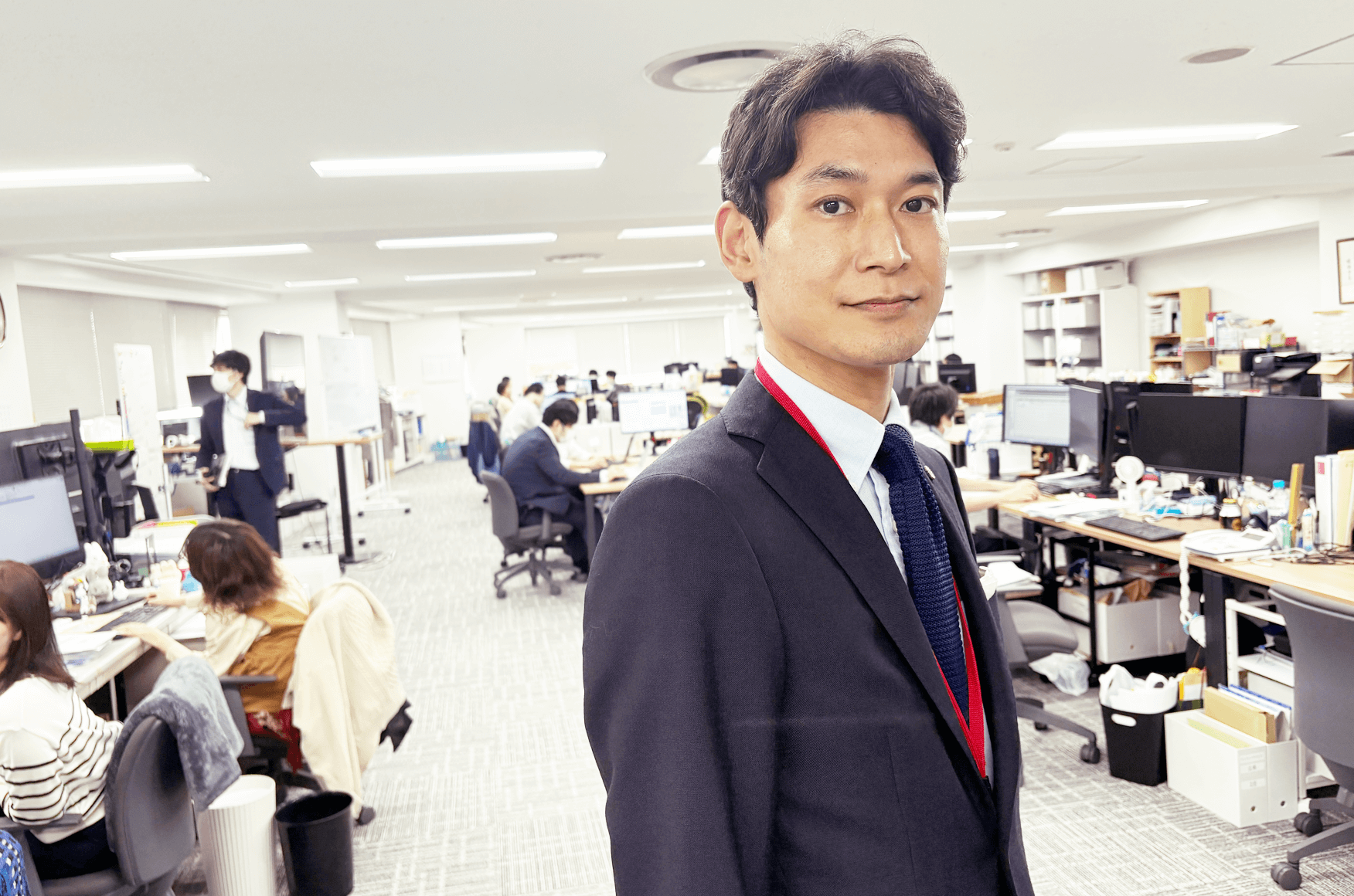エンジェル税制は非上場会社(※)に投資をしながら税負担を軽減できると同時にスタートアップ企業の成長に貢献できることから、日本経済の元気を取り戻すための鍵として近年、大きな注目を集めています。
(※)非上場会社:証券取引所で取引が出来ない株式会社をいう。日本の株式会社の99.9%は非上場会社である。
しかしながら、新NISA等の投資方法に比べるとまだまだ馴染みが浅い制度なので、メリットやデメリット・リスク管理のやり方など悩むところが多いのではないでしょうか。本記事ではエンジェル税制の概要やメリット・デメリット、具体的な活用方法について解説致します。
Contents
エンジェル税制とは?基本的な仕組みについて

エンジェル税制とは、創業して間もないスタートアップ企業に投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を講じ、スタートアップ企業への投資を促進するために作られた制度のことです。
眠っていた個人資産を将来有望な企業へ循環させることで、節税効果が期待できると共に大きなリターンを得られる可能性があります。
1997年の創設当初は100万円以上のまとまった資金が必要でしたが、令和2年度の税制改正をきっかけに株式投資型クラウドファンディング事業者が加わったことで、10万円程度の少額からでも気軽に投資ができるようになりました。
エンジェル税制の優遇措置
エンジェル税制によって受けられる優遇措置は『優遇措置A』、『優遇措置B』、『プレシード・シード特例』、『企業特例』の4種類があります。
| 措置の種類 | 控除対象 | 措置内容 | 控除上限 | 設立年数 |
|---|---|---|---|---|
| 優遇措置A | 投資全額-2,000円 | 課税繰延 | 所得金額の40%もしくは800万円の低い方 | 5年未満 |
| 優遇措置B | 投資額全額 | 課税繰延 | 上限なし | 10年未満 |
優遇措置A
設立年数5年未満の企業に対する投資額から2,000円を差し引いた金額をその年の総所得金額から控除し、課税繰延べの措置を受けることが可能です。
控除対象の投資額上限は、総所得金額の40%または800万円のいずれか低い金額となっています。優遇措置Aは所得水準が低く、早期に節税効果を実感したい方に向いています。
優遇措置B
設立年数10年未満の企業に対する投資額全額をその年に売却した他社の株式譲渡益から控除し、課税繰延べの措置を受けることが可能です。
控除対象となる投資額の上限はありません。株式で多額の利益が出ていたり、長期的な投資リターンを重視したい場合は優遇措置Aよりも優遇措置Bのほうが適しています。
| 措置の種類 | 控除対象 | 措置内容 | 控除上限 | 設立年数 |
|---|---|---|---|---|
| プレシード・シード特例 | 投資額全額 | 非課税 | 年間20億円(※上限を超える金額は課税繰延) | 5年未満 |
| 起業特例 | 自己資金による出資額全額 | 非課税 | 年間20億円(※上限を超える金額は課税繰延) | 1年未満 |
プレシード・シード特例
2023年の税制改正により新たに設けられた優遇措置です。設立5年未満かつ、営業損益0未満の企業に対する投資額全額をその年に売却した他社の株式譲渡益から控除できます。優遇措置A・優遇措置Bの措置内容については、課税繰り延べなので投資時点では課税されませんが、将来的にはスタートアップ企業の株式を売却すると繰延相当金額が売却益とともに課税される形になります。
これに対してプレシード・シード特例は課税の繰り延べではなく、年間20億円まで非課税になりますので投資家にとってはプレシード・シード特例のほうがリスクが低く、最も有利な制度であると言えるでしょう。ただし、優遇措置A・優遇措置Bよりも適用条件が厳しく、年間20億円を超えると課税繰り延べの対象になるためその点は注意が必要です。
起業特例
起業特例も2023年に新しく追加された制度の1つで、会社設立の際の出資額をその年の株式売却益から差し引き、20億円を上限として非課税の措置を受けることができます。
自らが保有している株式がその年に多額の譲渡益が見込める場合や、新たなビジネスを検討している方は是非この制度を有効活用すると良いでしょう。
エンジェル税制の優遇措置を受けるための要件

エンジェル税制を利用するには、個人投資家と対象企業の双方が以下の要件をクリアする必要があります。
個人投資家に必要な要件
- 1.金銭の支払いにより、対象企業の株式を投資をしたその年の12月31日時点で所有していること。(※他社からの譲渡株式や、現物出資は対象外)
- 2.投資先の企業が同族会社である場合、所有割合が大きいものから第3位までの持ち株割合を順に加算し、その割合が初めて50%超になる時における株主グループに属していないこと。
- 3.自らが営んでいた事業の全部を承継させた個人及びその親族等ではないこと。
企業に必要な要件
- 1.設立から10年未満の中小企業であること
- 2.未登録・未上場の株式会社であること
- 3.外部からの投資を1/6以上取り入れている会社であること
- 4.大規模法人グループの所有に属さないこと
- 5.風俗営業等に該当する事業を行う会社でない
- 6.設立経過年数毎に一定の要件(研究者の人数、営業キャッシュフロー、試験研究費の売上割合、売上高成長率等)を充足すること
エンジェル税制のメリット

個人投資家側のメリット
節税に繋がる
エンジェル税制の代表的なメリットとして、スタートアップ企業に貢献しながら自分自身の所得や投資額に応じて節税できる点が挙げられます。また、2023年に新しく誕生した起業特例を利用すれば所得税が非課税になるため、税負担を軽減できると同時に新規事業成功の確度を高めることに繋がるでしょう。
ハイリターンが期待できる
エンジェル税制は、出資先のスタートアップ企業の成長具合によっては少額の投資であっても大きなリターンが期待できる可能性を秘めています。例えばアメリカの『ジェイソン・カラカニス氏』は日本でも有名な配車サービス”Uber”の創業初期に1,000万の投資を行い、100億円もの利益を得た伝説のエンジェル投資家として知られています。
世の中には投資信託や不動産投資、生命保険、個人型確定拠出年金(iDeCo)といった様々な資産運用の手段がありますが、どの投資も年率数パーセントが基本です。エンジェル投資のようにホームラン規模の運用益を狙えるケースは他に存在しないと言っても良いでしょう。
損失が出ても所得控除が受けられる
エンジェル税制は投資時点だけでなく、株式を売却した時点でも優遇措置を受けることができます。具体的な措置内容としては、投資先の企業が経営破綻しても発生した損失をその年の他の譲渡益と相殺することができるというものです。また、その年に相殺できない場合は翌年以降3年間に渡って相殺できる点も今後エンジェル税制の利用を検討している投資家にとって大きな安心材料になることでしょう。
企業側のメリット

資金調達がしやすくなる
節税効果が期待できるエンジェル税制は個人投資家にとって非常に魅力的な制度であることから、訴求ポイントとしてアピールを行うことで投資が促進され、資金調達がしやすくなります。
また、エンジェル税制の対象企業として認可されると、経済産業省のホームページに会社名や所在地・連絡先などの情報が公開されます。これは厳しい審査にクリアした信用の証にもなりますので、多くの投資家の関心を惹きつけるチャンスがより一層広がることでしょう。
返済義務がない
銀行などの金融機関から資金調達を行う場合、元本と利息を返済する必要があります。一方、エンジェル税制を利用する場合、個人投資家から受けた出資金は返済義務がありませんので資金繰りにゆとりを持たせることができます。
人脈と新たなビジネスチャンスが広がる
個人投資家の中には自らが経営者だった元起業家も多いため、そのような投資家から出資してもらうことでビジネスにおけるフィードバックやアドバイスが得られることもメリットの1つです。
また、個人投資家はこれまで接点を持ってきた取引先や自社と同じように投資を受けているスタートアップ企業など人脈が豊富な傾向がありますので、そのような関係を通じて新たなビジネスチャンスやパートナーシップが生まれる可能性があるかもしれません。
エンジェル税制のデメリット

個人投資家側のデメリット
投資リスクが高い
エンジェル税制の対象となる企業は創業から間もないスタートアップであり、会社の事業モデルが確立していないケースが殆どです。そのため、成功するかどうかの判断が難しく、最悪の場合には投資した資金の全額を失う可能性も否めません。
このような事態を避けるためにも安易に出資を決めるのではなく、経営陣の話を入念に聞いたり、自身の資産状況やリスクの許容度を見極めるなどリスク管理を徹底的に行うことが大切です。
税優遇措置の限界
エンジェル税制の優遇措置は適用区分が分けられており、それぞれ享受できる内容が異なるため仕組みを十分に理解していなければ期待していた減税効果を実感できない場合があります。
例えば優遇措置AやBで受けられるのは、”課税の繰り延べ”です。一時的に税負担から回避できたとしても最終的には譲渡益に課税されますので、厳密に考えると節税に有利な対策であるとは言い切れない側面を持っています。
一方、プレシード・シード特例と起業特例は課税の繰り延べではなく、非課税措置であるため純粋な節税メリットを得ることができます。節税効果を最大限に高めたい場合はプレシード・シード特例や企業特例の導入を検討するようにしましょう。
各種手続きや書類の準備が煩雑
エンジェル税制の適用を受けるには、確定申告の手続きが欠かせません。一般的な申告時に比べると提出書類が増えるため、ただでさえ面倒な準備がより煩雑になります。特に持ち株が多い個人投資家の場合、多大な時間と労力を要しますので少しでも不安がある場合は税理士や専門家に依頼することを推奨致します。
企業側のデメリット
審査が厳しい
エンジェル税制を利用するスタートアップ企業は投資家による株式の払い込みを受けた後、各都道府県にエンジェル税制の適用対象企業であることを確認する必要があります。適用にあたっては設立年数や事業内容、外部資本比率など規定内の要件を全てクリアしなければならないため、その条件が思いのほか厳しいと感じるかもしれません。
ただし、審査に無事通過すれば個人投資家は安心して出資できると同時に、要件を満たす個人のみがエンジェル税制の対象として決められているため、投資を受ける企業側としても企業乗っ取りなどの悪意のある投資や詐欺行為を回避することに繋がります。
資金調達額の制限
エンジェル税制は法人ではなく個人が対象となるため、1人では出資できる金額には限りがあります。また、最小10万円から始められるということもあり、個人投資家の経済状況や投資スタイルによっては多額の資金調達は期待できないケースも考えられます。高額な出資を必要としている企業はベンチャーキャピタル(VC)からの出資や銀行などの金融機関から融資を受けることについて検討することが必要でしょう。
経営の自由度の低下
企業の経営権は原則として持株比率で決まるため資金調達を行う際、株式を渡し過ぎると個人投資家に経営の実権を奪われてしまう恐れがあります。シード期のスタートアップは今後企業価値が本当に上がるのか明確ではない場合が多いので、一度持分比率が減ってしまえば相当分を取り戻すことが難しいのが現状です。
また、成長ステージに立つ企業であるほど個人投資家側は最新の経営状況や重要なハイライトなどの情報を知りたいと感じています。
信頼性を高めるためにも、定期的にコミニュケーションの機会を設けることは大切なことですが、個人投資家によっては自らがリターンを得られる可能性を最大限まで高めるために助言やアドバイスを行うだけでなく、過度に干渉してくる場合もないとは言えません。過剰なサポートは経営に支障をきたすリスクがありますので、事業の状況に応じて適度な距離感を保つことが重要です。
エンジェル税制活用の流れについて

1.事前確認制度の利用の有無
エンジェル税制には事前確認制度というものが存在します。この制度を利用する場合、出資を受ける企業はエンジェル税制の適用条件を満たしていることを都道府県に認めてもらう必要がありますので、必要書類を用意した上で都道府県知事の確認書の交付を受けるようにして下さい。
主な必要書類について
- ・事前確認書
- ・特定新規中小企業者の要件に該当することの宣言書
- ・定款または登記事項証明書
- ・財務諸表
- ・その他必要な情報(業種や従業員数など)
事前確認制度を利用しない場合は投資を受けてからでも確認を受けることが可能です。どちらを選ぶかで申請手順が変わってきますので、企業側はまず最初に利用の有無について決めるようにしましょう。
2.投資契約の締結
ベンチャーキャピタルなど投資に慣れているプロの場合、契約締結を提示することが一般的ですが、会社法上においては投資契約の締結は特に義務付けられていないため、エンジェル税制などを利用する個人投資家の中には詳しい規定を定めないまま安易に投資を行っているケースも多く見受けられます。
エンジェル税制を利用した投資の実行、または出資を受けることが決まったら何らかのトラブルによって互いに損失を被らないためにも、出資条件や株式について十分に話し合いながら取り決め、投資契約を締結することが望ましいでしょう。
3.投資の実行
個人投資家側はエンジェル税制の対象要件を確認した後、出資を決めた企業に対して実際に投資を行います。スタートアップ企業に投資する方法としては、『直接投資』・『設定投資事業有限責任組合(LPS)』・『認定少額電子募集取扱業者』の3種類があります。
①直接投資
個人投資家がスタートアップ企業と直接取引を行い、株式を取得する方法です。この投資方法は投資条件や契約内容を自由に決められるというメリットがある一方、交渉する際に多くの時間や労力を要したり、想定していたよりも投資額や株式の保有率が高くなってしまう可能性があります。
②設定投資事業有限責任組合(LPS)
LPSとは、スタートアップ企業を支援するために創設された経済産業大臣認定の投資ファンドのことです。プロの目利きによっておすすめの企業や事業内容などの情報を詳しく知ることができるため、効率的な資産運用を実現することにも繋がります。
③認定少額電子募集取扱業者(ECF)
ECFは株式投資型のクラウドファンディングサービスのことで、個人投資家はインターネットを通じてスタートアップ企業の株式を購入することができます。時間がない方、投資経験が浅い方でも気軽に利用しやすく、投資額や株式の割合を低く抑えられる傾向にあります。
4.個人投資家に書類を提出する
スタートアップ企業は都道府県から交付される『エンジェル税制対象企業証明書』を個人投資家に提出する必要があります。この証明書は個人投資家が確定申告を行う際に欠かせない、重要な書類です。
また、その他にも会社の設立年月日や外部資本比率・株式の取得価額や売却価額等、個人投資家に対して開示すべき情報が多数ありますのでスムーズに取引が進められるようこれらの情報について予めまとめておくと良いでしょう。
5.確定申告を行う
個人投資家はスタートアップ企業から交付された確認書を含む、下記のような書類を居住地管轄の税務署に提出して確定申告を行います。受ける優遇措置に応じて必要な書類が異なりますので、不備が無いようご注意下さい。
- ①都道府県知事の確認書又は認定投資事業有限責任組合が発行した確認書及び認定証の写し、若しくは認定少額電子募集取扱業者が発行した確認書及び認定証の写し
- ②発行会社が交付する一定の株主に該当しない旨の確認書
- ③株式投資契約書の写し
- ④株式異動状況明細書
- ⑤株式の譲渡等に関する書類
- ⑥清算結了の登記事項証明書、破産手続開始の決定の公告等
- ⑦株式等に係る譲渡所得税等の金額計算明細書(特定権利行使株式及び特定投資株式分がある場合)
- ⑧特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書
- ⑨所得所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(特定投資株式に係る譲渡損失の計算及び繰越控除用)
- ⑩特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
なお、エンジェル税制はe-Taxからも申告することができますが、一部の添付書類は書面にて提出を要する場合があります。特に初めてエンジェル税制を利用する個人投資家の方で心配な点がある場合や、複雑なケースに該当する場合は投資先の企業へ直接確認したり、税理士への依頼について検討するようにしましょう。
投資先や個人投資家の探し方について

先述した通り、エンジェル税制の適用対象企業として認められることで中小企業庁のHPに社名が公開されますが、エンジェル税制は他の投資方法に比べると利用者が少ないため、スタートアップ企業サイドは連絡を待つだけの受け身の状態でいても、希望条件に合う個人投資家とのマッチング率を上げることは難しいです。
設定投資事業有限責任組合(LPS)や中小企業庁のHPなど国が創設したサービスも併用しながら、様々な方法でアプローチを行いましょう。
マッチングサイトを利用する
エンジェル投資家と資金調達を希望するスタートアップ企業を結ぶ、専用のマッチングサイトを利用することで経営方針や出資額などの条件も設定できるため、効率的に自社に合った個人投資家を見つけやすくなります。
具体的には『ANGEL PORT』や『StartupList』など様々なマッチングサイトが存在します。詐欺リスクを回避するためにもできるだけ実名制のマッチングサイトを利用したり、投資家のプロフィールや過去の実績について注意深く確認するようにしましょう。
交流会やセミナーに参加する
起業家に関連する交流会やセミナーなどのイベントに足を運ぶこともおすすめの手段のひとつです。これらの場には出資をしてもらえる可能性が高い投資家と直接会話する機会が得られるだけでなく、他の起業家から経営に関する情報なども入手できるためビジネス全体に良い影響を与えます。
特に”ビジネスコンテスト”とも呼ばれているピッチコンテストは、有名なエンジェル投資家が審査員や観客として参加しているケースが多いです。
ピッチコンテストを通じて自社が行っている事業内容や熱意をアピールすることで、投資家からの関心を引くチャンスが広がることでしょう。また、例え優勝を逃した場合でも登壇することによって会社の認知度が向上し、後日具体的な出資交渉が決まることも珍しくありません。
SNSを活用する
エンジェル投資家の探し方の1つとして、Xやビジネス領域に特化したLinkedIn等のSNSで情報発信を行っているエンジェル投資家を検索し、DMを使って直接コンタクトを取るという方法もあります。
ただし、全くツテが無い状態で連絡しても反応が返ってくる可能性は少ないため、もしSNSのフォロワーやお知り合いの中に、エンジェル投資家と繋がっている方がいればまずはその人にアプローチを行うのが理想的です。共通の知人を介して連絡が来れば、投資家サイドも『〇〇さん推奨の企業なら』と資金調達に成功する可能性も高まることでしょう。
その他、不特定多数の人々が閲覧しているというSNSの特性上、反社会勢力など詐欺を目的とした悪意のある人物が接触してくる恐れも考えられますので、活用する際には徹底したリスク管理が不可欠です。
エンジェル税制に関するよくある質問

エンジェル税制はサラリーマンでも利用できますか?
法人を除く個人投資家であれば新NISAや外貨預金などの投資方法と同じく、一般企業に勤める会社員(サラリーマンやOL)から個人事業主まで利用することが可能です。
ただし、通常は年末調整のみで済ませている方も、確定申告をしなければエンジェル税制の適用対象外となってしまうので必ず期限内に申告手続きを終わらせるようにしましょう。
エンジェル税制の適用範囲は全国ですか?それとも地域によって異なりますか?
エンジェル税制は日本に住所がある方、もしくは現在まで引き続いて1年以上『居所』がある個人であれば地域や国籍を問わず、エンジェル税制の利用が認められています。(※ここで言う、居所とは建設などの作業現場や工場・支店といった事業を行うための一定の場所のことを指します。)
日本にはエンジェル投資家がどのくらいいますか?
日本で活躍しているエンジェル投資家の数は約400人程度で、投資文化が根付いているアメリカに比べるとまだまだ少ないのが現状です。
しかし、日本におけるエンジェル税制の市場規模は2018年の時点で約43億円にも上っている他、Yahoo! JAPANの立ち上げやガンホー・オンライン・エンターテイメントの創業に携わってきた『孫泰蔵』氏や元サッカー選手の『本田圭佑』氏など有名な起業家の間でもエンジェル投資家が増えており、その存在感は急速に広がりつつあります。
確定申告以外に投資家が必要な手続きはありますか?
出資側は確定申告以外の特別な手続きは基本的に必要ありませんが、投資をしたスタートアップ企業の株式を保有している間に住所や名前の変更があった場合は企業に対して速やかに連絡を行うようにしましょう。また、将来的に株式を譲渡した際は、税制上の優遇を受けるためにも譲渡益や損失した金額について適切に申告することが求められます。
【まとめ】エンジェル税制で働く未来をもっと豊かに

個人投資家とスタートアップ企業がWin-Winの関係性を築きながら、様々な恩恵を受けられるエンジェル税制は増税や物価高騰など、経済の低迷に悩まされている日本人とってまさに天使のような救世主的制度です。
弊社では確定申告に関する書類作成のサポートから、資金調達を円滑に進めるためのアドバイスまでお客様のご希望や状況に合わせて多種多様なサービスをご提供しています。無料相談予約はお電話やメール、LINEからも承っておりますので、エンジェル税制の適用についてご不明な点がありましたら是非お気軽にお問合せ下さい。
なお、税理士法人や税理士事務所の中には、エンジェル税制の実施経験がないケースもございます。制度を正確に理解し、期限内に確実に申請を完了させるためには、豊富な実務経験を有する専門家への相談が重要です。エンジェル税制の申請でお困りの際は、経験豊富なストラーダ税理士法人までぜひご相談ください。