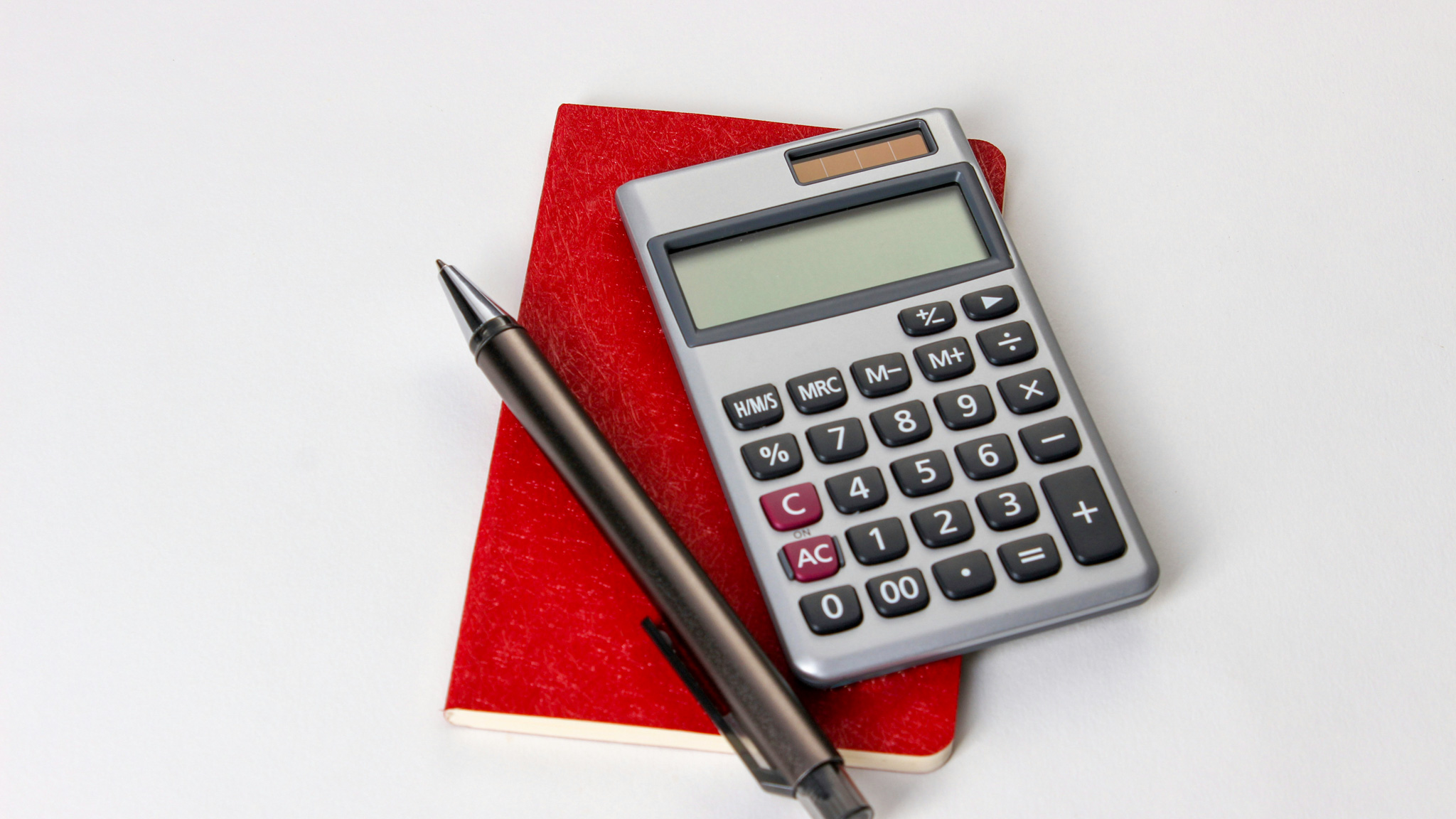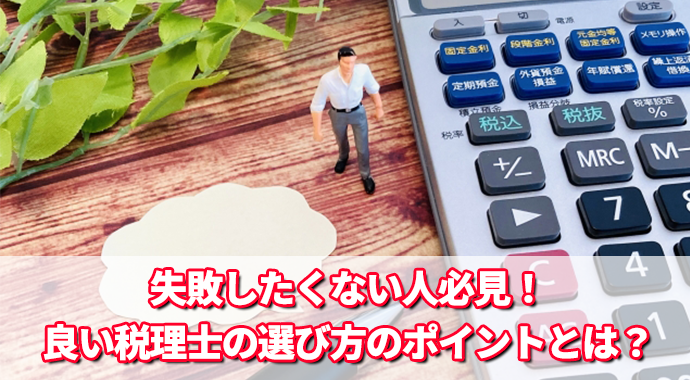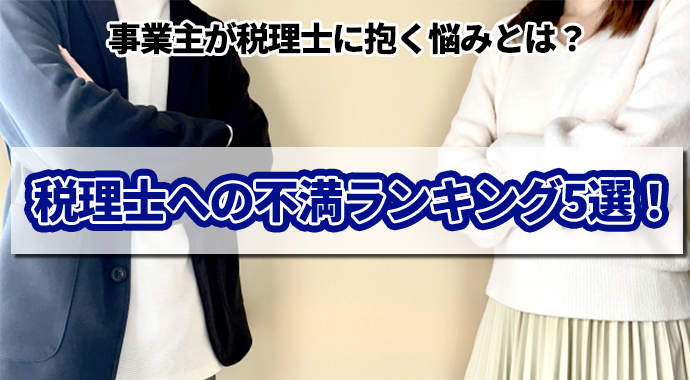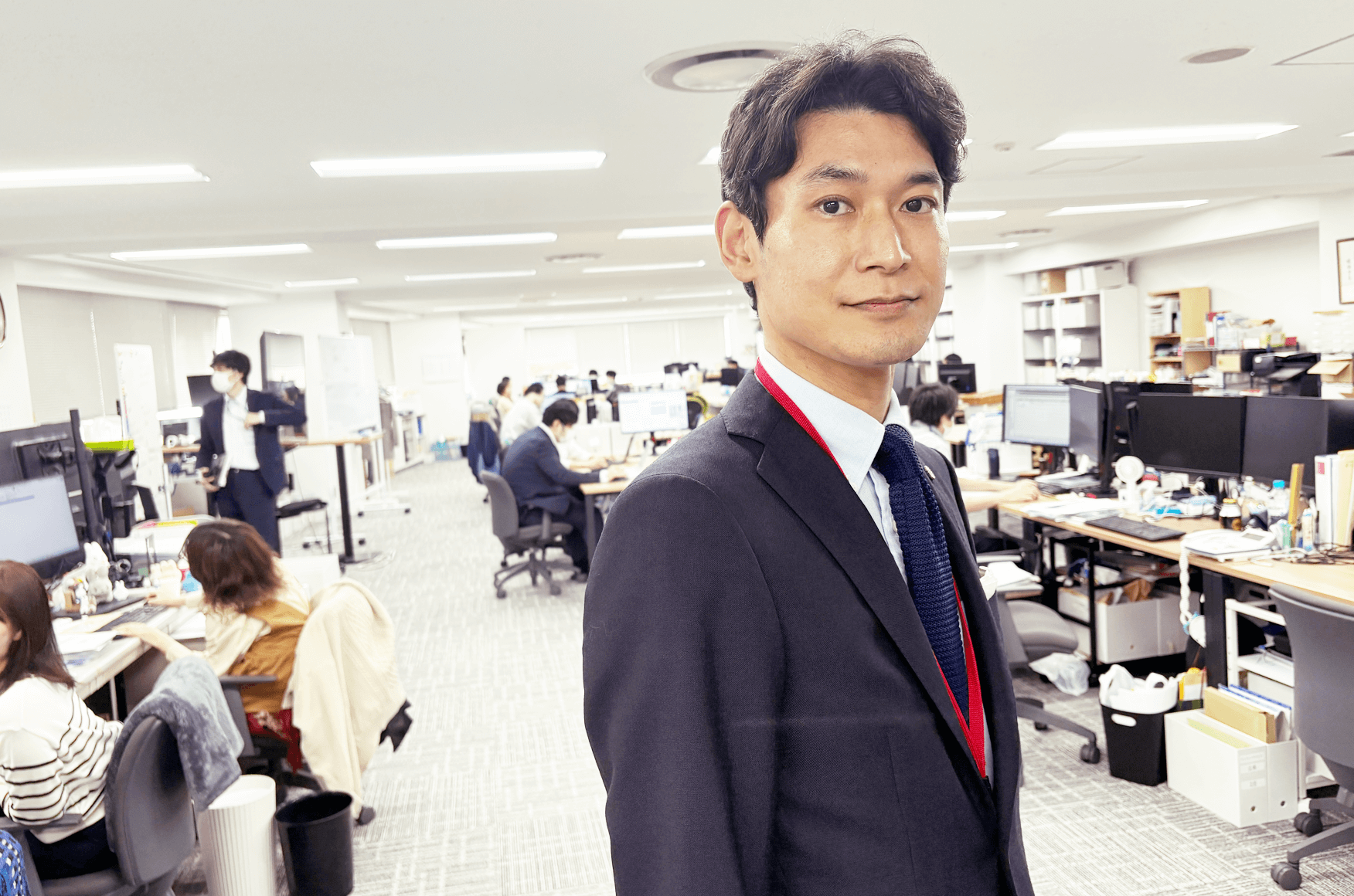税務調査は、企業や個人事業主にとって避けて通れない重要なプロセスです。適切に対応しなければ、余計な追徴課税やペナルティを受ける可能性があり、経営に大きな影響を与えることもあります。一方で、事前に適切な準備を行い、税務リスクを抑える対策を講じることで、スムーズに調査を乗り切ることが可能です。
本記事では、税務調査の基本的な仕組みや実施の流れ、調査当日の対応方法に加え、事前の予防策について詳しく解説します。税務署がどのようなポイントをチェックするのか、どのような申告や取引が調査対象になりやすいのかを理解することで、リスクを最小限に抑えることができます。
税務調査に対する不安を解消し、適切な対応と予防策を実践するための完全ガイドとして、ぜひ最後までお読みください。
Contents
税務調査の概要と基本事項
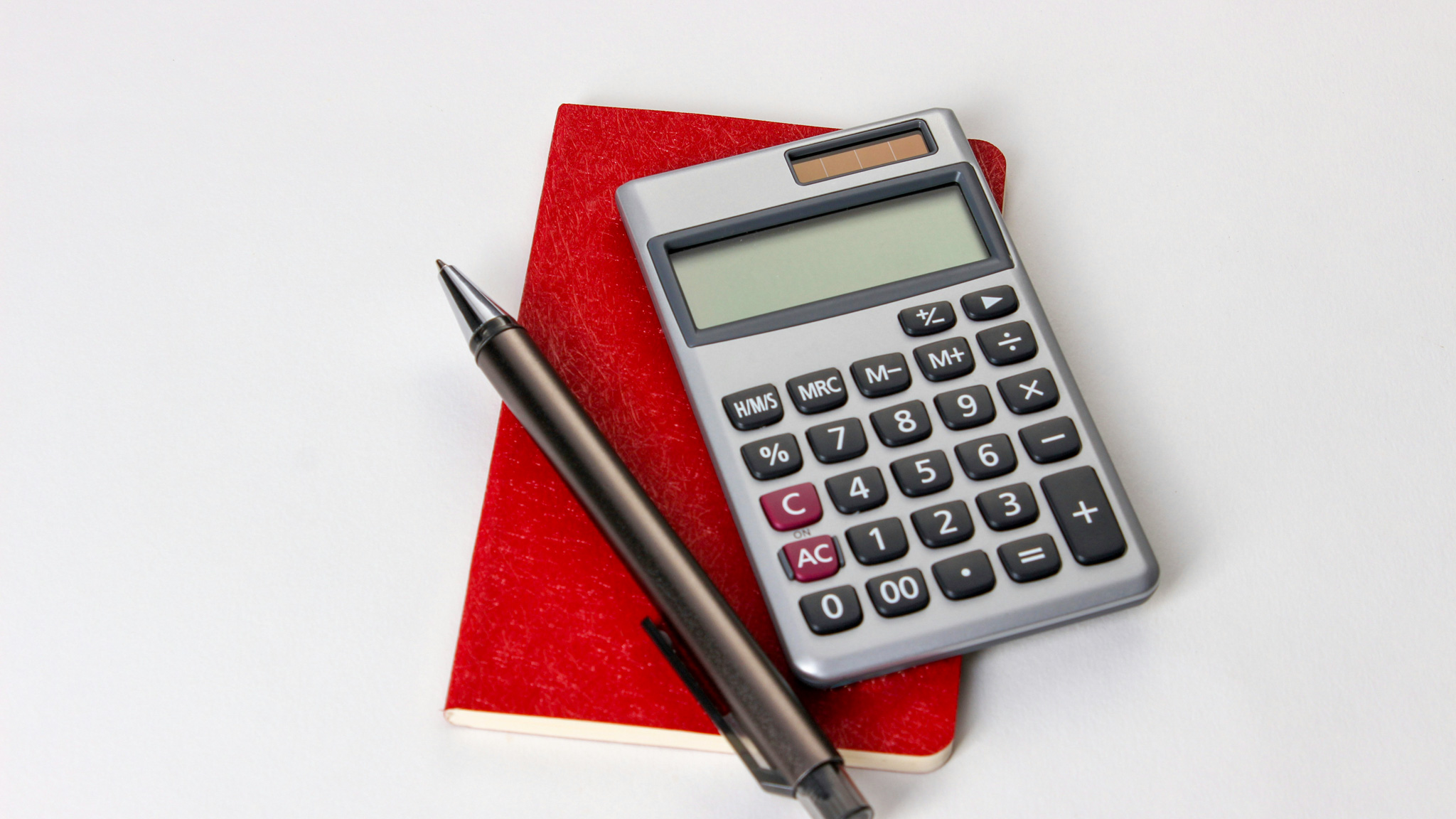
税金の申告・納付は自己申告制となっているため、納税者の申告が正しいかどうかを税務署が定期的にチェックし、必要に応じて指摘や修正を求めます。
まずは、税務調査の基本事項として、その概要や目的、種類、実施の背景について詳しく解説します。
税務調査とは?概要と目的を解説
税務調査は、法人や個人事業主の税務申告が法律に基づいて正しく行われているかを確認するために、税務署が実施する調査です。税務申告は自己申告制であるため、意図的な不正や計算ミスによる誤りが発生する可能性があります。税務調査は、こうした不正や誤りを是正し、公平な税負担を実現するために行われます。
税務調査の目的は大きく分けて以下の3つです。
| 3つの目的 | 内容 |
|---|---|
| 適正な納税の確認 | 正しく帳簿付けがされており、納税額が間違っていなかを確認する事である。 |
| 税務リスクの抑制 | 税金が間違いそうな論点がないかを確認して、間違いそうなところは注意喚起をしていただくこともあります。 |
| 税収の適正な確保 | 国は税収で運営されているので、間違いが発見され場合には税金の支払いが発生します。 |
税務調査は、すべての納税者に対して行われるわけではなく、申告内容や業種、過去の指摘歴などを基に、調査対象が選定されます。
税務調査が行われる背景には、税務署が注視するポイントや業界ごとのリスクが関係しています。税務調査の対象となるのは、申告内容に不審な点がある場合や業種特有のリスクがある場合です。例えば、売上や経費の増減が極端だったり、現金取引の多い業種では過少申告や経費の水増しが疑われやすくなります。また、過去に税務調査で指摘を受けた事業者は再調査の可能性が高まり、修正申告や追徴課税が発生した場合は継続的に監視されることもあります。さらに、取引先や元従業員からの情報提供によって調査が実施されるケースもあります。
このように税務調査は、単なるランダムな選定ではなく、申告内容や業界の特性、過去の実績などを基に慎重に決定されます。
税務調査の種類:任意調査と強制調査の違い
税務調査には、大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。
| 調査方法 | 説明 |
|---|---|
| 任意調査 | 一般的な企業や個人事業主を対象に行われる通常の税務調査です。税務署が必要と判断した場合に実施され、事前に通知が行われることがほとんどです。 |
| 強制調査 | 脱税の疑いがある納税者に対して、国税局査察部が行う調査です。裁判所の令状に基づいて実施され、事前通知なしに突然行われるのが特徴です。 |
税務調査でどこまで調べられるのか?
税務調査では、単に確定申告書や決算書を確認するだけでなく、売上や経費の根拠となる各種資料も詳しくチェックされます。調査範囲は広く、意外な点まで確認されることがあるため、日頃から適切な記録を残しておくことが重要です。税務調査で調べられるのは以下のような書類の内容や記録です。
- 帳簿や決算書
- 取引先との契約書や請求書
- 銀行口座の入出金記録
- 従業員の給与や社会保険
- 経費計上した領収書
税務調査では、申告内容の整合性を確認するため、帳簿や契約書、銀行口座の取引履歴など多岐にわたる資料が調査対象となります。
税務調査の通知・時期・頻度について
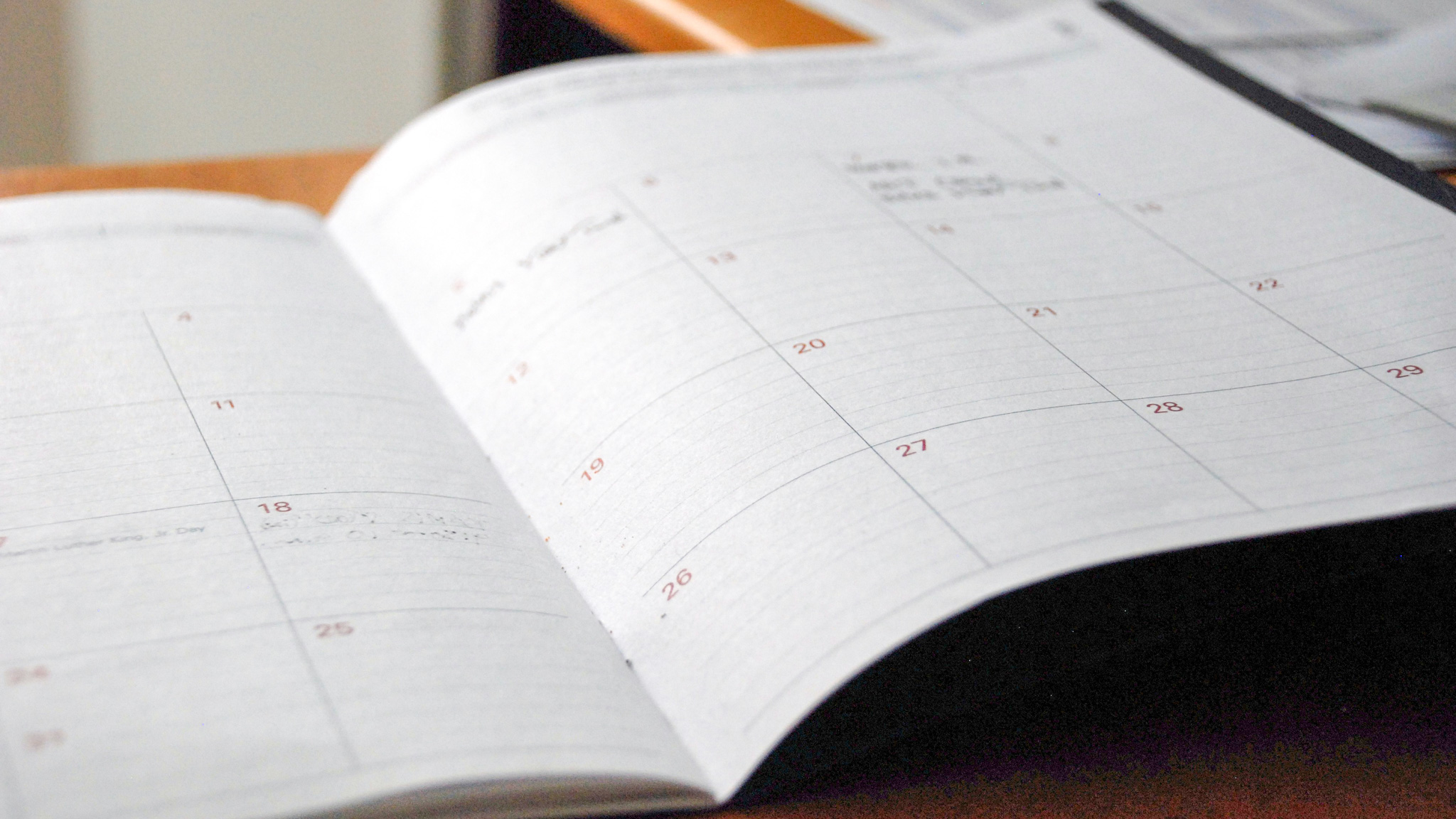
税務調査は、事業者や個人の税務申告が適正に行われているかを確認するために実施されますが、そのタイミングや頻度は一律ではありません。また、税務調査の頻度は、業種や事業規模、過去の申告状況などによって異なります。
本章では、税務調査の通知時期や調査が実施される頻度、さらに過去の申告状況が調査に与える影響について詳しく解説します。
税務調査でどこまで調べられるのか?
税務調査は、電話か書面の方法で、事前に通知が行われます。なお、税理士がついている場合には、原則税理士に税務署から連絡がきます。ただし、脱税の疑いがある場合や、緊急を要する案件(現金取引が多い事業)では、抜き打ちでの調査が実施されることもあります。
税務調査の頻度:何年に1回くるの?
税務調査の頻度は、事業の種類や申告内容によって異なりますが、一般的に法人の場合は5年に一度のペースで行われることが多いです。個人の場合には、10年に一度のペースと言われます。特に中小企業や個人事業主においては、毎年調査が入ることは稀であり、過去の申告状況や税務署の方針によって調査の間隔が決まります。
税務調査に入られやすいビジネスモデル・取引・業種等

税務調査に入られやすいビジネスモデルや取引、業種等あります。事業を行う以上は税務調査と無縁でいることは出来ません。最小限に税務リスクを低減する事も事業家として必要なことです。
税務調査に入られやすい7つの影響
1.現金取引が多い業種:現金は簡単に不正を行うことができます。本来あるべき売上を隠す事ができます。社長自身が指示をして、過少に売上を計上する場合もありますが、社長が知らない間に、社員が勝手に横領をしている場合もあります。
業種としては、小売業や飲食業等は、現金で商売しているため、売上除外が疑われやすいため、レジの記録を正確に管理し、帳簿への適正な記帳が重要です。
2.過去に税務調査で重大の過失を指摘:税務調査は一度入られた後も、定期的に税務調査がきます。申告漏れや重大な指摘を受けた場合には、次回の税務調査に入る頻度が多くなります。
3.取引先の反面調査:取引先に税務調査が入った場合に、その相手先として自社に税務調査が入る可能性があります。コンプライアンス意識が高い企業と取引する事も税務調査の可能性が低くする方法になります。
4.税理士がついていない企業:税理士がついている場合には、税金の申告書(法人税、消費税や所得税等)に税理士の氏名が記載されています。税務署としては、税理士が一度確認している税金の申告書であるため、間違えている可能性が低いと判断します。一方で税法の知識が少ない人が、申告書を作成した場合には、税務調査の可能性があがります。
5.外注費が多い業種:外注費が多い業種は、業務委託なのか、雇用なのかにより納税関係が大きく変わってきます。建設業や運送業では、外注費や人件費の過大計上が指摘されやすく、契約書の整備や給与・社会保険の適正な処理が求められます。
6.還付金が発生:税金は、最終的に集計した結果、納付する場合もあれば還付する場合もあります。毎回、還付が行われている場合には、税務調査が入る可能性が高まります。特に、国外との取引が多い業種では、消費税が還付される場合があります。
7.タレコミがある場合:税務署には、通報制度というものがあります。どなたかが、税務署の通報制度を利用して、脱税情報を伝達する場合あります。1つの情報のみだけでは、税務署も動きませんが、それが現実性が高く複数寄せられている場合には、それを期に税務調査が入る可能性が高まります。
法人と個人の税務調査の違いと範囲
税務調査は、法人と個人でその範囲やチェックポイントが異なります。
法人
主に法人税、消費税、源泉所得税の適正な申告が行われているかが確認されます。特に、以下の点が重点的に調査されます。
- ・売上や利益の計上方法:決算月をまたいでいる売上がないか等を確認します。
- ・経費の適正性:経費が事業で利用した経費なのかを確認します。経費計上した日にスケジュール帳に記載があるか、その方の名刺があるか等を確認して事業としての関係性があるかを確認します。
- ・関連会社との取引:子会社や関連会社との取引がある場合には、取引理由や取引金額が適正化を確認します。
- ・役員報酬や退職金の処理:役員報酬や役員退職金が過大に計上されていないか。
法人の税務調査は、規模が大きいほど詳細に行われる傾向があり、数日にわたることもあります。
個人事業主
個人事業主の税務調査では、所得税と消費税の申告内容が適正かどうかが確認されます。主なチェックポイントは以下のとおりです。
- ・事業所得と経費の計上:個人の場合には、所得の種類に応じて経費の考え方や税率が変わります。正しい、所得に計上されているかを確認します。
- ・家事費案分:個人事業主の場合には、経費が事業用なのかプライベート用なのかが不明確な場合があります。合理的に家事費案分がされているかを確認されます。
- ・現金売上の管理:個人事業主の場合は特に、現金の管理がしきれていない場合が多いため、全ての現金売上が帳簿に計上されているかを確認します。
- ・帳簿の適正性:税理士に依頼していない場合は、特に帳簿が適正に作成されているかを確認します。
個人事業主の調査は、法人に比べると短期間で終わることが多いですが、帳簿管理が不十分な場合は厳しい指摘を受けることがあります。
税務調査の流れと対応方法

税務調査が行われることが決まったら、事前準備をしっかり行い、当日は落ち着いて対応するようにしましょう。税務調査の流れを把握し、適切に質問へ対応しながら、必要な資料を的確に提示できるように準備しておくことで、スムーズな進行が可能になります。
本章では、税務調査当日の基本的な流れや、質問への対応方法、準備すべき書類について詳しく解説します。
前日までに準備すべき事項
税務調査では、帳簿や取引記録などの書類が確認されます。資料をあらかじめ準備しておくことで、スムーズな対応が可能になります。税務調査の連絡が来た際に、税務調査官から必要書類の連絡がきますので、指示があった資料をご用意いただければ大丈夫です。
準備すべき書類は一般的には、以下の通りです。
- ・会計帳簿(総勘定元帳等)
- ・決算書
- ・取引に関する書類
- ・給与関連書類
- ・過去の税務申告書類
さらに資料として社内規定や業務マニュアル、事業計画書もあわせて用意しておくと良いでしょう。
不安がある場合には、税理士にすぐ連絡をしてください。税理士がいない方は、税理士を付けるようにしてださい。税務署からの連絡が来たら、早急に連絡をしてください。税理士が付くかつかないかで納税額は大幅に違います。
当日の税務調査の流れ:基本プロセスを解説
税務調査は通常、朝10時から始まり夕方の16時で終了します。1日~3日間実施します。何日実施するや何名で来られるかは、会社の規模により異なります。内容によっては複数日にわたることもあります。税務調査の基本的な流れは以下の通りです。
調査官の訪問と調査開始
税務署の調査官が訪問し、名刺交換をして、税務調査官である事の身分証を提示して調査を開始します。
質問・ヒアリングの実施
初日の午前中は企業の概況ヒアリングが実施されます。ヒアリングの内容は、経営状況や会計処理に関する質問が行われます。
帳簿や書類の確認
過去3年分の帳簿や決算書、領収書などが確認されます。
指摘事項の説明と対応
税務調査の間で、指摘を受けた事項を一度、フィードバックを受けます。
ここから、どこまで実際修正するかは、交渉になります。交渉に不安がある方は、必ず税理士をつけましょう。
税務調査時の質問対応方法と注意点
税務調査では、調査官から事業の運営状況や会計処理に関する質問を受けることになります。事実に基づいた正確な回答を心がけ、分からないことは曖昧にせず確認した上で返答することが重要です。その場でわからない事は、「調べて解答します」と税務調査官にお答えいただければ構いません。
また、必要以上の情報を提供すると新たな疑念を招く可能性があるため、調査官の質問には簡潔かつ正確に答えましょう。税理士が同席する場合は、専門的な対応を任せることでスムーズに進めることができます。さらに、高圧的な態度や不誠実な対応は調査を厳しくする要因となるため、落ち着いて丁寧に対応することが大切です。
税務調査のチェック項目と調査の視点

税務調査では、税務署が重点的に確認するポイントがいくつかあります。特に、売上や経費の計上が適切に行われているか、帳簿や請求書が適切に管理されているかは、重要なチェック項目となります。
本章では、税務署が特に注視するポイント、売上や経費に関する主要なチェック項目、必要書類の適切な保管方法について詳しく解説します。
税務署が特に注視するポイントとは?
税務調査では、売上の計上漏れや不正処理がないかが重点的に確認され、特に現金取引の多い業種では売上除外が厳しくチェックされます。また、個人的な支出の経費計上や架空経費の計上がないか、帳簿の記録と実際の取引内容に食い違いがないかも調査の対象です。さらに、取引先が適正な事業者であるか、架空取引が行われていないかを確認し、給与や報酬の支払いが適正か、役員報酬が過大でないかも厳しくチェックされます。
売上に関する主要なチェック項目
税務調査では、売上や経費の処理が適切に行われているかを確認するため、具体的な取引内容が細かく調査されます。特に注意すべき主要なチェック項目は以下のとおりです。
1.売上が適正に計上されているか:売上が全て網羅的に計上するかを、預金通帳等で確認します。特に預金通帳を通らない、現金売上は注意深く見られます。
2.期がずれている売上がないか:会社は必ず決算期があります。決算期をまたぐ売上がないかを確認します。例えば、3月決算の会社においては、3月までにサービスを提供した売上が当期の決算に計上する必要があります。3月にサービスを提供して、4月に入金する取引は当期の売上に計上する必要があります。
経費に関する主要なチェック項目
- 1.事業に関係のない個人的な支出が経費として計上されていないか:会社の経費に計上できるのは、全て事業に関連する費用になります。プライベートで利用する支出が計上されていない事を確認します。
- 2.架空の経費が計上されていないか:実態のない取引が無いかを確認します。取引内容があいまいなコンサルティング費用等は特に対象なります。また、仕入先や外注先が実態のある事業者かどうかも確認します。
- 3.交際費や広告費、人件費などが適正に処理されているか:接待交際費は800万円以上は経費に入れることができません。そのため、「接待交際費」の勘定科目で計上していなくても、実質、接待交際費の取引がないかを確認します。
- 4.実際に取引が行われた証拠(請求書・契約書・支払い記録など)が揃っているか:実際の取引がある場合には、請求書・領収書・契約書・納品物等があるはずです。それがあるかどうかを確認します。
- 5.従業員の給与が適正に支払われているか:実際に働いている人に、給料が支払われているかを確認します。節税の観点で実際に勤務していない親族等に給料が発生していなかを確認します。
- 6.源泉徴収(※)が正しく行われているか:役員報酬や給料を支払う場合や個人の外注への支払い、外国の企業への支払いの場合には、源泉徴収を行う必要があります。
- (※)源泉徴収:源泉徴収とは、支払金額より一定の金額を差し引いて、税務署に支払う事をいいます。源泉徴収する義務は事業主になりますので、源泉徴収を忘れると会社が当該源泉徴収分の金額を負担する必要があります。
売上や経費に関する処理が不適切だと、税務署から指摘を受け、追徴課税の対象になる可能性があります。
帳簿・請求書など、必要書類の適切な保管方法
税務調査では、帳簿や請求書などの書類が適切に保存されているかも重要なチェックポイントとなります。
税務調査に備え、法人は7年間、個人事業主は5年間(青色申告なら7年間)帳簿を保管する必要があり、総勘定元帳や決算書を整理し、提示できる状態にしておくことが重要です。請求書や領収書は7年間(消費税課税事業者は10年間)保存し、取引先名や金額を明確に管理し、スキャンで紛失を防ぐとよいでしょう。また、契約書や納品書は取引証拠として整理し、銀行取引記録も事業用口座を分けて定期的に保存することが求められます。
税務調査で誤りや指摘を受けた場合の対応

税務調査の結果、申告内容に誤りが見つかった場合、指摘された内容に応じて、修正申告や更正請求などの手続きを進め、税務署と適切に対応することで、余計なペナルティを防ぐことができます。
本章では、修正申告と更正の違い、指摘事項への具体的な対応策、調査結果を受けた後のアクションプランについて詳しく解説します。
修正申告と更正の請求の違いと対応方法
税務調査で申告の誤りが指摘された場合、修正申告または更正の請求という手続きを行うことになります。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 修正申告 | 指摘を受けた場合に速やかに対応。納税者が自ら誤りを認め、過少申告していた税額を訂正する手続きです。税務調査の指摘を受けた場合、調査官の指導のもと修正申告を行い、不足分の税金と延滞税・加算税を納付する必要があります。 |
| 更正の請求 | 更正の請求は、過去5年間の申告について請求できるため、誤った納税があった場合は期限内に手続き。納税者が過大に納税していた場合に、税金の還付を求める手続きです。税務調査の結果、納めすぎた税金が判明した場合、更正の請求を行うことで、過払い分を取り戻すことができます。 |
税務調査結果を受けた後のアクションプラン
税務調査が終了した後は、指摘事項を踏まえて適切な対応を行うとともに、今後の税務リスクを低減するための対策を講じることが重要です。以下の3つのステップを参考に、適切なアクションプランを策定しましょう。
- 1.指摘事項の整理と対応:税務調査の最終日に指摘された事項を整理して、どこまでを認めて、どこまでを認めないかを判断をします。高度な税務知識が必要になりますので、税理士を話し合いながら決定する事を推奨します。
- 2.税務管理体制の見直し:二度同じ論点が指摘された場合には、罰則的な税金がつく場合があります。再発防止のために、事業としてどのような管理体制を構築するかを考えます。
- 3.今後の税務リスク対策:税務調査の時には指摘されていないが、潜在的な税務リスクがないかを確認します。実際に現状なくても、様々な企業と取引をしているうちに、税務リスクが増大していく場合があります。
税務調査で指摘を受けた場合は、内容を整理し、修正申告が必要であれば速やかに対応することが重要です。税理士と相談しながら適切な処理を進め、再発防止のために帳簿管理や税務処理の方法を見直しましょう。売上や経費の計上ルールを明確にし、会計ソフトの導入や専門家のサポートを検討するのも有効です。また、定期的に帳簿をチェックし、税務知識を更新することで、将来的な税務リスクを軽減し、次回の調査に備えることができます。
税務調査で焦らないための日頃の事前準備
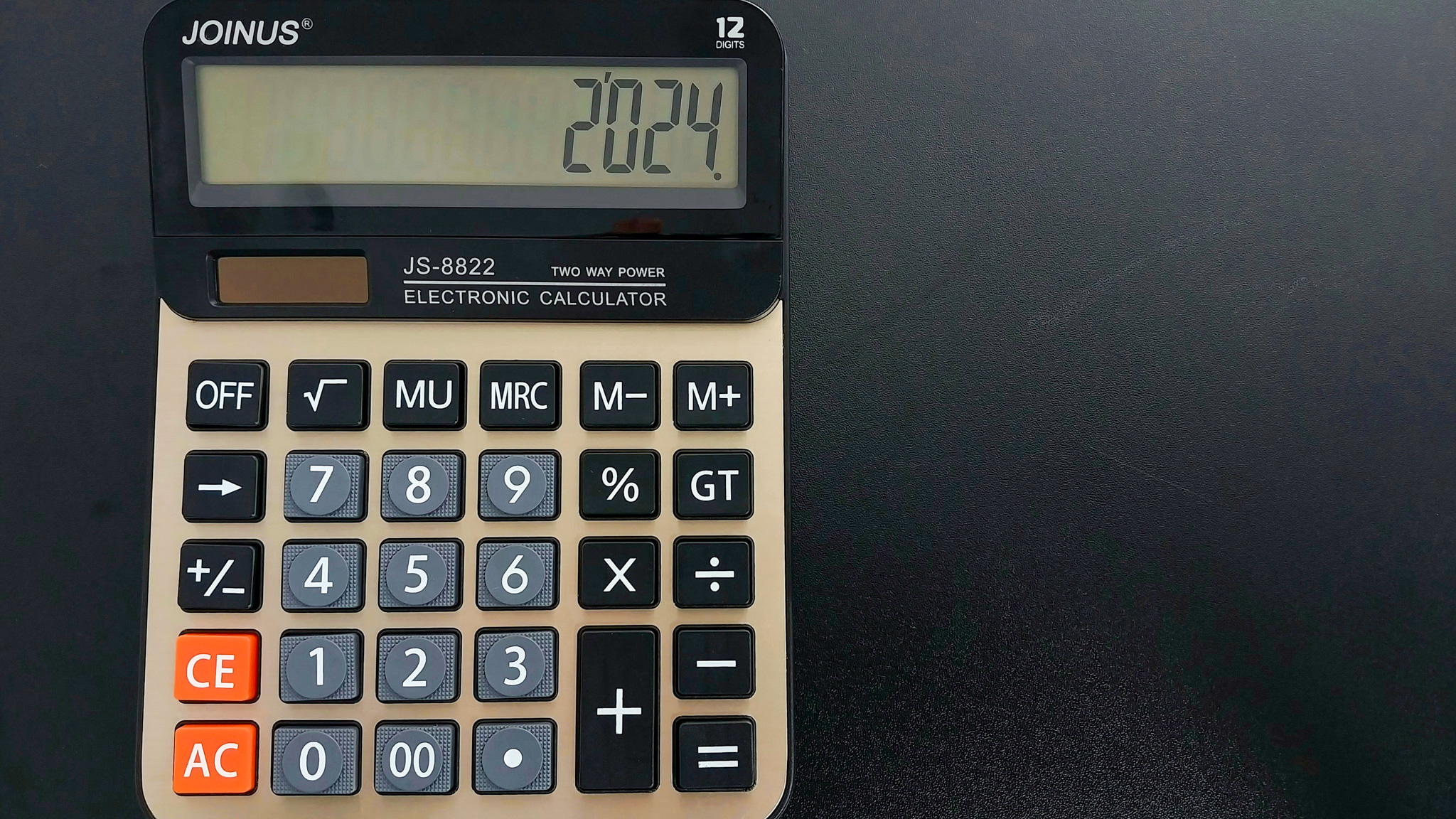
税務調査は事前の準備によって対応のしやすさが大きく変わります。日頃から帳簿や書類を適切に管理し、税務リスクを抑えることで、調査が入った際の負担を軽減できます。
本章では、日頃の書類管理の方法、税理士の役割、指摘事項への対応準備について詳しく解説します。
税務調査に備えた日頃の書類管理方法
上記でも述べた通り、帳簿類は法人7年、個人事業主5年(青色申告なら7年)保管の必要があります。請求書や領収書は取引先名や金額が明確になるよう整理し、紛失防止のためスキャンしてデジタル化をするの事がおすすめです。契約書や納品書も売上・仕入れと一致するよう管理し、コピーや電子保存を活用しましょう。また、事業用と個人用の銀行口座を分け、取引明細を定期的に確認し、帳簿との整合性を確保しておきましょう。
帳簿の作成と管理は、税務調査のリスクを低減するうえで不可欠です。適切な帳簿管理を行うことで、税務署からの信頼を得ることができ、調査の際にもスムーズな対応が可能になります。
まず、帳簿管理を適切に行うためには、取引ごとに詳細な記録を残し、仕訳帳や総勘定元帳を整理して、いつでも確認できる状態にすることが重要です。また、電子帳簿保存法に対応し、クラウド型会計ソフトを活用することで、データの紛失防止や迅速な検索が可能になります。領収書や請求書は分類・保管し、デジタルデータ化すると管理がしやすくなります。さらに、月次や四半期ごとに帳簿をチェックし、税理士の監査を受けることで、正確な帳簿管理が実現できます。
顧問税理士のサポートは必要?その役割とは
税務調査において、税理士のサポートは大きな助けとなります。顧問税理士の主な役割は以下の通りです。
- ・申告時のチェックとアドバイス
- ・書類管理の指導
- ・税務調査の立ち会いと交渉
- ・税務リスクの事前対策
税務の専門知識を持つ税理士がいることで、適切な申告や書類管理が可能となり、調査時の対応もスムーズになります。
税務調査はどう変わる?KSK2稼働とデジタル時代の調査対応

国税庁では、30年ぶりに基幹システムを更新し、令和8年9月からKSK (国税総合管理システム)2が稼働します。
KSK2は、税務調査関連においても、従来のKSK システムに
- ・税目の統合とデータ共有機能
(法人税、所得税、消費税などの情報が連携され、法人の取引と代表者の個人所得など、横断的な情報共有が可能になる) - ・調査現場でのリアルタイムアクセス機能
(調査官が、パソコンを用いて、調査現場から e-Tax等によるデジタルの取引データ等にアクセスできるようなり、取引先や関連会社の情報を現場で検索、分析することが可能になる)
などの機能が付け加えられており、調査の効率化や調査官の機動力も大幅に向上します。
そのため、納税者側においても主要な契約書や総勘定元帳はデジタル保存などで、即座に提出・説明できる状態にしておくなど、税務調査の「スピード化」への対応が必要となります。
税務調査のことなら税理士にご相談を適切な専門家のサポートで

税務調査は、企業や個人事業主にとって大きな負担となる可能性があります。適切な対応を怠ると、追徴課税やペナルティが発生することもあるため、専門的な知識を持つ税理士のサポートを受けることが重要です。税理士は、税務調査の事前準備から調査当日の対応、調査後のフォローまで幅広くサポートしてくれるため、リスクを最小限に抑えることができます。
税務調査に備え、日頃から税理士と連携し、適切な税務管理を行うことで、リスクを軽減し、安心して事業を運営することができます。税務調査に不安を感じる場合は、早めに税理士へ相談し、万全の準備を整えておきましょう。