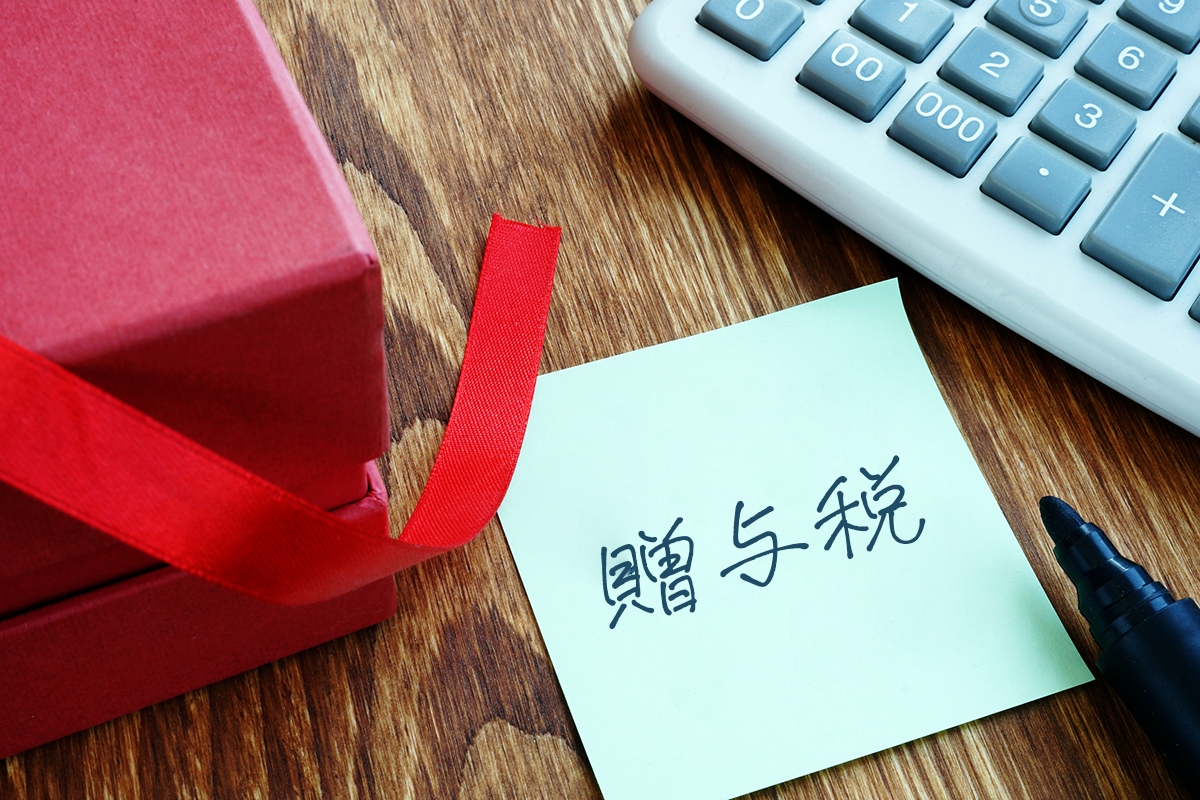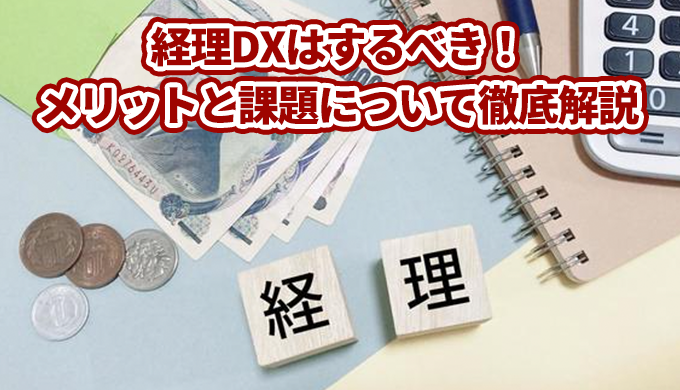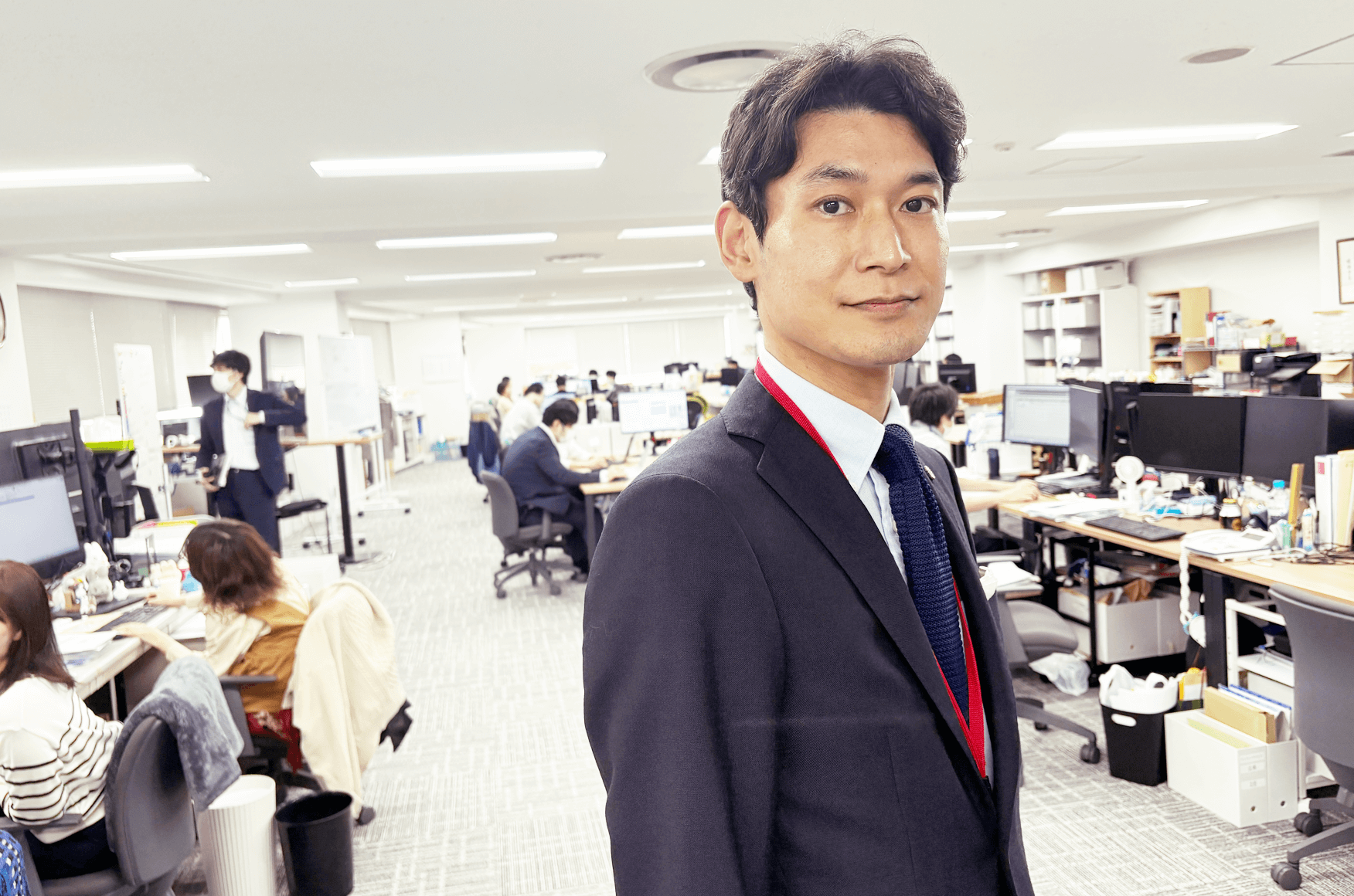高齢化の進行や、将来の相続トラブルを未然に防ぎたいという意識の高まりから、現金や不動産、株式などの資産を、大切なご家族へ計画的に引き継ぎたいと考える方が増えています。
そうした承継のプロセスを進めるうえで、避けて通れないのが「贈与税」の存在です。適切な制度や方法を活用すれば、贈与税の負担を抑えながら、スムーズに資産を渡すことが可能になります。
本記事では、贈与税の基本的な仕組みから、おすすめの節税対策、さらには生前贈与時に注意すべきポイントまでを網羅的に解説いたします。資産承継についてお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
Contents
贈与税とは?基本的な仕組みについて

贈与税とは、個人から金銭や不動産、株式などの資産を無償で受け取った際に、その受贈者に課される税金です。この税金は、「相続税法」に基づき課税され、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が対象となります。
たとえば、親から子へ現金や不動産を譲った場合、それが贈与と見なされると、一定額を超えた部分に対して税金が発生します。よって、いくらから贈与税がかかるのかを把握しておくことは、贈与の計画を立てるうえで非常に重要です。
贈与税の税率は、贈与された金額に応じて段階的に高くなる「累進課税制度」を採用しており、贈与額が大きいほど、計算上の税率も高くなる仕組みです。そのため、むやみに一括で大きな金額を贈与すると、予想以上の税負担となる場合があります。
以下に、一般贈与財産に適用される税率の速算表を掲載します。
| 課税価格(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円以上 | 55% | 400万円 |
※贈与額から基礎控除110万円を差し引いた「課税価格」にこの表を適用します。
一方で、贈与税には非課税枠や特例制度も用意されており、それらを適切に活用することで税負担を軽減することが可能です。特に後述する「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」などは、節税対策として広く活用されています。
また、贈与税の仕組みは相続税と密接に関係しているので、相続対策の一環として贈与を計画的に行うことが重要です。贈与は単なる財産移転ではなく、将来的な資産承継を見据えた戦略的判断として位置付けるべきでしょう。
贈与税の節税対策5選

贈与税を抑えながらスムーズに資産移転を行うためには、制度を正しく理解し、目的に合った方法を選択することが重要です。ここでは、実務上よく活用されている代表的な節税対策を5つご紹介いたします。
毎年110万円までの暦年贈与
年間110万円までの控除が適用される「暦年贈与」を利用すれば、毎年コツコツと贈与を続けることで大きな資産も無理なく承継できます。たとえば、親が毎年子ども2人に110万円ずつ贈与した場合、10年間で合計2,200万円を非課税で渡すことが可能です。
さらに、孫や配偶者など複数の親族に分けて贈与すれば、より多くの資産を効率的に移転できます。
暦年贈与における申告対応のTIP
贈与額を111万円とし、銀行振込により実行、基礎控除額(110万円)を超える1万円に対して10%(1,000円)を納税のうえ、申告書および関連資料を適切に保管しておくことで、将来的な税務調査時のトラブル回避につながる場合があります。
相続時精算課税制度を活用
2,500万円までの贈与が非課税となる「相続時精算課税制度」は、まとまった資産を一括で移したい場合に有効な手段です。自社株や不動産などの大きな財産を、早めに子どもへ引き継ぐ際に利用されることが多い制度で、贈与時には課税されず、将来の相続時にまとめて精算される仕組みとなっています。
この制度を活用すれば、贈与時の税負担を抑えつつ、相続税の見通しも立てやすくなるというメリットがあります。ただし、一度選択すると取り消すことができないため、慎重な判断が必要です。さらに、非課税枠である2,500万円を超えた部分については、一律20%の贈与税が課税される点にも注意しましょう。
配偶者への贈与(おしどり贈与)
婚姻期間が20年以上の夫婦間であれば、居住用不動産の贈与に際して、基礎控除110万円に加え「2,000万円の特別控除」が受けられます。いわゆる「おしどり贈与」と呼ばれるこの制度は、住宅の生前贈与に適しており、仮に夫が妻に2,100万円相当の自宅を贈与した場合であっても、贈与税はかかりません。
しかしながら、同一の配偶者間では一生に一度しか使えない制度であるため、将来の住まい方や資産状況を踏まえた計画的な活用が求められます。あわせて、不動産の名義変更や登録免許税、不動産取得税の負担についても事前に確認しておくと安心です。
住宅取得等資金の贈与
直系卑属(子や孫)が住宅を取得する際に、その資金を贈与する場合は、一定の条件を満たすことで非課税の特例が受けられます。令和7年(2025年)現在では、 一般的な住宅であれば最大500万円まで、省エネ性能等を満たす住宅であれば最大1,000万円までが非課税の対象となります。
このように、住宅取得等資金贈与の非課税枠は、購入予定の住宅の性能によって異なります。その他、受贈者の年齢や建物の登記など要件が細かく定められているため、制度内容を十分に確認しましょう。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や出産、育児にかかる資金を一括で贈与する際には、「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度」を利用することができます。1人当たり最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税の対象となり、ライフイベントの早期資金準備や、若い世代の生活安定を支援する方法として有効な制度です。
本制度は受贈者が50歳に達するまでに使いきる必要があり、使途ごとの領収書提出などの管理も求められます。もし贈与した資金が使われなかった場合は、その残額に贈与税が課されるため、事前の計画と信頼関係が重要となります。
生前贈与を行う際の注意点

節税メリットの多い贈与ですが、誤った手続きや見落としによって税務署から否認されるケースもあります。以下のポイントをしっかり押さえて、確実な対応を行いましょう。
贈与契約書を作成する
贈与は、双方の合意があって成立する契約です。税務上も「贈与があったこと」を証明する必要があるため、贈与契約書を作成しておくことが望まれます。契約書には、 日付・贈与額・贈与者と受贈者の署名などを明記しておきましょう。書面で証拠を残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
現金手渡しは避ける
贈与の事実を証明しにくくなることから、現金での手渡しは避け、金融機関を通じた振込で行うようにしましょう。通帳の記録は、税務調査時にも有効な証拠となります。
贈与税の申告は期限内に行う
贈与税の申告は、贈与を受けた本人が行います。申告書の提出並びに税金の納付は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される場合があるため、注意しましょう。
定期贈与と見なされないようにする
定期贈与とは、一定額の贈与を複数年にわたって継続的に行うことを指します。たとえば「毎年100万円を10年間渡す」といった贈与に対して事前合意がある場合、初年度に1,000万円を一括贈与したものと見なされ、110万円の基礎控除が適用されなくなる可能性があります。
暦年贈与として扱われるためには、毎年の贈与を独立したものとして認められる必要があります。たとえば、金額や時期を変える、毎年契約書を交わす、振込記録を残すといった工夫が有効です。
贈与税対策はストラーダグループまでご相談を

贈与税の対策は、制度の正しい理解と計画的な実行が不可欠です。一見シンプルに見える贈与も、相続や不動産、法人との関係性などが絡むと、判断を誤りやすい分野となります。
ストラーダグループでは、贈与や相続に精通した税理士や社会保険労務士などの専門家が、お客様一人一人の事情に応じた最適なプランをご提案しております。
節税だけでなく、家族間の信頼関係や相続全体を見据えた支援を行っており、贈与に伴う確定申告の手続きや必要書類の作成等についても当グループが一貫してサポートいたします。
将来に備えた第一歩として、ぜひこの機会に、長期的な視点に立った資産承継の準備を始めてみてはいかがでしょうか。