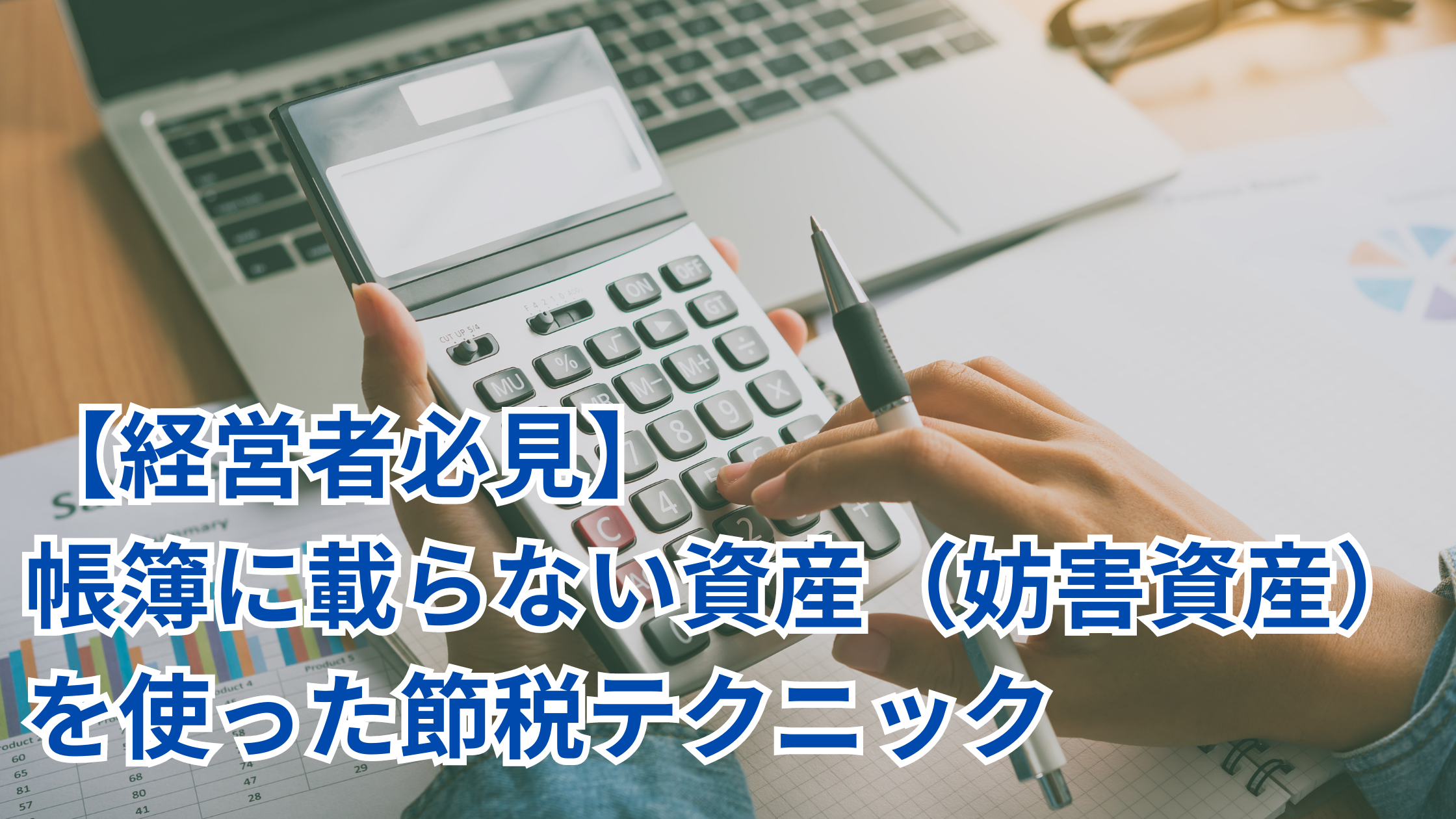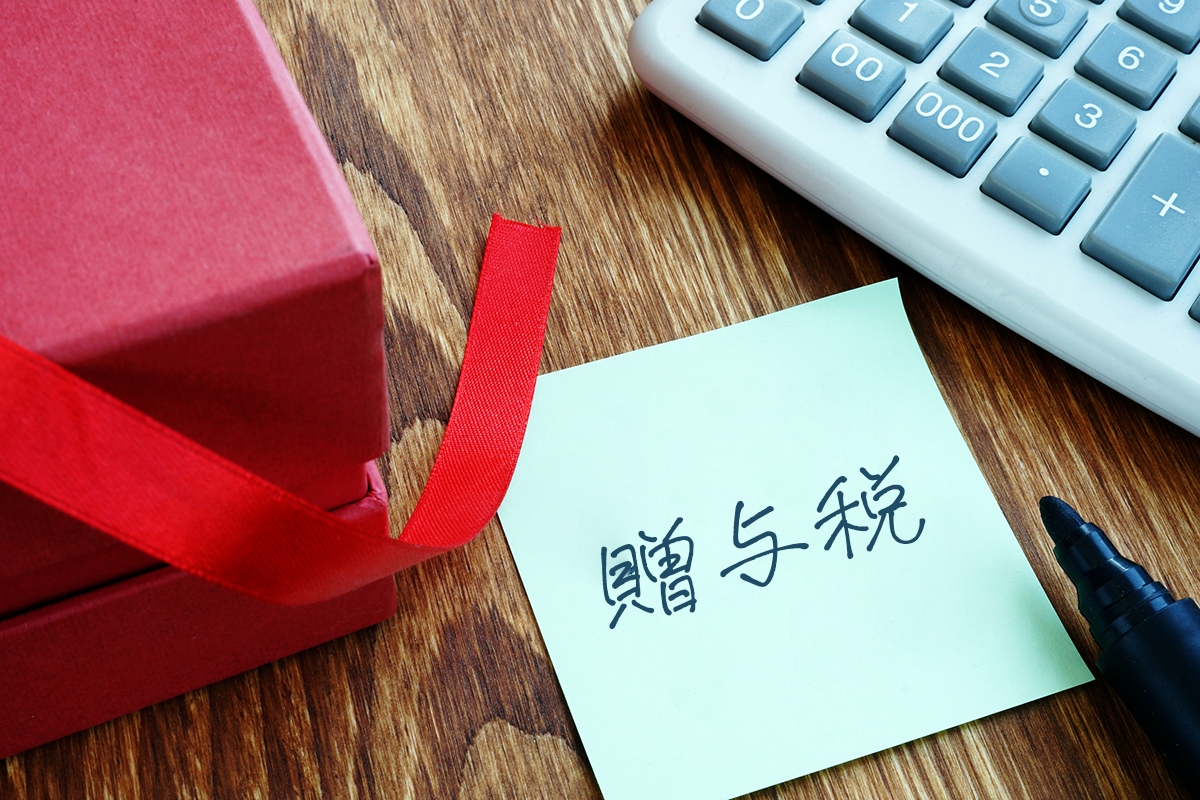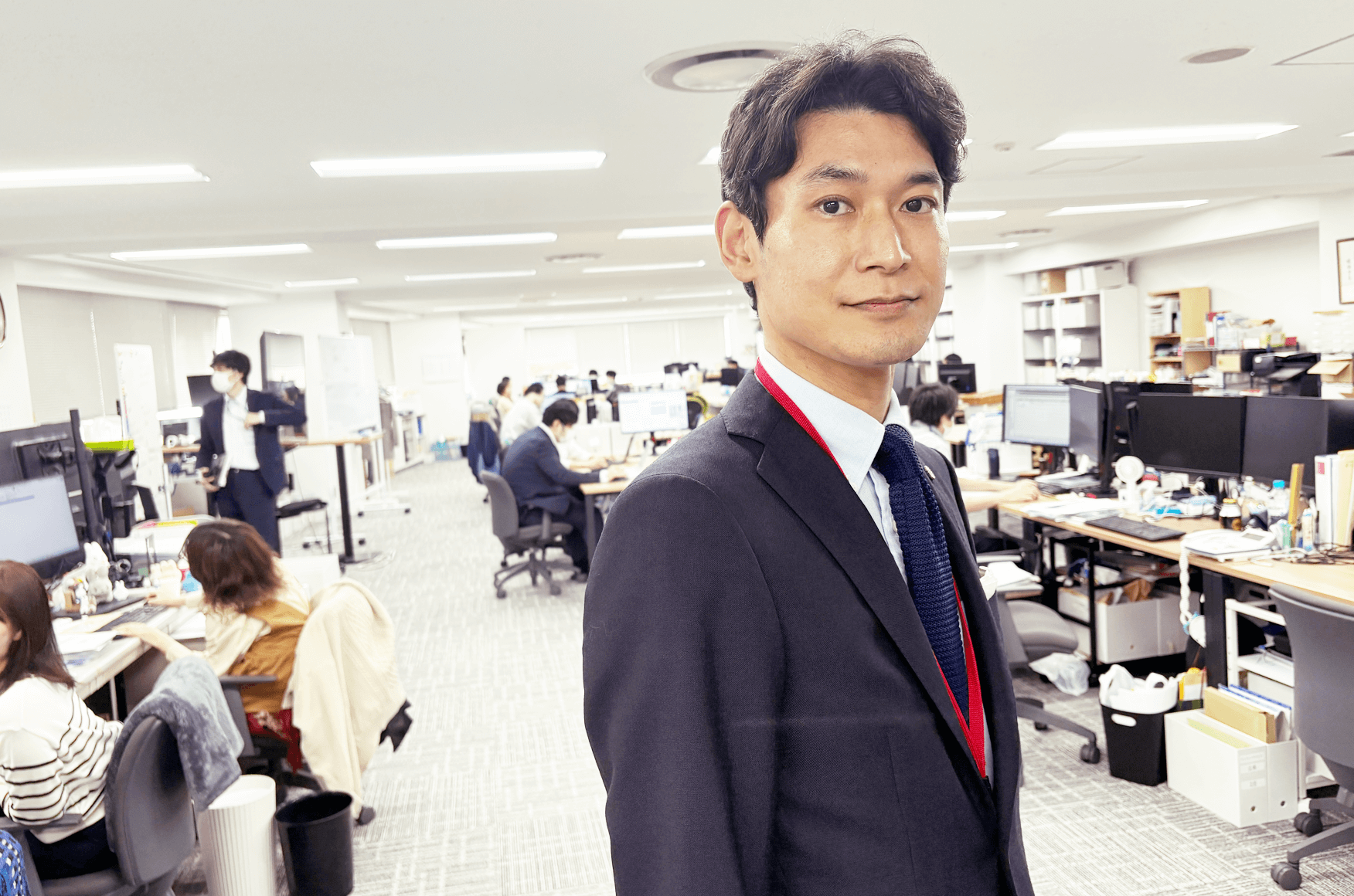企業経営において、税金のコントロールは資金繰りや利益確保に直結する重要な要素です。ただ、「節税」と聞くと、合法かどうかや自社に合う方法が分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
本記事では、「節税とは何か」という基本から、個人・法人それぞれの立場で実践できる具体的な対策までを解説します。健全な節税の考え方を整理する参考になれば幸いです。
Contents
そもそも節税とは?正しい理解が第一歩

企業経営において税負担は避けて通れない要素です。しかし、法律に基づいて適切に税金を軽減する「節税対策」を行うことで、キャッシュフローの改善や利益の最大化につなげることが可能です。
一方で、「節税」と「脱税」「租税回避」は混同されがちで、正しい理解を持たないまま実行するとリスクにもなりかねません。
節税・脱税・租税回避の違い
節税を考えるうえで、「脱税」「租税回避」との違いを理解することが重要です。意味や法的な位置づけは以下の通りです。
- 節税:法律の範囲内で、控除や特例を使って税負担を軽減する行為
- 脱税:所得の隠蔽や虚偽申告など、法律違反によって納税を逃れる行為
- 租税回避:法の抜け穴を利用した、合法だが不適切とされる手法
節税は正当な経営判断の一環として推奨される一方、脱税や過度な租税回避は大きなリスクを伴います。違いを明確に理解し、健全な方法で対策を行うことが求められます。
節税対策を考える3つの視点(収入・支出・控除)
節税を効果的に行うには、「どこに働きかけるか」という視点が重要です。大きくは、収入・支出・控除の3つからアプローチできます。
| 節税の視点 | 内容 |
|---|---|
| 収入の調整 | 売上計上のタイミングなど、会計処理によって課税所得の時期を調整できる場合があります。ただし、法令の範囲内で適切に行う必要があります。 |
| 支出の最適化(経費計上) | 正当な支出を経費として計上することで、課税対象を抑えることが可能です。交際費や減価償却費、福利厚生費などが代表例です。 |
| 控除制度の活用 | 各種税制優遇を活用することで納税額を減らせます。法人税の特別控除や中小企業向けの投資減税制度などがあります。 |
これらの視点を組み合わせて活用することで、無理なく健全な節税が可能になります。
サラリーマン・個人事業主ができる節税対策

節税対策は法人だけでなく個人の立場でも有効に取り組むことが可能です。特にサラリーマンや個人事業主であっても、控除制度の活用や申告方法の工夫によって、手元に残るお金を増やすことができます。
ふるさと納税・iDeCo・医療費控除などの「控除」活用
個人が行える最も基本的な節税対策は、各種控除制度の活用です。これらは所得税や住民税の計算上、課税対象額を減らすことができる仕組みです。
代表的な控除制度の特徴は以下の通りです。
| 控除制度 | 概要・効果 |
|---|---|
| ふるさと納税 | 売寄付額のうち2,000円を超える部分が控除対象。返礼品も魅力 |
| iDeCo(個人型確定拠出年金) | 掛金が全額所得控除対象となり、老後資金も同時に形成可能 |
| 医療費控除 | 一定額を超える医療費を支払った場合に適用。自費診療や通院交通費も含まれる場合あり |
副業・不動産収入と節税のリアル
近年、副業解禁や不動産投資ブームの影響で、本業以外の収入を得る個人が増えています。こうした「雑所得」や「不動産所得」も上手に節税することが可能です。
節税に関する基本的な考え方は以下の通りです。
- ・副業にかかる経費は必要経費として計上可能
- ・不動産投資では減価償却費やローン利息を経費として活用できる
- ・赤字の場合は、給与所得と損益通算できる可能性がある
ただし、副業や投資においては「節税目的のみ」で始めると本末転倒になりがちです。また、グレーゾーンの手法に手を出すと、税務調査のリスクが高まる点にも注意が必要です。
青色申告・経費計上・共済の活用(個人事業主向け)
個人事業主にとって、青色申告は非常に有効な節税手段です。要件を満たして申告することで、以下のような特典が受けられます。
| 節税手段 | 内容とメリット |
|---|---|
| 青色申告特別控除 | 最大65万円の所得控除。複式簿記と期限内申告が条件 |
| 経費計上 | 事業に必要な支出(家賃、水道光熱費、車両費など)を所得から差し引ける |
| 小規模企業共済 | 掛金が全額所得控除に。将来の退職金準備にも有効 |
また、倒産防止共済も、掛金が損金として認められるため、節税と資金確保の両立が可能です。
法人・中小企業の節税ポイント

法人や中小企業にとって、節税は利益確保と資金繰りの改善に直結する経営戦略のひとつです。売上拡大と同様に、税金を適切にコントロールすることで、キャッシュを社内に残すことができます。
役員報酬・福利厚生・法人保険の活用
法人では、給与や保険、福利厚生などの仕組みを整えることで、損金算入(=経費計上)による節税が可能です。
以下のような手段が代表的です。
| 節税手段 | 概要とメリット |
|---|---|
| 役員報酬 | 毎月一定額で支給すれば損金扱いに。(定期同額給与)事前確定届出給与の制度もあり。所得分散にも有効 |
| 福利厚生制度 | 社員として会社負担分の家賃が損金となる。社員の食事補助や健康診断費用なども経費にできる |
| 法人保険(定期保険など) | 一部を損金計上でき、資金準備と節税を両立可能 |
ただし、税務要件や運用ルールに注意し、制度に沿った設計が必要です。
節税商品・資産活用の注意点(リース・不動産など)
一部の企業では、「節税目的の商品」や資産への投資を検討するケースもあります。これらは短期的な節税効果が見込める一方で、リスクや将来的なコスト増につながる可能性もあるため慎重な判断が求められます。
代表的な事例とその特徴を以下に整理します。
| 節税スキーム | 主な内容と留意点 |
|---|---|
| オペレーティングリース | 高額設備のリース契約を通じて一時的に損金処理が可能。ただし中途解約は難しい |
| 不動産投資(法人名義) | 減価償却を活用した節税が可能だが、空室リスクや資金拘束もある |
節税目的だけでこれらの商品に手を出すのは危険です。特にリース契約や不動産購入は長期契約となることが多く、経営状況の変化に対応しにくいという課題もあります。
失敗しないための節税対策の進め方

節税は企業のキャッシュフローや経営効率を高める有効な手段ですが、方法を誤ると税務調査の対象となったり、想定外の追徴課税を受ける可能性もあります。重要なのは、ルールを守りながら計画的に実行することです。
やってはいけない節税とは?
一見すると節税に見える行為であっても、税法に抵触したり、形式だけを整えた不適切な処理は「脱税」や「租税回避」とみなされるリスクがあります。
以下のような行為には特に注意が必要です。
- ・事業関連がない経費計上(修繕費など)
- ・家事費と事業経費の線引き(自宅の家賃・光熱費など)
- ・損金処理できない保険の活用(返戻金目的の契約など)
- ・高級車・絵画などの資産購入による節税スキームの乱用
このような手法は、短期的には節税に見えても、後から否認されると大きなペナルティを受けるリスクがあります。
専門家への相談のすすめ
税理士などの専門家は、単に税額を減らすだけでなく、法令に沿った節税対策の適正チェックを行い、中長期的な資金計画の提案までサポートしてくれます。節税は単独のテクニックではなく経営全体の戦略と連動して考えるべきものです。
信頼できる専門家と連携し、無理のない堅実な節税対策を進めていきましょう。
節税対策なら「ストラーダ税理士法人」にご相談ください

節税対策をお考えの方は、実績豊富な「ストラーダ税理士法人」にご相談ください。法人・個人問わず、最新の税制に基づいた最適なプランをご提案いたします。経営視点を持った専門家が、節税だけでなく資金繰りや事業成長までトータルでサポートします。