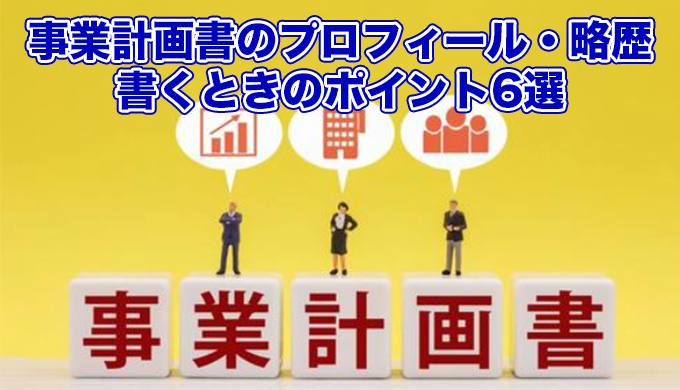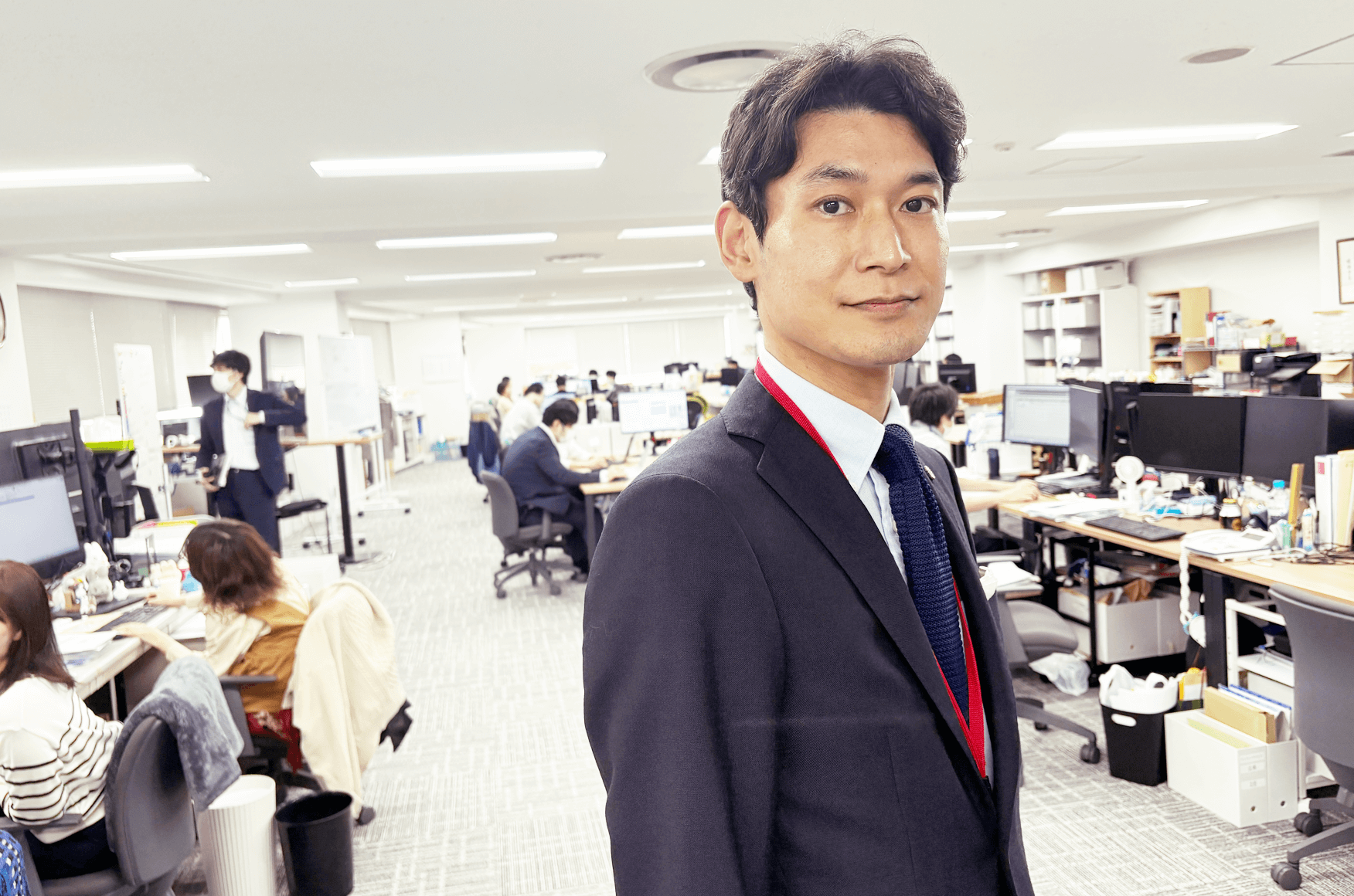企業買収や組織再編といった重要な意思決定の場面で、見逃せないのが「税務デューデリジェンス(税務DD)」です。これは、表面上の財務データだけでは把握しきれない、潜在的な税務リスクを明らかにするための調査であり、企業経営の安定と透明性を確保するうえでも欠かせないプロセスです。
本記事では、税務デューデリジェンス(税務DD)の概要から実施の流れ、費用相場、注意点までを総合的に解説します。
Contents
税務デューデリジェンス(税務DD)とは?

税務デューデリジェンス(税務DD)とは、M&A(合併・買収)取引に際して、対象企業が抱える税務上の問題点や繰越欠損金の引き継ぎの可否、組織再編、関連当事者取引の税務処理などを調査・分析する戦略的な取り組みを指します。十分に把握されない可能性がある、法人税や消費税の税務リスクを事前に把握することで、買収後のトラブルを回避し、契約条件の見直しや価格交渉を円滑に進めることができます。
とくに、海外子会社とのグループ間取引や、資産売却が多い企業では、思わぬリスクが潜んでいるケースも少なくありません。こうした「見えない負債」を適切に対処するうえでも、税務デューデリジェンス(税務DD)は極めて重要な役割を果たします。
税務デューデリジェンス(税務DD)の基本的な流れ

税理士など専門家へ依頼
まず最初に行うのは、税務デューデリジェンス(税務DD)の実務を担う外部専門家への依頼です。多くの場合、税理士や公認会計士のほか、M&Aに特化したコンサルティング会社などが対応します。
専門家を選ぶ際は、過去のM&A支援実績や、税務トラブルの経験が豊富であるかどうかを確認しましょう。公式サイトに記載されている情報に加え、利用者の口コミなども参考にしながら検討すると安心です。信頼できる専門家を選ぶことで、より精度の高いデューデリジェンスが期待できます。
調査範囲の決定
次に行うのは、税務デューデリジェンス(税務DD)で調査する対象範囲と期間の設定です。一般的には、基準日から過去3年分の法人税・消費税などの申告書、税務調査の履歴、帳簿資料、主要な取引に関する契約書類などが調査対象となります。
ただし、企業の状況によっては、5年以上遡って確認を行ったり、退職金の支給内容や長期間回収されていない未収金の貸倒処理といった、特定の分野を重点的に分析するケースもあります。
こうした調査を円滑に進めるためには、事前準備が欠かせません。具体的には、調査の目的や優先順位を明確にし、対象企業の経営陣と連携しながら、スケジュールや体制を整えておくことで、調査の効率と精度を高めることができます。
資料やヒアリングによる調査
あらかじめ設定した調査範囲に沿って、専門家が具体的な分析を進めていきます。対象企業から提供された各種資料をもとに、法人税を中心として消費税・源泉所得税・地方税などの納付状況や申告内容を中心に検証が行われます。
あわせて、経理・財務・税務の担当者へのヒアリング、過去に税務署から指摘を受けた内容の有無や、税務調査への対応履歴も重要なチェック項目のひとつです。
結果報告書を作成
すべての調査が完了すると、専門家によって税務デューデリジェンス(税務DD)報告書が作成されます。報告書には、確認された税務リスクや対応の緊急性といった情報が整理されており、状況次第ではM&A自体の見直しを行います。
この報告書は、最終的な買収判断や契約条件の見直し、価格交渉の際に大きな役割を果たす重要な資料となるため、紛失や情報漏洩を防ぐ観点からも、適切に保管することが大切です。
税務デューデリジェンス(税務DD)にかかる費用相場

税務デューデリジェンス(税務DD)にかかる費用は、対象企業の規模や調査内容、依頼先となる専門家の種類によって大きく異なります。主な相場は、下記の通りです。
| 会社の規模 | 費用相場 |
|---|---|
| 小規模事業者~中小企業 | 30万〜80万円以上 |
| 中堅企業〜上場企業 | 100万〜300万円以上 |
調査範囲が広がる場合や、海外子会社の税務確認を含むケースでは、追加費用が発生することもあります。また、報告書の提出にとどまらず、アドバイザリー契約を締結する際は、別途顧問料が必要になる点にも留意が必要です。
なお、初回相談や簡易的なレビューを無料で提供している専門家も多く、複数の候補から見積もりを取り、比較検討することは合理的な選択肢といえるでしょう。
このように、税務デューデリジェンス(税務DD)の実施には一定のコストがかかりますが、将来的な税務リスクによる損失を未然に防ぐという観点では、戦略的かつ有益な投資となります。
税務デューデリジェンス(税務DD)を実施する際の注意点

情報の管理体制を徹底する
対象企業から提供される情報には、税務申告書や契約書、従業員の報酬に関する資料など、機密性の高いものが含まれます。そのため、情報の受け渡しや保管にあたっては、漏洩防止のためのセキュリティ対策を徹底し、秘密保持契約(NDA)の締結が前提となります。
とくに、クラウド上での資料共有や外部とのやり取りの際には細心の注意が必要です。データの送受信には暗号化通信を用いるなど、技術的な安全対策を講じることも欠かせません。
適切なタイミングで行う
税務デューデリジェンス(税務DD)は、基本合意書(LOI)の締結後から最終契約に至るまでの間に実施するのが一般的です。契約締結の直前に重大な税務リスクが判明すると、交渉が白紙に戻るおそれもあるため、タイミングについてはあらかじめ留意しておくことが重要です。
理想としては、M&Aの交渉初期段階で実施し、その結果を踏まえて契約内容をスムーズに見直せる体制を整えておくことが望ましいでしょう。また、調査結果を契約書へ適切に反映させるためにも、スケジュールには十分な余裕を持って進めることが求められます。
潜在的な税務リスクも調査対象に含める
現在は表面化していなくても、将来的に課税対象となる可能性のある「潜在的リスク」にも目を向ける必要があります。たとえば、交際費や福利厚生費の範囲といった分野は、税務上の判断が分かれやすく、調査の対象となる可能性を孕んでいます。
こうした領域については、将来的に問題視されるおそれも踏まえたうえで、事前に調査項目を設定しておくことが重要です。必要に応じて法務部門や人事部門とも連携を図り、税務リスクを多面的に捉えるようにしましょう。
税務DDが導く、持続可能な未来と成長への第一歩

税務デューデリジェンス(税務DD)は、リスクを見極めるだけでなく、企業が安定的に成長していくための土台を築く、大切なステップです。健全な税務体制を可視化することで、取引先や金融機関、株主といった外部ステークホルダーからの信頼が高まり、結果として企業価値の向上にもつながります。
ストラーダグループでは、税務・財務・法務の各分野に精通した専門家が連携し、企業のあらゆる局面において最適なデューデリジェンス支援を提供しています。
ご相談はLINEにて無料で受け付けておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。今後の成長戦略や経営判断に伴う不安要素をひとつひとつ解消し、確かな未来へとともに歩んでまいりましょう。