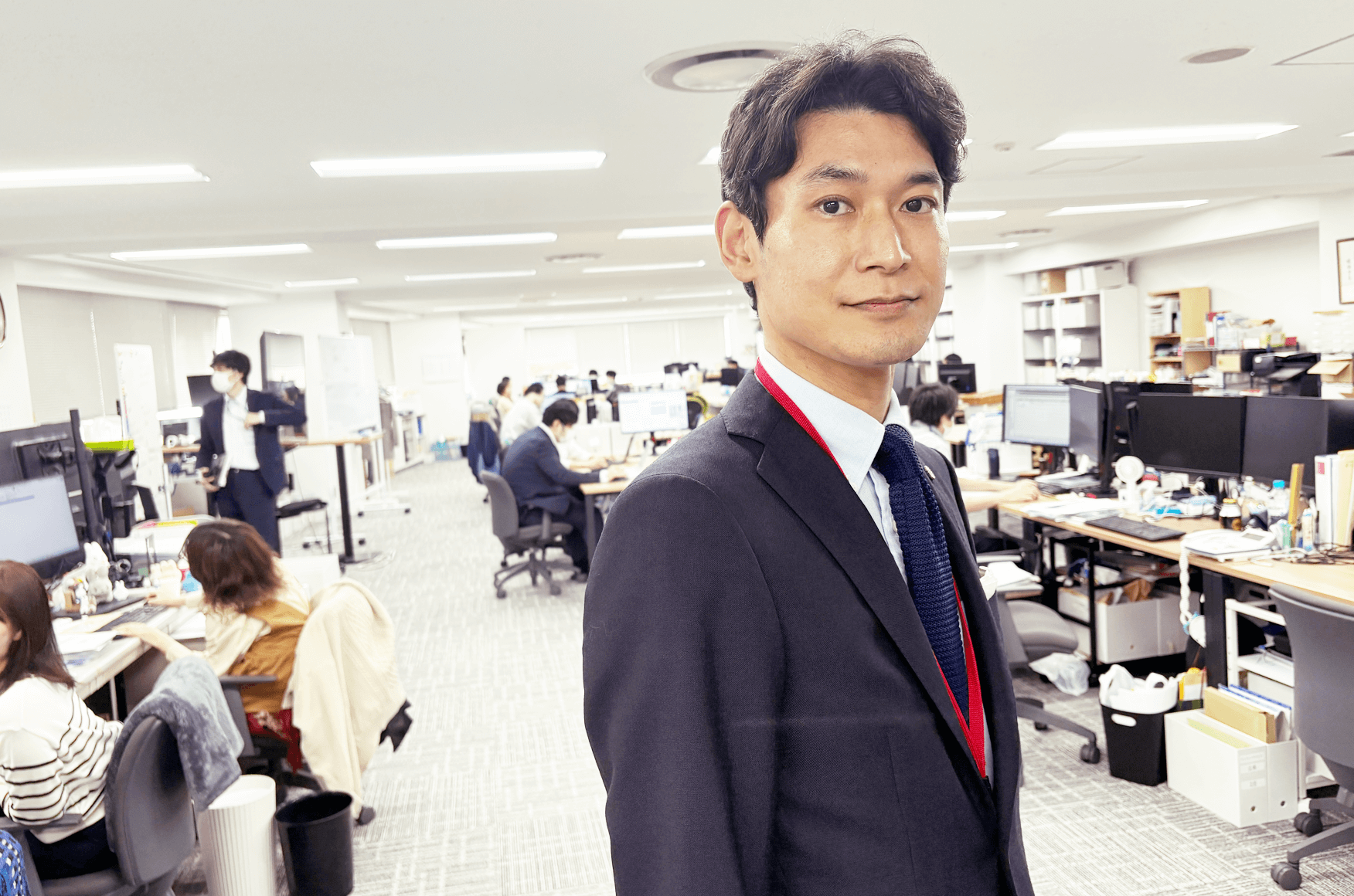中小企業を取り巻く経営環境は、少子高齢化による労働力不足、資源価格の高騰、そしてグローバル競争の激化などにより、これまで以上に厳しさを増しています。
そうした状況の中で、持続的な競争力を確保するために注目されている支援策が「経営力向上計画」です。
本記事では、経営力向上計画とは何か、どのような企業が対象となるのかを解説するとともに、活用するメリットについてわかりやすく紹介します。
Contents
経営力向上計画とは?

「経営力向上計画」とは、中小企業等経営強化法に基づき、国が定めた「事業分野別指針」等を踏まえて中小企業・小規模事業者等が策定し、所管する主務大臣の認定を受けることで、税制・金融・法的支援を受けられる制度です。
具体的には自社の経営力をどう向上させるか定性的に計画し、その計画に従って設備投資・人材育成・業務効率化・M&A・事業承継といった取組みを実施します。
経営力向上計画の認定を取得していると、ものづくり補助金や持続化補助金などの公的支援制度で加点対象となるケースが多く、支援を受けやすくなるため制度活用の“入口”として非常に重要です。
さらに、認定によって得られる恩恵は「資金面の後押し」だけではありません。計画の策定過程で、現状における強みと弱み、今後の市場環境や人材に関する課題などを客観的に整理することで、社内の意思統一にもつながります。
経営者だけが目標を持つのではなく、従業員と共有しながら推進できる点は、実務レベルで大きな効果が期待できます。
経営力向上計画の対象となる事業者と取り組み

事業者の範囲
経営力向上計画の対象となるのは、従業員数2,000人以下の要件を満たす法人・個人事業主・協同組合・協同組合連合会・医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人(NPO法人)など幅広い事業体が含まれます。
取組みの内容
人材育成・マネジメントの強化
経営管理体制の見直しや人事評価制度の整備、研修制度の導入、リーダー育成プログラムの実施など、従業員の能力向上と組織の統制力を高めます。社員一人ひとりのスキルアップと評価の透明性を確保することで、離職率低下や生産性向上につながります。
コスト管理
原価管理の強化や業務プロセスの改善、在庫管理の適正化などの施策により、コスト構造を見直し、生産性と収益性の両面で効率化を図ります。無駄な支出を削減するだけでなく、資金や人材をより戦略的な分野に振り向けることができます。
設備導入・デジタル化による生産性向上
新しい機械設備の導入、AIを活用した業務の自動化、クラウドシステムの導入など、生産性を高める投資です。実行することで、作業時間の短縮やデータ活用の高度化が可能になり、競争力の強化に直結します。
事業承継・M&A・業務再編による経営基盤の強化
事業承継計画の策定やM&Aの実施、業務再編を通じて、経営資源を最適に構築する取り組みです。これにより、事業の継続性を確保するとともに、新規事業の展開や成長の加速にもつながります。
経営力向上計画のメリット
税制優遇措置

経営力向上計画の認定を受けることで、中小企業は様々な税制優遇措置を活用でき、設備投資やM&Aなどの経営戦略を効率的に進めることが可能になります。
中小企業経営強化税制
中小企業経営強化税制は、経営力向上計画の認定を受けた企業が、新規設備を取得する際に、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
具体的には、業務効率化につながる機械設備やITシステム、ソフトウェア導入などの投資に対して、取得価額の10%もしくは7%の税額控除を受けることができます。
また、即時償却が可能な場合もあり、資金繰りの負担を軽減しつつ設備投資を促進できます。
事業承継等に係る不動産取得税の特例
中小企業等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき、合併・会社分割・事業譲渡を通じて、他の特定事業者等から不動産を含む事業用資産を取得する場合、事業承継に伴う不動産権利の移転に関して、不動産取得税を軽減できます。
中小企業事業再編投資準備金
中小企業事業再編投資損失準備金とは、中小企業がM&Aを実施する際、取得した株式等の費用の一部を損金算入できる制度です。
経営力向上計画の認定を受けた事業者が対象で、取得価額の最大70%を準備金として積み立て、その全額を損金として処理することで、M&A実施年度の税負担を軽減できます。準備金は5年間据え置いたのち、5年間で均等に取り崩して益金に算入する仕組みです。
さらに、2024年度の改正により、「特別事業再編計画」の認定を受けた場合は、取得価額の上限が10億円から100億円に拡大。積立率は最大100%、据置期間も10年に延長され、より大規模なM&Aにも対応できるようになりました。
金融支援

認定を受けた事業者は、金融面でも幅広い優遇措置を受けられる可能性があります。主に以下のような制度が整備されています。
日本政策金融公庫による融資
日本政策金融公庫が行う中小企業事業向けの融資において、経営力向上計画の認定を受けた事業者は低金利・長期返済・保証料率の引下げなどの優遇を受けることがあります。
たとえば、経営改善計画の実施資金や、生産設備の新設資金などに対して有利な条件で借入れが可能です。
中小企業信用保険法の特例
経営力向上計画の認定を受けた特定事業者は、計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会による普通保証とは別枠での追加保証を受けられます。対象となるのは、以下の取り組みに限定されます。
・新商品・新サービスなど、自社にとっての新しい取組(新事業活動)
・M&A等による事業承継(デューデリジェンスを含む)
※既存事業の運転資金確保など、通常の資金ニーズには適用されません。
中小企業投資育成株式会社法の特例
中小企業投資育成株式会社からの出資を受ける際、通常は資本金3億円以下が対象ですが、経営力向上計画の認定を受けていれば、より規模の大きい法人でも対象になる可能性があります。
日本政策金融公庫(中小企業事業)によるスタンドバイ・クレジット
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者は、海外取引に伴う信用リスクを軽減するため、日本政策金融公庫のスタンドバイ・クレジット(信用状)を活用できます。
国内親会社が認定を受けると、日本政策金融公庫が海外取引先や金融機関に対してスタンドバイ・クレジットを発行し、資金調達に必要な信用力を確保できます。これにより、海外取引をよりスムーズに進めることが可能です。
日本政策金融公庫(中小企業事業)によるクロスボーダーローン
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者の海外子会社は、国内にある親会社を通じて、経営力向上計画の実施に必要な設備資金や運転資金について、日本政策金融公庫から直接融資を受けることができます。
中小企業基盤整備機構による債務保証
中小企業基盤整備機構は、中小企業の経営安定や成長を支援する公的機関です。債務保証や経営相談、事業承継支援など、幅広い取り組みを行っています。
経営力向上計画の認定を受けた企業は、同機構による債務保証を活用することで、金融機関からの信用が向上し、有利な条件での資金調達が可能になります。
食品等流通合理化促進機構による債務保証
食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に、食品等流通合理化促進機構による債務保証を受けることができます。
この制度は、通常の信用保証が利用できない場合や、巨額の資金調達が必要なケースを想定した支援策です。経営力向上計画の認定を受け、計画に基づく設備投資や事業拡大などの取り組みを行うことが、保証の利用条件となります。
法的支援

経営力向上計画の認定を受けることで、事業譲渡や組合設立などに関して、法律上の特例措置が活用できる場合があります。
許認可承継の特例
事業譲渡や組織再編を行う際に、通常であれば新たに取得し直さなければならない許認可を、一部簡略化された手続きで承継できる特例があります。こうした特例を活用することで、再編・M&A時の事務コストを削減できます。
組合発起人数の特例
経営力向上計画に組合の組成を含めて認定を受けた場合、事業協同組合、企業組合、または協業組合を設立する際の発起人数に特例が適用されます。組合設立には最低4人の発起人が必要とされていますが、経営力向上計画の認定を受けていれば3人でも設立が可能です。
活用するためには、経営力向上計画の策定段階で、組合を組成する計画内容を明記しておくことが条件です。
事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
経営力向上計画の認定を受け、事業譲渡によって他者から取得する経営資源を活用する取り組みを行う場合、債務の移転手続きを簡略化できます。
通常、事業譲渡による債務移転では、債権者から個別に同意を得る必要があります。同意が得られない場合、譲渡元の企業は債務を免れません。
認定を受けた企業は、債権者に対して通知を行い、1か月以内に返答がなければ、債権者が同意したものとみなすことができ、手続きを簡略化した上で債務を移転できます。適用対象は、事業承継において譲渡先の特定事業者が株式会社である場合に限られます。
経営力向上計画の申請方法

経営力向上計画を申請する際の基本的な流れとポイントをご紹介いたします。申請にあたっては、最新の手引きや申請プラットフォームの案内等を必ずご確認ください。
日本標準産業分類で該当事業分野を確認
経営力向上計画を申請する際は、まず自社が属する事業分野が認定対象かどうかを、「日本標準産業分類」をもとに確認する必要があります。
日本標準産業分類とは、行政機関が統計調査などで用いる、日本国内のすべての経済活動を体系的に分類した基準のことです。多くの公的な申請や手続きにおいて、自社の事業内容を正確に特定するための共通の基準として活用されています。
この段階で自社の分類を正確に整理しておくことで、申請書への記載内容の正確性が高まり、審査もスムーズに進みます。
対応する事業分野別指針を確認する
次に、自社の計画が「事業分野別指針」の内容を満たしているかを確認します。事業分野別指針は、中小企業等経営強化法に基づき、各業種を所管する省庁が策定したもので、分野ごとに生産性を高めるための具体的な取り組みや方向性が示されています。
指針と基本方針を踏まえて計画書を作成
経営力向上計画の計画書には、企業の概要、現状認識、目標設定、取り組み内容、そして事業承継などがある場合はその時期・内容を記載する必要があります。併せて「数値目標(売上高や労働生産性)」を明確にすることで、審査時の説得力が高まります。
事業分野に応じた担当省庁の大臣に提出する
経営力向上計画は、各事業分野を担当する大臣の認定を受けて初めて有効になります。そのため、申請の際は分野を所管する大臣へ、必要書類(経営力向上計画認定申請書・経営力向上計画チェックシート等)を添えて提出する流れとなります。
申請書の郵送もしくは電子申請
経営力向上計画の申請は、郵送または電子申請のいずれかの方法で行います。従来は郵送による提出が一般的でしたが、現在はオンラインで申請できる「Jグランツ」などの電子申請システムを利用する方法も整備されています。
電子申請を実施することで、申請書類の作成サポートや審査期間の短縮といったメリットがあり、審査の進捗状況も簡単にチェックできます。
経営力向上計画の認定を受ける際の注意点

認定までの期間を考慮する
申請から認定までには一定の期間を要します。電子申請を利用した場合、中小企業庁では目安として「約14日(休日等を除く)」と公表されていますが、申請内容の複雑さや審査状況によって前後する可能性があります。
そのため、設備導入や契約・投資の予定がある場合には、認定取得のタイミングを逆算して計画する必要があります。認定前に設備を取得してしまうと、税制優遇や各種支援の適用を受けられないケースがあるため注意が必要です。
支援に必要な追加書類あり
経営力向上計画の認定を受ける際には、経営力向上計画認定申請書や経営力向上計画チェックシートに加えて、追加書類の準備が必要な場合があります。
特に設備投資を前提として税制優遇措置を受ける場合は「工業会証明書」や「経済産業局の確認書」の提出を求められることがあります。さらに、計画の実行状況を報告する義務がある場合もあるため、実施体制などもあらかじめ整えておくことが大切です。
専門家のサポートを受ける
経営力向上計画の対象範囲や優遇措置内容等は、常に最新動向があり、内容が入り組んでいるため、自社単独での申請は難易度が高いのが現状です。
たとえば、対象設備の定義・耐用年数・適用業種の除外・適用可能な期間など、細部において誤りが生じると優遇措置を受けられない可能性があります。そのため、申請策定時には、中小企業診断士・税理士・公認会計士等の専門家の支援を受けることを推奨します。
経営力向上計画で会社の成長を加速化!

経営力向上計画は、補助金・融資・税制優遇などの公的支援を受けられるだけでなく、自社の事業戦略を整理し、成長のロードマップを明確にすることができる、実践的な経営ツールです。
ただし、制度の内容は複雑で、認定要件や添付書類に注意すべきポイントが多いのも事実です。申請を進める際には、正確な知識と経験が必要となります。
ストラーダグループでは、税理士、公認会計士、社会保険労務士、中小企業診断士、司法書士、行政書士が連携し、企業の状況に応じた手厚いサポートを提供しています。「何から手をつければよいか分からない」という段階でも問題ありません。まずはお気軽にご相談ください。