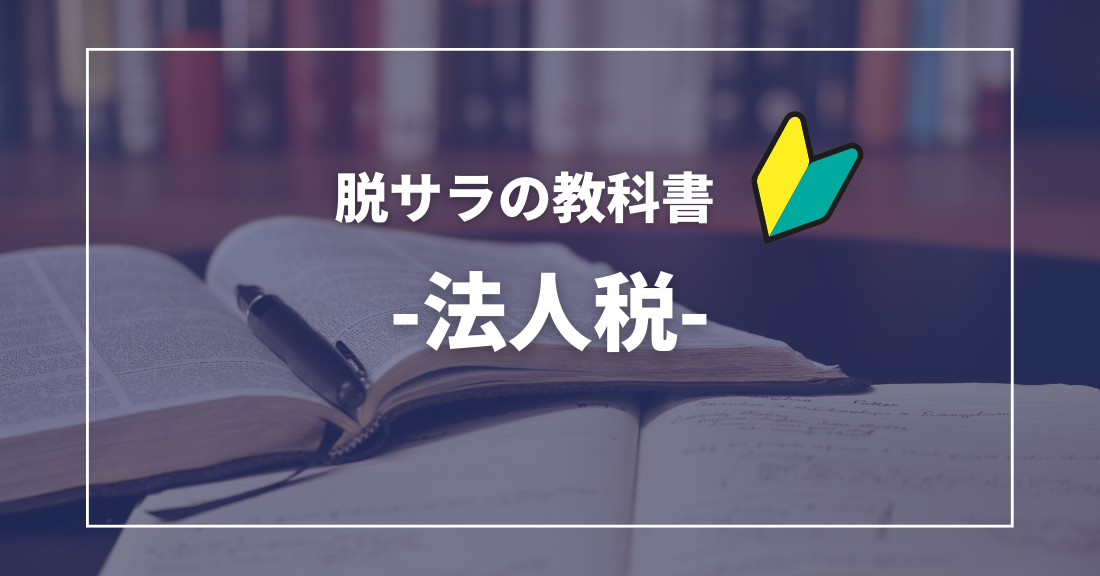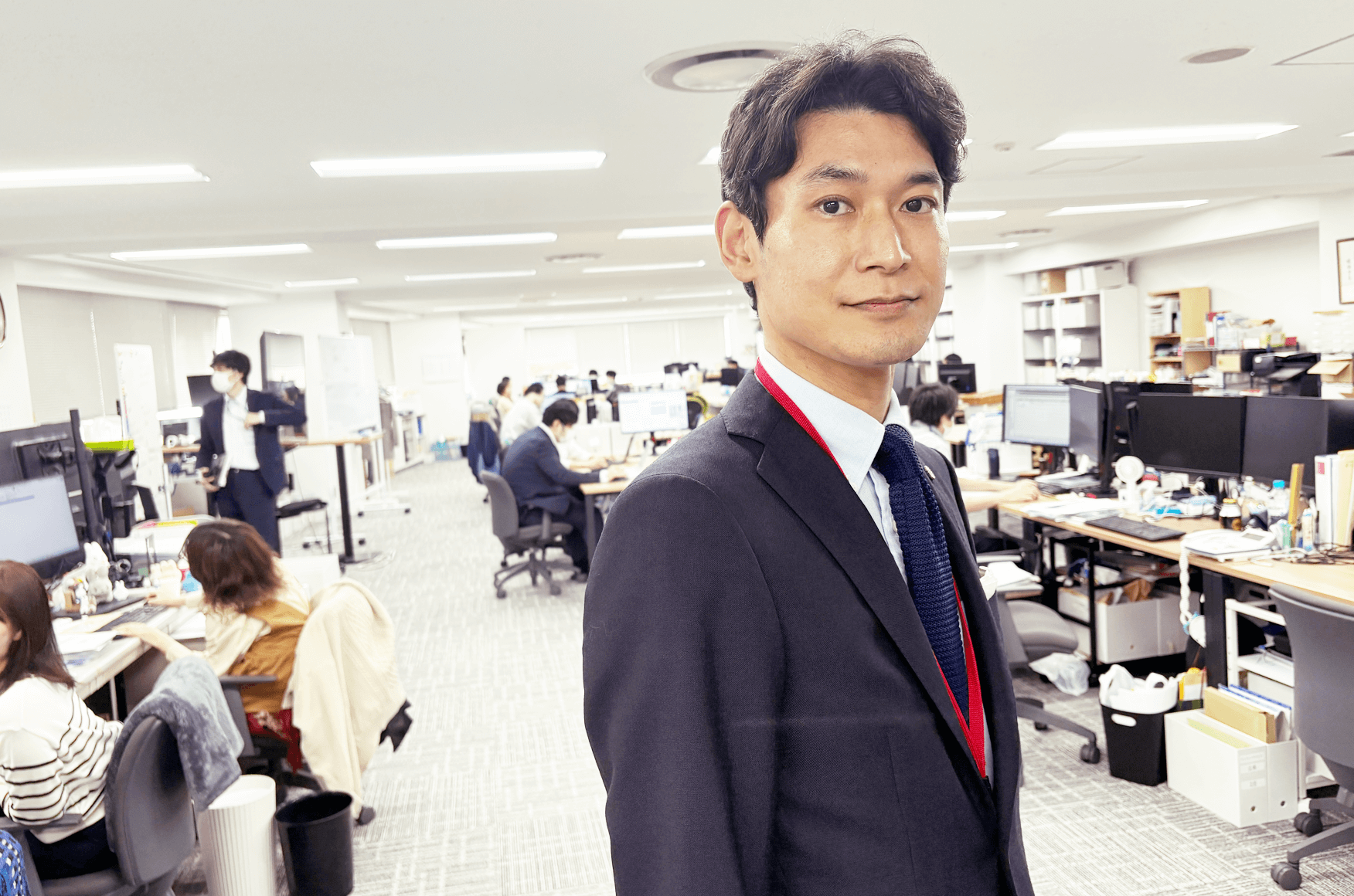法人を設立し、事業を行っていく中で避けて通れないのが「法人税」です。経営者や経理担当者にとって、法人税の仕組みや税率、申告や納付の流れを正しく理解しておくことは、健全な財務運営に欠かせません。
本記事では、法人税の基本的な仕組みから、具体的な税率や計算方法、実務上の注意点、さらには知っておきたい節税対策までを分かりやすく解説します。
Contents
法人税とは?仕組みと基本をわかりやすく解説

まずは「法人税とは何か」という基本的な定義から、法人がどのような条件で課税対象になるのか、さらに法人税の種類やその内訳、実効税率について解説します。
法人税の定義と課税対象
法人税とは、法人の所得に対して課される国税のことを指します。法人が1年間の事業活動で得た利益(所得)に応じて税額が決まり、原則として毎年1回、法人税申告書を提出し、納税する必要があります。
法人税の納税義務があるのは、次のような法人です。
- 株式会社
- 有限会社
- 合同会社(日本版LLC)
- 一般社団法人・財団法人(営利活動を行っている場合)
- 医療法人・学校法人など特別法人(一定の条件により課税)
なお、法人税は「法人税法」に基づいて課税されます。個人が支払う所得税とは異なり、法人格を有する団体の経済活動に課税される点が特徴です。
法人税法の中でも、課税の基本的な構造を定めているのが「法人税法第22条」です。ここでは、法人の課税所得の計算方法が規定されており、益金から損金を差し引いた金額をもとに課税される仕組みになっています。
また、法人税法施行令や法人税法基本通達、租税特別措置法などの関連法令もあわせて理解しておくことで、実務での誤解やミスを防ぐことができます。
法人税の種類と実効税率の仕組み
法人が支払う税金は法人税だけではありません。法人にかかる主な税金は、国税と地方税に分かれており、これらを合算したものが「法人実効税率」と呼ばれます。法人にかかる主な税金と概要は以下の通りです。
| 税目 | 概要 |
|---|---|
| 法人税(国税) | 法人の所得に対して課される基本税 |
| 地方法人税(国税) | 法人税の一部として課される追加的な税 |
| 法人住民税(地方税) | 地方自治体に支払う税。法人税額をもとに計算 |
| 事業税(地方税) | 所得や付加価値などを基準に課税される税 |
これらを合算した「法人税 実効税率」は、法人が実際に負担する全体的な税率を示すもので、法人税(国税)に加え、地方法人税、法人住民税、法人事業税といった地方税を含むため、企業の規模や所在地、事業内容によって実効税率は若干異なります。
2025年時点の法人税率は23.2%ですが、中小法人(資本金1億円以下の普通法人、その他一定の条件を満たす法人)で所得800万円以下の部分に対しては軽減税率15%が適用され、東京23区に本社を置く中小法人の地方税を含めた実効税率は29.05%とされています。東京23区に本社を置く大企業では、実効税率は30.62%%とされています。
このように、実効税率は法人の規模により異なります。節税を考えるうえでも、どれだけの負担になるのかを理解しておくことが重要です。
法人税の歴史と税率推移から読み解く税制の変遷

法人税は、企業の経済活動に応じて課税される重要な国税です。その税率や制度は、時代の変化や経済状況に応じて見直されてきました。
ここでは、日本における法人税の税率推移と、その背景にある政策的な意図を解説します。過去から現在までの流れを知ることで、現在の法人税率がどのように位置づけられているのか、より深く理解できるでしょう。
法人税率の変遷(昭和〜令和)
法人税の税率は、戦後から現在にかけて段階的に変化してきました。特に昭和後期から平成、そして令和にかけては、国際競争力の強化や経済のグローバル化に伴い、引き下げが進められています。
以下に主な時代ごとの法人税率の推移をまとめます。
| 時期 | 法人税率 |
|---|---|
| 昭和59年 | 43.3% |
| 昭和62年代 | 42% |
| 平成10年 | 34.5% |
| 平成27年 | 約23.9% |
| 令和7年現在 | 23.2% |
かつては昭和59年の43.3%をピークとして「法人税40パーセント以上」が当たり前の時代もありましたが、現在では23.2%にまで抑えられています。
また、世界的な動きとしても法人税率の引き下げ競争が起こっており、日本もそれに追随する形で段階的な減税を実施してきました。
なぜ法人税は引き下げ・引き上げされるのか?
法人税率の変更には、単なる財政上の理由だけでなく、国家の経済政策や国際的な要因が大きく関係しています。引き下げや引き上げが行われる主な背景には以下のような理由があります。
- 法人税率が引き下げられる主な理由
- ・海外企業の誘致・国内企業の海外流出防止(国際競争力の確保)
- ・経済の活性化と投資促進
- ・税収構造の見直し(消費税など間接税への転換)
- 法人税率が引き上げられる主な理由
- ・社会保障費や公共事業などの財源確保
- ・財政赤字の是正
- ・所得再分配政策としての役割
法人税は、以下のようなバランスの上に成り立っています。
| 要素 | 説明 |
|---|---|
| 経済成長への影響 | 高すぎる税率は投資や雇用を抑制する懸念がある |
| 国際的な比較 | 他国と比べて税率が高いと企業が海外へ流出する可能性が高まる |
| 財政需要 | 税収として国家予算を支える役割を持つ |
たとえば、法人税が高すぎると日本の法人税は高いと敬遠され、海外企業の日本進出が鈍ることもあります。一方で、税率を下げすぎると税収が不足し、社会保障などにしわ寄せが来るリスクもあります。
近年では、法人税の引き下げと引き換えに、消費税の引き上げなどが議論されており、税制全体のバランスを見ながら制度設計が進められています。
法人税率とその計算方法

節税対策を検討する前提としても、まず正確な税率や計算方法を理解することが重要です。ここからは法人税率の基本的な考え方から、中小法人に適用される軽減税率、そして法人税の実際の計算手順や必要書類について詳しく解説します。
法人税率の基本と中小企業への適用
法人税には、所得に応じて異なる税率が設定されています。大企業と中小法人では適用される税率が異なり、中小企業に対しては税制上の優遇措置が設けられています。法人税の税率は2025年現在以下の通りです。
| 所得区分 | 税率(適用対象) |
|---|---|
| 年800万円以下の所得 | 15%(中小法人:資本金1億円以下) |
| 年800万円超の所得 | 23.2%(中小法人・大法人共通) |
※中小法人の判定は、原則として資本金1億円以下かつ大企業の子会社等でないことが条件です。
また、地方法人税が加算されるため、実質的な負担率はもう少し高くなります。東京23区の場合、法人住民税や事業税と合わせた実効税率で考えると、以下のようになります。
| 法人の区分 | 実効税率の目安 |
|---|---|
| 中小法人 | 29.05% |
| 大法人 | 30.62% |
このように、企業の規模により、負担する税率は異なります。
法人税の計算方法と必要書類
法人税の計算は、まず会社の決算書をもとに課税所得を算出し、その所得に税率をかけて税額を求めるという流れで行います。実際の税額計算には、会計上の利益と税務上の所得に差が出るため、一定の調整が必要です。
法人税計算の基本ステップは以下の通りです。
- 1.決算書から当期純利益を確認
- 2.税務調整で課税所得を算出
- 3.所得に応じた法人税率を適用
- 4.地方法人税・住民税・事業税を加算
- 5.税額控除・中間納付分を差し引いて納付額を確定
また、計算に必要となる書類は以下の通りです。
- ・損益計算書(PL)
- ・貸借対照表(BS)
- ・勘定科目内訳書
- ・法人税申告書(別表一式)
- ・前期・当期の帳簿資料
特に、税務調整が必要な項目は、会計と税務で取り扱いが異なるため注意が必要です。
法人税の申告と納付に関する実務知識
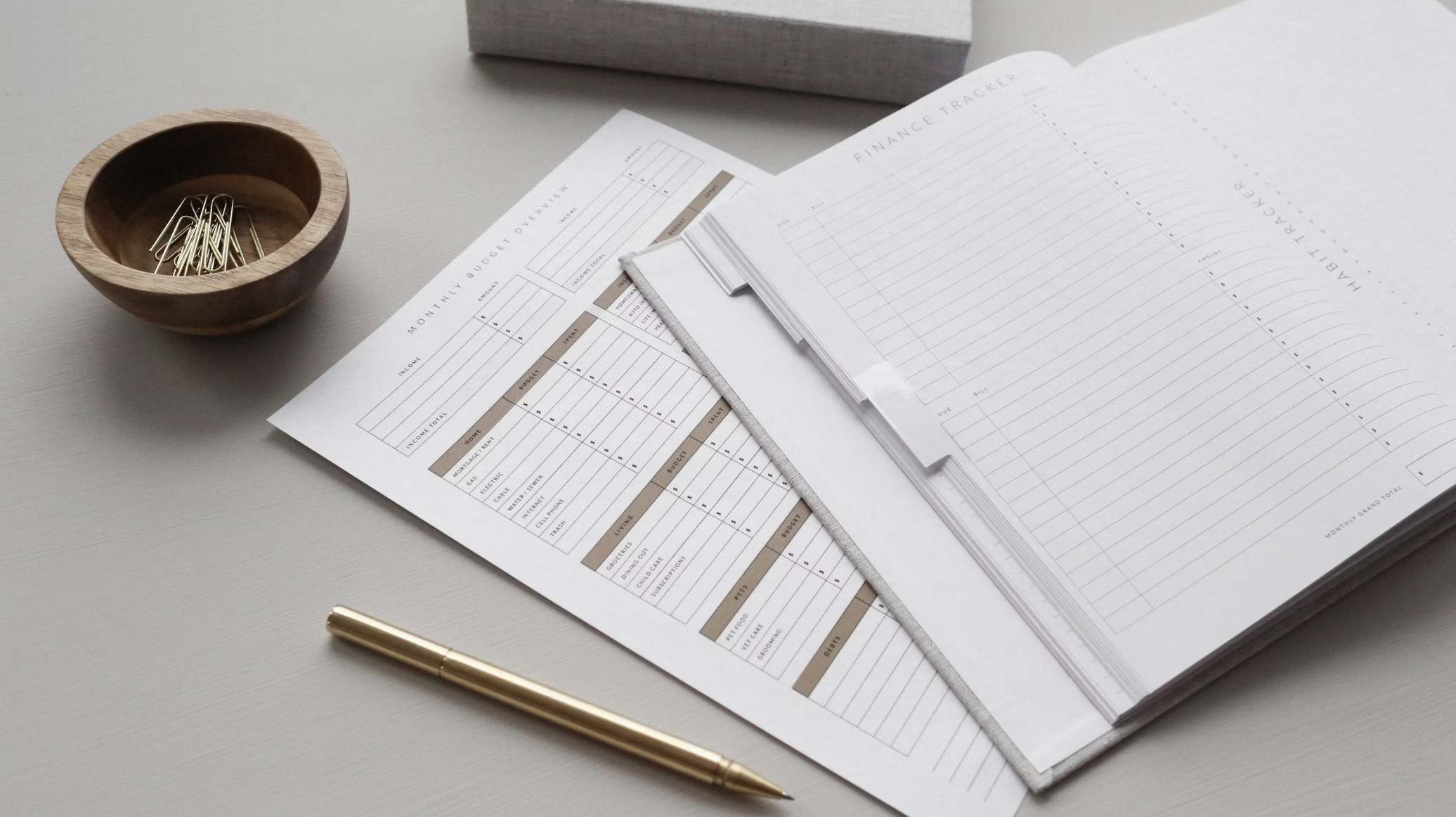
法人税の申告と納付は、企業にとって毎年発生する重要な業務のひとつです。期限を守ることはもちろん、必要な書類の準備や手続きの流れを理解しておかないと、加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性もあります。
申告期限と予定納税の流れ
法人税の申告には、明確に定められた期限があります。期限内に申告・納税を完了させるためには、事前のスケジュール管理が欠かせません。また、所得に応じて「予定納税(中間納付)」の義務が発生する場合もあります。
原則として法人税の申告と納付は、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内にしなければなりません。ただし、所轄税務署への申請により「申告期限延長の特例」が認められれば1ヶ月の延長が可能となります。
前事業年度の法人税額が20万円を超えている場合は、中間申告(予定申告方式または仮決算方式)が義務付けられます。この納付は、原則として事業年度開始から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に行う必要があります。
納付・還付の方法と電子申告(e-Tax)のポイント
法人税の納付は、いくつかの方法から選ぶことができます。近年では、利便性の高い電子申告(e-Tax)の利用も増えており、業務の効率化に繋がっています。また、過納があった場合には還付手続きを行うことも可能です。
法人税の納付方法は以下の通りです。
- ・金融機関の窓口で納付書を使用して支払い
- ・インターネットバンキング(ペイジー)
- ・コンビニ納付(30万円を超える場合は利用できない)
- ・ダイレクト納付
- ・クレジットカード納付(1,000万円以上の場合は利用できない)
- ・スマホアプリ納付(30万円を超える場合は利用できない)
近年利用者が増えているe-Taxのメリットは以下の通りです。
- ・24時間いつでも申告可能
- ・郵送コスト・手間を削減
- ・勘過去のデータを活用しやすい
- ・添付書類の省略が可能になるケースもあり
e-Taxの利用には、事前の電子証明書登録や利用者識別番号の取得が必要となるため、余裕を持って準備しておきましょう。
また、以下のようなケースでは差額分の還付を受けることが可能です。
- ・仮決算による中間納付が多すぎた
- ・税額控除などの適用により本税が減額された
還付は、法人税申告書の「還付請求欄」に記載することで自動的に処理され、所轄税務署での確認後、2週間〜1か月ほどで指定口座に振り込まれます。
法人税と赤字・還付・繰越の関係

法人税というと「利益が出たら支払うもの」というイメージを持たれるかもしれませんが、実際の制度はもう少し複雑です。たとえ赤字であっても、法人税が全くのゼロになるとは限らず、一定の負担が発生することもあります。また、赤字の年度がある場合には、繰越欠損金や還付制度を活用することで税負担を軽減できる可能性もあります。
赤字でも法人税はかかる?
企業が赤字決算になった場合でも、法人税がまったくかからないわけではありません。主に次の以下の2つの理由により、一定の納税義務が発生することがあります。
- ・法人住民税の「均等割」
- ・繰延資産や交際費などの「損金不算入項目」
たとえ所得がゼロまたは赤字であっても、法人として登記されている限り「法人住民税の均等割」は原則発生します。これは利益の有無に関係なく課税されるため、赤字企業でも負担が生じます。
- 例)資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人の場合
- → 東京都では年間7万円の均等割が発生
赤字計上していても、会計と税務のルールが異なるため、一部の支出が税務上の損金として認められず、課税所得が生じるケースがあります。これにより、実質的な赤字でも課税対象になる場合があります。
| 主な例 | 内容 |
|---|---|
| 租税公課 | 法人税、地方法人税など |
| 損金不算入項目 | 交際費損金算入限度超過額など |
こうした点を踏まえると、たとえ利益が出ていない年度でも法人税に関連する処理や納付が必要になることがあります。
還付や繰越欠損金の基本と注意点
赤字となった年度には、将来の税負担を軽減するための制度が用意されています。代表的なものが「繰越欠損金」と「欠損金の繰戻し還付」です。
「繰越欠損金」とは、赤字となった金額(欠損金)を、翌期以降の黒字から差し引くことができる制度です。これにより、将来の法人税額を軽減することが可能になります。
- 繰越可能な期間:原則10年間(青色申告が条件)
- 適用上限:所得の50%まで(中小法人等は制限なし)
「繰戻還付」とは、主に中小法人等が赤字となった事業年度の損失を、前期の黒字にさかのぼって適用し、すでに納めた法人税の一部を還付してもらう制度です。こちらも青色申告が前提です。
これらの制度を活用することで、赤字による資金繰り悪化を一定程度緩和することが可能です。
- 注意点と実務上のポイント
- ・青色申告をしていないと適用できない
- ・別表7(繰越欠損金の明細)など、申告書類の整備が必要
- ・繰戻還付の申請は、対象年度の確定申告と同時に行う必要がある
これらの制度は、「赤字なら節税は関係ない」という誤解を避けるためにも知っておきたい内容です。特に創業期や業績が不安定なフェーズの法人にとっては、節税と資金繰りの両面で重要な施策となります。
法人税の節税対策と賢い経営のコツ

法人税の納税は企業の社会的責任である一方、正しく知識を持つことで、合法的に税負担を軽減する節税も可能です。ただし、節税と脱税は全くの別物。法律の範囲内で、事業の健全な成長に資する「攻めの節税」を実行することが大切です。
節税と脱税の違い
節税と脱税の違いは以下の通りです。
- 節税:法令の範囲内で税金を減らす正当な行為
- 脱税:意図的な所得隠しなどのや不正経理により税を免れる違法行為
目的が税負担の回避そのものになってしまうと、税務調査で否認されるリスクが高まります。
合法的な節税の基本と注意点
節税策は数多くありますが、ここでは中小企業でも実践しやすい代表的な方法を中心に紹介します。
| 節税策 | 概要 | 効果・留意点 |
|---|---|---|
| 減価償却の活用 | 少額減価償却資産の特例、一括減価償却の特例の活用 | それぞれ30万円未満、20万円未満の減価償却資産は、購入した年度又は3年間での費用化が可能 |
| 福利厚生費の活用 | 社宅、健康診断、社員旅行など損金算入が可能 | 要件を満たせば節税可。制度設計が重要。 |
| 投資促進・経営強化税制の利用 | 指定設備導入で即時償却や税額控除が可能。 | 条件や期限の確認必須。税制改正に注意。 |
| 在庫・固定資産の見直し | 不良在庫や不要資産の処分で利益圧縮。 | 行き過ぎた圧縮は翌期以降に影響するため注意。 |
法人税についてのご相談は「ストラーダグループ税理士法人」へ

法人税に関する対応は、税率や計算方法の理解だけでなく、申告や納付、節税対策まで多岐にわたります。ストラーダグループ税理士法人では、豊富な実績と専門知識をもとに、法人の成長フェーズや業種に合わせた最適な税務サポートを提供しています。申告業務の効率化から、将来を見据えた節税・資金繰りのご相談まで、税務のプロフェッショナルが丁寧に対応します。