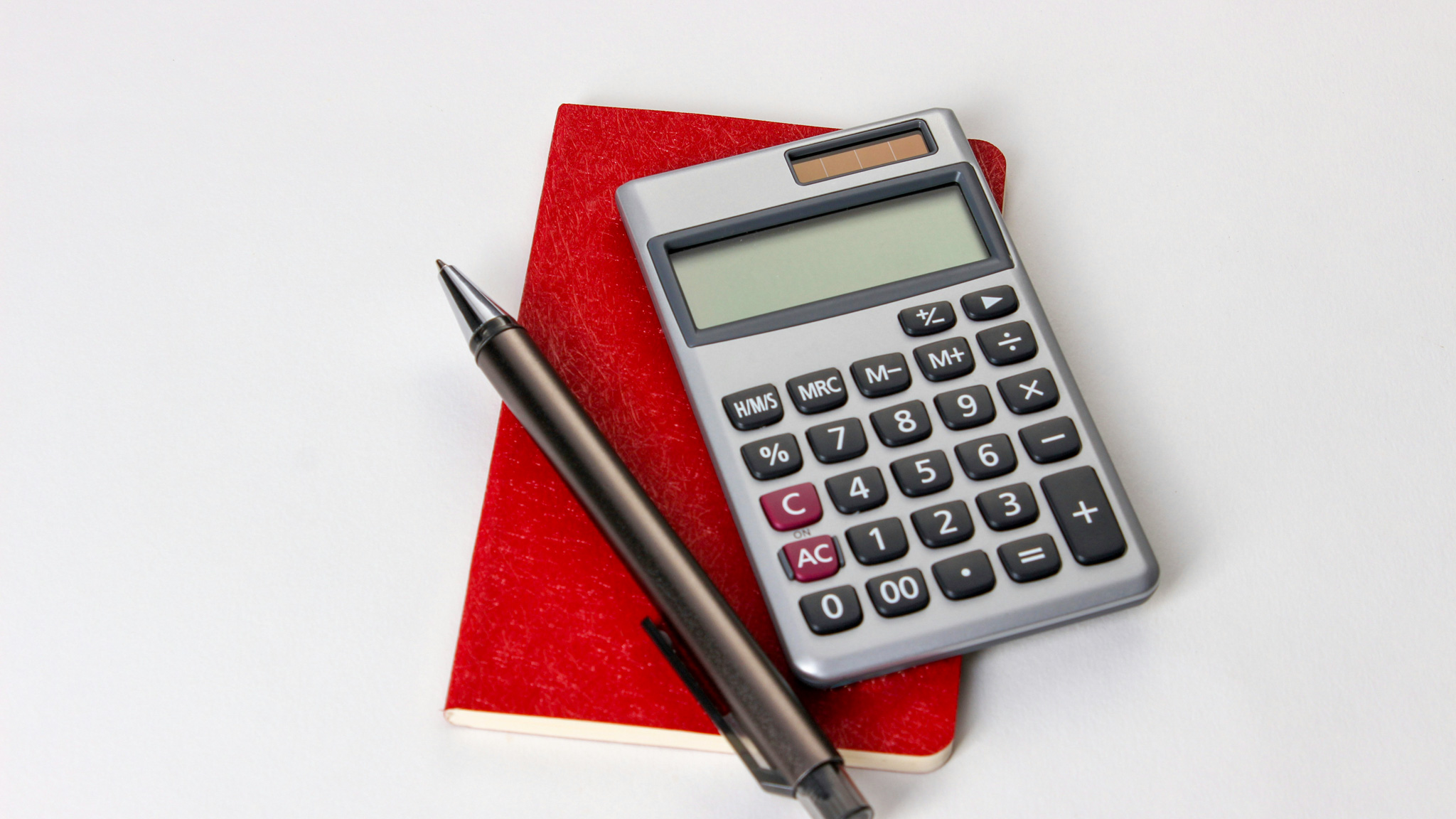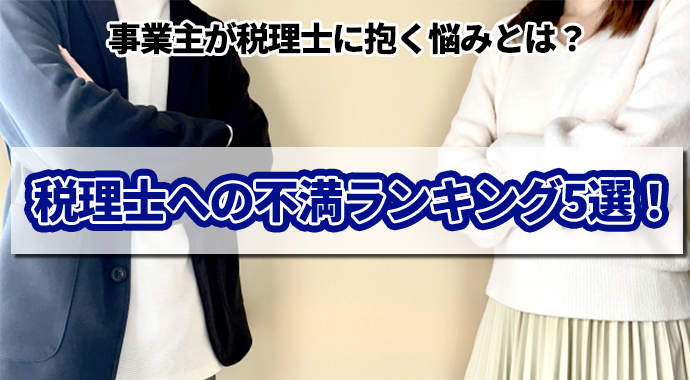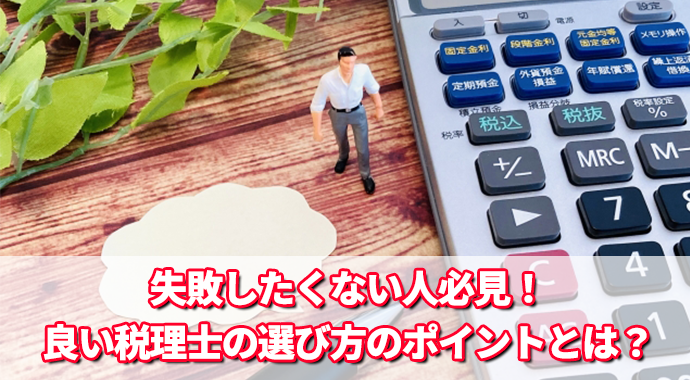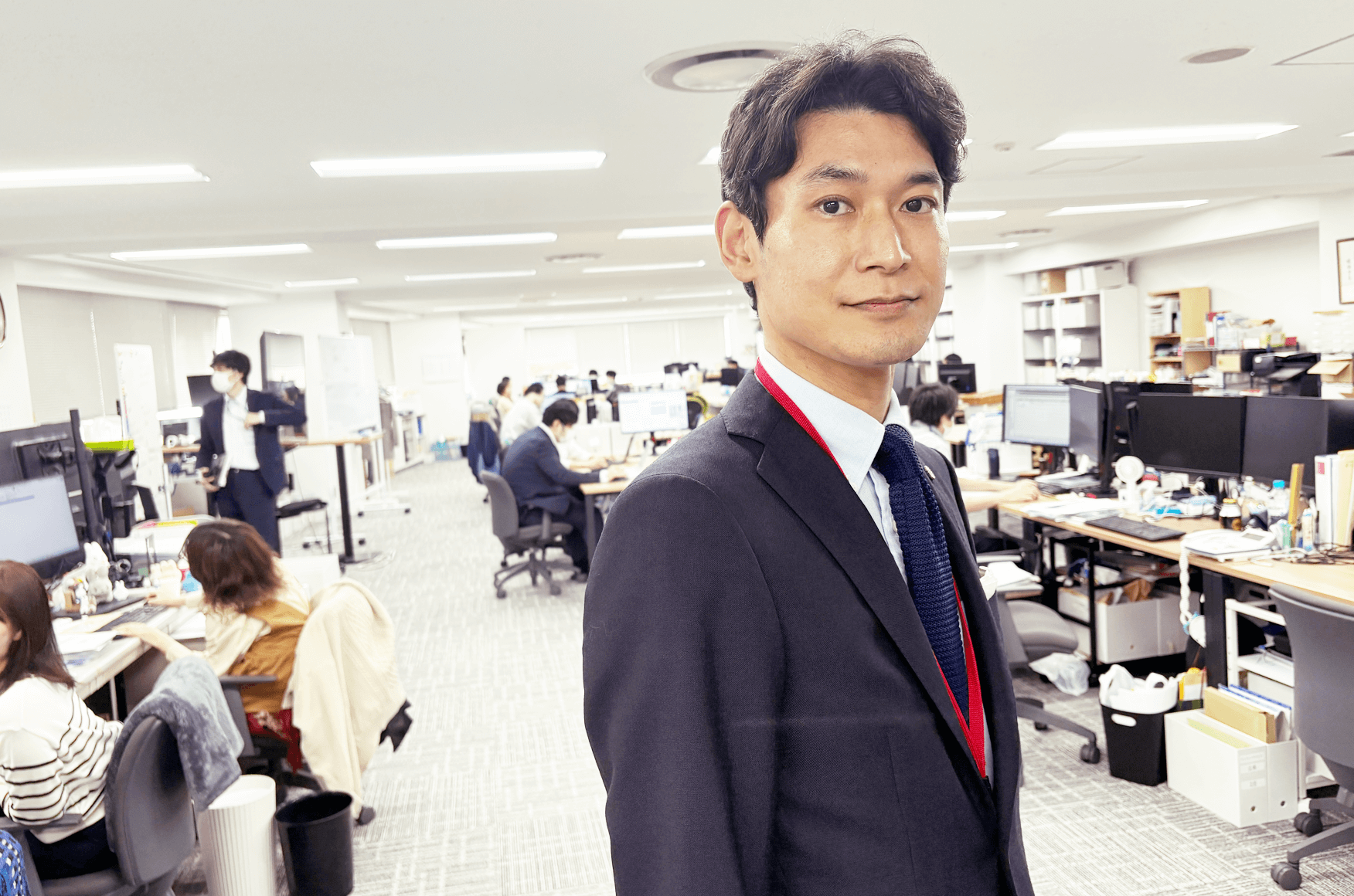海外に住んでいる日本人や、日本国内に納税義務があるものの管理が難しい方にとって、「納税管理人」という制度は欠かせないものです。納税管理人を選任することで、納税に関する手続きを円滑に進め、税務上のリスクを軽減できます。しかし、「納税管理人とは具体的にどのような役割を担うのか?」「どのように選任すればよいのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、納税管理人の基本的な役割や選任方法、業務内容、さらには解任や変更の手続きまで詳しく解説します。納税管理人の制度を正しく理解し、適切に活用するために是非参考にしてみてください。
Contents
納税管理人とは?

納税管理人とは、日本国内に納税義務があるものの、日本に住所や事務所を持たない個人や法人に代わり、税務手続きを行う代理人のことです。海外に居住している日本人や、日本に不動産を所有している非居住者、外国法人などが納税義務を果たす際に、納税管理人を選任することでスムーズな税務対応が可能になります。
納税管理人の選任が求められる主なケースには、以下のようなものがあります。
| ケース | 内容 |
|---|---|
| 日本に不動産を所有する非居住者 | 日本国内で不動産を賃貸し、所得を得ている場合、所得税の申告・納付が必要となります。 |
| 海外転勤や移住による非居住者の税務対応 | 海外に居住していても、日本に収入源がある場合は、納税義務が生じることがあります。 |
| 日本で事業を展開する外国法人 | 日本に拠点を持たない海外企業が、日本国内で事業活動を行う際には、法人税や消費税の申告・納付をする必要があります。 |
納税管理人の基本的な役割
納税管理人の主な役割は、納税義務者に代わって税務手続きを遂行することです。具体的には、以下のような業務を担います。
- 税務署からの通知・書類の受領
- 所得税や法人税などの申告および納付
- 税務調査への対応や税務署とのやり取り
特に、税務署からの通知や指導は重要なものが多く、対応が遅れると延滞税やペナルティが発生する可能性があります。納税管理人を選任しておくことで、こうしたリスクを未然に防ぐことができます。
また、納税管理人は単なる郵便の受け取り役ではなく、税務の専門家であることが求められるケースもあります。税務に関する知識が不足していると、適切な申告ができなかったり、税務署とのやり取りに不備が生じたりする可能性があるため、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。
納税管理人の業務の詳細については下記でも詳しくご紹介しているので、そちらも参考にしてみてください。
納税管理人を選任するメリット
海外に居住している個人や国外に本社を持つ企業が日本で納税義務を負う場合、納税に関する手続きを円滑に進めることが課題となります。納税管理人を選任することで、日本国内での税務手続きをスムーズに進められるようになります。
例えば、税務署からの通知や書類の受領、税金の申告・納付などは、納税管理人が代理で対応できます。これにより、時差や郵送の遅れなどによる申告漏れのリスクを軽減し、適切な税務管理が可能になります。
納税管理人を選出することで軽減できる主な負担は以下の通りです。
税務署とのやり取り
| 納税管理人を選任しない場合 | 納税管理人を選任した場合 |
|---|---|
| 書類の送付や質問への対応をすべて自分で行う必要がある | 納税管理人が代理で対応し、必要な情報のみ提供してもらえる |
申告・納付手続き
| 納税管理人を選任しない場合 | 納税管理人を選任した場合 |
|---|---|
| 日本の税制や手続きに詳しくないとミスや遅延のリスクが高い | 納税管理人が正しく手続きを進めるため安心 |
書類の管理
| 納税管理人を選任しない場合 | 納税管理人を選任した場合 |
|---|---|
| 重要な通知や書類を適切に保管・管理する必要がある | 納税管理人が整理・保管し、必要に応じて納税者に共有 |
日本の税法は複雑であり、税務申告や納付の期限を守らないと延滞税や罰則が発生する可能性があります。特に、海外在住者は日本の税制に関する情報をリアルタイムで得るのが難しいため、知らないうちにルール違反をしてしまうリスクがあります。納税管理人を選任すれば、こうしたリスクを回避し、適切な税務対応が可能になります。
納税管理人を活用することで、税務に関する業務負担を軽減し、本業や他の重要な業務に集中することができます。
納税管理人の選任方法

納税管理人を選任するには、税務署への届出が必要です。適切な手続きを行うことで、税務に関する通知の受領や申告・納付をスムーズに進められます。ここでは、納税管理人の選任手順と届出書の書き方について詳しく解説します。
納税管理人を選任する流れ
納税管理人の選任は以下のような流れで進めます。
- 1.納税管理人の決定
- 2.必要書類の準備
- 3.届出書の提出
- 4.受理後の確認
納税管理人の選任は、納税義務者自身が手続きを行うことが基本ですが、代理人(税理士など)が代行することも可能です。
納税管理人の決定
納税管理人を選任する際は、適任者を慎重に選ぶことが重要です。信頼できる人物や法人を選び、スムーズな税務対応ができるよう準備する必要があります。
納税管理人として選任できるのは、次のような個人や法人です。
- ・税理士や会計事務所
- ・親族や知人
- ・企業・法人
納税管理人を選任する際は、税務知識の有無、長期的な対応の可否、スムーズな連絡が可能かといった点を慎重に検討する必要があります。税務手続きに関する知識が不足していると、申告漏れや納付遅延のリスクが高まるため、税理士などの専門家を選ぶことでリスクを最小限に抑えられます。
また、一時的な選任ではなく、継続的に税務対応を行えるかも重要なポイントであり、特に知人や親族に依頼する場合は、長期間にわたって対応できるかも相談し慎重に検討する必要があります。
さらに、納税管理人は税務署からの通知を受領し、納税義務者へ迅速に伝える役割も担います。そのため連絡が取りやすく確実に情報を共有できる相手を選ぶことも大切です。
必要書類の準備
納税管理人を選任する際に提出が求められる書類は、以下の通りです。
- ・納税管理人届出書
- ・納税義務者の本人確認書類
- ・納税管理人の本人確認書類
納税管理人の選任は、原則として納税義務が発生する前に行う必要があります。書類の提出が遅れると、手続きが完了するまでの間に税務対応が滞る可能性があるので早めに準備を進めましょう。
届出書の提出
必要書類を準備した後、「納税管理人届出書」を税務署に提出します。提出方法とそれぞれの特徴、注意点は以下の通りです。
| 提出方法 | 特徴と注意点 |
|---|---|
| 窓口提出 | 税務署の窓口で直接提出でき、その場で書類の不備を確認してもらえるため、手続きを迅速に完了できる。受付印が押された控えを受け取ることで、届出の証拠を残せる |
| 郵送提出 | 税務署まで行く必要がなく、遠方からでも手続き可能。ただし、書類の到着や受理状況を確認するため、簡易書留やレターパックなどの追跡可能な方法で送るのが望ましい |
| 電子申請(e-Tax) | 一部の税務手続きでは、国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用してオンラインで届出が可能。事前に税務署のウェブサイトで対応状況を確認し、利用環境を整えておく必要がある |
届出書の提出
納税管理人の届出書を提出した後は、税務署での受理を確認し、今後の税務手続きに問題が生じないよう準備を整えます。受理後の対応を怠ると、納税管理人としての業務が適切に行えず、税務署からの通知が届かないなどのトラブルが発生する可能性があります。
受理後に確認すべき事項は以下の通りです。
| 確認事項 | 内容 |
|---|---|
| 税務署での受理確認 | 窓口提出の場合はその場で確認できるが、郵送やe-Taxで提出した場合は数日後に税務署へ問い合わせると安心 |
| 届出控えの保管 | 受付印のある届出書の控えや、郵送の場合は送付記録を保管し、必要時にすぐ確認できるようにする |
| 納税管理人への通知 | 届出の受理を納税管理人にも共有し、税務署からの通知が正しく届くように手配する |
| 税務署からの初回通知の確認 | 納税管理人として正式に登録された後、税務署からの通知が適切に届くかを確認する |
もし、届出後に納税管理人のもとに税務署からの通知が届かない場合や、税務署のデータベースに登録されていないと判明した場合は、速やかに税務署へ問い合わせましょう。特に、申告期限が迫っている場合は迅速な対応が必要です。
納税管理人届出書の書き方
納税管理人を選任する際は、「納税管理人届出書」を税務署に提出しなければなりません。届出書の記入項目と内容、注意点は以下の通りです。
納税義務者の情報を記入
- ・氏名(法人の場合は法人名)
- ・住所(海外在住者は現住所を記入)
- ・納税地(日本国内の住所または不動産所在地など)
納税管理人の情報を記入
- ・氏名(法人の場合は法人名)
- ・住所(日本国内の住所を記入)
- ・連絡先(電話番号・メールアドレスなど)
届出の内容を記入
- ・届出の理由(例:「海外転居のため」)
- ・代理する税目(所得税・法人税・消費税など)
- ・届出日と署名
税務署によっては、追加書類の提出を求められる場合もあります。必要な書類は税務署のホームページなどで事前に確認しておきましょう。
納税管理人の業務と責任

ここでは、納税管理人が対応する主な手続きや、責任・罰則について詳しく解説します。
納税管理人が対応する手続き
納税管理人が担う手続きは多岐にわたります。代表的な業務は以下の通りです。
- ・税務署からの書類受領
- ・税金の申告・納付
- ・税務調査への対応
- ・還付手続き
- ・税務相談・アドバイス
それぞれについて簡単にご紹介します。
税務署からの書類受領
納税管理人の重要な業務の一つに、税務署から送付される書類の受領があります。納税義務者が国外にいる場合でも、税務関連の通知や書類は日本国内の住所に送付されるため、納税管理人がこれを受け取り、適切に対応します。
税金の申告・納付
納税義務者に代わって税金の申告・納付を行うことがあります。
納税管理人が関与する税金の種類や申告方法は、納税義務者の状況によって異なります。主な税目と対応内容は以下の通りです。
| 税目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税(個人の確定申告) | 日本国内で所得を得ている非居住者の確定申告を行い、所得に応じた税額を計算し、期限内に納付します |
| 法人税(外国法人の申告) | 日本で事業を行う外国法人の法人税申告を代行し、必要な書類を作成・提出します |
| 消費税(事業者としての納税義務) | 日本国内で課税売上を持つ非居住者や外国法人の消費税申告・納付をサポートします |
| 固定資産税(不動産所有者の税務管理) | 日本に不動産を所有する非居住者に代わり、毎年の固定資産税や都市計画税を納付します |
税務調査への対応
税務署は、申告内容の正確性を確認するために調査を行うことがあり、納税義務者が海外にいる場合でも、日本国内での対応が求められることがあります。そのため、納税管理人が窓口となり、必要な対応を適切に行います。
税務調査が行われる際、納税管理人はまず税務署からの調査実施通知を受領し、速やかに納税義務者へ報告します。次に、申告書や帳簿、取引記録などの必要書類を整理し、税務署に提出できる状態に整えます。調査当日は税務署の担当者と対応し、調査の進行を管理するとともに、必要に応じて税理士と連携して適切な説明を行います。調査の結果、修正申告が求められた場合は納税義務者と協力して対応し、指摘内容に納得できない場合には異議申し立ての準備を進めることもあります。
還付手続き
還付とは、納税義務者が支払った税金が過払いとなった場合に、税務署から払い戻される手続きのことです。特に、源泉徴収や予定納税で納めすぎた税額がある場合、適切な手続きを行うことで還付を受けることができます。
還付手続きが必要となる主な税目と、還付の理由は以下の通りです。
| 税目 | 内容 |
|---|---|
| 所得税 | 年末調整や確定申告で納めすぎた場合 |
| 法人税 | 予定納税額が実際の税額を上回った場合 |
| 消費税 | 仕入税額控除の適用により納税額がゼロになった場合 |
| 固定資産税 | 誤納や課税額の変更による還付が発生した場合 |
税務相談・アドバイス
納税管理人が対応する税務相談の内容は多岐にわたります。以下に、主な相談内容は以下の通りです。
| 相談内容 | 主な対応 |
|---|---|
| 税金の申告方法 | 所得税・法人税・消費税など、適切な申告手続きについて案内 |
| 税務リスクの回避 | 申告漏れや過少申告を防ぐためのアドバイスを提供 |
| 節税対策の提案 | 税制上の優遇措置や控除の活用方法を説明 |
| 納税スケジュールの管理 | 申告・納付の期限を把握し、適切なスケジュールを提案 |
| 税務調査の対応 | 調査に備えた準備や、指摘事項への対処方法を助言 |
納税管理人の責任と罰則
納税管理人には、納税義務者に代わって税務手続きを適切に処理する責任があります。しかし、義務を果たさなかった場合、納税義務者だけでなく、納税管理人自身にも影響が及ぶ可能性があります。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 申告漏れ・虚偽申告 | 延滞税・加算税の発生、重度の場合は刑事罰 |
| 税務署からの通知を放置 | 適切な対応が取られなかった場合、行政指導や過料 |
| 納税義務者への報告義務違反 | 信用問題に発展し、契約解除のリスク |
例えば、申告漏れや虚偽の申告を行った場合、延滞税や加算税が発生し、重度の違反では刑事罰の対象となることもあります。また、税務署からの通知を放置すると、適切な対応が取られなかったとみなされ、行政指導や過料が科されることがあります。さらに、納税義務者への報告を怠ると、信用問題に発展し、最悪の場合、契約解除につながるリスクもあります。
納税管理人の解任と変更方法

納税管理人は、一度選任した後でも解任や変更が可能です。しかし、税務署への届出が必要となるため、適切な手続きを踏まなければなりません。ここでは、納税管理人の解任方法と、変更時の注意点について解説します。
納税管理人を解任する方法
納税管理人を解任する場合、納税義務者は税務署へ「納税管理人解任届出書」を提出する必要があります。解任の手続きは、以下の流れで行います。
- 1.解任の意思確認
- 2.必要書類の準備
- 3.税務署への届出
それぞれのステップについて詳しくみていきましょう。
解任の意思確認
納税管理人を解任する際は、まず納税義務者と納税管理人の間で解任の意思を確認することが重要です。納税管理人を税理士や法人に依頼している場合、契約書に解約の手続きや通知期限が定められていることがあります。違約金の有無や、解約の申し入れ期限などをチェックし、トラブルを防ぐための準備を行いましょう。
納税管理人を解任する意思を伝える際は、口頭ではなく書面やメールなど、証拠が残る方法を選ぶのが望ましいです。特に、税務手続きをスムーズに進めるためにも、次の管理人が決まっている場合は、その引継ぎについても納税管理人と相談しておくと安心です。
また、解任の時期によっては、税務申告や納税の対応に影響が出る可能性があります。例えば、確定申告の直前に解任すると、納税手続きが滞るリスクがあります。解任のタイミングを慎重に選び、必要に応じて新しい管理人への引継ぎをスムーズに行うことが大切です。
必要書類の準備
税務署に提出する「納税管理人解任届出書」の準備をします。
解任届出書には、以下のような情報を記入します。
- ・納税義務者の情報(氏名・住所・納税地など)
- ・解任する納税管理人の情報(氏名・住所・連絡先など)
- ・解任の理由(転居、契約終了など具体的に記載)
- ・解任日(正式に解任を適用する日付)
- ・納税義務者の署名・押印
記入内容に誤りがあると手続きが遅れることがあるため、正確に記載しましょう。納税管理人が複数の税目を担当している場合は、それぞれの税目に応じた解任届が必要になることもあります。事前に税務署へ確認しておくと安心です。
税務署への届出
納税管理人の解任届は、納税義務者の納税地を管轄する税務署へ提出します。提出は窓口、郵送、電子申請(e-Tax)の3つの方法があります。
窓口で提出すれば、その場で書類の不備を確認してもらえ、受付印が押された控えを受け取ることで届出の証拠を残せます。郵送の場合、税務署まで行く必要はありませんが、書類の到着や受理状況を確認するために、簡易書留やレターパックなど追跡可能な方法を利用すると安心です。また、一部の手続きはe-Taxを利用したオンライン申請も可能です。電子申請を希望する場合は、税務署のウェブサイトで対応状況を確認してみましょう。
届出を提出した後は、税務署からの受理連絡の有無を確認します。控えを適切に保管し、旧納税管理人にも解任が完了したことを共有することで、手続きを確実に完了させることができます。
窓口で提出した場合はその場で確認できますが、郵送の場合は数日後に税務署へ問い合わせて確認しておくと安心です。また、受付印のある控えや郵送の送付記録を保管しておけば、後日確認が必要になった際に対応しやすくなります。税務署の手続きミスを防ぐためにも、解任届が受理されたことを旧納税管理人にも伝えておくとよいでしょう。
納税管理人変更時の注意点
納税管理人を変更する際には、スムーズに税務対応を継続するために、以下のような点に注意しましょう。
- ・新しい納税管理人の選定は事前に行っておく
- ・納税管理人の業務引継ぎを適切に行う
- ・税務署への届出を忘れずに行う
それぞれについて詳しく解説します。
新しい納税管理人の選定は事前に行っておく
納税管理人を変更する際は、解任と同時に新しい管理人を選定し、税務手続きが滞らないよう準備しておきましょう。納税管理人が不在の期間が生じると、税務署からの通知が届かなかったり、申告・納付が適切に行えなかったりするリスクがあります。そのため、解任を決めた時点で、新たな納税管理人の候補を検討し、スムーズに引き継ぐ体制を整えておくと良いです。
新しい納税管理人を選定する際は、税務知識があり(税理士や税務経験者が望ましい)、長期的な対応が可能で契約条件が明確な信頼できる相手であること、さらに日本国内で迅速に連絡が取れることが重要な基準となります。特に、税務手続きに不慣れな個人よりも、税理士や専門の法人を選ぶことで、確実な対応が期待できます。
納税管理人の業務引継ぎを適切に行う
納税管理人を変更する際は、税務手続きに支障が出ないよう、業務の引継ぎを適切に行うことが重要です。引継ぎが不十分だと、税務署からの通知が新しい納税管理人に届かない、申告や納税が遅れるといったリスクが発生する可能性があります。
納税管理人の業務引継ぎでは、以下の情報を新しい管理人に適切に共有しましょう。
- ・過去の申告・納税状況(直近の申告書や納付履歴)
- ・税務署からの通知書類(未対応の書類がないか確認)
- ・今後の税務スケジュール(次回の申告期限や納税予定)
- ・納税者情報(納税義務者の住所、連絡先など)
- ・税務代理権限の移行(新しい管理人が適切に手続きを行えるようにする)
納税管理人の変更を円滑に進めるためには、旧管理人と新管理人の間で事前に打ち合わせを行い、過去の税務処理や今後の予定についてしっかり共有しておきます。さらに、重要書類をファイル化し、必要に応じてデジタルデータも共有するなど、書類やデータを整理して分かりやすい形で引き渡すことが求められます。
税務署への届出を忘れずに行う
納税管理人を変更した際は、速やかに税務署へ届出を行いましょう。届出を怠ると、旧納税管理人に税務署からの通知が引き続き送付され、新しい管理人が正式に手続きを行えないなどのトラブルが発生する可能性があります。
納税管理人を変更する際には、税務署へ「納税管理人変更届出書」を提出します。この書類には以下の内容を記載する必要があります。
- ・納税義務者の情報(氏名・住所・納税地など)
- ・旧納税管理人の情報(氏名・住所・解任日など)
- ・新納税管理人の情報(氏名・住所・連絡先など)
- ・届出の理由(納税管理人の交代による変更であることを明記)
届出書の様式は税務署のウェブサイトからダウンロードでき、提出方法としては、窓口持参・郵送・e-Tax(電子申請)が利用可能です。届出を提出した後は、税務署での受理を確認します。届出の控えや提出記録の保管もしっかり行いましょう。
納税管理人をお探しならストラーダ税理士法人にお任せください

納税管理人を選任する際には、国税や地方税に関する税務申告の手続きも同時に進める必要があります。特に、日本非居住者の税務は専門的な知識を要する分野が多く、適切な対応を行わなければ税務上のリスクが生じる可能性があります。ストラーダ税理士法人は、納税管理人業務に関する豊富な実績と蓄積されたノウハウを活かし、スムーズな税務対応をサポートいたします。
バイリンガル対応で国際的なサポートを提供
ストラーダ税理士法人には、英語や中国語に堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しており、外資系企業の日本進出や、日本企業の海外派遣など、多様なケースに対応しています。特に、外国法人や海外居住者が納税義務を果たす際には、言語の壁が大きな課題となりますが、当法人では英語や中国語を用いた納税管理人サービスを提供し、多くのクライアントから高い評価をいただいております。
海外企業の納税管理も多数対応
ストラーダ税理士法人では、日本国内に事務所を持たない外国法人の納税管理人業務も幅広く担当しております。例えば、海外で上場している企業の中には、日本に恒久的施設(PE)を持たずに事業を展開するケースが多く見られます。特に、近年ではLCC(Low-cost carrier)と呼ばれる格安航空会社の日本路線が増加しており、当法人はこうした大企業の納税管理人としての豊富な実績を有しています。
納税管理人の選任を検討されている方は、ぜひストラーダ税理士法人にご相談ください。専門的な知識と実績を活かし、税務手続きを円滑に進めるお手伝いをいたします。