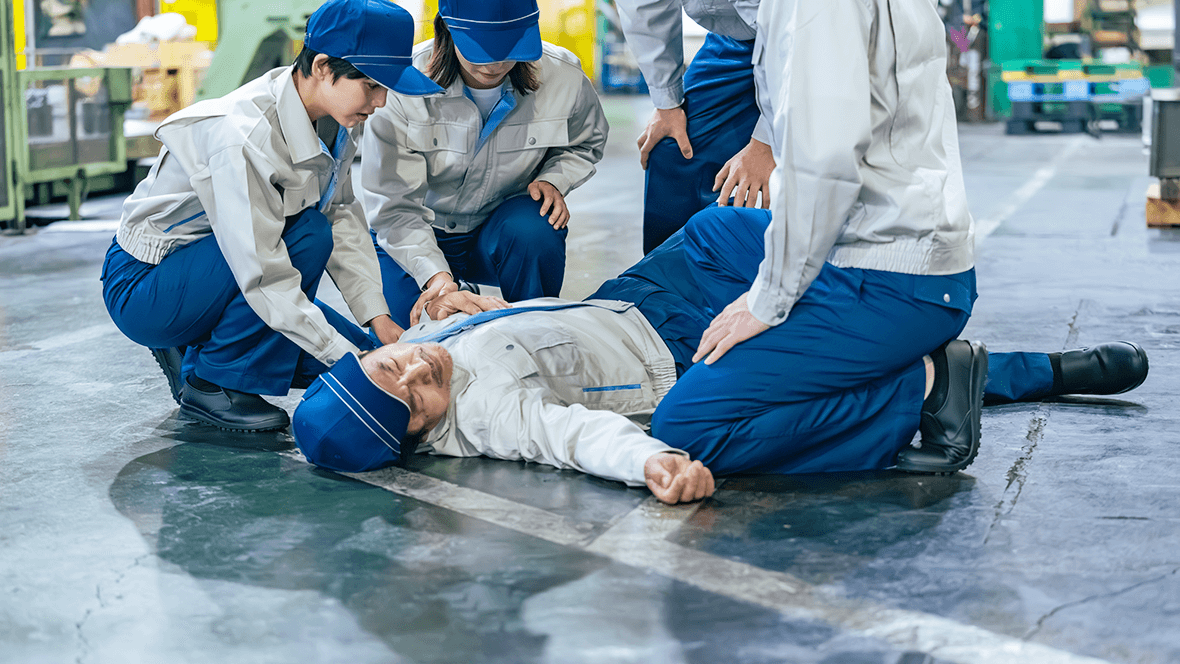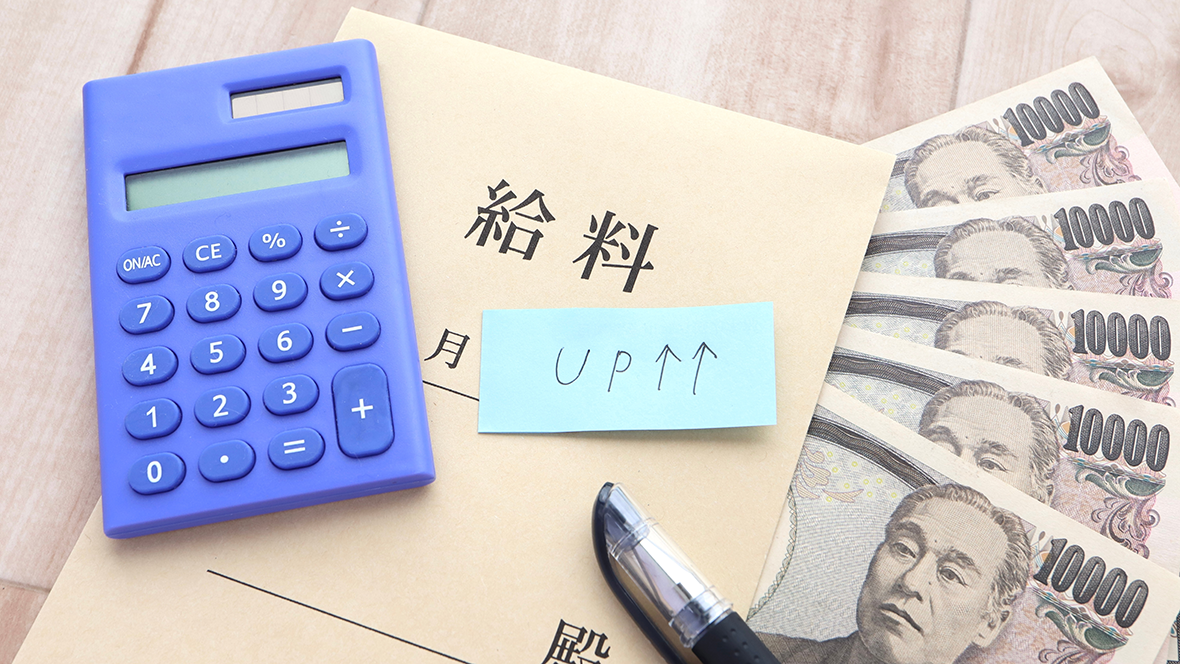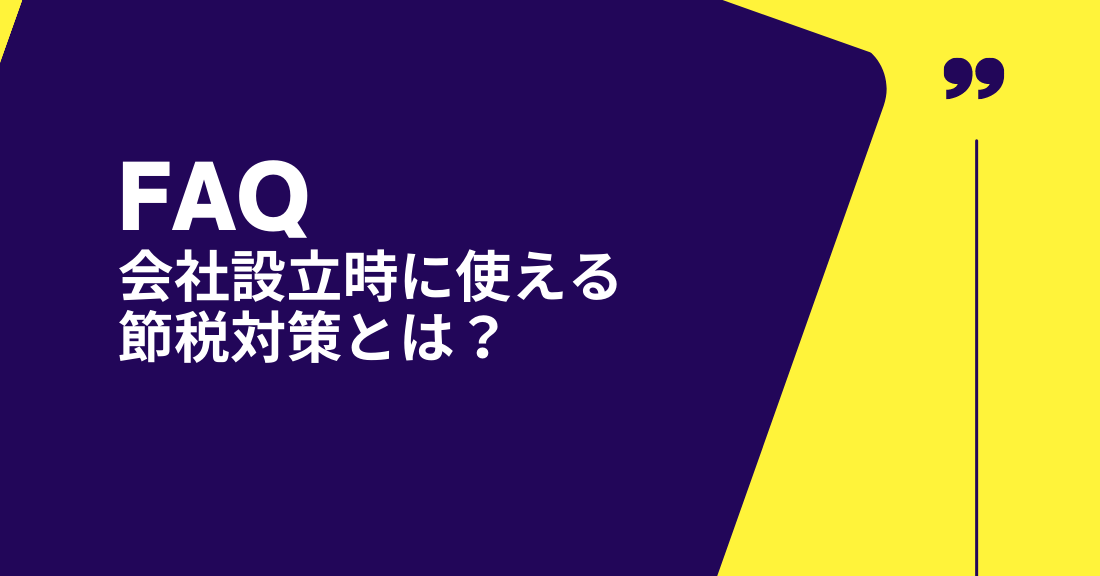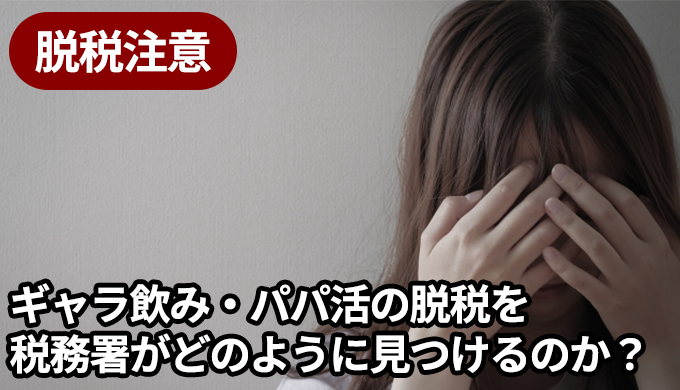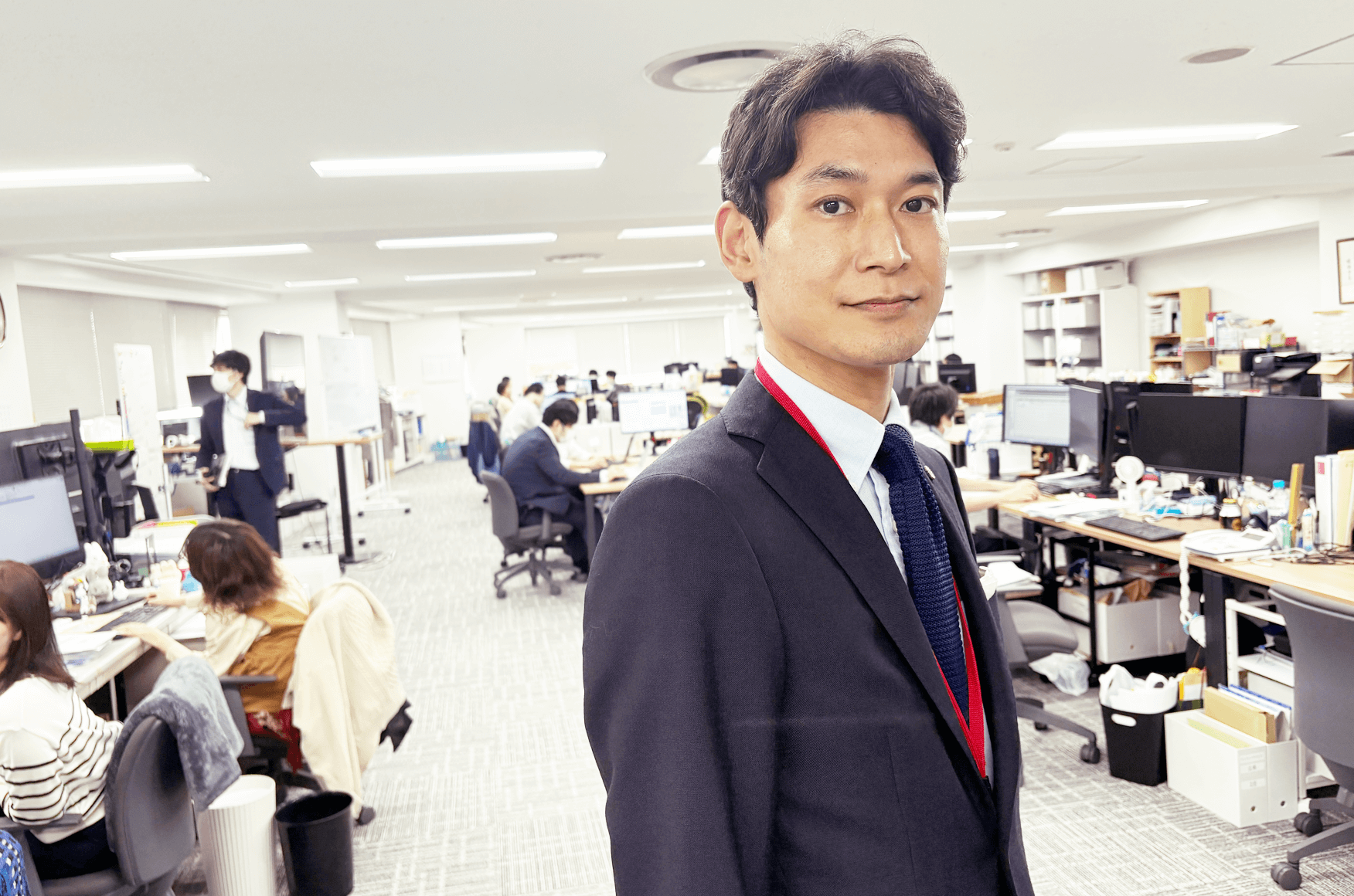労災保険は業務中または通勤途中に発生した事故や怪我に対する保険制度のこと。この制度は企業から雇われている労働者の保護を目的としているため、個人事業主やフリーランス、会社の役員などは適用対象外となるのが一般的です。
しかし、一定の条件を満たすことで適用対象外となる方も治療費や失業給付などの手厚い補償が受けられる『特別加入制度』を利用することが可能です。今回は労災保険の特別加入制度の概要をはじめ、対象者の種類や申請方法等の情報について解説します。
Contents
労災の特別加入とは?

労災保険の特別加入制度とは、通常労災保険の対象とならない個人事業主やフリーランス、会社の役員などうち、労働者と同様の業務に従事していることが多い場合や災害の発生状況などから見て、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に対して、特別に加入を認めている制度のことです。
強制的に加入が義務付けられている通常の労災保険と異なり、加入や脱退は原則として自由に決められることが特徴の1つです。ただし、建設業に関しては特別加入をしていないと現場に入場できないケースもありますので、建設業の一人親方として独立している方の場合、基本的には加入しておいたほうが良い制度と言えるでしょう。
特別加入制度の対象となる主な職業
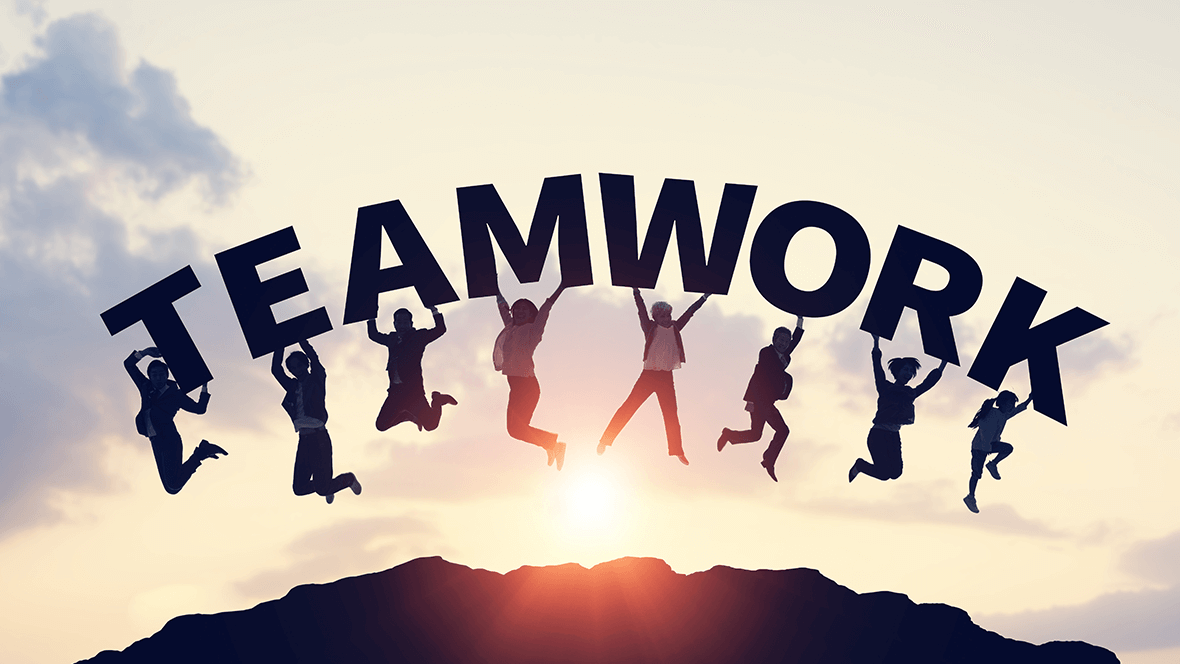
特別加入制度の対象者は『中小事業主』・『一人親方』・『特定作業事業者』・『海外派遣者』の4つに大別されます。それぞれの詳しい条件について確認していきましょう。
中小事業主
労災保険に特別加入できる『中小事業主等』 の対象者は、次の2つに該当する方を指します。
①下の表に定める、特定の人数の労働者を常時使用している事業主。
| 業種 | 労働者数 |
|---|---|
| 金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100人以下 |
| その他の業種 | 300人以下 |
②労働者以外で①の事業主の事業に従事している人(家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合の代表者以外の役員など。)
また、労働者を通年雇っていない場合も年間100日以上労働者を雇っていれば、常時労働者を使用している中小事業主として認められます。
一人親方
一人親方とは会社から雇用されずに自分ひとりで事業を行う自営業者のことです。原則、労働者を雇わないことが加入要件として挙げられますが、労働者を使用していても使用日数が年間100日未満であれば、労災保険の特別加入制度を利用することができます。
具体的には以下のような業務に従事する方が対象となります。
- ・自動車を使用して行う旅客や貨物の運送業(個人タクシー、引っ越し業者等)
- ・自転車を使用して行う貨物の運送業(フードデリバリーサービスの自転車配達員等)
- ・漁船による水産動植物の採捕の事業
- ・土木・建築・その他工作物の建設・改造・保存・現状回復・修理・変更・破壊もしくは解体やその準備(大工、左官、とび職等)
- ・植林、伐採、木炭製造等を行う林業
- ・柔道整復師が行う事業
- ・歯科技工士が行う事業
- ・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業
- ・医薬品の設置販売事業(自宅用又はオフィス用の救急箱の配置販売業者等)
- ・再生利用の目的となる廃棄物などの収集・運搬・選別・解体などの事業(古紙、くず鉄、あきびん類といった廃棄物のリサイクル業者等)
- ・船員法第1条に規定する船員が行う事業(漁業、貨物運輸業、旅客船事業等)
特定作業事業者
特定作業従事者とは、主に以下のような業務に取り組んでいる人が該当します。
- ・特定農作業従事者→一定以上の農産物の販売額又は農地面積を有している農業者であり、高所や危険場所における作業・大型農機具を使用した作業などを行う方
- ・指定農業機械作業従事者→トラクターや動力草刈機等の各種農業機械を使用して土地の耕作、植物の栽培又は採取などの作業を行う自営農業者
- ・国または地方公共団体が実施する訓練従事者→国職場適応訓練従事者、事業主団体等委託訓練従事者。
- ・家内労働者およびその補助者→家内労働者や補助者のうち、プレス機・研削盤・有機溶剤などを用いた危険度が高い業務に従事している方
- ・労働組合等の常勤役員→常時労働者を使用しない労働組合等で、公園や集会場など各種公共施設での組合活動に必要な作業を行う方
- ・介護作業従事者および家事支援従事者→介護作業従事者は日常生活の世話や食事などの介護を行う方、家事支援者は日常生活を営むのに必要な行為を代行又は補助を行う方
- ・創業支援等措置を講じられた高年齢者→創業支援等措置に基づいて高齢者が新たに開始する事業、事業主が行う社会貢献活動等
- ・芸能関係作業従事者→俳優、ダンサー、歌手などの実演者や演出家、カメラマン等の制作関係者
- ・アニメーション制作作業従事者→キャラクターデザイナー、作画担当等の制作関係者や監督、脚本家等の演出関係者
- ・ITフリーランス→情報処理システムの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理等を行う方
なお、創業支援等措置を講じられた高年齢者・芸能関係作業従事者・アニメーション制作作業従事者・ITフリーランスは2021年より特定作業事業者として新たに追加されました。
海外派遣者
諸外国の中には労災補償がない場合や、仮にあったとしても補償内容が不十分な場合があります。そこで日本から海外の事業に派遣される場合も、一定の範囲で労災保険の加入が認められています。海外派遣者として特別加入制度を利用できるのは、以下のような人々が対象です。
- ・日本国内の事業から海外で行われる事業に労働者として派遣される人
- ・日本国内の事業から海外にある中小規模の事業に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
- ・発展途上地域で技術協力の事業を行う団体から派遣され従事する人
ただし、海外出張ではなく”海外派遣”されているかどうかという点が重要なポイントです。どちらに当たるかは勤務の実態によって異なりますので、判断に迷った場合は予め労働基準監督署に確認しておくと良いでしょう。
2024年秋より全フリーランスが特別加入の対象に!

従来、特別加入制度の対象となるフリーランスは建設業の一人親方や芸能・アニメーション事業者、フードデリバリーサービスの配達員など一部の職種に限られていましたが、2024年11月より業種を問わず企業から委託されている全てのフリーランスが『労災保険特別加入制度』に加入できるようになっています。
特別加入の対象が拡大された背景には近年、テレワークなど雇用関係によらない働き方の多様性が進んでいることが挙げられます。これによって更に多くのフリーランスの方が、ケガや病気などで働けなくなった時のセーフティーネットを確保できるようになりました。
ただし、全ての加入要件を満たさなければ申請してもフリーランスの労災保険給付の対象となりませんので十分ご注意ください。
フリーランスの労災保険加入要件
1.業務委託契約で働いており、主な取引先は事業者である
2.現在は個人だが、将来的に企業や個人事業主と取引する予定や気持ちがある
3.従業員を雇用していない
4.下記の職種に該当しない『特定フリーランス事業』を行っている
(※下記に記載されている職種の方の場合、特定フリーランス事業とは別の特別加入団体から手続きを行う必要があります。それぞれの手続き方法については別の項目で詳しく解説させて頂きます。)
| 特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業 | |
|---|---|
| 個人タクシー業者、個人貨物運送業者等 | 建設業の一人親方等 |
| 漁船による自営漁業者 | 林業の一人親方等 |
| 医薬品の配置販売業者 | 再生資源取扱業者 |
| 船員第1条規定の船員 | 柔道整復師 |
| 創業支援等措置に基づく高年齢者 | あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師 |
| 歯科技工士 | 特定農作業従事者 |
| 指定農業機械作業従事者 | 国・地方等が実施する訓練従事者 |
| 家内労働者等 | 労働組合等の一人専従役員 |
| 介護作業従事者 | 家事支援従事者 |
| 芸能関係作業従事者 | アニメーション制作作業従事者 |
| ITフリーランス | |
特別加入制度の補償内容
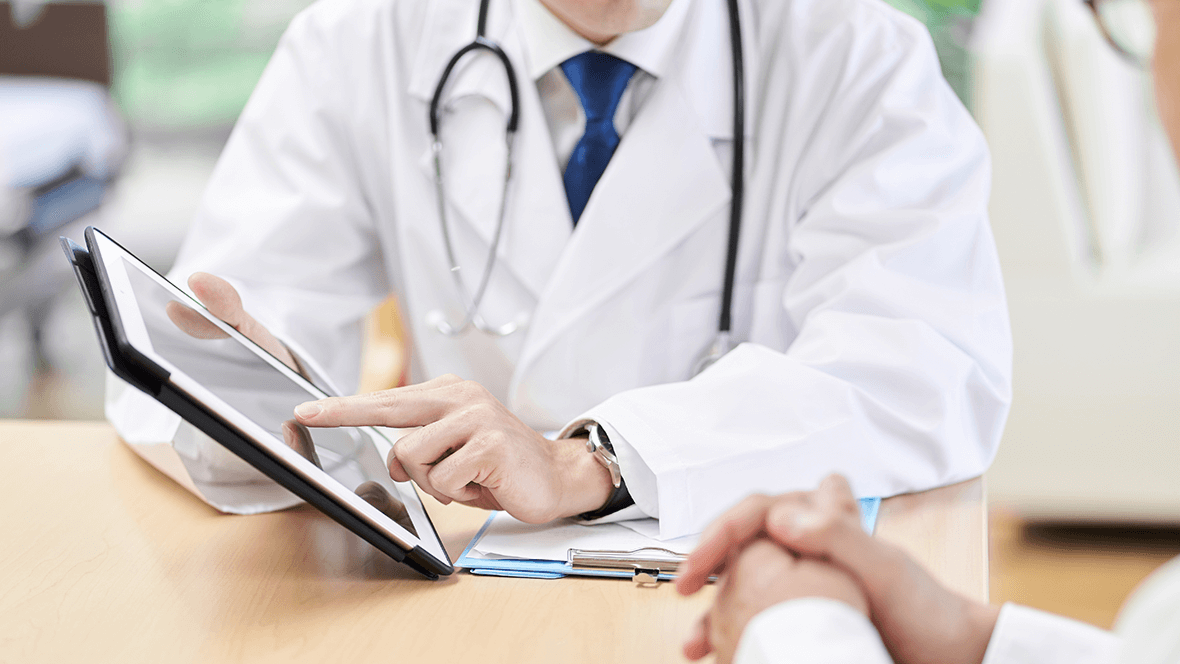
特別加入制度を利用することで、原則として労働者と同等の給付を受けることが可能です。ただし、特別加入者の健康診断の受診は自主性に任せられているため、『二次健康診断等給付』については対象外となっています。下記では特別加入制度の具体的な補償内容について解説致します。
療養補償
療養補償とは、業務中もしくは通勤中に負った怪我や病気に対し、治療を受けるために支給される補償のことです。補償の範囲には次のようなものが含まれます。
- ・初診料
- ・診察料
- ・入院費
- ・手術費
- ・装具、器具購入費
- ・リハビリ費
- ・薬代
- ・通院費
- ・移送費
なお、治療と考えると健康保険について思い浮かぶかと思いますが、健康保険と労災保険は根拠となる法律が違いますので、労災事故の場合は健康保険が適用できません。
労災であるにも関わらず、健康保険証を提示して治療を受けた場合、一時的に治療費の全額を自己負担しなければなりませんので注意が必要です。誤りに気付いた段階で速やかに労災保険への切り替え手続きを申し出るようにしましょう。
休業補償
休業補償は業務中もしくは通勤中に負った怪我や病気が原因で働けなくなった際に支給される補償です。休業補償が受けられるのは最初に休業した日から4日以上に及ぶ場合です。休業1~3日目までは対象外となりますのでご注意下さい。
傷病補償
業務上の事由による怪我や病気が療養開始後、1年6カ月を経過しても治癒せず、かつ傷病等級(第1級~第3級)に該当する場合は傷病補償の対象になる可能性があります。給付される額は傷病等級に応じて異なります。
- ・傷病等級第1級の場合→給付基礎日額の313日分
- ・傷病等級第2級の場合→給付基礎日額の277日分
- ・傷病等級第3級の場合→給付基礎日額の245日分
障害補償
障害補償は労災を原因とする怪我や病気の治療後、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付金のことを言います。障害補償給付の金額は障害の程度に応じて異なります。そのため、医師による診断と併せて労働基準監督署における障害等級認定の審査を受ける必要があり、場合によっては支給の決定までに半年間から1年ほどの期間がかかるケースもあるようです。
遺族補償
遺族補償とは、業務または通勤が原因で死亡した労働者の遺族に対して支給される給付金です。ただし遺族補償は遺族であれば誰でも受け取れるわけではなく、妻以外の遺族については労働者が死亡した当時に一定の高齢または年少であるか、一定の障害の状態にあることが必要です。また、受給権者の条件に一致していたとしても優先順位が高い受給権者が存在する場合は給付金を受け取ることはできません。
遺族補償の受給権者とその順位は次の通りです。
| 1位 | 妻、60歳以上の夫、一定障害の夫 |
|---|---|
| 2位 | 18歳になって初めて迎える3月31日までの子、一定障害の子 |
| 3位 | 60歳以上の父母、一定障害の父母 |
| 4位 | 18歳になって初めて迎える3月31日までの孫、一定障害の孫 |
| 5位 | 60歳以上の祖父母、一定障害の祖父母 |
| 6位 | 60歳以上の兄弟姉妹、18歳になって初めて迎える3月31日までの兄弟姉妹、一定障害の兄弟姉妹 |
| 7位 | 55歳以上60歳未満の夫 |
| 8位 | 55歳以上60歳未満の父母 |
| 9位 | 55歳以上60歳未満の祖父母 |
| 10位 | 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹 |
葬祭補償
葬祭補償は労災が原因で亡くなった被保険者の葬儀を行った方に対して支給される給付金のことを指します。葬祭料は315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分のうち、いずれか高い方が支給額となります。
また、請求時には死亡診断書や死体検案書の写しなど、死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類の提出が必要です。
介護補償
介護補償は傷害補償又は傷病補償の受給者のうち、障害等級・傷病等級が第1級の方と第2級の『精神神経・胸腹部臓器の障害』を有している方が、実際に介護を受けている場合に支給される補償です。支給限度額については常時介護と随時介護の場合でそれぞれ設定が異なります。
特別加入制度の保険料について

特別加入者の保険料は『給付基礎日額』に応じて算定されます。給付基礎額とは、特別労災の保険料や支給額等の計算基準となるものです。
一般の労働者の場合、労働時間に対して支払われた賃金総額に保険料率を乗じる形になりますが、特別加入者は3,500円〜25,000円の16段階の中から任意で設定した365日分の給付基礎日額に、それぞれの事業に定められた保険料率(※)を乗じて算出します。
給付基礎日額が高ければ高いほど、保険料そのものも高くなりますが、その分手厚い保証を受けられるということです。適切な給付基礎日額を設定するには既に加入している災害保険の給付金等と比較したり、ご自身の年間所得や生活費などを考慮すると良いでしょう。
特別加入制度の手続きのやり方

特別加入制度の申請方法は大きく分けて、次の2種類があります。
- 1.既存の特別加入団体を通じて加入
- 2.新しく特別加入団体を設立
なお、申請後に業務内容等に変更があった場合や脱退を希望する場合は、加入した団体へ速やかにその旨を連絡しましょう。
既存の特別加入団体を通じて加入
特別加入団体とは、都道府県の労働局から承認を受けて特別加入者の労災保険の事務手続きや、災害防止措置の規定などを行う団体のことです。特別加入団体は全国に4,000団体以上存在しますが、利用できる団体は業種ごとに異なります。
例えば、日本労働組合総連合会が設立した『連合フリーランス労災保険センター』は特定フリーランス事業のみ利用できる団体です。オンライン申請に対応しているため、日本全国どこからでも手続きを行うことが可能です。
特定フリーランス事業に該当しない場合、ご自身の事業または作業に適した団体が付近にあるかどうか労働局に問い合わせるようにしましょう。
※特定フリーランス事業以外の特別加入の事業または作業
※特別加入団体一覧表
新しく特別加入団体を設立する
新たに特別団体を立ち上げて申請するという方法もあります。ただし、新設するには次のような要件を満たす必要があります。
- ・一人親方等の相当数を構成員とする単一団体であること
- ・その団体の定款などに規定された事業内容からみて労働保険事務の処理が可能であること
- ・その団体の事務体制、財務内容などからみて労働保険事務を確実に処理する能力があると認められること
- ・その団体の地区が、団体の主たる事務所の所在地を中心として労働保険徴収法施行規則第6条第2項第4号に定める区域に相当する区域を超えないものであること
特定フリーランス事業の場合も特別団体を新設することができますが、100名以上の会員数に達していることなど厳しい条件が設定されていますので難易度が高いと言えるでしょう。
独立して間もない方や、知識に自信がない場合は既存の特別加入団体を通じて手続きを進めることを推奨致します。
災害が発生した場合の手続き

【手順(1.)】医療機関を受診して労災保険の使用を伝える
業務中または通勤中に事故が発生したら医療機関を受診し、窓口で労災である旨を伝えるようにしましょう。緊急手術が必要な場合などやむ得ないケースを除き、労災保険指定の医療機関であるか確認した上で治療を受けると手続きがスムーズに進みます。
もし労災指定病院以外を選んだ場合は窓口で一旦、治療費の全額や預り金を支払う必要がありますが、労災保険の申請が完了すると後日に返金してもらえますのでご安心下さい。
【手順(2.)】特別加入団体に労災事故について報告をする
労災の申請は被保険者本人が自ら請求手続きを行う必要があります。これは特別加入者に限らず、一般の労働者の場合も会社側ではなく、原則として労災を利用したい本人が行わなければなりません。
しかし、中には請求書の提出代行を承っている企業や特別加入団体もありますので、怪我や入院等で手続きがすぐに行えない場合は社会保険労務士など労働・社会保険に関する専門家に依頼することも一つの手段です。
請求手続きの具体的な流れとしては、まず最初に加入している団体へ『労災事故報告書』を提出します。労災事故報告書の書式は団体ごとに異なる点に注意が必要です。公式ホームページにフォーマットが無い場合、電話やメールで問い合わせて書類を取り寄せるようにしましょう。
- ・氏名
- ・住所
- ・職種
- ・災害が発生した日時・場所
- ・災害の原因・発生状況
- ・治療を受けた医療機関の名前
- ・請け負っていた工事名、元請会社の連絡先
なお、労災事故報告書に記入する主な項目は上記の通りです。正確に記載できるよう災害直後にメモを取ったり、現認者に事故が発生した当日の状況について十分に確認しておくようにして下さい。
【手順(3.)】保険給付の請求書を提出する
労災事故報告書の提出後、団体から申請する給付に応じた様式の申請書類が送られてきます。提出先は医療機関や労働基準監督署など、給付の種類によって異なりますので団体の指示に従うようにしましょう。
労災保険の支給決定がなされると窓口での費用負担無く、無償で治療を受けることが可能です。薬剤ついても同様に無料で支給が行われます。
なお、労災保険の申請には一定の期限が設けられています。遅れて申請すると給付を受ける権利が消失してしまう恐れがありますので、できるだけ早めに申請することをおすすめします。各補償の時効期限については次の通りです。
| 補償内容 | 時効 |
|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
| 休業(補償)等給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
| 遺族(補償)等年金 | 被保険者が亡くなった日の翌日から5年 |
| 遺族(補償)等一時金 | 被保険者が亡くなった日の翌日から5年 |
| 葬祭料等(葬祭給付) | 被保険者が亡くなった日の翌日から2年 |
| 未支給の保険給付・特別支給金 | それぞれの保険給付と同じ |
| 傷病(補償)等年金 | 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない |
| 障害(補償)等年金 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
| 介護(補償)等年金 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
労災保険の特別加入制度を利用するメリット・デメリット
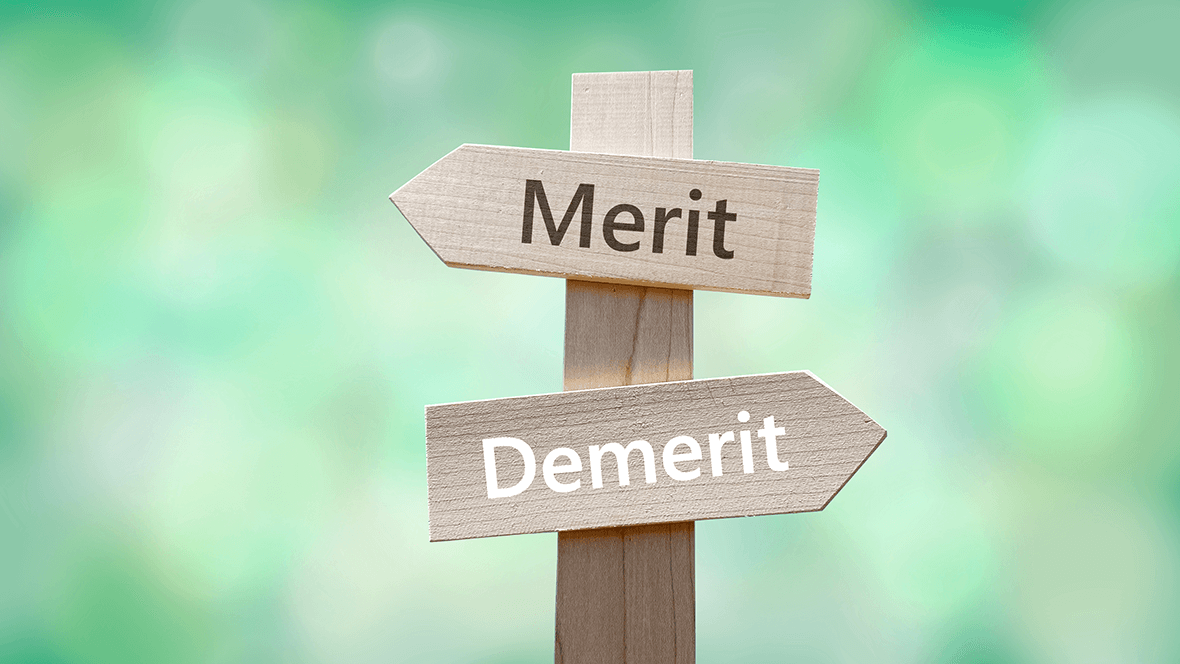
労災保険の特別加入のメリット
万が一の際の医療負担を抑えられる
会社に属さないフリーランスや一人親方は、企業に雇用されている労働者と違って業務にかかる責任は全て自身で責任を負うことになります。身体を負傷してしまうと最悪の場合、失職してしまう可能性も否めません。
そうしたリスクを回避するために、特別加入制度を通じて労災に入っておけば、休業補償給付・障害補償給付など一般の労働者とほぼ同等の給付を受けることができるため、万が一災害に見舞われた際も医療費の負担を軽減することができます。
また、労災は国が直接管理・運営を行っている公的制度なので安心して利用できるのも嬉しいポイントです。
保険料を自分で設定できる
労災保険の保険料は給付基礎日額に基づいて計算されます。通常の労災保険は被保険者の収入によって給付基礎日額が自動的に決定する仕組みとなっていますが、特別加入者の場合、自分の意思で設定できるというメリットがあります。
例えば病院での治療や処方薬のみ無料で受けられれば良いと考えている場合、給付基礎日額を低めに設定したり、怪我や死亡のリスクが発生しやすい危険作業を伴う業務に従事している方は給付基礎日額を高くしておけばその分、手厚い補償を受けることに繋がります。
労災保険の特別加入のデメリット
会費や手数料などの費用が発生する
通常の労災保険料は会社側が全額負担する形になりますが、特別加入者は保険料に加え、特別加入団体に加入するための入会金や会費を自身で支払う必要があります。
現状、入会していない場合には出費が増える形になりますが、将来的に医療負担が軽減されることを考えると”支払いが発生する”=デメリットでは無いかもしれません。かかる費用は団体によって違いますので、加入を検討している方は事前に確認することをおすすめします。
必ずしも業務災害の認定が下りるとは限らない
フリーランス新法の施行により、特別加入制度の適用範囲は一気に広がっていますが、どなたでも加入できる制度というわけではありません。具体例としては加入前の段階から既に疾病にかかっており、就労ではなく療養に専念すべきと判断された場合には労災保険を利用できない可能性が考えられます。
なお、次の特定の業務に従事した期間がある方は、特別加入の申請を行う際に健康診断を受診する必要があります。
| 健康診断が必要な特定の業務 | 特別加入前に左記の業務に従事した期間(通算期間) | 必要な健康診断 |
|---|---|---|
| 粉じん作業を行う業務 | 3年以上 | じん肺健康診断 |
| 振動工具仕様の業務 | 1年以上 | 振動障害健康診断 |
| 鉛業務 | 6カ月以上 | 鉛中毒健康診断 |
| 有機溶剤業務 | 6カ月以上 | 有機溶剤中毒健康診断 |
健康診断書を提出しなかったり、業務歴などについて虚偽の申請をしてしまうと特別加入の申請が通らず、いざ保険給付を受けたいと思っても受けられないという事態になりかねませんので、該当者の方はきちんと受診した上で申し出るようにしましょう。
働く人々の強い味方!特別加入制度を有効活用しよう
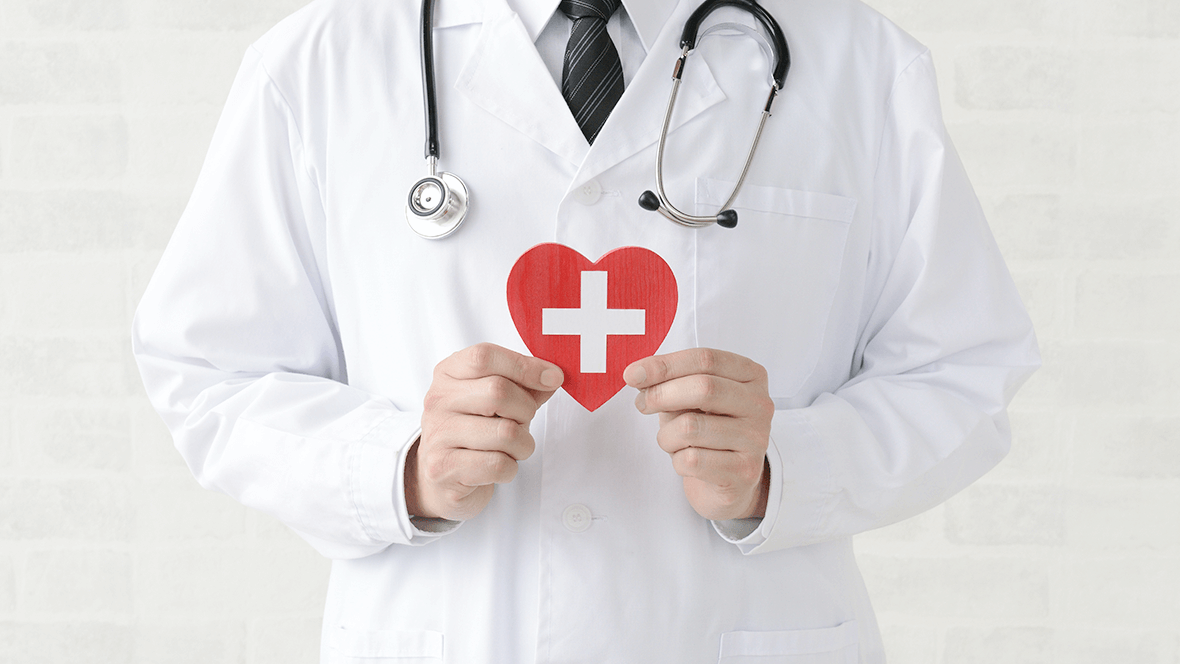
労災保険の特別加入は組合又は団体を通さなければ加入できないため、手続きの時間や手間がかかるという懸念点があります。繁忙期等の理由で、申請手続きを後回しにすると『入会前の段階で労働災害が発生してしまった』なんてことも起こり兼ねません。
ストラーダ社会封建労務士法人では厚生労働大臣の認可を受けた労働保険事務組合を併設している他、労働法や社会保険、労務管理などの専門知識を有する社会保険労務士が常駐しておりますので、お客様のご希望やお悩みをお伺いしながら労働保険(労災保険・雇用保険)に関する書類作成から申告、納付手続き等の代行作業等もワンストップで承ることが可能です。
特別加入制度の利用をご検討している方は是非、お気軽にお問合せ下さい。